A Guide to Guides
Guidesのガイド
Quartz読者のみなさん、こんにちは。週末は米国版Quartzの特集〈Guides〉から、毎回1つをピックアップ。世界がいま注目する論点を、編集者・若林恵さんとともに読み解きましょう。
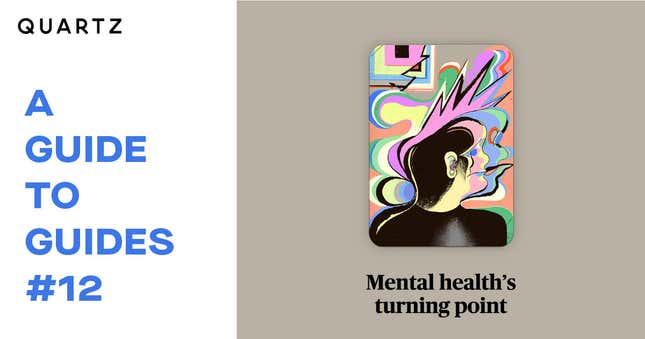
──今回のお題は「メンタルヘルス」ですね。
重たいですね。ちょうど今、「ネットの中傷地獄で自殺未遂、そして出家…元女性アナ、執念で加害者を特定『被害者の駆け込み寺をつくりたい』」という『弁護士ドットコム』に掲載されていた記事を読んでいたところでして、ここではネットやソーシャルメディアでの誹謗中傷が問題となっていまして、こうした問題にどう取り組むのかは喫緊の社会問題になっていますよね。
──どう取り組むんでしょうね。
もちろんひとつは、先の記事もそうですし、あるいは伊藤詩織さんが、荻上チキさんらの協力を仰ぐかたちで加害者を特定し、裁判というかたちで加害責任を問うことをされていましたが、そうしたことは重要なことだと思いますし、ネット上での加害については、メディアプラットフォーマーの責任も厳しく追及されるようになっていますので、そうした動きを、法的に後押しできるようにする制度的な変革は重要だと思います。
──加害者をどうプラットフォームから排除するか、あるいはどう罰しうるか、というところですね。
はい。そこは、ずっとないがしろにされてきたというか、見ぬふりをされてきた領域だと思いますので、政府の介入も含めた問題の解決が進むのは望ましいことだと思います。ただ、その一方で、日本であまり議論されずにいるのは、そうした事態に対して“そもそもどう防御するのか”という点かな、とも思うんです。
──と言いますと。
先の記事にも自殺されてしまった木村花さんの話が出ていましたが、いくら加害者を排除し、罰することができたとしても、彼女の場合のように、その前に被害者当人が自殺してしまっては元も子もない、と言いますか。
──たしかに。
木村花さんの事件にかかわらず芸能人が社会的な事件として取り上げられたときに、自分がいつも思うのは「いったいマネジメントはなにをしてたんだ?」ということでして、コミュニケーションが基本一方通行である従来のマスメディアに関わるときのやり方では、双方向メディアであるインターネットやソーシャルメディアによってかたちづくられた環境は御しきれないということは、随分前からわかっていたことでもあるはずなのですが、有名人のマネジメントを管轄するはずの組織が、自分たちのメシの種であるはずのタレントやアーティストを防御するための手立てを、システマティックに講じているのかどうかは非常に疑問に思うところです。
──どうなんでしょうね。
アーティストやタレントは、その知名度から言って、一般市民とはまったく異なる立場にいるわけですから、それを個人がSNSに向き合うレベルでの対処法しか授からぬまま「タレント本人の自己責任での対処」に委ねられてしまっているのだとしたら、そこにはビジネスの観点から見ても重大な欠落があるように自分には見えるのですが、そのことを真剣に取り組もうという話はあまり聞かないので、とても心配です。

社会問題として政治が介入しろ、という前に、タレントやアーティストをメシの種にしている企業や組織は、タレントやアーティスト、あるいはスポーツ選手といった人たちのメンタルヘルスについて、かなり本気で取り組むべきなのではないかと思います。
──ソーシャルメディアのあり方の改善や、利用者のリテラシーの向上を促すような取り組みは、それはそれとして必要だとしても、それ以外にもやるべきことはたくさんある、ということですね。
だと思います。木村花さんの事件のあとに、どこかの新聞の論評で「SNS教育が必要」といったことが語られていまして、個人的には、何を言ってるんだ、と非常に腹を立てたのですが、一般論として社会の問題の解決を考えたときに、そのソリューションとして「教育が大事」という話に結果として行き着くというのはもちろん間違いではないとは思うのですが、じゃあ、その「教育」とやらの成果が出るまで、どれだけ被害者が出続けるのかと考えると、当然短期的な対処も必要になるわけですよね。
──いますぐに何をすべきか、ということですよね。
はい。教育が大事という議論は、特に日本でそれが語られる場合は、単なる思考停止にすぎないことが多いような気がするんです。結局のところ、それって現状のひどさを直視しないで解決を先送りにすることでしかないようにも見えますし、場合によっては、自分は変わる意志がないことの表明ですらあるわけですよね。
──むむ。ほんとですね。
かつ、先の記事に紹介されていた加害者側の問題というのもありまして、ネットで被害者を追い詰めていった人たちは、記事を読むとたしかに同情にも値しない人たちであるのは、その通りで「こういう虫けらどもは法的な制裁を受ければいいんだ」って気持ちにもたしかになりはするのですが、記事のなかで注目したほうがよさそうに思うのは、こうした人たちは、いざ会ってみると自分のことを「弱者である」と必ず言い募るというところなのかな、と思うんです。
──「何を甘ったれやがって」って気持ちにもなりますが。
自分だってもちろんそうです。ただ、実際にそうした人たちが果たして本当に弱者であるかどうかはわからないにしても、そうやってひたすら「自分は弱者である」と思い込んで、ひたすら鬱屈していく人たちがいることは社会的な事実であって、そうした人たちの抱える問題を「SNSリテラシー」の問題に還元して、そうした人びとを「教化」していくことが改善の道のりである、と考えるのは、問題を矮小化しすぎなように思えますし、彼らの問題が、本当に「SNSの使い方」の問題なのかといえば、大いに疑問があるような気もします。

Mental health’s turning point
メンタルケアの転回点
──ふむ。
つまり、これはデジタルリテラシーの話ではなく、メンタルヘルスの問題として考えるべきではないか、ということなんですが。
──そうか。
日本ではそれがなかなか政策課題にもあがってこず、社会的に重大なイシューであるということが十分に認知されていないような気がするのですが、海外ではメンタルヘルス、あるいは「孤独」という問題はすでに最重要の政策課題と見なされていまして、これは公衆衛生的な観点からも、社会厚生という観点からも、社会の安全という観点からも、さらにはビジネスにおける組織ガバナンスという観点からも重大な課題と見なされているんですね。
──そうなんですね。
COVID-19が発生する数年前から、メンタルヘルスイシューとしての「孤独」という問題は、「見えないパンデミックである」という言われ方で警鐘が鳴らされていまして、それを受けるかたちで、英国には孤独担当大臣というポストがつくられたほどなんです。
──へえ。
そうした認識があるので、COVID-19によるロックダウンの敢行は、国民をより深い孤独に陥らせる可能性があるわけですから、国民のメンタルヘルスに甚大な被害がもたらされることは最初から懸念事項としてあったわけですよね。
──ああ、なるほど。そうした文脈が見えると、今回のGuidesの意味もよくわかってくるような気がします。
SNSによる誹謗中傷というものが、実際どういう人たちによって行われているのかは詳細な調査などが必要ですが、そうした事象全体を社会の安全に関わる危機であるとみなしているのが、例えば英国や、孤独担当大臣の設置を検討しているドイツなどで、それはまず第一に、ソーシャルメディアがテロリストや極右や原理主義のリクルーティングのプラットフォームになっているからで、実際、英国で「孤独」という問題に取り組んでいたジョー・コックス議員は、テロリストによって殺害されているんですね。

もちろん、Facebookなどのプラットフォーム規制は重要な課題なのですが、彼らは、その問題の根底に横たわっているのは「孤独」というメンタルの問題で、そこの改善に取り組まない限り、問題は悪くなるばかりだと考えていることが見てとれます。
──ソーシャルメディアは、それを増幅しているだけだ、と。
だからといって免罪されるわけではないのですが、ソーシャルメディアというのは、その設計の根本において、そもそもが自分の欠落に目を向けさせるものなんですよ。
──というと。
随分昔に、南太平洋の小島で起きたある事件の記事を読んだことがありまして、それはある若者4人が「もうこんな島、うんざりだ」とボートで脱出を試みるのですが、ほんのいたずら心だったのが島に帰れなくなり、海上を、たしか数十日彷徨うことになったという内容なんですが、彼らが、そもそも「こんな島はうんざりだ!」と思った理由がソーシャルメディアだったというんです。
──ははあ。
「外の世界はこんなに楽しそうにやってるのに、うちらの惨めさときたらどうだ」っていうふうに思ったというんですね。といって、もちろん外の世界が、そんな楽しいはずもないのですが、そう頭でわかったところで、自分が何か楽しいこと、大事なこと、大事な情報に、参加したりアクセスできていないんじゃないかという気持ちは残るわけです。「情弱」ということばがありますが、自分が「情弱」の側にいるのではないか、という感覚を昂進させることに、ソーシャルメディアというものはやはり驚くほど長けているんですよ。
──「その情報知らなかった!」って思うたびに、なんというか、自分が取り残されているんじゃないかって感覚を、ちくりと感じますよね。
そうなんです。で、人種差別にもとづく排斥運動って、わりとその心理が根底にあるように見えるんですよね。「ほんとうは自分たちが享受すべき何かを、誰かが奪っている」という、そうした運動の基礎的なナラティブは、「ちくしょう、あいつら、おれらより楽しんでやがる」という、さっきの南太平洋の小島の少年たちと基本的には変わらないですよね。
──ほんとですね。
問題は「自分は取り残されている」という感情のなかで、人がとても危険な状態にどんどんなっていくということで、話をGuidesに戻しますと、COVID-19は、そうした危険な状態をさらに増大させるものであったということですね。アメリカがあれほどの騒乱状態に陥ったのもこうした状況と無縁ではないと思いますし、木村花さんの事件がパンデミックのさなかで起きたことは、であればこそ象徴的な意味をもっているように思います。
──たしかに。
逆にいえば、メンタルヘルスという問題にきちんと取り組まなければならないと考えていた人たちにとっては、COVID-19はひとつの大きな“ウェイクアップコール”、つまりは目覚まし時計になったということで、実際アメリカやイギリスのメディアは、メンタルヘルスの問題をやたらとクローズアップしていましたし、Quartzが、このような特集を組むのも、必然的ですらあるわけです。
この特集のオリジナルのタイトルは“メンタルヘルスの転回点”というものですが、その含意は、「COVID-19を機にメンタルヘルスという問題が、ようやく前景化しはじめた」ということになります。
──実際そうなんですか?
例えば、アフリカの現状をレポートした〈What it took to spark a mental health reckoning for Africa’s doctors〉という記事は、これまでなかなか政策課題として取り上げてもらえなかったメンタルヘルスの問題について、パンデミックを機に、対策やインフラの整備に目が向けられるようになったことを伝えています。ケニアなどでは、昨年末から、自殺者の増大が大きな問題としてクローズアップされていたそうですが、政府の危機感が、COVID-19によって高まったとされています。

──いま、インフラとおっしゃいましたけれど、メンタルヘルスにおいて必要なインフラって例えばどういうものなのでしょう?
なんらかの助けが必要なときに、助けを求めることができる場所やサービスがあるということになりますが、〈Covid-19’s hidden mental health crisis〉という記事によれば、アメリカの場合、なんらかのメンタルな変調を来たしたときに、多くの人があてにしてしまうのが、アルコールであったりオピオイドのような薬物であることが明かされていますが、これはコロナ以前からアメリカでは深刻な問題になっていたものですが、それにコロナは拍車をかけています。
アメリカでの統計によれば、だいたい20%の人がメンタルヘルスに問題を抱えていると言われていますが、COVID-19下の調査では、パンデミックが自分のメンタルに悪影響を及ぼしていると考えている人が、45%にまで上昇したとも明かしています。
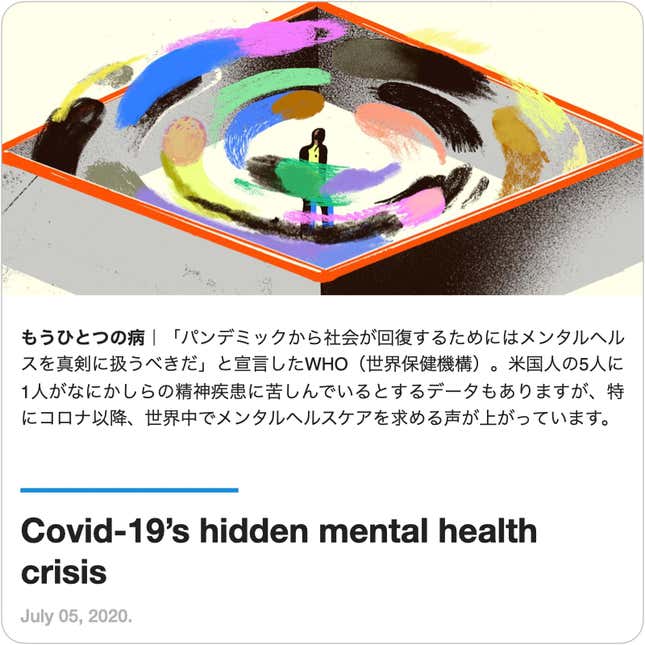
──ものすごい上昇率ですね。でも気持ちはたしかにわかります。経済的なダメージがそこに重なったら、平常ではいられないですよね。
そうしたなか、「The Disaster Distress Helpline」のような、いわゆるコールセンターへのアクセスが50%以上増加したともあります。また、COVID-19は「遠隔医療」の解禁・一般化を大きく後押ししていますが、〈Teletherapy is finally here to stay〉という記事では、電話やオンラインによる遠隔の問診やカウンセリングの方が、対面で行うよりも効果が高いという調査結果も明かしています。

オンラインによる「テレヘルス」サービスは、これから行政上の重要なインフラになっていくでしょうし、民間においても、この領域のサービスへの需要は大きくなっていくかと思います。〈Covid-19 is exposing the inequality of mental health care access for essential workers〉という記事内ではGingerというメンタルヘルスソリューション企業が、いわゆるフロントラインワーカーを従業員として抱える100以上の企業や組織にサービスを提供していることが報告されています。
──それはどういうサービスなんですか?
基本はチャットボットを使った応答システムのようですが、それ以外にもヘルスコーチングのプログラムなどもあるようで、冒頭の話に戻りますと、これからタレントやアーティストのエージェンシーで働く人は、こうしたコーチングを受けたほうがいいのではないか、と思ったりするんですね。というのも、メンタルヘルスの問題は、それが「パンデミックである」と言われている通り、ある種の伝染性をもっているからで、COVID-19下で、大きく問題となっていたのは、市民全体のメンタルの問題もさることながら、医師やケアワーカーなどのメンタルヘルスなんですよね。
──それはそうですね。人のケアをする仕事の人たちが受けるストレスは、生半可なものではないでしょうし、メンタルな部分に限らず、現場の方たちの“ヘルス”が崩壊したら、患者が殺到する以前に、医療崩壊ですもんね。
おっしゃる通りですよね。どこで読んだ記事かは忘れてしまいましたが、英国のケアワーカーがあまりの激務と、数多くの死を間近で見すぎたことで、「もうこの仕事は辞める」と語っていたのが印象に残っています。それはもはや単なるメンタルイシューではなく、エッセンシャルワーカーと呼ばれる人たちが、待遇面や福祉面でも劣悪な状況に置かれれば置かれるだけ、システムとして弱体化していくことになりますので、システムの崩壊を語るなら、それは内部から崩壊していくことにもなりかねません。

──かなりシビアな悪循環ですね、それは。
先の記事、〈Covid-19 is exposing ~〉では、エッセンシャルワーカーになればなるほど、メンタルケアへのアクセスから遠ざかっていることが明かされています。先に挙げたアフリカのレポートにおいても厳しく指摘されていることなのですが、「メンタルヘルスの状態に困難を抱えている人ほど、過度な人権侵害を頻繁に体験することになる」とある通り、メンタルヘルスの問題を放置することは、社会における格差を広げ、すでに奴隷的な状況にある人を、精神的に追い詰めることで、さらに奴隷的な環境へと追い込むことになりえるということなのだと思います。
──深刻ですね。
ですね。また同時に、それは、ケアシステムによる診断を受けたことがない人たちであるということも指摘されています。自分がなんらかの困難を抱えていると認識し自ら助けを求める人たちは、可視化されているという意味で、なんらかのサポートが可能となりますが、実際はそうでない人たちがたくさんいるわけで、記事は、変化の兆候がなかなか察知されない高齢者や、学校のリソースにしか頼ることのできない若年層、またエッセンシャルワーカーたちが、そうした対象になりうると警鐘を鳴らしています。

──日本でも、引きこもりが100万人にも上り、そのうち実は中高年が60万人を占めるという衝撃的な数字が昨年くらいに報道されていましたが、そうした問題と完全にオーバーラップする話ですね。
その報道がされたときに、中高年の女性の動態がまったく見えていない、という話を読んだ記憶がありますが、たとえば近所から、「ほとんど家から出てこない」と言われる女性がいたとして、その方が、ただ家にいるのが好きな主婦なのか、あるいはなんらかの問題を抱えているのかがまったく見えないそうで、そうだとすると、100万人という数字は実際よりも少ない見積もりである可能性がある、と言われていたはずです。
──聞けば聞くほど、やはり重大な社会問題ですね。
もっとも、この問題は、さっきお話したようなやり方でインフラを整えればそれでいいのかといえば、決してそうではないというところが難しいところだと思います。
──と言いますと。
これは、以前自分が書いた文章ですが、孤独、およびメンタルヘルスという問題の困難は、こういう言い方で説明できるのではないかと思います。
「『孤独』は、これまでのようなトップダウンの配給型のソリューションがまったく役に立たない課題だ。『孤独な人に行政が友だちをつくってあげることはできない』。クラウチ大臣はこれまでの行政のアプローチの限界をそんな言い方で表した」(『次世代ガバメント』若林恵・編)
──ああ、なるほど。ほんとですね。これは難しい。
これまでの行政府のあり方の限界が、ここでは一気に露呈するわけですが、それでも英国政府は、その課題にどう戦略的に取り組むかについて、詳細な政策立案書〈A connected society: A strategy for tackling loneliness〉(Department for Digital, Culture, Media and Sport)を提出していますが、取り組むにあたっての考え方や政府としての構えを、こんなふうに取りまとめています。
- ビジネス、医療機関、地方政府、ボランティア組織、市民社会と協働すること。政府はそれらをとりもつ重要な媒介者であると考えること
- さまざまな実験を繰り返し行い、そこから学ぶこと。現状のデータやエビデンスは十分でないと常に認識すること
- 部門、領域横断的で横串のアプローチが必須
- 何が人を孤独に陥らせ、そこからの脱却を可能にするトリガーになるのかを重視し予防的な施策を講じること
- 孤独という課題のもつ主観性や複雑さを十全に鑑みて、パーソナライズされたローカルなソリューションの重要性を認識すること
──社会全体として取り組まないとどうしようもない、ということですね。
この問題が及ぶ範囲は保健・医療政策、労働政策、経済政策、都市政策、文化政策にまで及んでいまして、逆にいえば、現在、さまざまな国や都市で行われている、新たな社会システムの構想や計画は、そうやってみるとすべて、市民の広義の「ウェルビーイング」を軸に展開していて、そのなかで「メンタルのウェルネス」は中心的な課題に据えられていることが見えてくるはずです。前回のお題の「通勤」や「自転車」といった話も、実は背後には、メンタルヘルスをめぐる課題が控えているんです。
──スマートシティとか「ソサエティ5.0」みたいなキャッチフレーズのなかで、そのイシューはまったく論点になっていない気がしますね。
多少は触れているかもしれませんが、COVID-19を受けても、そうした問題が浮上しているという感じはあまりしませんね。パンデミックによる経済封鎖によって自殺者が多数出ている、といったニュースもいまのところ聞こえてきませんし、なんとなく社会としては大丈夫という感じなのかもしれませんが、冒頭の誹謗中傷によって病んでしまった方の記事にある通り、そうした被害はあるのに警察などがそれに対応してくれないという事実があるなら、問題がただ可視化されずにいるということにすぎない可能性も大きいですよね。

──同調圧力のなかで声をあげたくてもできない、みたいなこともありそうです。ちなみに、今回のGuidesの各記事には、文末で支援ホットラインが案内されていて、メディアとしてもどれだけ深刻に捉えているかがわかりますね。また、下手をするとアフリカのように「メンタルヘルスの状態に困難を抱えている人ほど、過度な人権侵害を頻繁に体験することになる」というダウンスパイラルがどこかで発生している可能性もありそうです。
問題を可視化できないと対処もしえないというのは、まさに“パンデミック”ですよね。ただ、先ほどの英国の立案書にもある通り、メンタルヘルスの課題は、非常に主観的なものであるので、外から“客観的に”“診断する”ということが、どこまでできるのかという問題もありますので、近代医療の考え方に従って、メンタルに困難を抱えている人を「病人」と認定することの妥当性や是非も考慮しなくてはいけません。
言うなれば、これまでの行政や企業が慣れ親しんできた、課題を“外科的”に取り扱うやり方ばかりに頼っていると、事態はむしろ悪くなりそうに思いますので、まずは、それが簡単に解決できる困難ではない、ということをキモに命じておくのがよさそうです。
──その上で、実効的なソリューションを長期、短期の双方で考案しなくてはならない、と。
と思います。そうでないと、言うのが簡単で実効力もありそうに見える「排斥」というソリューションばかりが幅を効かせることになって、社会の分断が一層深まり、結果、人びとの精神的困難は、より深まることになってしまうのではないかと個人的には危惧しています。
──怖いですね。
ほんとに。怖いです。
若林恵(わかばやし・けい) 1971年生まれ。『WIRED』日本版編集長(2012〜17年)。2018年、黒鳥社(blkswn publishers)設立。著書『さよなら未来』のほか、責任編集『NEXT GENERATION BANK』『NEXT GENERATION GOVERNMENT』がある。NY在住のジャーナリスト 佐久間裕美子とともホストを務めるポッドキャスト「こんにちは未来」は、書籍化が決定(7月末刊行予定)!
若林恵さんによる本連載は、毎週末お届けしています。Quartz Japanメンバーには、過去の配信記事もご希望に応じてお送りしています。下記フッター内のメールアドレス宛てにお問い合わせください。
このニュースレターはSNS👇でシェアできるほか、お友だちへの転送も可能です(転送された方へ! 登録はこちらからどうぞ)。Quartz JapanのPodcastもスタート。Twitter、Facebookもぜひフォローを。
