Deep Dive: Impact Economy
始まっている未来
[qz-japan-author usernames=”qzdotcom”]
自然を「資本」として考えると、気候変動にまつわるアクションもビジネスとして捉えやすくなるかも知れません。毎週火曜の「Deep Dive」では気候変動を中心に、いま世界が直面しているビジネスの変化を捉えるトピックを深掘りしています(英語版はこちら)。

The true wealth of nations
モノ、ヒト、自然
アダム・スミスは『国富論』で、世界を「物的資本(physical capital、機械や工場)」と「人的資本(human capital、能力や経験、知識など)」という2種類の資本に分けて説明しました。しかし「自然資本(natural capital)」に言及することはありませんでした。
とはいえ、スミスが、わたしたちに食糧と避難場所を与えてくれる自然が人類の繁栄の鍵となることを理解していなかったわけではありません。現在、78億人に上る地球の人口は、スミスが想像していたよりはるかに多くのエネルギーと資源を消費していますが、経済学者たちは自然資本という概念でもって、その恩恵をより多くの人が理解できるかたちで提示しようとします。
自然資本(きれいな水や空気など自然によって得られるサービス)の価値は総額で年間160兆ドル(約1京6,735兆円)に上ります。自然が与えてくれる財やサービスを、銀行預金から得られる利子のようなものだと考えてみましょう。人類は自然という銀行口座にある資産をあっという間に使い果たし、赤字に転落しようとしている状況にあります。
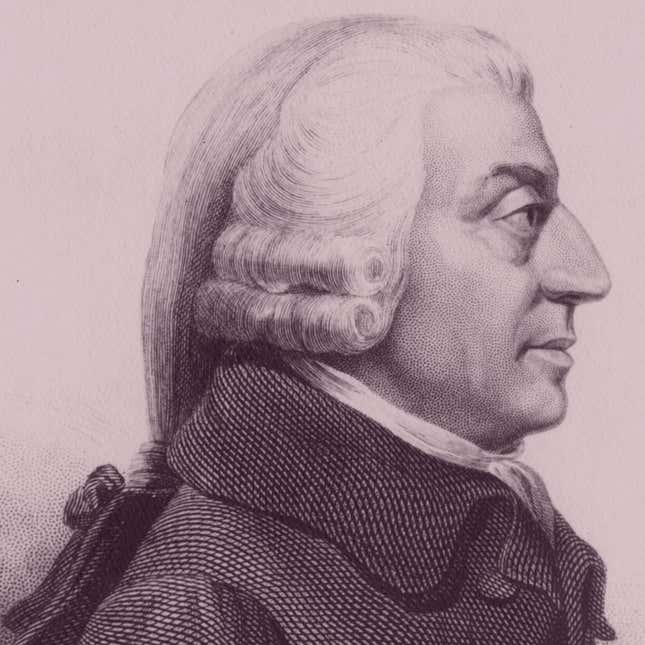
BY THE DIGITS
数字でみる
🧮 2.3ヘクタール:生物学的に生産力のある空間(耕作可能な土地、牧草地、森林、海洋)を地球人口で割ったときの1人当たりの面積(数字は1997年のもの)
🏕 1.2ヘクタール:地球人口が2100年に109億人に達した場合の1人当たりの面積
🏘 4.2ヘクタール:平均的な人間がものやサービスを消費することで使う地球の生産面積。ただし、大半は先進国の国民によるもの
⏳ 5兆〜23兆ドル(約523兆〜2,407兆円):自然生息地の減少や環境悪化によって毎年失われるサービスの規模
🌏 1.7個:現在の自然資本の消費レベルを維持するために必要な地球の数
💸 86%:自国の自然資本の能力を超えた生活水準を送ることで「環境赤字(ecological deficit)」になっている国の割合
🏝 57億ドル(約5,970億円):グレート・バリア・リーフがオーストラリア経済にもたらす年間の貢献額
EXPLAIN IT LIKE I’M 5!
1分で説明する
カール・マルクスからジョン・メイナード・ケインズまで、経済学者たちは資本を「生産の手段」(工場や機械)と、それを利用する「人間の能力」(スキルや専門知識)とに分けて扱ってきました。
こうした考え方は財とサービスの流れを予測するにはいいかもしれませんが、しかし、これらすべてが依拠する自然という要素を無視しています。
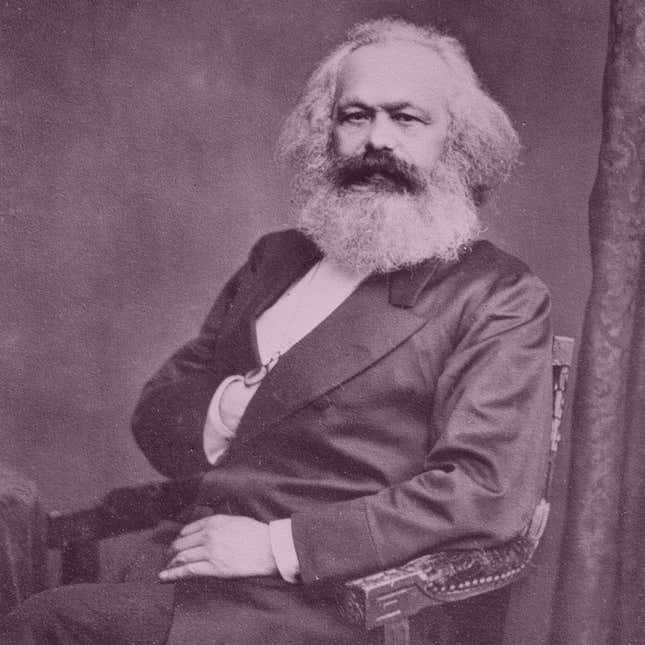
1973年、エルンスト・フリードリッヒ・シューマッハー(Ernst Friedrich Schumacher)は、その著書『スモール イズ ビューティフル(Small Is Beautiful)』のなかで初めて自然資本という言葉を使いました。シューマッハーの言う自然資本とは、土、空気、水、動植物、そしてこれらが提供するエコシステム全体のことです。このエコシステムは人間や野生生物が受益者の信託基金のようなもので、わたしたちはこれなしには生きていくことができません。
経済学では100年近くにわたり、国内総生産(GDP)をもとに国の豊かさを考えてきました。しかし、ここに来て「富」を表す計算式が間違っていたのではないかという議論が巻き起こっているのです。大気汚染や海洋汚染と引き換えに経済成長を手にしても、それは本当に豊かになったこと意味するのでしょうか?
国連の「包括的な豊かさに関する報告書(Inclusive Wealth Report)」、持続可能な経済福祉指標(Index of Sustainable Economic Welfare、ISEW)、真の進歩指標(Genuine Progress Indicator、GPI)など、富を測るための新たな尺度が提案されつつあります。これらの指標に基づけば、GDPが大幅に上昇しても、並行して自然資本が破壊されれば実際には思っているほど豊かにはなっていないのです。
economists gotta try
試算してみる
自然のように価格をつけることのできないものの価値を測るのは不可能だという反論はありますが、とにかくやってみなければ始まりません。
生態経済学者のロバート・コンスタンザ(Robert Costanza)と研究チームは2011年に科学誌『Nature』に掲載された論文で、自然資本によるサービスの総額は少なくとも160兆ドル(約1京6,735兆円、インフレ調整済み)に上ると試算しました。これは数十年前から3倍以上に拡大しています。ただ一方で、自然生息地の減少や環境悪化によって毎年5兆〜23兆ドル(約523兆〜2,407兆円)の自然資本が失われているとされてもいます。

金銭換算する以外に自然資本を数値化する方法として、「エコロジカル・フットプリント(ecological footprint、EF)」という指標があります。これは人間の活動に必要な自然資本の量とそれを維持するためのエコシステムを計算することで、自然資本をどれだけ消費しているかがわかるようになっています。
シンクタンクの新経済財団(New Economics Foundation)によると、人類の現在の消費レベルを支えるためには地球1.7個分の生産力が必要です。この数字は人類の自然資源需要の合計を地球が生み出す資源で割ることで算出され、拡大の一途をたどっています。
完全に正確な数字だとは言い切れませんが(生態系の破壊を計算する方法に不確実な要素があります)、人類は間違いなく地球1個では賄い切れないほどの資源を消費しているとされています。
BRIEF HISTORY
歴史を振り返る
1776年:アダム・スミスが『国富論』を発表。ここでは自然資本の初期コンセプトが農業と結び付けて語られています。
1937年:全米経済研究所(NBER)に所属する経済学者サイモン・クズネッツ(Simon Kuznets)が、初めてGDPの計算方法を考案。ただし自然資本には触れていません。
1970年:人類による年間の自然資源の消費量が地球の再生能力を超過。グローバル・フットプリント・ネットワーク(Global Footprint Network)によれば、この年のアース・オーバー・シュートデイは12月29日と、初めて年内に食い込みました。
1973年:E.F.シューマッハーが『スモール イズ ビューティフル』で自然資本という用語を提示。シューマッハーは、経済学者たちの言う所得拡大とは、実は地球の資源を消費していることにほかならないと指摘しました。
1989年:生態経済学者ハーマン・デイリー(Herman Daly)と神学者ジョン・コブ(John Cobb)が、自然資本を含めた豊かさの指標である「持続可能な経済福祉指標(ISEW)」を提唱。これはその後、26項目で経済や社会、環境を評価する「真の進歩指標(GPI)」につながっていきます。
1995年:メリーランド州がGPIを採用。2012年にはバーモント州もGPIを使うようになりました。
2006年:中国が「グリーンGDP」を組み込んだ経済報告書を発表。環境破壊を考慮すると、2004年の中国のGDPは3%縮小しました。
2012年:世界銀行の一部である国際金融公社を含む43の機関が、民間企業に環境関連のデータを公表するよう提言。各社の自然資本への依存度と、企業活動によってどれだけの環境破壊が起きているかを明らかにするよう求めました。また、この年にはアフリカの10カ国が「持続可能性に向けたハボローネ宣言(Gaborone Declaration for Sustainability)」を採択。政策決定に「自然資本の価値を組み入れる」ことを決めています。
2016年:自然資本会計の共通の枠組みとなる「自然資本プロトコル(Natural Capital Protocol)」が完成。企業が「自然資本に及ぼす直接的および間接的な影響と依存を特定、計測、評価する」ことを目的としています。
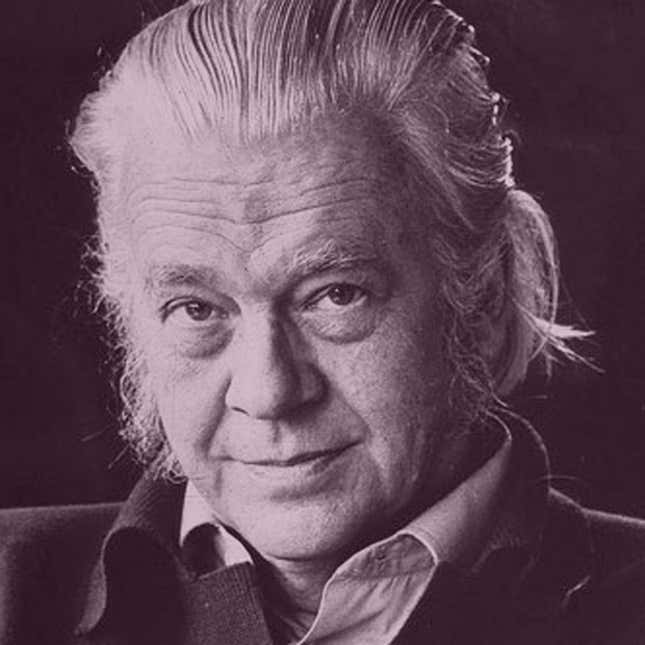
COMPLETELY UNFUN FACT
最後に…不都合な真実
年初からのわたしたちの資源の消費量が、地球の1年間の再生能力を超過(オーバーシュート)する日が「アース・オーバーシュート・デイ」です。1970年には12月下旬でしたが、今年は8月22日になっています。
今年は新型コロナウイルスのパンデミックの影響を加味するために計算方法が少し変更されていますが、状況が好転したということではありません。感染対策による経済活動の鈍化で大気汚染などは一時的に軽減しましたが、すでに以前の水準に戻っているだけなく、今後はさらに悪化していく見通しです。
Column: What to watch for
掘り出せ、リチウム

電気自動車(EV)の普及に欠かすことのできないもののひとつがリチウム、「ホワイトゴールド」とも呼ばれる水に浮くほど軽い銀色の金属です。リチウムは、EVに搭載するバッテリーの重要な構成要素となりますが、世界各国がこの金属の供給を確保しようと奔走しています。
世界のリチウムの大半を供給しているのは南米です(米国の輸入の93%はアルゼンチンとチリからのもの)。米国は世界の推定埋蔵量7,300万トンの10%を保有していますが、国内で開業している鉱山はひとつだけで、バッテリーのリサイクル施設もオハイオ州の1件を数えるのみです。
今年1月、米国土地管理局はネバダ州に位置する露天掘り鉱山に承認を出しました。カナダのLithium Americas社が運営するこの鉱山は、数年後の操業開始が見込まれていますが、少なくとも40年間の操業が期待されています。
(翻訳:岡千尋、編集:年吉聡太)
🎧 月2回配信のPodcast。最新回では、編集部の2人がいま話題の音声SNS「Clubhouse」などのトピックについて雑談しています。Apple|Spotify
👀 Twitter、Facebookでも最新ニュースをお届け。
👇 のボタンから、このニュースレターをTwitter、Facebookでシェアできます。ニュースレターの転送もご自由に(転送された方へ! 登録はこちらからどうぞ)。
