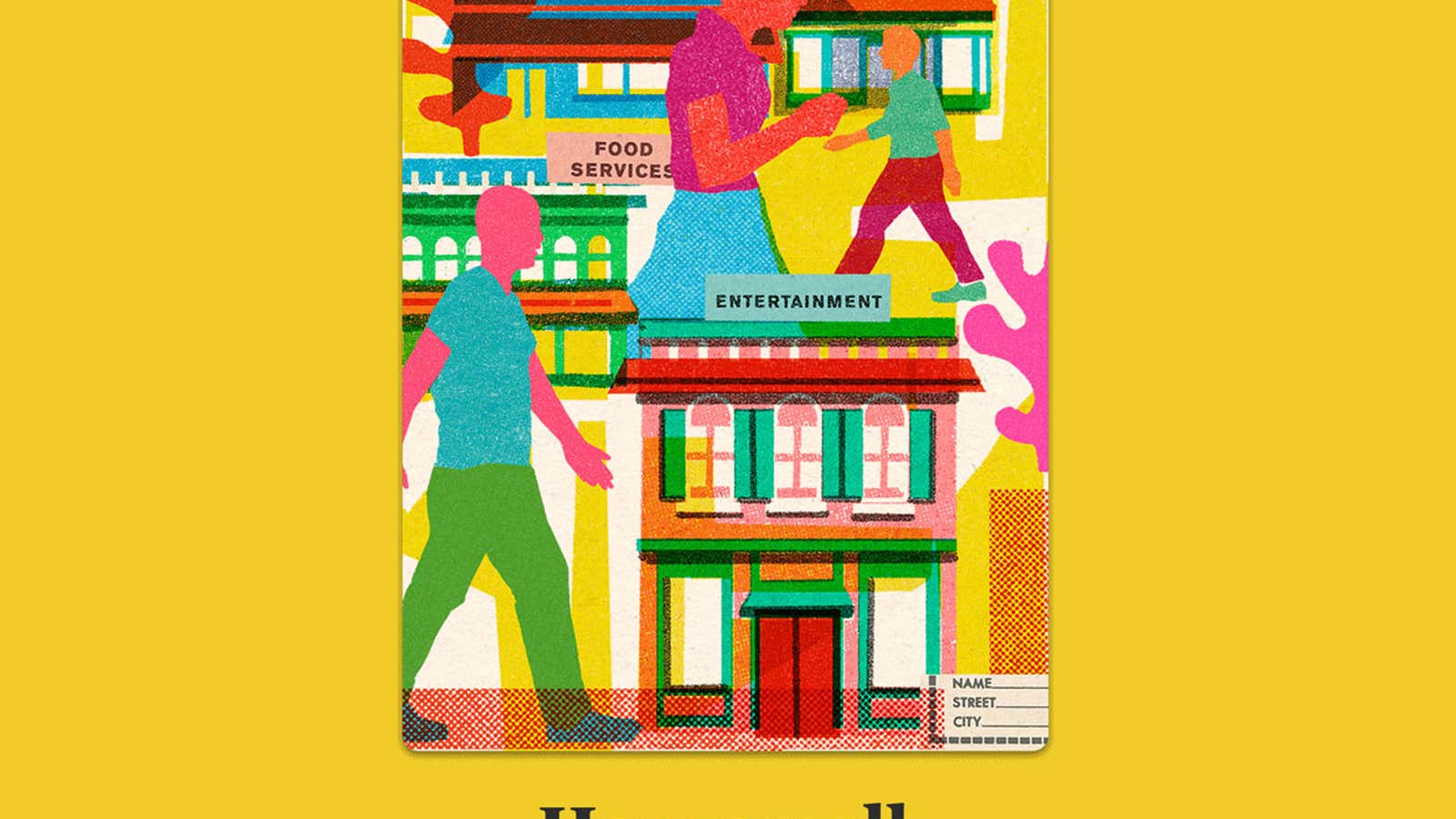A Guide to Guides
週刊だえん問答
世界がいま何に注目しどう論じているのか、米国版Quartzの特集〈Field Guides〉から1つをピックアップし、編集者の若林恵さんが解題する週末のニュースレター「だえん問答」。今回は先週の前編につづき「スモールビジネス」の後編をお届けします。前編ならびにQuartzの原文(英語)、そしてプレイリストとあわせてお楽しみください。

このニュースレターは、現在、期間限定で配信から24時間、ウェブ上で無料で閲覧できます。ニュースレター末尾のボタンからぜひシェアしてください。
How small business bounces back
スモールビジネスの希望
──今回は前回に続いて「スモールビジネス」がお題でして、早速本題に行きたいところではあるのですが、とはいえ今回もやはりオリンピックの話題に触れないわけにも行かなそうです。
そうですか。
──というのも、IOCが開催に向けて強硬な姿勢を強めていまして、ここのところの発言は、なんと言いますか、いよいよ、隠し立てすることもなく、本性をむき出しにしてきたように見えます。
幹部が「世論に動かされることはない」と言ったとする一連の報道についてですよね。
──さすがに頭来ちゃいましたね。というか、あからさますぎませんか。
そうですね。はなからそこまで配慮する気がなかったことを明かしたようなものですからね。
──改めてオリンピックって何のためのものなのか、考え込んでしまいますね。
それこそ『週刊文春』の最新号において、沢木耕太郎さんが寄稿し、今回のオリンピックには「開催の『大義』がない」と書かれていましたが、それは本当にそうなんですよね。沢木さんは、クリント・イーストウッド監督・主演による映画『リチャード・ジュエル』に触れ、アトランタ五輪開催中に起きたテロ事件と、その重要参考人に仕立てあげられ世間から誹謗中傷の総攻撃にあった会場警備員に起きたことを振り返りつつ、アトランタ五輪が、そもそもアメリカのテレビネットワークが半ば強奪するように開催権を得たことなどを紹介していますが、それを読んで思い返したのは、1968年のメキシコ五輪の開催直前に起きた「トラテロルコの虐殺」という事件です。
──そんなのがあるんですね。
はい。これをわたしは山本敦久さんの『ポスト・スポーツの時代』という本で知ったのですが、メキシコ五輪の開催10日前に起きた事件でして、オリンピックの開催反対をひとつのスローガンとした、反独裁、反官僚主義、民主化を謳った1万人ほどのデモ隊を突然警官と軍隊が包囲し発砲、約2,000人が投獄され、300人に上る死者が出たとされているそうです。
──ひどいですね。
本は、ジョン・カーロスというアメリカ人陸上選手の手記から、当時の状況を語った一節を紹介しています。こういうものです。
「メキシコ市は、大きな緊張とトラウマのなかにあった。一触即発の状態が続いていた。アメリカチームがオリンピックに行く直前、メキシコでは大虐殺が行われたのです。数百人の学生や若いアクティヴィストが殺されました。メキシコには貧困にあえぐ人たちがあまりにも多いという事実に我慢できなくなった人々は、オリンピックで得た収益がどう使われるのか、貧しい者たちの援助にそうした資金があてられるのかどうかを問題にしていたのです。当局は、オリンピック開催の場所を確保するために、貧しい者たちを立ち退かせようとしていました。多くの若者が瞬時に命を落としたのです。……あらゆる手段を使って排除の命令がくだったのです。…….大勢の若者が殺されました。遺体を炉に投げ込み、灰にしました。そこに入りきらない遺体は海に投棄されたのです」

──何だか身につまされる話です。これを読むと、もはや日本国民も、「オリンピック開催の場所を確保するために」「立ち退かせようと」されている側なのだな、という気持ちになってきます。つまり、わたしたちは、どこかで自分たちの「安心安全」をオリンピックが脅かすものだという理解のなかにいますが、開催したい側からすると、むしろわたしたちが排除の対象であり、隔離の対象なんだなと。
はい。ちなみに、先の引用が意味あるのは、これがジョン・カーロスという選手の回顧だからなのですが、彼がどういう人かと言いますと、まさに、このときの五輪の表彰台で黒い手袋をして拳を突き上げるという、五輪における大きなモメンタムを刻んだ出来事の主役であった人物なんです。
──ああ、そうか。
はい。ですから、このときの「拳」には、母国における人種差別に対するプロテストだけではない、より広範なプロテストが含まれていまして、そこには当然、トラテロルコ広場で「排除」された人びとへの連帯の意も含まれていたんですね。
──オリンピックのありようそのものに対する批判でもあったと。
であればこそ、このとき拳をあげたカーロスとスミスのふたりの黒人選手は即刻選手村から「排除」されましたし、同じ表彰台に銀メダリストとして上り、拳こそあげなかったものの「人権を求めるオリンピックプロジェクト」(OPHR)という組織のバッジをつけてカーロスとスミスへの連帯を表明したオーストラリア代表のピーター・ノーマンは、以後IOCのブラックリスト入りし、オリンピックに関わることは二度と許されませんでした。
──1968年のことですから、50年以上も前のことですが、構造的には何も変わっていないという感じなんですかね。
この話が、2021年のいままた重要なのは、IOCが、この4月に五輪憲章の「第50条」という条項の運用の厳格化を表明したからなんです。
──へえ。それはどういうものなのでしょう。
これは競技内や表彰式において「あらゆる種類の政治的、宗教的、人種的プロパガンダをデモンストレーションすること」を禁止するものなのですが、4月の発表において、IOCは具体的に「Black Lives Matter」を明示しながら、そうした文言が描かれたものを着用することを禁じ、代わりに「平和」(peace)、「敬意」(respect)、 「連帯」(solidarity)、「包摂」(inclusion)、「平等」(equality)といった文言の使用を認めるとしており、さらに、この禁を犯したものには制裁を加えるとしています。
──五輪担当大臣が「絆」なんてことばを持ち出していましたが、「絆」も、まさにこの一群に連なるキーワードですね。
日本ではあまり報道はされなかったかもしれませんが、アメリカのオリンピック・パラリンピック委員会(USOPC)は、実は、2020年12月に選手による平和的なデモンストレーションへの制裁をやめることを発表し、さらに昨年8月に組織された「チームUSA人種と社会正義に関する評議会」(Team USA Council on Racial and Social Justice)は 、選手たちの言論の自由、表現の自由を侵害しているとの見解から、先の第50条の見直しをIOCに提起しています。
──それこそジョージ・フロイド事件を受けて、アメリカではスポーツ選手のアクティビズムが盛り上がってプロスポーツにおける「政治的表現」をめぐる態度が大きく変化しましたね。
NFLのコリン・キャパニック、アメリカ女子サッカー選手のミーガン・ラピノーや、女子ハンマー投げのグゥエン・ベリーらによって継承されてきた運動が、大坂なおみ選手に引き継がれていくなかで、昨年のBLMの運動がひとつの大きな転回点となったことでスポーツ界のアップデートが促され、その流れのなかでUSOPCの方針転換が起きたわけですが、IOCが、今年4月に行った発表は、そうした流れを真っ向から否定したものとなるわけですね。当然アメリカでは、選手たちの間から批判が出ています。
──ですよね。
『Woman’s Running』という主に陸上競技を扱うメディアの「オリンピアンたちはデモを禁じられた:でもそれを止めることはできない?」(Olympians Are Not Allowed to Demonstrate, But Will They Anyway?)という記事のなかで、2019年のパンアメリカ選手権の金メダルの表彰台で拳を突き上げ、12カ月間に同様の行為を行った場合には厳重処分を受ける可能性があるという「注意」を受けたグゥエン・ベリー選手は、表彰台やフィールドにおける表現の自由は「基本的人権の問題だ」と語っています。さらに走り幅跳びと400mリレーの五輪金メダリストで、先に紹介した「チームUSA評議会」のメンバーでもあるティアンナ・バートレッタ選手は、IOCの声明に、こう反発しています。
「評議会はIOCに対してデモを行うための『許可』を求めたのではありません。わたしたちが伝えたのは『あなた方はわたしたちのことが見えている? 競技をするのはわたしたちで、わたしたちがいるからこそイベントが成り立っているのに、本当にわたしたちのことが見えている?』ということでした。そして、その答えは『いいえ、見えません』だったのです」
──全面対決という様相ですね。
はい。IOCのアスリート・コミッションは「言論および表現の自由は普遍的に認められた基本的人権ではあるが、無制限ではない」としていますので、かなりの頑さがうかがわれます。先のベリー選手は、そんな姿勢に対して、さらにこんなことばをぶつけています。
「わたしのことばを、わたしが自分が信じることのためにどのように戦うかを、あなた方はコントロールすることはできません。なぜならあなた方はわたしの人生を生きていないからです。それがどんな人生であるか想像もつかないのです。わたしのナラティブをコントロールすることも、それをコントロールすることで自分たちの都合のいいように資本化することもできません」

──激しいですね。五輪が開催されるとなると、間違いなく悶着が起きそうな雲行きですね。
アメリカの五輪パラリンピック委員会が、アメリカ選手団をバックアップすることになれば、これはかなり大規模な鍔迫り合いともなりそうですね。さらに、こうした事態が起きたとすると、昨年BLM運動への連帯を示したスポンサー企業も、困った立場に立たされるだろうとも指摘されています。
──たしかに。一度、BLMへの連帯を表明したのであれば、オリンピックでも支持しないわけにはいきませんよね。
「Color of Change」という組織は、「スポンサー企業が黒人への連帯を表明している以上、IOCの抑圧的なステートメントは意味をなさない。スポンサー企業はブラックコミュニティとの約束をいまこそ果たすべきだ」というツイートをし、コカ・コーラ、VISA、Hershey’s、トヨタ、Procter & Gamble、Ralph Lauren、Samsungを名指ししています。
──うーん。開催されたらされたで騒然としそうですね。
ただ、2004年の400m×4リレーの金メダリストであるムーシャウミ・ロビンソンは、カーロス/スミスにはじまる沈黙のプロテストは、実は「プロテスト」ではないのだとも語っています。彼女はこう言います。
「それは畏敬の念なのです。『わたしたちは、わたしたちの前にいた人たちが多くをくぐり抜けてきたからこそ、こんな遠くまで来ることができたのだ』と、先達たちの栄誉を称え、感謝するための時間なのです」
──いまオリンピックが、世界中のアスリートが人種や宗教を問わず参加ができる「平和の祭典」と威張っていられるのも、実際は、過去のアスリートたちが、そうやって権利を主張し、拡張を勝ち取ってきたからだというわけですね。
はい。今回の記事でも、カーロス/スミスの残したレガシーは盛んに語られていまして、「彼らの行動があったからこそ自分たちはここにいる」という感覚は極めて強くありますし、先のロビンソン選手は、そうやってレガシーを観客も含めて確認しあうことは五輪憲章の趣旨にも叶うものだと語っています。
──ほんとですね。
冒頭に紹介した『ポスト・スポーツの時代』は、カーロス/スミスがもたらした功績をこんなふうに解説しています。
「ボイコットせずに、参加することで何ができるか。オリンピックを外部から批判するのではなく、その内側から批判することは可能か。カーロスたちの闘争の方向は、ボイコットから参加へとシフトした。支配的なものの内部で、支配に対抗するという政治のスタイルは、現在のキャパニックたちの動向とも共通するものであるし、近年のオリンピックのなかにも同様の動きが散見される」
──2022年の北京五輪のボイコット運動について、IOCは「ボイコットはなにも解決しない」といった言い方でボイコット論を一蹴しましたが、カーロス/スミスから大坂なおみ選手にまでいたる運動の様式は、そのIOCのスタンスを逆手に取ったようなところもありますね。
そうですね。山本敦久さんは、そうした運動の大きなうねりが「スポーツ界、さらには社会における人種差別、性差別、同性愛嫌悪に抗議する多様な人々を結びつけ、新たな抗議の方法を創案するネットワーク型のプラットフォームを作り出している」と解説しています。
──オリンピックというそれ自体が巨大な運動でありプラットホームであるものを、ある意味、逆用するようなかたちで、そこに主催者の意図をかいくぐりはみ出していきながら、そこに別のネットワーク型プラットホームを形成していくということですね。
おっしゃる通りですね。ここで面白いのは「プラットホーム」というものがもつ両義的な側面ですよね。つまり、運営者がいくらそれを管理的に運用したいと思っても、それがプラットホームである以上多様な人びとが集まってこないことには意味がないわけですから、そのなかで起きる想定外の動きを管理しきることが、とても困難でもあるわけですね。それを嫌がって抑圧的に動けば、そのなかにおいて反発が高まって自壊を招くことにもなりかねないのは、おそらくテックプラットホームにおいて起きている問題と同じで、それはちょうど、今回の〈Field Guides〉でもスモールビジネスとテックサービスの関係性とも相似形であるようにも思います。
──お。いきなり話をつなげた(笑)。
若干飛躍があるかもしれませんが、オリンピック選手の戦い、例えばテイラー・スウィフトのようなミュージシャンがSpotifyに対して仕掛けた戦いなどとも相似形のものがあるような気がしなくもありません。それは、経済が、ワーカーをどんどん個人事業主化させながら、テックプラットホーム内で、その仕事を管理し、最悪「農奴化」していく状況に対抗する意味でも、とても重要な参照点になるのではないかと思います。

──そうですか。
前回・今回の〈Field Guides〉のタイトルは「スモールビジネスはいかに復興するか」(How small businesses bounces back)でして、記事のひとつに、「テック企業はスモールビジネスから得た分を返しているか?」(Do tech companies give back to small business as much as they take?)という記事がありまして、そこでは、スモールビジネスにとってサードパーティのテックサービスが不可欠な状況を、以下のように言い表しています。
「オーディエンスにリーチするためにはFacebook、Google、Amazonにお金を払うことなく事業を転がしていくことは難しい」
──そうですよね。
そして、それがもたらしている事態をこう簡潔に整理しています。
「スモールビジネスはテック企業にとってビッグビジネスである」

──前回お話された、コーポレート・エコノミーからシビック・エコノミーへの転換を促していくのがデジタル・ネットワークであるとして、そこには企業プラットフォーマーが関与してくるので、場合によってはスモールビジネスは、そこでは格好の搾取の対象となってしまい、より過酷な状態におかれる可能性があるということですよね。それがAmazonやUberの問題を生み出しているわけですもんね。
はい。Uberのような個々のサービスであれば、まだ「嫌なら他のサービスに乗り換える」こともできるかもしれませんが、例えばAWSのようなクラウドサービスに行政組織までもが依存してしまうなかでは、「公共」の空間でさえ最終的にはテック巨人の管理下に置かれることが発生しうるわけですね。これはとても危険なことで、日本でもつい最近Salesforceのシステムがダウンしてしまったことで、ワクチン接種の予約システムが不通となる事態が起きましたが、こうしたことが起こるにつけ、プラットホーム上において、個々のサービス提供者は「まな板の鯉」にすぎないということを実感させられます。そういう意味でも行政府のLINE依存は、望ましいものとも言えないのですね。ゆくゆく国営化でもしようと考えているのなら、また若干話は変わってくるのかもしれませんが。
──いずれにせよ、そうした環境は、おそらくより一層強化されていくのでしょうから、逃げ道はどんどんなくなっていくことになりますね。
前回、シビックエコノミーというものについてお話ししたなかで、「消費者というものは消えて、ファンダムだけが残る」状況がネット空間において進行していることに触れましたが、これは、ある意味プラットホーム内で「消費者」という存在が質的な変化を遂げているということを意味していまして、そこには、もしかしたら、そもそもの対立の基軸となっている「生産者・サービス提供者」と「消費者・ユーザー」という区分けと、そこに介在する収奪の構造を無効化してしまう可能性があるのかもしれません。
──そうですか。
前回きちんと紹介できなかったのですが、中国の「Xiami Music」という音楽ストリーミング・アプリのUXを解説した「中国の音楽アプリを拝見:Xiami Music」(A look at a Chinese music app: Xiami Music)という記事に触れました。Xiami Musicはアリババが買収したあと今年になってサービス終了してしまったのですが、記事に書かれている内容は、それこそ「消費者はいなくなってファンダムだけがある」世界において、ビジネスやサービスがどういうものとなっていくのか、そのベーシックな視点を授けてくれるものではあると思いますので、解説させてください。
──ぜひお願いします。
記事は、まず、SpotifyやApple Musicといった配信サービスがいかに「Passive」(受動的)なものであるかを指摘するところからはじめています。もちろん能動的に、音楽を「探す」ことはできるのですが、そこから先は、基本的には、ただ「聴く」ことだけしかないんですね。
──まあ、そうですね。せいぜい、気に入ったものをソーシャルメディアに投稿したりするくらいです。
それが、このXiami Musicのサービス内では、ユーザー側が「色んなこと」ができるようになっていることに筆者は非常に感銘を受けることになります。
──例えば、どういうことですか?
一つひとつはつまらないことなんです。お気に入りの歌詞の一節を引用して「ポスター」をつくることができる機能であったり、好きな画像に文字を乗せて曲やアルバムを誰かにプレゼントする機能であったり、あるいはあるアーティストやアルバムが好きな人たちが集まって「パーティ」ができたり、といったことなんです。もちろんこうした機能が作動するためには、そもそもの前提としてソーシャル機能がありまして、ユーザー間でフォローしあうことで、フォローした相手がいま何を聴いているのか知ることができたりします。さらに、サービス内でトークンを用いた投げ銭などもできるようになっています。といった感じで、とにかく、ユーザー側がアプリ内で「色んなことができる」ように、「これ必要?」と思うような機能がてんこ盛りに盛られています。
──目新しいものではないといえばそうなのかもしれませんが、とはいえ、そうした機能がほとんどないようなサービスを使っている身からすれば、とても楽しそうです。
この記事の筆者もまったく同様の感想を漏らしておりまして、こんなふうに総括しています。
「Spotifyは言ってみれば個人主義的なアプリで、その体験はかなりスタティックだ。消費は一方通行で、ソーシャルの要素は友達のアクティビティを知ることができるくらいだ。対照的に、わたしが見たところXiami Musicは、音楽を中心に活気に満ちて、アクティブで、共生的(symbiotic)なコミュニティをつくりあげている」
──なるほど。
榎本幹郎さんが『音楽が未来を連れてくる』という本のなかで、中国のアプリに見られる、こうしたサービス設計の考え方を「ソーシャルミュージック」と名づけていますが、この考え方のキモは、ファンの心理を読み解きながら、ファンが求める「あんなことをしたい」「こんなことをしたい」といった願望を、ひとつずつサービスに置き換えていくところにあるのだと思います。
──ファンダムの「行動」を促すということですよね。
はい。この記事の筆者がSpotifyを「Static」と呼んだのは、そこに、まさに、人びとの「アクション」を誘発する機能がないことを指しているわけですね。
──面白いです。「消費者」は「ただ消費するだけの静的な存在」であるのに対して、「ファンダム」は「自分の『推し』をめぐってさまざまなアクションを発動する存在」だという切り分け方ができそうですね。
はい。これは、ここでも何度か語ってきたことかもしれませんが、かつてオードリー・タンさんが、デジタル社会においては「リテラシー」ではなく「コンピテンシー」が大事なんだとおっしゃっていたのですが、「スタティックな消費者」に求められたのが「リテラシー」であったとすると、「なにか行動をしたいファンダム」に必要なのは、行動を可能にするための「コンピテンシー」(やりたいことをやれる力)である、というふうに対比することもできるのかもしれません。
──そうか。先のアプリに搭載された機能は、別の言い方をすると、ユーザーの「あれがしたい、これがしたい」という欲求を行動に変えるための「コンピテンシー」を授けているということになりますね。
この間何度も引用させていただいて恐縮なのですが、田中絵里菜さんの『K-POPはなぜ世界を熱狂させるのか』が、その「熱狂」の理由を、「音楽でも、パフォーマンスでもなく、 5つの “バリアフリー”にあった」としているのは、こうした意味でも非常に鋭い指摘なんです。
その5つとは、
- お金:ライブに行くまではすべて無料
- 時間:いつからでも後追い可能
- 距離:どんなに遠くからでもリアルタイムで参加
- 言語:どんな言語にも翻訳されるコンテンツ
- 制約:ファンがどんどんシェアして広めていく
なのですが、ここで問題になっている「バリア」というのは、端的にいえば、「スタティックな消費者」が「アクションをするファン」へと変わることを阻んでいた障壁なんですね。ですから、その障壁をサービス面や制度面において壊したり下げたりしていくことが、ファンが主体的に「アクション」を起こすための「コンピテンシー」の獲得につながっていくことになるわけです。

──面白い。
こうやっていわば「参加型」のネットワークが形づくられていきますと、そこには生産・労働と消費という二項によって支えられた経済とは異なる経済圏が見えてくることになるわけですが、こうした経済モデルは、どこかにすでに存在しているのではないかと漠然と考えていましたら、いま仕事でご一緒しているロフトワークという会社の黒沼雄太さんという、かつて文化人類学を学んでいた面白い人に「コミケとアレッポのスークがそれですよ」と言われて、「ん? なにそれ」となったんです。というが、たまたま昨日のことだったんですが。
──いいタイミングでいい話が出てきますね(笑)。で、アレッポのスーク?
あまりに面白い話だったのでちょっと録音させていただいたのですが、こんな話です。
「コミックマーケットという文化は、シリアのアレッポという都市で行われていた経済と近い経済行動が行われていて、そこでは生産者と消費者は存在せず、商人と商人だけが存在します。コミックマーケットにも『売り手』と『買い手』は存在せず、そこでは売り手も買い手も等しく『参加者』と呼ばれます。で、売り手は『売る』ということばを使うことを禁じていまして、『頒布』『頒布物』という言い方をしています。これは頒布する者が『これは価値がある』と思っているものを発表する運動を指していまして、頒布を受け取る側は、「それに価値がある」と認める運動を行っている人たちと考えます。ですから、「これは価値がある」と思って頒布する人と、そこに価値を見出す人とが、そこで出会うということが最も重要な原理として保護されている空間で、そこで最も重視されるのは『どれだけ頒布できたか』ではなく、『どれだけそこで価値が認められたか』なんです。そこで『価値が生じる』いうことに作用しているのは、発見した人の『発見する』という労働と、頒布した人の『発表した』という労働によって価値が生まれているんです」
──ははあ。面白いですね。これは「推し」という概念が「経済行動」としてどういうものなのか、ということの説明にもなりそうですね。
黒沼さんは、こうした経済原理は、シリアの商人の世界にあったものだと語っていまして、参考書として中東現代史、イスラーム文化・社会論の黒田美代子先生の『商人たちの共和国:世界最古のスーク、アレッポ』、イスラム研究の第一人者であられる黒田壽郎先生の『イスラームの構造:タウヒード・シャリーア・ウンマ』、そして中沢新一さんの『緑の資本論』を薦めてくださったのですが、その場で購入したものの、残念ながらまだ届いていませんので、これから楽しみに読みたいと思っています。
──どれも勉強になりそうですが、その黒沼さんの語るところによれば、参加型の経済圏においては、全員が「商人」として、そこに参加することになるということなのだと思いますが、そう言われるとスモールビジネスの面白さや楽しさは、そこに「商人世界」といってイメージする猥雑さやダイナミズムが感じられるからなのだな、と改めて思いますね。
そうですね。かつて何かの本で「経済学の歴史は『商人』を経済から排除していく歴史だ」といったことが書かれているのを読んで、なるほどと思ったことがあるのですが、それが仮に本当だとするなら、わたしたちの経済が、生産と消費しかない極度に痩せ細ったものになってしまったことの理由も、なんとなく腑に落ちます。
──たしかに。
これもなんども引用していて恐縮なのですが、「働くことの人類学」というポッドキャストの第5話で、南フランスでズッキーニ農家をやっているモン人の調査をされている文化人類学者の中川理先生が、マーケットというものの重要性についてこんなふうに語っています。
「モンの人たちだけでなく、南フランスの農民一般にとって、市場というものは基本的にすごくいいものなのです。『市場は小さな者たちの自由を保障してくれる制度である』『だから守らないといけない』と彼らは言います。それに対して独占は悪いものと考えられています。
わたしたちは、市場万能主義イコール資本主義のように思ってしまいがちですけれども、彼らの頭のなかでは市場と資本主義のあいだには、かなりきっちりと線が引かれていて、市場はわたしたちのもの、資本主義は彼らのもの、と明確に分けています。ですからいま起きているのは、市場という『わたしたちの自由空間』に資本が入ってきて、自由を奪っている現象だと認識されているわけです」
──「わたしたちの自由空間」っていいですね。オリンピックの話に戻ってしまい恐縮ですが、築地市場もなんだか閉鎖的な感じの場所に移転してしまいましたしね。
それを移転させることによって、IOCや都や国が、なにを排除しようとし、何を守ろうとしているのかが、ちょっと見えてきそうな感じもしますね。
──遠大な話でしたね。
結局、〈Field Guides〉の個別の記事については触れられませんでしたが、今回の〈Field Guides〉は、スモールビジネスは「地域やコミュニティ」を守る社会的に大事なものだから大事なのだ、というのが基本的な論調で、それはそうだと思うのですが、それだけではやはり、その価値を支えきれないような気もして、あれやこれや考えてみたわけですが、個人的には、ちょっと面白い道行きをたどれて、発見もありましたし、楽しかったですね。
──相当あちこちに話が飛びました。
この1週間ずっと、Fatima Al Quadriというセネガル生まれのクウェート人で現在はニューヨークで活動する女性電子音楽家の作品をずっと聴いていまして、その彼女の最新作が、アラブの中世の女性詩人の詩をモチーフにした作品なのですが、電子音楽で奏でられた中世のアラブ世界のイメージが、思わぬかたちでテキストの内容と重なり合ったのも、ちょっと興奮してしまいました。
──聴かないとですね。
ぜひ。
若林恵(わかばやし・けい) 1971年生まれ。『WIRED』日本版編集長(2012〜17年)を務めたのち、2018年、黒鳥社設立。原稿執筆時のBGMをプレイリストで公開中。今回のプレイリストには、本文中で紹介しているFatima Al Quadriの新譜も。
✏️ このニュースレターの前編は、メンバーシップ会員の方はログイン後、こちらから全文お読みいただけます。
🎧 Podcastでは月2回、新エピソードを配信しています。Apple|Spotify
👀 Twitter、Facebookでも最新ニュースをお届け。
👇 のボタンから、このニュースレターをTwitter、Facebookでシェアできます。ニュースレターの転送もご自由に(転送された方へ! 登録はこちらからどうぞ)。