A Guide to Guides
週刊だえん問答
世界がいま何に注目しどう論じているのか、米国版Quartzの特集〈Field Guides〉から1つをピックアップし解題する週末ニュースレター。Quartzの原文(英語)と、原稿執筆の際に流していたプレイリストとあわせてお楽しみください。
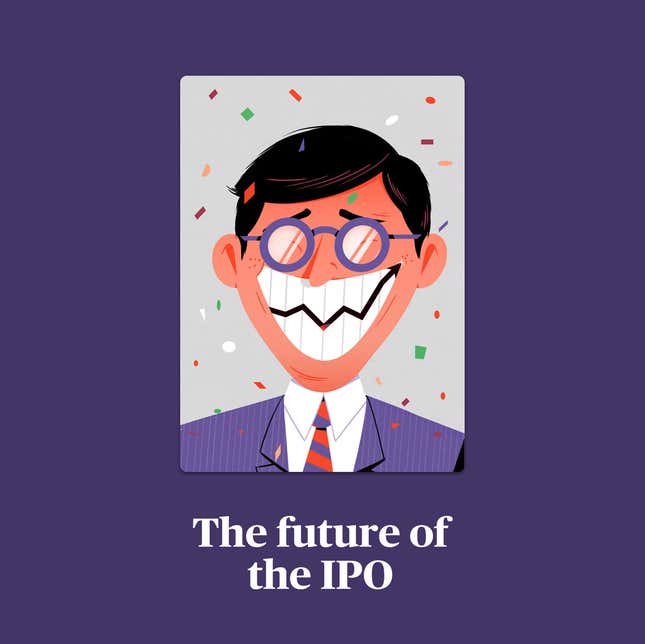
The future of the IPO
IPOの黒魔術
──お疲れさまです。最近めちゃくちゃ機嫌が悪いらしいじゃないですか。
そうですね。
──どうしたんですか?
うーん。よくわからないですね。
──昨日はインスタライブをやって6時間近くずっとしゃべっていたそうじゃないですか。無茶しますね。
無茶したつもりはないですが、よくそれだけしゃべるな、と自分でも呆れます。ストレス発散というかセラピーみたいな感じですね。
──視聴者はいい迷惑ですね(笑)。
そうだと思います。
──で、機嫌は治ったんですか?
そこそこよかったんですけどね、ついいましがた、めちゃ頭くることがありまして。
──どうしたんです?
6月頭から弊社が制作をお手伝いした行政府のDXをテーマとした「GDX」という冊子を、エントランスの軒先で無料配布しているのですが、「おひとりさま一部」と書いてあるのに、3冊くらいカバンにこそこそ入れてるヤツがいまして、注意しようと外に出たら、そいつどうしたと思います?
──どうしたんですか?
走って逃げたんですよ(笑)。
──万引きしたわけでもないのに(笑)。
無料ですからね。別にこれまで友だちや知人にあげたいと、複数冊もっていく人はいましたし、まあ、別にそれはいいんですよ。なぜ走って逃げるのか、ですよね。何がそんなにやましいのか、走って逃げるって、久しぶりに見たみっともなさだなと思いまして。途中まで追いかけてやりました(笑)。
──それで、その彼はどうしてました?
慌てて逃げてましたよ。
──行政府のこれからに興味をもってる人なんですかね、そやつ。
読むつもりなら、そんなみっともない感じでこそこそしなくてもよさそうですが。メルカリにでも売りに出すんじゃないですか?
──(笑)。いくら値段がつくんですかね。
値段なんてつきませんよ、そんなもの。
──いくつくらいの人ですか?
どうでしょう。30前後くらいの男ですね。こちらとしては、地方などで入手したいと思いながら入手できていない人たちの声も届いていて申し訳ないなと思っているところ、こういう輩が出てきますと、なんというか、まあ、不機嫌にもなりますね。
──それはお察しします。
「二度と来んな」ですし、うちでつくるものを一切触ってほしくもないです。
──そこまで、ですか。
そんなみっともないヤツに手にしてもらうためにつくっているわけではないですから。限られた部数しかないわけですから、つくる側としては、そんなのの手に渡るくらいなら他の人に手に渡ってほしいと、当然思いますよね。
──なんらかの事情があるのかもしれませんよ。
だったら言えばいいじゃないですか。自分、すぐそこにいたんですよ(笑)。
──たしかに(笑)。
基本、つくったものについて、客は選べないので、別に誰が手にとってもいいんですけどね、目の前でこういう哀れなのを見ると、さすがにげんなりしてしまいます。

──そいつ、真面目に「DX」について考えたいんですかね?
この間、何にうんざりしちゃっているかと言いますと、そこなんですね。この冊子は、行政情報システム研究所という行政系のシンクタンクが発行したものなので、基本は霞ケ関、地方自治体など役人に配布されるものでして、研究所の方が、熱心に配ってくださっていまして、また、親しい官僚の方が、IT大臣に渡しに行ってくれたかくれるらしいのですけれど、そういう話を聞くと、走って逃げた輩と同じ感じで萎えるんですよね。
──なんとなくわかります(笑)。恫喝大臣の手に渡ったところでな、と(笑)。
まさにそうです。内容をどうせ理解もしないだろう、みたいなことじゃないんですよね。触ってほしくもないって感じなんですね。
──あはは。それってどういう感じなんですか?
ずいぶん前のことになりますが、ゲームクリエイターの水口哲也さんに初めてお会いしたときのことを思い出します。水口さんは、背が高くシュッとした見た目も素敵なのですが、とにかく優しい方で、いまも勝手に慕っているのですが、赤坂の喫茶店で打ち合わせをして、そこで『WIRED』の見本誌をおもちしたんですね。で、水口さん、だいたい打ち合わせには手ぶらでいらっしゃるので、帰り際に、お渡しした雑誌をくるっと巻いて、颯爽と歩み去っていったんです。たしか、お渡しした号は、派手な蛍光ピンクと銀の特色を使った表紙で、水口さんは上下黒一色だったのですが、それがほんとにかっこよくて、やたらと、ときめいたんですよ。
──いいですね。水口さん、かっこいいですもんね。
こういう人のためにつくってるんだな、と手応えを感じたんですよね。
──なるほど。
そのときの水口さんは雑誌に出演していただく立場で、純粋な読者ではないのですが、こちらとしては当然水口さんに対して尊敬や共感があればこそご登場をお願いしているわけですから、そうした水口さんの素敵さやお話や視点の面白さに見合った誌面を用意することになりますよね。
──そりゃそうですよね。
ということはつまり、誌面のクオリティは、登場している水口さんのクオリティの水準に合致していなくてはならないということでして、かつまた、その記事を読んで共感する読者がいたとしたら、その方のクオリティの基準が、そこに合致するからこそ共感するわけですから、そこにおいてもクオリティの基準値は揃っているはずなんです。
──なるほどなるほど。つくり手の基準値と、そこで扱うコンテンツの中身の基準値と、読者の基準値とが揃うことによって、そこにある種の共感性が発動するということでね。
そうなんです。ですから、さきのIT大臣に手に取ってほしくもないというのは、自分としては、自分がつくるものには登場してほしくないということと同義でして、特に雑誌のような商業メディアがつくりだすコミュニティっていうのは、そういうものなんですね。メディアでどういう人を取り上げて、どういうふうに見せたいか、どういう人に読んでもらいたいか、と、自分たちがどういう人たちでありたいか、どういう人たちとして見られたいかは、ほぼイコールなんですよ。
──面白いですね。
もっとも今回の「GDX」という冊子の発行元は行政府につながる組織で、商業誌とはまったく異なる機能と意義をもっていますから、その観点からいえば所轄大臣の手に渡ることはもちろん重要なので、わたしがここまで言ってきたことは、基本、つくり手のエゴでしかないのですが、少なくとも商業空間においては、そういうエゴの発露であるからこそ特に雑誌のようなメディアは意味あるのだよね、と思うんですね。
──そういうエゴに立脚していないメディアは意味ないぞ、と。
って、商業空間というのはそういうものだから面白くダイナミックなものになるわけじゃないですか。
──そりゃそうですね。
って、ここまで書いたところでですね、また『GDX』を取りにきた人がいまして。
──また持ち逃げですか?(笑)。
いえ、今度は知り合いの20代のウェブ編集者でして、「最近どうしてる?」なんて聞いたところ、「どうしたらいいかわからなくなってきまして」と、もう非常に浮かぬ顔をしておりまして。

──さすが「福祉センター」を名乗っているだけある。駆け込み寺ですね(笑)。で、どうしちゃったんですか?
これはまあ、もうおなじみの「ウェブ編集者あるある」でして、要はバズらせてなんぼに立脚せざるをえなくなったウェブメディアでは、せっかく面白い仕事ができそうだと思って入ってきた編集者が、「PV=数字」と「面白いこと」の間で、モチベーションをすりつぶされていくということですね。
──編集の世界に限らず、あるあるって感じの話ですね。
それが「あるある」だということは本人も百も承知なのですが、そういうなかでいくら歯を食いしばって自分が面白いと思える記事をつくってもなんの反応もなく、なんの評価にもつながらないともなれば、だんだんそこから抜け出す手立ても意欲も削がれていきますよね。
──しんどいですね。
しんどいんですよね。
──どうしたんですか?
ウーバーイーツでバーガーキングのワッパーを頼んで、ふたりで食べましたけど、しんどいのはそうやって話し相手になることではなくて、そうやって若いやる気を削いで行っている環境そのものですよね。
──ほんとですね。
もちろん経営的な観点からみればバズに頼らざるをえないことは現実的には致し方ないことなのですが、それに依存していけばいくほど、ワーカーのモチベーションが下がっているのは目に見えているわけですから、そこになんの考慮もないまま「PVを稼げ」といえば現場のモチベーションは下がりますし、それにつれてメディアのクオリティは下がりますし、それは同時にお客さんのクオリティの低下を招くわけですね。で、結局経営者自身が、メディアというものの投資効果の低さに、あとから気づいて後悔することになるのでしょうけれど、その浅はかさが、若いワーカーの貴重な時間を奪っているわけですから、その浅はかさは、浅はかの一言では済まないわけですよね。
──悔いるなら、まずそこを悔いて、なんなら詫びろよ、と。
最近、津野海太郎さんという偉大な編集の先達が「編集」について書いた文章をまとめて読む機会があったのですが、津野さんは「雑誌はつくるほうがいい」とおっしゃっていまして、それはけだし名言だと思うんです。津野さんはこう書いています。
いきのいい雑誌をみたときは、「なんのなんの、おれたち読者よりも、本当はあんたがいちばん楽しんでるんだよ」と、腹の底で未知の編集者の呟いてやる。本はつくるよりも読むほうがよく、雑誌は読むよりもつくるほうがいい。すくなくとも私の場合はそうである。つくる側にまわったほうが、はるかによい。(「雑誌はつくるほうがいい」/『歩く書物:ブックマンが見た夢』より)
そして、こう書きます。
私たちのまわりにある雑誌のおおくはプロではなくアマチュアの仕事として、すなわち、読者の側からつくる側にまわりたいと願う昨日までの読者たちの手によってはじめられた。
──面白いですね。
そして、ここからが面白いのですが、津野さんは、「つくる側にまわりたい」と読者に思わせるには、なんらかの「魔術」が必要で、それは一種の「演技」に宿るというんですね。
──演技?
津野さんは、こう言います。
「それでも雑誌にはなんらかのかたちで、そこにしか存在しないなにかが必要なのだ。そのなにかのまぼろしをつくりだすのが雑誌の演技である」
──ふむ。
津野さんは編集の仕事を、舞台制作における「演出家」になぞらえて語るのですが、それに従えば、雑誌の編集者は、そこに登場した人や、テキストなどを舞台にあげて、そこに演出を加えることで、すでに魅力的であるはずの人や文章などになんらかのイリュージョンをふりかけて、「自分もそっち側にいきたい」と読者に思わせるような「まぼろし」をつくりあげるということになります。
個人的には、それを「演技」ということばで捉えたことはないのですが、それでも体感的にわかるところはありまして、常々感じていたことで言いますと、雑誌メディアの影響力って、実際の部数よりもはるかに大きいものだったりするんです。つまり、なぜか実態よりも大きく見えるものだったりしますし、編集部というものも、実態としては、非常に散文的でつまらない仕事を日々行っているだけにもかかわらず、外からは、やたらとクリエイティブなものに見えたりするんですね。
──たしかに。
ただし、そうやって実態よりも大きく見えたり、生き生きしているように見えたりするのは、そのメディアプロダクト自体が「いきのいい」ものに見えるという前提があるからで、裏を返せば、「演技」というのは、その「いきのよさ」を、誌面の振る舞いにおいてどう生み出すかということでもあります。もっとも、ここも難しいところで、やっぱり舞台上の役者も、それなりのモチベーションやクオリティ感をもっていないと、いくら演出だけが気張ったところで、変に鼻につくものにしかならないと、津野さんは書いていらっしゃいます。
──なるほど。結局のところ、舞台上の役者と演出家が、同じ目線やレベル感で共感、信頼しあっていないといけないということになりそうですね。
はい。で、津野先生のこのお話は、先に問題にしたメディアビジネスの浅はかさにつながるところがありそうでして、結局よく考えもせずメディアビジネスに参入する企業や経営層というのは、結局のところ、この「演技」のところだけを欲しがって、そこに手を出すわけですが、それがウェブメディアであった場合、そもそもウェブメディアには「演技」の余地がほとんどないということや、アマチュアが簡単に参入できたプリントの世界と違って、ウェブメディアは莫大な運用コストがかかるということを、愚かにも見落とすんですね。
──あはは。
演技の余地がありませんから、「まぼろし」は生まれませんし、「まぼろし」が生まれなければ、そこに「つくる側にまわりたい」という人も生まれず、それは広告主が見つからないということに直結しますから、結局、つまらない数字を積んでネットワーク広告に依存するハメになるんですね。
──自らダウンスパイラルに入っていく、と。たしかに愚かですね。
そんな愚かさに、やる気のある人間を濫費しないでほしいんですね。という意味で、これはほぼほぼ意思決定権者の責任なんですよ。で、自分としては、そういうことに自分で気づけもしないような人たちに向けて、なにかをつくるようなことはしたくないんですね。というのも、それ自体が、その濫費に付き合うことでしかありませんから。
──なるほど。
といって、自分ももう50歳なので、どちらかといえば、そっち側の立場でもあるので、責任を感じる部分もあるはあるんです。であればこそ、行政府のこれからを扱った「GDX」という冊子なんかも、最初から、「霞ケ関のしょーもないおっさんのためにつくるつもりはないですが、いいですか?」というところは、行政情報システム研究所の方とも握っていたんです。むしろ、さきの悩める若い編集者と同じように、ほんとに現場でいやな思いをしながら、それでも「きっとどこかに意味ある仕事があるはずだ」と思っている人たちに、「間違っているのは君らじゃないからな」とせめて思ってもらえるようにしましょうよ、ということで制作したんです。
──なるほど。
でも、それも意味ないんですよ。
──なんでですか?
そうやって仮に誰かが鼓舞されたところで、結局、得するのは濫費する側でしかないわけで、ずっとそういうやる気のあるひとたちを、煉獄にとどめおくことにもなりかねないわけですから。
──希望が苦しみのもとにもなるということですね。
最近Netflixで公開されたザック・スナイダー監督の『アーミー・オブ・ザ・デッド』という映画がありまして、公務員や行政府のこれからを考えようとすると、なぜかゾンビ映画を参照したくなるのですが、このゾンビ映画も非常に示唆に富んだものでした。

──めちゃ面白かったですよね。
はい。これはあくまでもわたしの理解ですが、ゾンビ映画のゾンビって、怖いというよりも、実際は、悲哀に満ちた存在ではあるんですよね。つまり、なんらかの理由で、生きるでもなく、死ぬでもない状態に置かれ、人の生き血を吸うことしかできない気の毒なもので、しかも、それが襲ってくるともなれば当然打倒しなくてはならないのですが、でも、それは「敵」ではなく、「明日の自分」でもある存在ですよね。
──たしかに。最近のゾンビ映画には、その愛嬌の部分を取り上げるものもあったりもしますもんね。
そこで重要なのは、ゾンビと、それと戦うハメになった市民とは、あくまでも等価の存在だというところなんだと思うんです。つまり、ゾンビ化は、誰にでも平等に起きるということですね。これは、パンデミックに近い状況で、それを意識したものなのかどうかはわかりませんが、『アーミー・オブ・ザ・デッド』では、「隔離キャンプ」が設置されていて、そこでは隔離された人たちが、ゾンビになっていないかどうかを検査するために検温させられていたりします。この辺に、コロナがもたらした状況を重ね合わせても面白いところですが、この映画のポイントは、腕力もスピードも強化された「アルファ・ゾンビ」というものの存在で、これがどこからもたらされたか、という点にあるんだと思います。
──ほほう。映画の冒頭ですよね。軍の輸送車がコンテナを運んでいるシーンですね。
はい。詳しくお話してしまうとスポイラーになってしまうのでやめておきますし、この辺りは、続編のモチーフになるところだと思いますのでいまのところ詳しく話せる内容もないのですが、少なくとも今作で示唆されているのは、ゾンビを「兵器」として利用したがっている勢力がいる、ということでして、強化されたスーパーゾンビを、人間に対して差し向けようという意志が、どこかから発動しているんですね。
──たしかに。ゾンビの首を切り取って、持ち帰ろうとしている輩がいました。
つまり、意志のない気の毒な有象無象が、誰かの意志をもって放たれたということなのだとすると、ゾンビは、わたしと置換可能な平等な存在ではなく、明確に敵になるわけです。ゾンビに意志はなくとも、その無意志が、人間に差し向けられるわけですから。
──なあるほど。なんでですかね、お話を聴きながら、ずっと「パソナ」という社名と、その会長のヘラヘラした薄笑いを思い浮かべてしまいましたが。
おっしゃる通り、実際にこの間のオリンピックのボランティアをめぐるありようなどを見ていると「戦略的ゾンビ化」とでも呼ぶべきものが作動している感はありますよね。つまり、人を無気力にしていくことで、反発を抑え込むと言いますか。オリンピックの話題などは、多くの人がすでに呆れ尽くして、もはやどうでもよくなってきて萎えてしまうというか、脱力してしまう感じがあるのではないかと感じます。
──って、首相から、五輪担当大臣、五輪組織委員会会長、JOC会長といった面々のほうが、よほどゾンビ感ありますけどね。
ゾンビ映画は、言ってみればずっと、人が奴隷化させられてきた社会状況を、時代ごとに風刺してきたものと言えますが、それが扱ってきた問題は、政治や社会ではなく、実は一貫して「経済」の問題だったというところはかなり重要なポイントだと思うんです。このことは、アートフィルムのSVODチャンネル〈MUBI〉に、映画批評家ブライアン・エーレンプライスが寄せた「ロメロ論」で指摘されています。
ゾンビは資本の論理を極限まで推し進めた果ての過剰の産物だ。終わりなき消費は必要や空腹によって要請されたものではない。ゾンビ神話は、労働と支配というテーマと切っても切れないものとされてきたが、それは永遠に続く苦痛をめぐるものでもある。(中略)ゾンビのコンセプトは、それが生まれた17世紀のハイチの砂糖プランテーションから中産階級向けショッピングモールへと一直線でつながっており、『ドーン・オブ・ザ・デッド』においてロメロは、それを新しい時代の奴隷制として描き出した。
──おお、すごい。『アーミー・オブ・ザ・デッド』のザック・スナイダーは、それこそロメロ監督の『ドーン・オブ・ザ・デッド』のリメイクでデビューしたんでしたよね。
そうですね。まだ観れていないのですが。ちなみに、出すタイミングを失ったまま公開していない、ゾンビを題材にしたテキストがありますので、長いですが、割と気に入ったものですので貼っておきましょうか。
──いいんですが、それを貼っちゃうと、〈Field Guides〉に触れられないまま終わっちゃいません?
そうですね。では、ざっと記事を見ておきましょうか。今回の〈Field Guides〉は「IPO」をテーマにしたもので、記事は1本しか収録されていません。「IPOの未来を完全ガイド」(A complete guide to the future of the IPO)という記事ですが、記事はPayPalの創業者のひとり、マックス・レフチンのことばを紹介しながら、こんな文章で始まっています。
シェアを誰がいくらで得るのかの決定プロセスの問題がある。少なからぬエグゼクティブたちが、そのプロセスを、ウォール街とクライアント企業に利益をもたらすために投資銀行が構築した「ブラックボックス」と呼んでいる。「シェアの分配と価格の決定は、頭のいい人たちの小難しい会話による黒魔術の世界だ」とマックス・レフチンは言う。「それは決して変わらないだろう」。
──黒魔術(笑)。ゾンビといえばヴードゥーですが。
そうした冒頭から、記事は、それでも少しずつであるとはいえ、IPOのかたちも変わっていると語っていまして、その変化のドライバーとして以下を挙げています。
「SPAC」(特別買収目的会社)や「ダイレクト・リスティング」(直接上場)といったオルタナティブな方法を選ぶことができるようになったこと。ニューヨーク市場を頂点に一元化しつつあった世界の株式市場が、ローカルな個性を打ち出すようになってきたこと。女性や有色人種、あるいは両方の人たちを含めた、これまで見過ごされてきた起業家たちの台頭。「Robinhood」などのリテールアプリの勃興によってもたらされた「投資の民主化」。です。

──なるほど。
記事の最後には、ゴールドマン・サックス・インターナショナルのファディ・アブアリCEOの「投資の民主化は、今度さらに進むでしょう」ということばが紹介されています。
──希望もありそうな感じですが、どうなんでしょうね。
わたしはよくわかりませんが、アプリを通じた投資の民主化は、わたしの勘では、ソーシャルメディアの普及と同じ道をたどるような気もしますので、いい面はありつつも、ダウンサイドも大きいのではないないかと予測します。
──インフォデミックによる汚染に似たことが起きるようなイメージですか?
はい、その通りです。株の売買というのも、本質的には情報の取引であるようにも思えますので。
──なるほど。
というわけで、今回は若干手抜きにはなりますが、以下の原稿を対照しながら、〈Field Guides〉を読んでいただくといいのかもしれません。
──投げやりな(笑)
不機嫌だと言ったじゃないですか。
──はい(笑)。タイトルはなんですか?
「ゾンビがいるから世界がまわる:資本主義の不都合な真実」です。
──面白そう。
はい。結構気に入っているテキストなんです、実は。では、どうそ。
ゾンビは経済の産物である
ゾンビというのはハイチ生まれの代物だそうで、プランテーションで働く奴隷の数をちょろまかすために農園主が考案したものなのだとテレビのバラエティ番組で観たことがある。
農民を仮死状態にして、生き埋めにし、葬式を執り行い、死んだことにしたあとで掘り起こして叩き起こす。するとほらびっくり、公式には存在しない幽霊奴隷が一丁上がりというわけだ。うまいこと仮死状態にするために用いられるのがヴードゥーの秘術ということになっているあたりにおとぎ話めいた面白さも宿るが、ゾンビというものを考える上では、それが資本家が考え出した「戸籍ロンダリング」というスーパーブラックな労務管理の産物であるところはまず押さえておきたい。
ゾンビは、文化的であるよりも、まずもって経済的、資本主義的な主体だ。カール・マルクスという人は、資本主義というものは奴隷の存在がなくては作動しないことを明らかにし、資本主義と奴隷制の抜き差しならぬ関係性の淵源をカリブ海における砂糖プランテーションに求めていたというから、ゾンビの発生が、奴隷制と資本主義の発生と分かち難く結びついていると考えることは、さほどトンチンカンなことではない(はずだ)。
ロメロの慧眼
ゾンビ映画というジャンルを確固たるものにしたアメリカの映画監督ジョージ・A・ロメロは、傑作『ナイト・オブ・ザ・リビングデッド』の編集を終え、完成したばかりのマスターフィルムを配給会社に届ける車のなかで、マーチン・ルーサー・キングが銃撃されたニュースを聞いたのだという。そのエピソードが重要な意味をもつのは、ゾンビホラーの最重要作と目される本作が、ただの娯楽映画ではなく1968年という時代を色濃く反映した極めてクリティカルなものだったからだ。
まずもって、本作はゾンビ退治に明け暮れるヒーローたるべき主人公が黒人であるという点においてラジカルだ。そして、その主人公のベンは、ともに戦うはずの白人たちとの微妙な緊張関係のなかに絶えず置かれる。『ナイト・オブ・ザ・リビングデッド』の気持ち悪さは、殺しても殺しても生き返るゾンビたちの怖さにではなく(彼らはある意味可愛い)、ゾンビたちの反乱/氾濫にパニックに陥り、何をしでかすかわからない錯乱状態のなかにいる白人たちの挙動に宿る。ただひとり冷静に事態に対処しようとするベンは、前面から襲ってくるゾンビと、背後できな臭い動きをする白人たちとの二面闘争を強いられる。映画は、ベンが画面に登場した瞬間から、彼が決してこの夜を生きてはサバイブできないだろうという悪い予感とともに推移し、案の定ベンは救援部隊にゾンビと間違えられて射殺され、ゾンビとともに処分されるという、とことん後味の悪い結末を迎える。
公民権運動が吹き荒れる時代のコンテクストのなかにおけば、本作は「人種」という深刻な政治課題を扱った政治的な作品に見える。ワッツやデトロイトで起きた暴動とゾンビの襲来は時代のなかで完全にシンクロしている。建国の原風景としての奴隷制は、忘れたくとも忘れることのできない悪夢として、ゾンビの姿を借りていまなおアメリカに取り憑いている。しかし、それは決して国家や国民をめぐる道徳的・倫理的命題ではない。奴隷制が問題となるとき、それは、そこで問題となっているのは、常に「資本主義」なのだ。
そしてロメロ監督の慧眼は、そのことを的確に読み解いていた。ゾンビはあくまでも経済主体なのだ。かつてゾンビは第1、第2次産業をドライブさせる資源として使役される「奴隷」だったが、経済のあり方が変わっていくにしたがって「奴隷」の姿も変わる。そしてロメロ監督は、1978年の『ドーン・オブ・ザ・デッド』において消費の奴隷と化した市民のありようを、ショッピングモールに殺到するゾンビたちの姿を通して描くこととなる。
アートフィルムのSVODチャンネル〈MUBI〉に掲載された、映画批評家ブライアン・エーレンプライスによるロメロ論はこう書いている。
「ゾンビは資本の論理を極限まで推し進めた果ての過剰の産物だ。終わりなき消費は必要や空腹によって要請されたものではない。ゾンビ神話は、労働と支配というテーマと切ってもきれないものとされてきたが、それは永遠に続く苦痛をめぐるものでもある。(中略)ゾンビのコンセプトは、それが生まれた17世紀のハイチの砂糖プランテーションから中産階級向けショッピングモールへと一直線でつながっており、『ドーン・オブ・ザ・デッド』においてロメロは、それを新しい時代の奴隷制として描き出した」
またの名を「負債」
ゾンビは、ハイチのプランテーションから産業資本主義へ、さらに消費資本主義へと取り憑く先を次々と変えていく。返済能力のない人びとへと融資を重ねることで成立していたサブプライムローンなどは、その先にあるべき金融資本主義の格好のゾンビ空間であったとみなすことができる。ゾンビは、資本主義の移ろいにあわせてすみやかにその出没場所を転移していく。そして、リーマンショックをもたらした金融資本主義のさらに先を見れば、そこには無料で便利ツールを提供され、それを使っているうちに個人データをごっそりと抜き取られたあげく超強力な監視・管理システムに支配されるデータ資本主義の悪夢が待ち受けていたりもする。
文化人類学者のデヴィッド・グレーバーは「負債」こそが資本主義というものの最大の「商品」で、それを流通させるためにさまざまなプロダクトがつくられるのだと倒錯したそのシステムのありようを説明したが、その線で行けばゾンビは、つねに「負債」を負わされてきた者であるとも言える。かつては「労働者」として。ついで「消費者」として。その後、文字通りの「負債者」として。そしていまここで「データ商材」として、人はゾンビ化され続ける。
マルクスが、資本主義を動かしている見えないサブシステムとして「奴隷制」が作動していることを指摘したのは『資本論』のなかでだったそうだ。社会学者の植村邦彦は、マルクスがそこで述べた「隠された奴隷制」がいかに執拗に社会のなかで温存され引き継がれているかを、その名も『隠された奴隷制』という本のなかで述べているが、植村は、同書のなかで、そこから逃れるための希望のよすがのひとつを、グレーバーが語る「コミュニズム」という概念に求めている。
グレーバーが「コミュニズム」の語を通して語るのは、例えば水道工事をしている配管工が仲間の配管工に、「そこのスパナを取ってくれない?」とお願いした際に、相手が「その代わりに何くれる?」と聞くことなく取ってくれる、そうしたやり取りのことだ。グレーバーは、そうした「コミュニズム」が資本主義の底流に隠れて流れてきたことを、奴隷制の温存とならぶ不都合な真実=「スキャンダル」として語っている。世界中の「奴隷=負債者=ゾンビ」が、それでもなんとか生きているのは、そうした隠れた扶助システムがつねに存在してきたからだと彼は指摘する。そして、そこにはたしかに一縷の望みがある。
GAFAを強奪する?
ゾンビ映画の面白さは、明確には敵が存在しないところにある。ゾンビはそもそも敵ではない。彼らは悲しき被害者であって、明日の我が身でしかない。ゾンビ映画に悪は存在しない。強いていえば、悪はゾンビを生み出すシステムであって、『バイオハザード』シリーズであれば、なんらかの意図をもって人をゾンビ化し続けるアンブレラ社がそれに該当する。しかしそうやって悪を設定してそれを打倒するという道筋は、新たにゾンビを再生産していくだけであることは、ロメロの映画が繰り返し描いてきた通りだ。
むしろわたしたちは悪の存在を介在させることなく、ゾンビと向き合わなくてはいけない。ゾンビがわたしたち自身であるのなら、ゾンビ世界のなかに、グレーバーが語ったような扶助の仕組み、すなわちコミュニズムのネットワークを張り巡らせるようなことを想像すべきなのかもしれない。そして、積極的にそこにデジタルテクノロジーを関与させるべきなのかもしれない。P2Pのコミュニケーションを実現するツールは、先に言ったような「スパナ取って」「あいよ」というようなやり取りを拡張すべきものとして本来あったのではなかったか。
いま、かりに巨大IT企業にゾンビの一群が襲いかかるようなゾンビ映画をつくったとしたらどんなエンディングが想定されるだろうか。ハッピーな結末があったとしたら、それはどんなものか。巨大IT企業がガバナンスを奪還して終わるような結末は、よもやハッピーエンドとは言えまい。
ゾンビ映画はただの寓話ではない。それは政治的寓話、道徳的寓話のようにも見えながら、その本質において経済の寓話なのだ。そして、わたしたちはいま、データ資本主義の生み出す「新しい奴隷制」をめぐるゾンビ物語を生きていて、その重大な分岐点にさしかかっている。にもかかわらずゾンビはどうしたって知能も意志もないので、いいようにおもちゃにされても、悲しいかな気づきもしないのだ。
若林恵(わかばやし・けい) 1971年生まれ。『WIRED』日本版編集長(2012〜17年)を務めたのち、2018年、黒鳥社設立。責任編集を務めたデジタルガバメントについてのハンドブック「GDX:行政府における理念と実践」の序文がこちらで公開されています。
👇 のボタンから、このニュースレターをTwitter、Facebookでシェアできます。ニュースレターの転送もご自由に(転送された方へ! 登録はこちらからどうぞ)。
