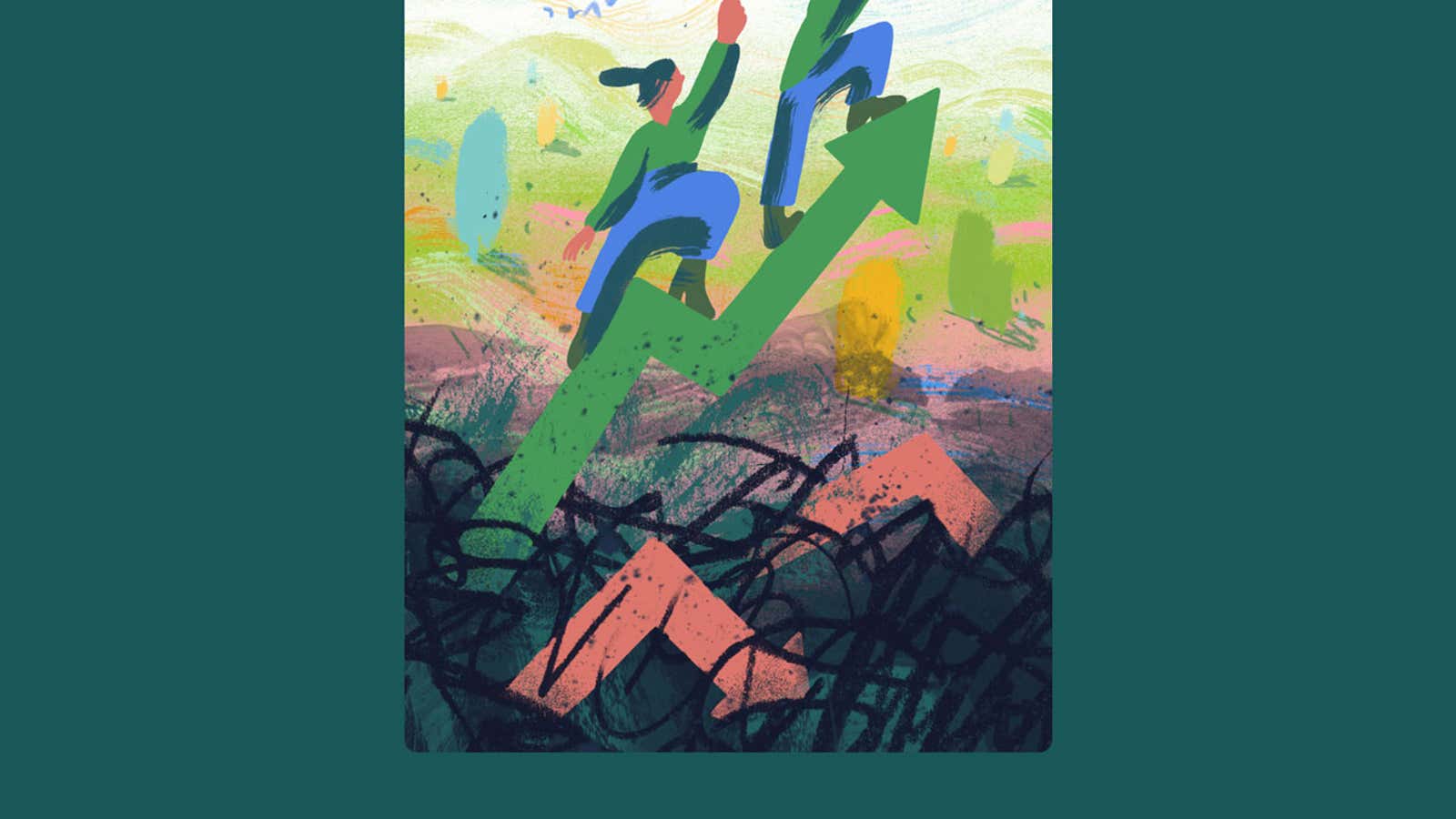A Guide to Guides
週刊だえん問答
Quartz読者のみなさん、おはようございます。世界はいま何に注目し、どう論じているのか。週末ニュースレターでは、米国版Quartzの特集〈Field Guides〉から1つをピックアップし、編集者の若林恵さんに解題していただきます。今週、来週は2回に分けて、「気候変動」をめぐる論点に挑みます。

──こんにちは。
はい。
──お疲れですか?
はい。
──まだ単行本の制作が続いているんでしょうか。
はい。
──大変ですか。
はい。
──あはは。死んでますね(笑)。
はい。
──なんかしゃべってください。
えー。はい。この週末で校了するのですが、何を隠そうようやく全貌が見えまして、トータルのページ数が448ページもありました。
──マジすか。そんなになりますか。
どうりで読み終わらないわけです。
──色んなこと語ってきましたからねえ。
そうですね。
──概観すると、ご自分としては何を語っている本だと思われます?
うーん。難しいですね。なんでしょうね。ゲラを読みながら自分なりに思うのは、自分が一番気にしているのは、結局「情報の問題」なのかなというところですね。
──情報?
はい。いわゆるフェイクニュースだったり、インフォデミックだったりといったテーマなのかな、と思っています。いま世界を苛んでいる一番の困難は、そこだと思うんです。世の中的には、おそらく、反知性的な言動を「知性」や「理性」といったもので押し返すことができるはずだという考えが、まだ根強くあるように思えるのですが、この状況はそんな生易しいものではないのではないかという気が、とても強くします。

──それは、この連載でも何度か指摘されてきたことのようにも思いますが、そこ、やはりそんなに重大ですか。
重大だと思いますね。実は今月末に弊社から武邑光裕先生の新著『プライバシー・パラドックス』という本を出すのですが、武邑先生がおっしゃるには、「fact」(事実)と「fake」(偽物)は、語源が一緒だそうです。つまり、ともに「fiction」、すなわち「つくりもの」なんですね。
──あれま。
要は、わたしたちが突入しようとしているのは「本当」と「嘘」がもはや不分明な、中世以前の世界のようなものなのではないか、と先生は本書で書かれています。「魔術」と題した最終章にこんな一節があります。
「現代のネットユーザーは、『精霊の領域』やテクノ魔術や黙示録(ディープ・フェイク)に魅せられ、遠く離れた独裁的な地主の捕虜になっている中世の農民のように見える。インターネットは、日常生活の上に置かれた一種の超自然的なレイヤーへと発展し、人びとは恐ろしい力、熱を帯びたビジョン、終末的で精神的な戦いの領域へと容易にアクセスできるようになった。
私たちはサイバーパンクの未来に加速されているのはなく、空想的で魔術的な前近代の過去に放り込まれている」(武邑光裕, 『プライバシー・パラドックス』, 黒鳥社)
──なんと。
この数十年だと思いますが、映画やゲームなどをみても、中世的想像力が明らかにメインストリームになっているわけですよね。『ロード・オブ・ザ・リング』や『ゲーム・オブ・スローンズ』といったところが典型だと思いますが。ちなみにMMORPGの9割は舞台が中世だそうですから、時代の心性はすでにサイバーパンク的なイマジネーションとは異なる方向に向かっていて、それを通して想像されていた未来はすでに失効しているとのことばは、言われてみるとリアリティがあるような気がします。
──そうなんですね。
結構お気に入りの映画で、『ラスト・ウォリアー 最強騎馬民族スキタイを継ぐ者』という、11世紀を舞台にした『マッドマックス』みたいな変な映画があるんですが、ご覧になったことあります?
──あるわけないですよね(苦笑)。
ですよね(笑)。アクションシーンも非常にカッコよくて面白いものですので、ぜひオススメしたいので、ちょっと、アマゾンに掲載されているディスクリプションを引用しておきますね。
「11世紀のユーラシア大陸―一つの文明が瞬く間に新しい文明にとって代わられてしまう激動の時を迎えていた。誇り高き戦士、遊牧騎馬民族スキタイの末裔たちは今や邪悪な傭兵へと転身し、残酷な報酬目当ての暗殺者となり、村人たちを襲撃していた。村を襲われた戦士ルトバーは、人質に取られた妻と子供を救うため、捕虜にしたスキタイ戦士マーテンを案内役として同行させる。旅の道中で敵対する2人だったが、互いに仲間の裏切られた者同士協力し合うことに。だが、次々と襲う刺客と罠に瀕死の状況に追い込まれたルトバーは怒りと復讐により己に眠る戦闘民族の血を覚醒させる!」(『ラスト・ウォリアー 最強騎馬民族スキタイを継ぐ者(字幕版)』, Amazon)
──面白そうじゃないですか(笑)。
はい。このあらすじで説明されている「激動の時代」というのは、さまざまな未開部族と言いますか、民間宗教やアニミズムを信仰している土地土地のトライブがキリスト教文明に飲み込まれていく時代背景をさしています。で、主人公の戦士ルトバーは、たしかキリスト教に宗旨変えした諸侯の家来なんですね。その彼が、スキタイの戦士マーテンと連れ立って、キリスト教化されていない奇妙な未開部族のいる土地土地を旅していくことになるのですが、あるところで、土地の部族の長老にこう言われます。
「おまえの神はここにはいない」
──ほほお。
このフレーズは、なかなかすごいなと思いまして、中世という時代がどういうものかと考えたときにピンとくるものがあったんです。
──たしかに、なんかすごいですね。そう言われるとハッとするところがあります。
キリスト教的な世界観では、神というものは普遍的な存在として想定されているはずですが、昔からその土地に暮らす部族から見たら、それはあくまでもどこかよそのローカルな神さまでしかなくて、その土地ではなんの実効性ももたないんですね。とはいえ、そうした「未開部族」も、やがては普遍宗教に「平定」されていくことになるのですが、映画はどちらかというと「未開」を平定していく普遍性の側ではなく、いずれ失われていくことになるバナキュラーな世界の側に立っていまして、ラストで戦士ルトバーは衰亡していくスキタイの一味として「普遍」に争う側に身を置くことになります。
──面白いですね。
近代国家のリーダーであるよりは、もはや土着的な部族長を目指そうとしているようにすら見えるプーチンのロシアでこんな映画がいま制作されることの意味を考えることは、それはそれで非常に面白そうですが、ここでお伝えしておきたいのは、いわゆる「マルチポーラー化=多極化」する世界というのは、「普遍」によって一度は「平定」されたはずの世界が、徐々に溶け出してかたちを失い、もう一度「それぞれの神がいる世界」に戻っていこうとしている状態をさしているのではないのだろうか、ということです。
──あー。うーん。なるほど。
例えばアメリカ大統領選の様子を見ながら、自分は「この土地におまえの神はいない」ということばを何度も反芻してしまうのですが、そう考えると「フェイクニュース」「陰謀論」といったことばは、近代が措定してきた普遍的な世界像そのものを相対化していく非常に大きな強い趨勢のようにも思えてきてしまうんです。近代的理性によって、それを押し返すことは本当に可能なのかと、正直思ってしまったりもします。

──そう言われると、西洋近代の「普遍」の側から見るよりも、「いまは中世なんだ」というフィルターをもって物事を見るほうが見通しが利くような気もしてきますね。
やや脱線してしまいましたが、ところで武邑先生は先の引用部分の直前に、サイバーパンクを葬り去った存在としてある特定の人物を挙げています。この人物こそが中世化する世界のアイコンとも言えそうですが、いったい誰だと思います?
──うーん。難しいですね。
引用しましょう。
「凍った北欧の果てから、古い世代の虚栄心を非難し、大惨事が起こることを警告し、王や女王と対決するためにやってきた予言者の少女、グレタ・トゥーンベリの登場が、すべてを変えた」
Climate tech’s second shot
気候テックの神話
──ははあ。なんでずっとこんな話をしているのかと思ってましたが、そこで今回の〈Field Guides〉のお題の「クライメート・テック」、つまり「気候変動とそれをめぐるテクノロジー」の話につながるんですね。
うまくつながるのかどうか自分でも自信がないのですが、「グレタさん」をどういう存在として理解すべきなのかというのは、自分も正直腹落ちできぬままいたのですが、彼女が中世の予言者であると言われると、妙に納得してしまうところがありました。
──にしても武邑先生は本当に面白いですね。
間違いないです。それはそうと、グレタさんについて言えば、つい先日知人から、面白いメッセージをもらったんです。あるところで気候変動の話をしたところ、それなりの大企業の代表クラスの人が「気候変動は陰謀だから」と真顔で言ってきたそうで、それに対して「グレタさんはじめ、多くの若者はリアルな危機感があって活動しているんですよ」って返したところ、「それも操られてるんでしょ?」と言われたというんです。
──日本のおっさん、マジやばいですね。典型的な陰謀論じゃないですか。
それはそうなんですが、こうした感覚は、何もおっさんに限らないような気もしています。というのも、先日ある会合で、気候変動やサステイナビリティをめぐる話題が議論の俎上にあがったのですが、「地球環境をなんとかしなくてはいけない」という議論が出てくると、なぜかその会議に参加していた若者が、それについて懐疑的になり、「そのことを認めたくない」という感じで防衛的に反応する場面に出くわしたのですが、これは経験上は、そんなに珍しい反応でもなく、それこそ中央官庁の人と話していたときにも同じような反応をされたことがあります。
──やばいですね。日本人、大丈夫ですか?
やばいかどうかは別にして、ここで考えておいたほうがいいと思うのは、何が日本人をして「気候変動」や「地球環境」という概念に強い心理的抵抗を催させるのか、という点だと思います。そして、それを考えることは、逆に言えば、グレタさんをどう理解するのかということにもつながるような気もします。
──抵抗の原因はなんだと思います?
うーん。まあ、こう言ってしまうと非常に語弊があるのですが、先ほどのスキタイの映画に出てきたような、「普遍に怯える土着部族」みたいなところがあるんじゃないかな、と思ったりします。そもそも「普遍」という概念が、おそらく日本人はハナから苦手なんだと思うんですね。ただでさえ市民とか国民といった概念が苦手なところで、その延長線として「世界市民」や「地球」なんてことばを持ち出されても、正直なんのことやら、みたいな感覚はあると思うんです。自分ですら「なんだよ世界市民って」って思うところもないではないですから。
──まあ、それはわからなくもないです。
なので「地球」ってものを持ち出されて、「あなたもそのステークホルダーである」「ステークホルダーであるからには責任をもて」と言われると、責められているように感じてしまうようなところがあるのかもしれません。しかもグレタさんの場合、かなりの詰問調で上の世代を責め立ててきますので、まあ、こう言ってはなんですが、「なにを!」と反射的に思ってしまうんでしょうね。
──「地球」という巨大な普遍を持ち出されて、その責任を問われても、実際のところ何をどうしたらいいかわからないですもんね。
しかもその概念の厄介なのは、それを誰も否定したり拒否することができない強制力をもっている点です。「地球に対する責任」と言われたら、そこから免罪される人はいないわけですよね。ただ、じゃあ一方で、それが実体的に何を意味しているのかといえば、それを特定することがとても困難です。
思想家のイヴァン・イリイチは、「環境科学という新しい神話ないし哲学における主役」である「生命」ということばを『生きる思想』という本のなかで分析しているのですが、彼はそれをこんなふうに批判しています。
「『生命』ということばは、現在のエコロジー、医学、法律、政治、倫理などに関する話しのなかにかならず登場する不可欠な用語となっています。ところが、この用語を使う人たちは、この概念が歴史をもったものであることをいつも忘れています。実はこれは西洋の概念であり、もとをたどれば、キリスト教の教えがねじ曲げられた結果あらわれたものなのです。そして同時に、これはきわめて現代的な概念でもあります。しかし、その意味あいが混乱しているために、このことばは何ひとつ正確に言い表せられなくなっているのです。『一つの生命』とか『人間の生命』といったことばでものを考えていると、人は漠然と、何か非常に重要なことについて語っているような気がしてきます」(イヴァン・イリイチ, 『生きる思想』, 藤原書店)
──なるほど。「生命」や「地球」といったことばは、あまりに当たり前になってしまって、それがなにを意味しているのか真剣に考えたこともありませんでしたが、言われてみると、なんだかもやっとしていますよね。
はい。生命ということばをめぐって「意味あいの混乱」が起きていて、それが「何ひとつ正確に言い表せなくなっている」というのはまさに環境問題における大きな問題で、エコロジーの議論はなぜゴミ情報まみれなのかという問いを、哲学者のティモシー・モートンは『Being Ecological』という本の冒頭に提出していますが、要は、気候変動問題はそれ自体が巨大なフェイクニュースの温床なんですよね。しかもイリイチのことばに沿うなら、それはある意味、構造的に起きていることなので、陰謀論に与するおっさんが、ただの間抜けだというわけでもなさそうです。
──そうですか。
地球環境の問題のなかでも、とくに天候という領域は、古来より深く「天」という概念と関わるところですよね。つまり、そこは長らく神の領土だったわけじゃないですか。そこを今後誰の管轄下においてどう管理をするのかという問いが気候変動問題をめぐる話であるわけですが、イリイチが指摘するように、そもそも「生命」やそれを根拠にして支えられている「地球」といった概念がキリスト教由来の、あるローカルな神さまをめぐる神話でしかないのだとすると、それに普遍ヅラをされる筋合いもない、と感じるのはその通りだと思うんです。なぜなら、気候変動の問題はこれまでの西洋近代のフレームでは取り扱えない問題なのではないか、というのが根本的な問題意識としてあるからです。
──ふむ。
そのときに考えないとなのは、グレタさんは、西洋近代の神話をもう一度神話化するために現れた存在なのかどうか、というところなのだと思います。おそらく少なからぬ日本人は、新しい普遍による抑圧であると感じるところから反発も覚えるのだと思いますが、本当に彼女はそうなのか、なんですよね。

──それを武邑先生は否定されるわけですね。むしろ彼女は、ある固有の部族の予言者であるとおっしゃるわけですから。
はい。そうなんです。じゃあグレタさんはいったいどういったトライブの偶像なのかといえば、わたしの見立てでは、おそらく「ソーシャルメディア」ということになるのではないか、という気がします。
──えええっ。どういうことですか?
グレタさんおよび、彼女のデモに賛同したと言われる世界中の若者たちの領土は、おそらくソーシャルメディアで、彼女らはその空間内においてつながっているんですよ。グレタさんが体現する新しい気候の神話が、ことさら大人を苛立たせるのは、それがソーシャルメディアというものと深く関わっているからのようにも感じます。
──気候変動は、ソーシャルメディア世界の新しい神話だ、ということですね。
あくまでも仮説ですが、そう考えると自分としては腑に落ちるところがあります。若い世代がソーシャルメディアを通じて感得される世界像というのは、ハナからグローバルですし、しかも実感的にそうなんですね。地球の裏側に自分と同じような個人がいるという実感は、テレビや新聞といったマスメディアでは体得できないものでしたから、外から見るとそれは得体のしれないものなのだとは思います。そのなかで育まれた神話は、たしかにうさんくさくは見えるのでしょうけれど、注意しなくてはならないのは、批判する人たちの言うことも結局はうさんくさいということで、気候変動という問題系は、そもそも誰が何を言ってもうさんくさくなる構造を孕んでいることを、わたしたちは、つねに留意しておいたほうがいいのではないかと思います。
──「神学論争」になってしまいがちですもんね。
そうなんです。気候変動はそういう意味で情報の問題ですし、「天」という神の領土が関わってくる分だけ文化的なものでもあり、そうであればこそ、「中世化」というものを最も先鋭的に表出させてしまうのではないかと思います。
──そうだとすると、日本は逆にどういう神話のなかを生きているんですかね?
昨年だったと思うのですが、ジェームズ・プライドルという方が書いた『ニュー・ダーク・エイジ』という本について議論をするイベントをやったのですが、そこで得た気づきはいくつかありまして、そのひとつは、まず、そもそも科学技術というものが、天候というものと深く関わっているということです。イベントをレポートした文章がありますので、長いのですが、引用させてください。
「そもそもコンピュータやデジタルネットワークをつくりあげた計算論的思考は、気象予測、天気を計測し、モデル化し、それを予測することによって、あわよくば天気そのものをコントロールしたいという欲望から生まれ出たものだという。そして、その欲望の追求こそが地球規模の気候変動を促していくというパラドクスを生み出したという指摘は、なるほどと頷かされる」
「『気象を操作したいと願った人間の歴史』という本は、環境改変への執着がやがて軍事技術へと転用され、50年代から70年代にかけて、朝鮮半島やヴェトナムやラオス、カンボジアなどで展開された「人工降雨作戦」などへと発展していった経緯などを詳細に明かしている。コンピュターの父として名高いフォン・ノイマンが1955年に執筆した論文が本書で引用されているが、「人類はテクノロジーより長く生き残れるか」と題された文章は、『ニュー・ダーク・エイジ』と響きあうようで興味深い」
「フォン・ノイマンは気候制御を完全に『常軌を逸した』産業と呼んだ。(中略)地球の熱収支や大気の大循環に手を加えると、『核戦争やこれまで起きたあらゆる戦争の脅威よりも徹底的なやり方で、個々の国の事情をあらゆる他国の事情と混ぜ合わせることになる』。(中略)フォン・ノイマンは気象や制御の二面性を明らかにした。最も大事な問題は、『人間に何ができるか』ではなく『人間は何をすべきか』だった。(中略)最終的な解決策を求めながらも見つけられないまま、彼はこう述べている。生き延びる見込みを最大限に増す鍵は、忍耐、柔軟性、知性、謙虚さ、熱意、監視、犠牲、そして十分な幸運であると」
──なるほど。
続けて引用しますね。
「それほどまでに気候変動は重大なイシューであるにも関わらず、それにしてもなぜか自分にはどうしてもピンとこない、という感覚は抜き難い。そんなことを、池田純一さんに漏らすと、こんな答えが帰ってきた。
『それは、ノアの箱舟があるからでしょう』
言われてみれば、その物語のなかの雨と洪水は世界を破滅にいたらせる、それはそれは恐ろしいものなはずなのだが、ノアと世界の破局の物語を、趣旨がいまひとつわからない教訓話のようなものとしてしか読まなかった身としては、その恐ろしさがいまひとつ真に迫ってこない。けれども、それが西洋ではいまなお重要なモチーフになっていることは、グリーンランドのズヴァールヴァルにある種子貯蔵庫が、ずばり「箱舟」と呼ばれていることからも伺うことができる。著者のブライドルも『ニュー・ダーク・エイジ』のなかで、その箱舟の重要性を熱を込めて語っている。
それで思い出したのは、だいぶ昔に熊野の熊野本宮大社を訪ねたときのことだ。
ともに旅した民俗学者の畑中章宏さんがそこで教えてくれたのは、熊野本宮大社は、現在建っているところにあったのではなく、3つの川の合流地点にある「大斎原(おおゆのはら)」と呼ばれる中州に建っていたということだった。
中洲に建っているので、当然大雨で増水・洪水が起きるたびに流されてしまう。けれども、そうやって数年か数十年に一度流され、そのたびに再建することが、ちょうど伊勢神宮における遷宮と同じ役割を果たすことになっていたらしい。大雨や洪水はたしかにカタストロフにはちがいない。けれども、それは破滅であると同時に、再生のための禊でもある。そこでは時間は直線的に進むのではなく、ぐるぐると円を描くようにまわる。空や雲がもたらす破壊は、いわば織り込みずみ。災害列島と言われるこの島々に代々暮らしてきた人たちにしてみれば、巨大災害は避けられないものとして共同体の時間のサイクルのなかにあらかじめ埋めこまざるを得なかったにちがいない。
そうした時間感覚なりが自分のなかにも受け継がれて、それが気候変動の脅威に対する望ましい理解を阻んでいるのかどうかはうっかり即断はできないが、考えれば考えるほど「空を制御しよう」などという大それた欲求は出てきそうにない」(若林恵, 『ニュー・ダーク・エイジ』を読む, academyhills)
──あー、なるほどー。気候がどんどん予測不能、制御不能になっていることを、西洋文化はことさら恐れているのに対して、日本では、最初から予測不能、制御不能なものとして扱われている、ということですね。それはたしかにそうかもしれませんね。
これはあくまでも自分の勝手な見立てなので間違っているのかもしれませんが、少なくとも気候というもの(遡ると「天」というもの)の理解が、それぞれの文化の基層の部分で違っているのは間違いないように思います。西洋がそれをもって科学技術を進展させてきた気候へのオブセッションは、やはり日本人には希薄なのだろうとは思います。

──困りましたね。
とはいえ、日本は日本で、ただぼんやりと天に翻弄されるがままでいたかといえばそんなことはなく、もちろんさまざまな知恵を発動してきたわけですが、その知恵は、気候そのものをターゲットにするのではなく、それがもたらす「災害」にむしろ焦点があったのだろうと思います。
──ああ。気候変動の責任をどう考えるのか、と詰問されるよりは、災害をめぐる知恵を出せ、と言われるほうが、考えやすそうです。
そうですよね。いずれにせよわたしたちも一応近代以降の世界を生きているわけですから、そのフレームから勝手に外れてしまうわけにもいかないのは、もとより当たり前のことなのですが、その一方で、世界が本当に中世化しているのであれば、これまでのような世界連邦的イメージをもってして、それに向き合うことの限界も今後ますます露呈してきてしまうようにも思えますので、その議論の枠組みそのものを検討し直す必要があるのではないかと思います。ファクトとフェイクの境目がもはや見えない状況を「普遍的理性」で押し返そうというのでは、議論はむしろ後戻りしてしまいかねません。普遍的理性というものも、結局のところひとつの神話でしかないわけですから。
──うーむ。
本が見つからないので、うろ覚えのままお話してしまいますが、先ほど引用したイリイチは、別の本『生きる意味:「システム」「責任」「生命」への批判』のなかで、宇宙から撮影された「地球」のイメージというものが、わたしたちの生きる科学技術の神話世界をいかに強化しているかを語り、たしか、「『地球』は触れることも匂いを嗅ぐこともできない」という言い方で断罪していたはずです。「地球」や「環境」といった概念(イリイチはそれを「ことばのアメーバ」と呼んでいますが)をできるだけ排して、触れることのできるなにかとして、それらを取り戻す回路が必要なのだろうと思います。そうしたことを踏まえると、日本ではむしろ気候変動の話題は、まずひとつは「災害」をめぐる問題としてナラティブ化すべきようにも感じます。そこには手に触れる具体性が、「地球」と言われるよりはありますから。
──なるほど。
最後になってしまいましたが、今回の〈Field Guides〉は、「気候テック」というお題ですが、ここで言う「気候テック」は、かつて「クリーンテック」、もしくは「グリーンテック」と呼ばれていたもので、こうしたことばは下手すると、イリイチ言うところのアメーバ化を促進しかねませんので、それらが、どういう回路を通じて、わたしたちのコミュニティや社会を助けうるのかをよほどちゃんと考えないと、結局は普遍的管理に隷属させられるだけになってしまうように危惧します。自分は「持続可能性」という概念は決して嫌いではないですが、それを指示できるのは、あくまでも物事の一回性や偶発性が保全される前提においてのみです。そうでない持続可能性は、ただの延命治療ですし、ただのエコディストピアじゃないですか。近代のそうした管理構成から逸脱するという意味において、自分はさっきからお話している「中世化」は面白いわけですし、なんならちょっとした希望と感じさえします。
──そうなんですね。
というところが、今回の〈Field Guides〉を語る上でまず思うところでして、実際の中身は、次回見てみることにしましょう。
──長い前置きでしたね(笑)。
すみませんでした。
若林恵(わかばやし・けい) 1971年生まれ。『WIRED』日本版編集長(2012〜17年)を務めたのち、2018年、黒鳥社を設立。NY在住のジャーナリスト 佐久間裕美子さんとともホストを務める「こんにちは未来」をはじめさまざまなポッドキャストをプロデュース。本連載をまとめた単行本の発売は12月8日。同じく黒鳥社から刊行されるメディア美学者・武邑光裕さんの『プライバシー・パラドックス』は、11月30日発売です。
🎓 ウェビナーシリーズ「Next Startup Guide」がスタートします。会員の皆さんは、無料で参加いただけます。第1回の開催は11月26日(木)。申込みはこちらから。
🎧 リニューアルしたPodcastもぜひチェックを。最新回では、メディアアーティストの草野絵美さんをゲストにお招きしています。Apple|Spotify
👀 Twitter、Facebookでも最新ニュースをお届け。
👇 のボタンから、このニュースレターをTwitter、Facebookでシェアできます。ニュースレターの転送もご自由に(転送された方へ! 登録はこちらからどうぞ)。