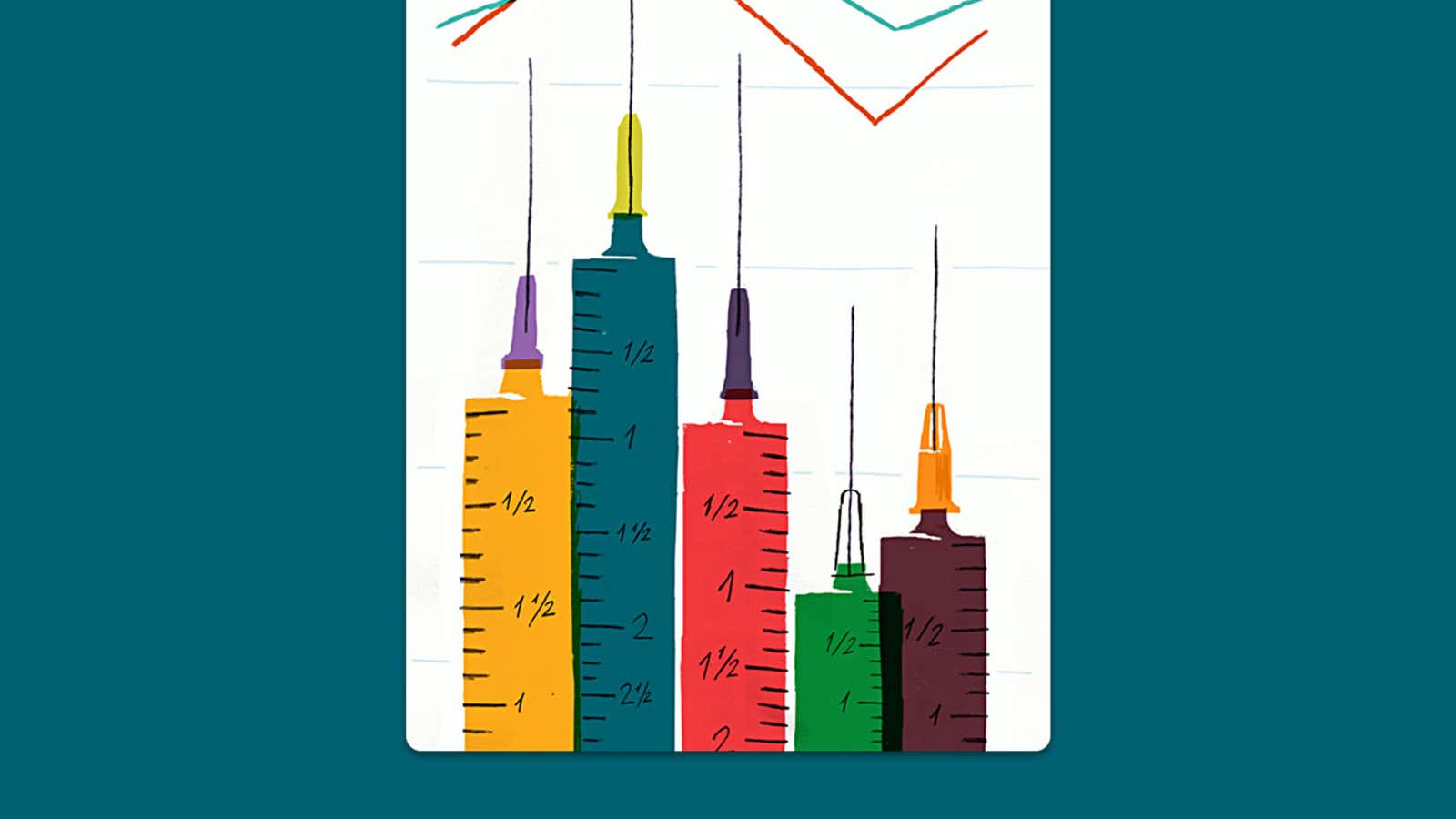A Guide to Guides
週刊だえん問答
Quartz読者のみなさん、おはようございます。週末のニュースレター「だえん問答」では、世界がいま何に注目しどう論じているのか、米国版Quartzの特集〈Field Guides〉から1つをピックアップし、編集者の若林恵さんが解題します。今週のテーマは「2021年の世界経済」です。

──ごきげんいかがですか?
ダメですね。
──どうしたんですか?
わからないんですが、今日はまったく原稿が書けないです。
──いま、土曜日の23時ですが、普段ですと、もう7割方は終わっているようなタイミングですよね。
まったく手がつかなくて、洋服でも買おうかとずっとネットを見てました。
──ダメじゃないですか。……オンラインで洋服、よく買うんですか?
どの程度買うと「よく買う」ということになるのかわかりませんが、ちょこちょこと何かしら買ってますね。
──最近は何を?
ミュージシャンのマーチャンダイズ(マーチ)ですが、LomeldaのTシャツやらBig Thiefのビーニーやら買いましたね。LomeldaのTシャツはまだ届いてないですが。

──マーチは楽しいですよね。
ですね。言ってもマーチはTシャツやキャップが主流で、それこそまだ「お土産」の域を出ないところはありますが、おそらくミュージシャン側もそれなりに商品性にこだわるようになってきているように感じます。それこそ、カニエ・ウェストやビヨンセのように自身のブランドをもって、本格的にアパレルビジネスをしている人もいますから、そういう感じでより進化すると嬉しいなと思うところはありますね。
──どういうことでしょう。
自分はニットのセーターが好きなので、Big Thiefのセーターが売られていたら買っちゃうだろうなと。
──ああ、なるほど。
もちろん、ミュージシャンが皆、ファッションデザインのセンスをもっているとは限りませんから、それが簡単なことだとも思いません。とはいえ、いまどきのミュージシャンはPVから衣装まで、ある程度ディレクションにまでコミットしているようになっていますので、具体的なデザインはプロがやったとしても、まだまだやれる余地があるんじゃないかと思ったりします。というのも、ファンとしては、そうした複合的なセンスを信頼しているということなんだと思います。
──ミュージシャンに限らず、「いまどきの表現者」はそうした包括的なセンス全体が売り物になっている、ということでもありますよね。
ですね。ミュージシャンのマーチも最近は色んなアイテムが出るようになっていまして、それこそ音楽メディアの『Pitchfork』は、おそらく2017年から、毎年年末になると「Best Merch」を発表しています。それを見ると、それこそBig Thiefのエイドリアン・レンカーは、自身のソロアルバムの発売に合わせて、ジグソーパズルなんかを出しているんですね。
──へえ。かわいいですね。
そういえば、自分もこの記事を見てLomeldaのキャップがかわいいなと思って、マーチサイトに飛んだのでした。
──まんまと買わされた、と(笑)。
おっしゃる通りです。で、マーチについて色々と記事を探ってみたのですが、アメリカの『Vogue』が気になる記事を昨年8月に出しています。「お気に入りの場所を自分のものにしてくれるマーチ」(Merch That Brings Your Favorite Places To You)という記事でして、記事の冒頭にはこんなことが書かれています。
「2016年に隆盛を極めたマーチのトレンドが2020年に再び盛り上がりを見せている。マーチブームの第一波は、リアーナの『Anti』ツアーや、ジャスティン・ビーバーの『Pupose』ツアーといった、特別なイベントの記念品が主流だった。2020年のマーチはちょっと違う。マーチは、これまでも自分のお気に入りの場所をサポートしたりレペゼンしたりするために買うものだったが、今年のマーチは、そうした場所を自分のものにするためのものとなっている。スローガンTシャツ、グラフィックスウェットシャツやトートバッグは、レストランやショップなどをサポートし(そして思い出し)、失われた休暇を自分の家で楽しみ、数カ月にわたって訪れることを禁じられた文化的な空間へと繋がることを可能にしてくれる。小さく、タンジブルなやり方で、これらのモノたちは、たとえそれが象徴的な意味しかもっていなかったとしても、自分のコミュニティに繋がることを助けてくれる」(Rachel Besser「In 2020 The Best Merch Brings Your Favorite Places To You」2020/8/2、Vogue)
──ははあ。たしかに、アメリカでは、カフェやパン屋さんがTシャツを売っていたりしますもんね。面白いですね。
そうなんです。そう言われてみると、ミュージシャンの場合でも、ライヴができない時間のなかにあってマーチというのは、アーティストをサポートするための重要な収益回路ではあったわけですよね。
──はいはい。そういえば、ライヴハウスがTシャツをつくって販売しているのを買っている知り合いもいました。
そうしたなか、これは昨年6月の『Vogue』の記事ですが、Merch Aidという非営利団体がR/GAというデザイン/マーケティング会社のメンバーによって創設されたことがレポートされていまして、この団体はロックダウンで困っている飲食店や小売店、とりわけ黒人によって経営されているスモールビジネスをサポートすべく、アーティストたちと組んでマーチの制作・販売を行っています。
──めちゃいいですね。
そうなんです。記事には、創設メンバーのインタビューが掲載されていますが、ファウンダーのひとりはファッションとマーチの関係性をこんなふうに語っています。ここは非常に面白いところですので、少し長いですが、引用させていただきます。
「Q:マーチということばは、ファッションというより広い視点からみると非常にトリッキーなものでもあります。これまでも、Tシャツは、政治的マーケティングのツール、もしくはブランドの『意識の高さ』をアピールするためのPR手法として利用されてもきました。Merch Aidとしては、マーチというものが、そうではなく、より意義と実行力のある変化をもたらしうるものであるためには、何が必要だと考えていますか?
A:広告の世界ではたしかにメッセージ性の強いマーチャンダイズを、ただ目立ったり、賢く見せたりするためのPR施策として使うことはありました。けれども、消費者はブランドが自己満足のためにやっているかどうかを見抜くことができます。消費者は、非営利組織をサポートしようとしているブランドをサポートしたいわけで、ただトレンドに乗りたいわけではありません。
Merch Aidが証明したのは、ファッション産業のなかにおいても、正しく用いることができればマーチは意味のあるインパクトをもたらしうるということです。マーチはある特定のイシューをお客さんに対して啓蒙することを可能し、同時にそれを通してアクションに参加させることができます。お客さんがTシャツを欲しがるのは、人びとが、自分がそのトピックについて心から賛同しているからで、それをみんなに見てもらうことを望んでいるからです。ファッションは『スタイルの誇示』であることから離れ、『価値の誇示』へと移行しています」(Brooke Bobb「Can Fashion Merch Create Real Change? This Group of Creatives Proves Its Power」2020/6/22、Vogue)

──佐久間裕美子さんが、著書の『Weの市民革命』のなかで、「Wear your values」という標語を紹介されていましたが、まさにそれですね。
おっしゃる通りです。そうした論点から『Vogue』はメディアとしても、マーチ関連の記事をちょこちょこ掲載していまして、10月には「選挙前に投票マーチを買うならこの店」(All of the Voting Merch to Shop Ahead of the Election)、12月にはアレクサンドリア・オカシオ・コルテスのマーチ騒動についてレポートした「AOCのマーチをめぐるドラマ」(What’s the Drama Over Alexandria Ocasio-Cortez’s Merch?)、年末にはジョージア州の選挙前に「公正な選挙を支持するマーチで、ジョージアの選挙をいま一度思い出そう」(Make Sure Georgia’s On Your Mind With Merch That Will Support a Fair Run-Off Election)などを公開しています。
──どれも政治絡みなんですね。
そうなんです。ただ単にミュージシャンを応援する、といったようなところから、コロナを経て、マーチというものの意味性がドラスティックに変わってきていることは、いまさらですが、かなり明確になっていますよね。もっともそうは言っても、根っこの部分は、自分の好きなブランドやお店やアーティストを応援するということにおいてさほど変わっていないという点は重要だと思うんです。
──と言いますと?
平時においてはただの記念品だったものが、パンデミックによるロックダウンや活動休止を余儀なくされた環境のなかで、それが一種の「共助」の回路になったことで、そこに政治性が強く付与されたということなんだと思うんですが、それが「共助」の回路だからといって、別に好きでもなかったり自分と関わりのなかったりする場所や人のTシャツを身につけたところで意味はないわけですし、逆にそれこそ、ただ「意識高い」ことを表明するためだけの身振りでしかなくなってしまうわけですね。
──結局は「スタイルの誇示」じゃんか、と。
そうなんですよね。その辺のバランスは結構難しいですよね。
──アメリカの議会に襲撃した人たちが着ていたTシャツも、なかなかヤバかったですよね。
ですね。トランプ支持者たちのTシャツや旗などに描かれたイラストやスローガンを読み解いた非常に面白い動画が『TIME』に掲載されています。こうした図像学的な読み解きは、さまざまな思想信条の人たちが流れ込んでいたトランプ支持者たちの多種多様なコンテクストを知る上で非常に有効であることが、この動画からはわかります。また、この動画では触れられていませんが、襲撃者のひとりが着ていた「キャンプ・アウシュヴィッツ(Camp Auschwitz)」と書かれたロンTは、ETSY上で販売されていたものだったそうですが、この商品も販売していた事業者も、プラットフォームから追放されたことを『Reuters』が報告していましたね。
──あ、そうなんですね。どこであんなものを売っているのかとは思いましたが。
ちなみにですが、ずいぶん前に買ったスレイヤーという大御所バンドのロンTがありまして、割と気に入って着ていたんですが、デザイン的には、似た感じなんですね。
──やばいじゃないですか。
とはいえ、デザイン的には、メタル系バンドのマーチの多くはあんな感じですから、それ自体がダメということにはならないとは思うのですが、ただ、自分がもっているロンTには、たしかナチスの将校のような図像が描かれていたようにも思うんですね。それをもってナチスを賛美しているわけではないのですが、なにせ、スレイヤーの初期の名曲「Angel of Death」という曲は、ナチスで化学実験を行っていたジョセフ・メンゲレを扱った歌でして、リリース当時からこの曲についてはすったもんだがあったとされていますが、それをいまの時代状況のなかで着るのは、どうなんでしょうね?
──スレイヤーのメンバー自身がプロ・ナチ(親ナチス)だったわけではないんですよね?
それについては2016年の『Rolling Stone』の記事がありまして、そのなかでメンバーは、歌詞自体は一種のドキュメンタリーであって賛美しているわけではない、と語ってはいるのですが、一方で、この曲を書いたジェフ・ハンネマンは、第三帝国についての本はよく読んでいて、そのナチスの「エクストリームさ」に魅せられたと語っていたりはするんですね。
──うーん。
これは以前、自分が編集した『次世代ガバメント』という本のなかの「官僚制とヘビーメタル」というコラムで書いたことでもあるんですが、メタルと官僚制というのは実際のところ非常に相性のいいものでして、もちろんナチスのような超エクストリームな官僚主義を肯定するような歌こそ歌いはしないのですが、それに魅せられてわざわざ歌にまでしてしまうところに、ある種の親和性が滲み出てしまうんですね。どうでもいいような余談ではあるのですが、メタル好きとしては、この辺、なかなか微妙な気持ちになってしまうところでして。
──どんどん本題から離れて言ってますが(苦笑)。
すみません。いずれにしましても、トランプサポーターの「マーチ」を改めて見てみますと、これはスポーツチームなんかでも同様ですが、「マーチ」というものは、放っておくとユニフォームのようなものになっていくものでもある、というところが厄介なところでもあるんですね。それは、根っこのところでいずれの陣営にとっても「連帯の証」であるわけですが、それがどこかのポイントを超えると、個と個の連帯であることを離れて、一元化された群衆へと変わっていくというのは、やはり不気味なところではありますね。

The Economy in 2021
「ぐにょぐにょ」な世界
──難しいですね。
で、だいぶ話が関係のない遠くまで来てしまったのですが、最初にマーチの話をしたのは、スレイヤーのお話をするためではなく、マーチというものが、単なる記念品やグッズといったものからハミ出して行っているところの面白さを語りたかったからなんですが、要は、マーチの世界で起きていることは、例えばTシャツというメディアを通して、ファッション産業と音楽産業が融解していってしまっているというところで、これまであった産業ごとの隔たりというものが変なやり方で融解していっているのは、何もファッション業界に限ったことではないのではないか、というお話をしたかったからなんです。
──ひどい遠回りじゃないですか(苦笑)。
というのも、今回の〈Field Guides〉は「2021年の経済」がお題でして、そのお題にどうもいまひとつ乗り切れないせいで、こんな遠まわりをしたわけなのですが、なぜ乗り切れないかと言いますと、そもそも自分にはマクロの視点から経済を眺める発想が完全に欠落しているのと、そもそも「経済」っていう概念自体も、いまお話したような「融解」の対象なのではないかと思うからだったりするんですね。
──どういうことですか?
ここまで見てきたマーチの話なんかは格好の例だと思いますが、ただの記念品やお土産であるという点で、ただの消費材だと思っていたものが、いつの間にかポリティカルなツールになっているわけですよね。という意味で、ここからが経済の話でここからが政治の話、というようには、もはやそれぞれを切り出せなくなっているんだと思うんです。
──ふむ。
ちなみに、今回の〈Field Guides〉のなかで個人的に面白かったのは、「2021年のグローバルエコノミーを妨害しうる鬼札」(The wildcards that could sabotage the global economy in 2021)という記事で、「バブル」「香港」「家主」「アメリカ財政」「気候変動」「サイバーリスク」「ブレグジット」「戦争」「インフレ」「戦争」といった項目が2021年の「ブラックスワン」として挙げられているのですが、よくわからないなりに興味があるのは「家主」という項目でして、ここで何が語られているのかと言いますと、こういうことです。
「コロナ禍のなか閉鎖を余儀なくされたバー、レストラン、ジム、ホテル、オフィス、サロンなどには共通項がある。彼らは家主に家賃を払っていないのだ。仮に不況が終わったとしても、都市部がかつてのような賑わいを取り戻すには数カ月はかかるだろうし、リモートワークの時代にあって人びとのビルの利用の仕方は永遠に元に戻らないかもしれない。こうした事態は、商業不動産業者を危機に追い込むことになるだろう。パンデミック前に都市部の地価がインフレ気味に上昇していたように見えていたのだからなおさらだ。アメリカの商業不動産の負債は2020年に3兆ドルという史上最高額に達した。もはやキャッシュを生み出すことのない不動産から借金を少しずつ返済していくためにコストのかかる努力は避けられない。加えて、不況が長引き、さらに都市生活にもたらされた変化が想像していた以上に永続性のあるものであった場合、新規開発は落ち込み、再起は一層困難になるだろう」
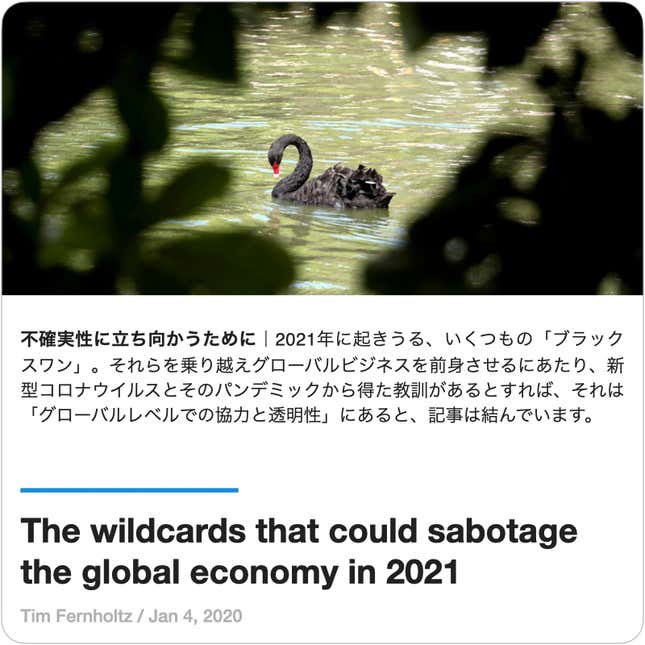
──なるほど。不動産ビジネスが大きく崩壊していくことになる、というわけですね。
不動産ビジネスのテクニカルなところはよくわからないのですが、リモートワークによってオフィスが不要になっているという状態がいつまで、どの程度、常態化・永続化するのかという、実際のところ誰にも読めないことが非常に大きな懸念点になっているのは、当たり前といえば当たり前なのですが、やはり興味深いところですよね。
──実際、どうなるんでしょうかね?
例えば、10人ほどの小さな事務所を経営していた知人は、早々にオフィスを解約し、完全リモートにしました。その彼にしたところで、コロナが収束した際に改めて新規にオフィスを借りるのかどうか、直接聞いてはいませんが、おそらく悩ましいところだろうとは思います。もちろん小さな会社で、大型の設備が必要な業種でもありませんから、参考になる話かどうかはわかりませんが、大企業にしたって、リモートワークが長引けば長引くほど、ワーカーのいない状態でフロアあたり何百万、何千万とかかるようなオフィスを構えていることの合理性を見直さざるをえなくなるであろうことは予測できますよね。
──そりゃそうですよね。
加えて、リモートが長引けば長引くほど、家の近くにワークスペースを確保したいといった需要は高まってくるでしょうし、それをチャンスと見て郊外型のコワーキングオフィスのビジネスなどが増えてくるとなれば、ますます都心のオフィスに戻る理由がなくなっていくことにもなりますよね。
──難しい判断ですね。ワクチンが広まればひとまずこの状況は収束するだろうという見立てはあったとしても、それがいつ達成されるのかは諸説ありますし、変異株のようなものが出てきてしまっているなか、そもそもそのワクチンで大丈夫なのか、といった問題もありますよね。
どのタイミングで、何をどう判断するのかは本当に難しい状況ですが、とはいえ、ずっと様子見をしているわけにもいかないとなると、少なくともオフィスにはもう人は戻ってこないという前提で、新しい可能性を追求したほうがいいんじゃないかという話も当然出てきます。不動産についていえば、例えばニューヨーク市はすでに新しい動きが出ているそうで、『The New York Times』の「瀕死のミッドタウン:オフィスはアパートになるべきか?」(Midtown Is Reeling. Should Its Offices Become Apartments?)が、それを詳細にレポートしています。

──面白そうです。
まず、ニューヨーク市の状況を簡単に概説しておきますと、こういうことになります。マンハッタンのオフィス地区であるミッドタウンの現在の空き家は全体の14%で、これは2009年、つまりリーマンショック以来最も高い数値となっています。さらにマディソン街に面した小売店の3分の1が空き家になっており、100万人いるオフィスワーカーのうち出社しているのはわずか10%だそうです。
──ひえー。
また、ニューヨーク市全体でみても新規のビル建設の申請は2020年で22%も落ち込んだそうです。こうした状況のなか、ニューヨーク不動産協会のプレジデントは、「これがどん底というわけではない」と警鐘を鳴らしています。
──ふむ。
こうした苦境のなか、家主とテナントが反目しあうケースも増えているそうで、パンデミックを理由に賃料を支払わない大手テナントを家主が訴えたり、そうした取り立てに対してテナント側が「店が開けられないのに、家賃を払えとは何事だ」と反撃したりするようなケースが頻発しているそうです。
──さもありなん、ですね。どちらも背に腹は変えられない状況ですからね。
そうしたなか、先の業界団体は、市や州に対して、オフィスビルを住居へと簡単にコンバートできるよう規制を緩めるように働きかけているようなんです。
──へえ。面白いですね。
マンハッタンには4億平方フィート(約3,700万平方メートル)のオフィススペースがあるとされていますが、そのうちの1.4億平方フィート分は平均的なクオリティのもので、なかには老朽化したものも相当あるそうです。そうしたオフィスを住居に転換するとマンハッタンのなかだけでも1万の住居を確保できるそうで、こうした転換を行うにあたっては、一定の割合で廉価な住居を用意することを条件にするといったアイデアも提出されています。
──いいアイデアじゃないですか。
市の担当者も「賢いアイデア」と語っていると記事は書いていますが、実際パンデミック以前のニューヨーク市は、ワーカーの増加にハウジングが追いつかないという問題を抱えていたそうですから、このアイデアによって、それが解消されることも期待されます。さらに、ミッドタウンのようなオフィス専用の街区は、日中には人出はあっても夜にはまったく人がいなくなってしまいますから、ある意味非効率ですし、飲食店や小売店なども少なく楽しくないエリアになってしまいがちです。ローワーマンハッタンも、かつてはそのようなエリアでしたが、住居を増やしたことで活気ある街へと変貌したと言われています。
──なるほど。街をオフィス専用、住居専用といったかたちで区切っていると、かえって効率が悪いし、活気もないしレジリエンスも低い、ということですよね。
そうなんです。また、この提案には、パンデミックの打撃を強く受けているホテルを住居に変えることもアイデアとして含まれているそうです。
──観光も出張もなくなっているわけですからね。
そうなんです。ホテルについては、先日とあるイベントで、大阪の独立系ホテルを経営している方とご一緒させていただき、色々とお話をさせていただいたのですが、観光客の減少によって、大きな打撃を受けているものの、その一方で、価格が下がっていることから、地元の人が使うケースが増えているとおっしゃるんですね。
──ん? どういうことですか?
仕事で遅くなった人がタクシーを利用せずホテルに泊まるケースが増えていたり、それこそリモートワーク用の空間として長期で借りたりといった方もいるそうです。
──なるほど。一種のシェアオフィスとしてホテルを利用するということですね。そういえばちょっと前にカプセルホテルがシェアオフィスに転向しているといった記事を見かけたような気がします。
一般的なホテルチェーンでもそうしたサービスが始まっていると聞きますので、それ自体は、取り立てて驚くべきことでもないのかもしれませんが、この話が面白いは、まさに前半にマーチについてお話したことと同様の「融解」が起きているところだと思うんです。
──ああ、なるほど。つまり、ホテル、オフィス、住居といったこれまでまったく別のものとセグメントされてきたものが、ぐしゃっと溶け合ってしまうということですよね。
このときのホテルは、家の延長でもありオフィスの延長でもあるわけですよね。ここがさらに面白いのは、その使い方は、あくまでもユーザーが決定するというところではないかと思うんです。観光のための宿泊施設として使う人もいれば、オフィスとして使う人もいるし、もしかしたら住まいとする人もいるかもしれない。そのときに供給側に必要なのは、その使い方に合わせて、例えば時間貸しもできるし、1カ月滞在での賃貸もできるといった柔軟性ということになります。

──そうなっていくと、それまでも価格帯の設計や、そもそものビジネスモデルも変わっていくことになりそうですね。
ニューヨークの事例に戻りますと、提案されているアイデアに対して、古いオフィスビルをたくさん抱えている業者のなかには、「古いオフィスビルの需要は十分にある」と住居への転換という提案を否定する方もいらっしゃるそうですが、いまお話しした考えに立てば、今後のありようとしては、そこを住居として利用しようがオフィスとして使用しようが、利用する側が決めればいい、というような格好になっていることが望ましいように思えてもきます。もちろん、さまざまな規制はあるでしょうから、それがすぐに実現するわけもないとは思うのですが、とはいえ、リモートワークによって、もはやすでに空間を機能ごとにゾーニングするような設計思想は、なし崩し的に崩壊しているとも言えるわけですから、そうしたぐにょぐにょした状態を、なんとかかつての建て付けのなかに回収しようという発想は捨てたほうがいいんじゃないかという気はします。
──そのぐにょぐにょした状態のなかに新たなチャンスがある、ということですよね。
そんな気がします。そうしたぐにょぐにょした状態も、そこにやがて名前が与えられ、ビジネスモデルが見出され、そして一般化していけば、それ自体が秩序だったものであるかのように見えるようなことになっていくと思うんですね。
──たしかに、スマホみたいなものだって、最初はぐにょぐにょした何かにしか見えなかったわけですもんね。
そう考えると、社会というもの、あるいは経済というものは、そこに生きる人びとのニーズや変な欲求に押されながら、そうやって絶えずぐにょぐにょと動いているものなのだろうと思えてきますよね。今回の〈Field Guides〉は「2021年のグローバルエコノミー」というお題で、結局それについてはほとんど触れていないのですが「いつ、どうやって経済がノーマルに戻るのか」というのは、もちろん考えておくべきことではあるとは思います。こんなかたちで強制的に経済がストップさせられるような事態は極めて稀なことなのですが、とはいえ、そのなかでも人は生きていかなくてはなりませんから、ある意味抑圧された「生きる欲求」みたいなものが出口を求めてさまよっているのが現状であるように思うんですね。で、そうやって外に向かって押し出されている出口のない欲求に出口を与えることができれば、それが新たなビジネスになりうるわけですから、経済ということでいえば、やはり、そういうところに目を向けておくことは意味あるんだと思います。
──現状の制度や産業構成のなかで考えていてもダメだぞ、と。
いまのようなエクストリームな状況であればこそ起きている変なことは、たくさんあると思いますし、それはおそらく、これまで自分たちが自明だと思ってきた領域区分やジャンル構成などの間の隙間で起きているような気がしますので、そういうところに目を凝らしておくのは、大事なんじゃないかと思います。ぐにょぐにょしたなにかのなかにこそ次の可能性はきっと見出されるんですよ。
若林恵(わかばやし・けい) 1971年生まれ。『WIRED』日本版編集長(2012〜17年)を務めたのち、2018年、黒鳥社を設立。NY在住のジャーナリスト 佐久間裕美子さんとともホストを務める「こんにちは未来」をはじめさまざまなポッドキャストをプロデュース。これまでの本連載を1冊にまとめた『だえん問答』、好評発売中です。
🧑💻 世界各地で活躍する日本人VCが現地の声で伝える月イチのウェビナーシリーズの第3回は、シンガポール。1月28日(木)、Rebright Partnersの蛯原健さんをお招きして開催します。お申込みはこちらのフォームから。
🎧 月2回配信のPodcast。高校卒業後すぐにMITメディアラボで研究者としての活動を始め、現在は「ワイルドサイエンティスト」として生物学の民主化をテーマに研究を続ける片野晃輔さんを迎えたトーク前編の配信がスタートしています。Apple|Spotify
👀 Twitter、Facebookでも最新ニュースをお届け。
👇 のボタンから、このニュースレターをTwitter、Facebookでシェアできます。ニュースレターの転送もご自由に(転送された方へ! 登録はこちらからどうぞ)。