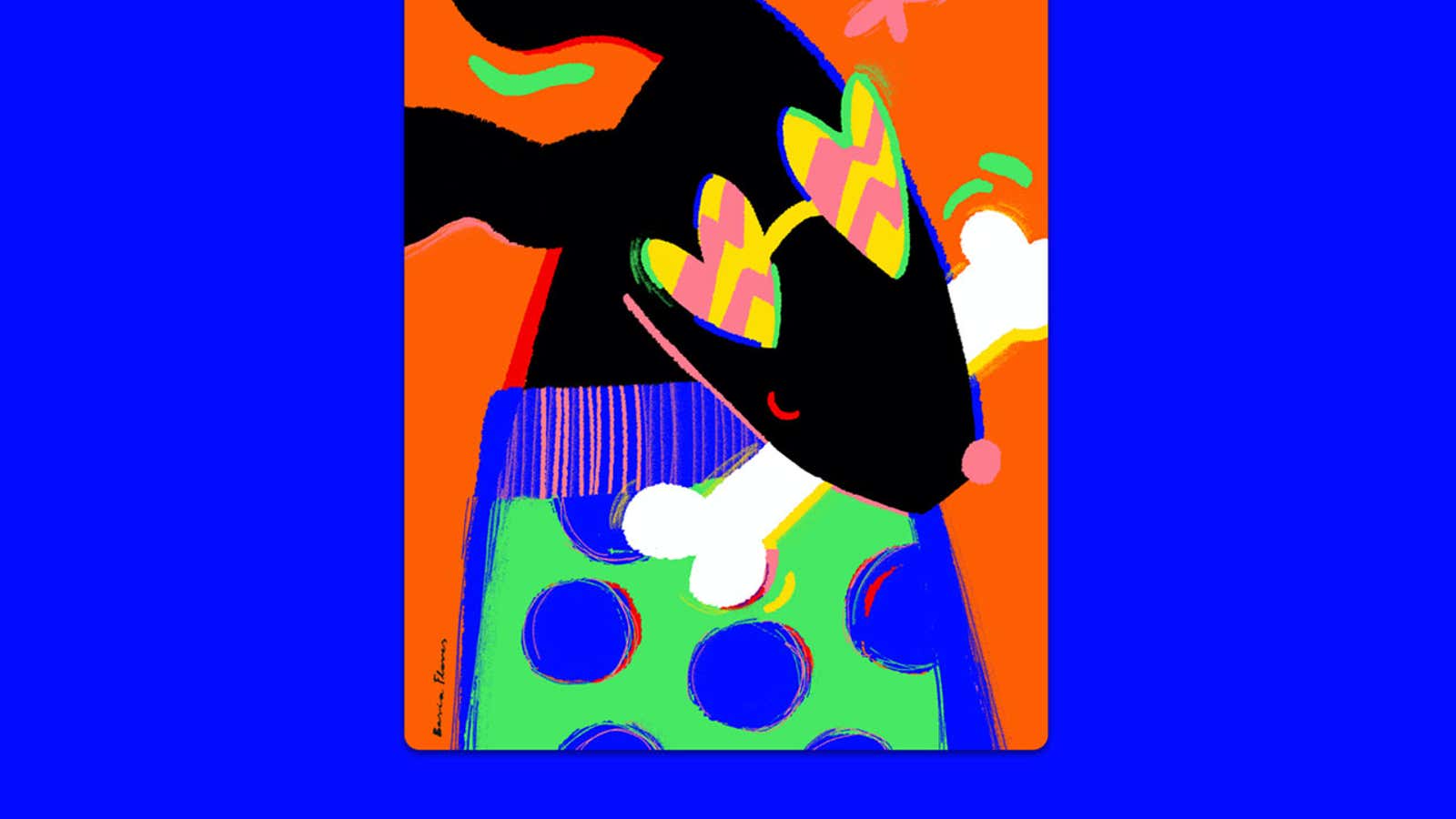A Guide to Guides
週刊だえん問答
Quartz読者のみなさん、こんにちは。週末のニュースレター「だえん問答」では、世界がいま何に注目しどう論じているのか、米国版Quartzの特集〈Field Guides〉から1つをピックアップし、編集者の若林恵さんが解題します。今週のテーマは「ペット産業」です。

──こんにちは。いかがですか?
なんだか気が滅入りますね。
──緊急事態宣言のせいですか?
おそらくそうなんだと思いますが、それが理由なのかどうかもあんまり定かでなくなってきてしまいました。毎日それなりに違う1日を過ごしているはずなのに、同じ1日のような気がしてきちゃってるんですよね。
──デジャヴのような感じですか?
それとはちょっと違うような気もするんですが、なんか檻のなかにいるような感覚というか。映画やしょうもない動画とソーシャルメディアばかり見ているせいのような気もしますが。何かを待っていて、それが来るまでの時間を無為にやり過ごしている、という感じなのかもしれません。
──何を待っているのですか。
それがよくわからないんですよ。というのも昨年の自主ロックダウンのときも、それまでと同じように出社していましたし、特に生活がドラスティックに変わっているわけでもありませんので、コロナの終息を待っているというわけでもないのですし、「早くライヴを観に行きたい!」とか「フェス行きてえ」と思ったりもしないわけではないのですが、そもそもそんなに熱心にコミットしてきたわけでもないので、特に欠如感や飢餓感があるわけでもないんですよね。
──おかしいですね。とはいえ、何かを待っているという感覚はちょっとわからなくもないです。
何を待っているんでしょうね。あるいは逆にいうと「何も待っていない」状況って、どういうことなんでしょうね。
──現在に没入している、みたいなことなのでしょうか。
うーん。先のスケジュールが立たない、というのは実は大きな困難なのかもしれないですよね。例えば、オリンピックのような大きなイベントは、自分が特段それに期待しているわけでもないとしても、現状の見通しのなかでは、それが開催されるのか、あるいはされないのかは、社会全体にとっては非常に大きな分岐になるわけです。今後の仕事の見通しを立てる上でも、それがどういう判断になるかによって、シナリオが当然変わってくるわけですよね。
──夏の音楽フェスを開催するかどうかといった判断にも大きく影響するでしょうしね。そうしたなかで、なんとなく社会全体が「待ち」の状態になっているような気はしますね。変な話、例えば飲食店なども、いまなんとか歯を食いしばって踏みとどまるべきなのか、それとも、早めに諦めるのかという判断があったとしたら、その見極めは相当苦しいですよね。
判断の基軸がないわけですからね。
──ですよね。
こういう状況のなかで日本の現状について思うに、これまで、例えばスタートアップの世界について「日本は失敗を許容しない社会だ」といったことが言われてきましたが、どうもそれはスタートアップや起業についてばかりではなく、社会全体においてそうなんだろうな、と思うんですね。

──そうですか。
はい。とある飲食関係者にお伺いしたことなのですが、このことには、実はふたつの側面があるんですね。
──ほお。
「失敗が許容されない社会」というのは、これまでは主に、エントリーのハードルが高いという側面において語られることが多く、要は、ビジネスを始めるための参入障壁やコストが高かったり、やたらと手間がかかったりするので、最初から大きなリスクを背負わなくてはならず、そうであるがゆえに、スタートする前から「失敗できない」仕組みになっているわけです。それは実際その通りだとしても、その問題を裏側で強化しているのは、飲食の場合、「店を畳む」ということにも、非常に大きなコストと手間がかかるということなんだそうです。
──ああ、なるほど。
そう教えられて自分もハッとしたんですが、店を畳むのって、特に飲食の場合は、言うほど簡単ではないそうなんですね。例えば、賃貸契約についても、次に入るテナントを自分で探さなくてはならず、そうでなければ、自費で現状復帰しなくてはいけない、といったことがあったりするそうですし、とするなら、そのための労力もコストも、かなりかかるわけですよね。結局、最も現実的なオプションは「夜逃げ」ということになってしまったりするそうで、かつ、いったん店を畳むと、それが例え黒字倒産だったとしても「店を畳んだ」という事実をもって判断されてしまうので、次に新たに店を始めようとしても金融機関などが融資をしてくれないといった問題もあるそうなんですね。
──そうか。エグジットの仕方がないのですね。それがないから再エントリーもできない。悪循環ですね。
まさにそうなんですよね。貯金を残したまま一旦撤退する、みたいなことが簡単にできない仕組みになっているということなんだと思うのですが、そこは案外盲点なのかもなと思ったりするんですね。例えば「持続化給付金」というものがあって、これは、基本的に「とりあえず事業を継続できるよう支援する」というものですが、いつ終わるともしれないこうした状況になってきますと、「持続化支援が持続しない」ことは目に見えているわけです。そうした観点からすれば、「一時撤退/再起」のための支援策というものも想定しておく必要があるのではないか、という気もしてきます。
──持続できるのかできないのか判断もつかないなかで「持続化」と言われても、生煮えの状況が煮詰まっていくだけですよね。
下手するともっと早くに撤退しておけば、色んな意味で力をセーブしておくことができた、ということが起きてきてしまうような気がするんですね。判断が遅れれば遅れた分だけ傷口が広がる、といったようなことですが。
──持続可能性ということばは、単に現状を延命させることではなく、むしろ新陳代謝を活発に起こしていくということでもあるんでしょうね。
おそらく両方の視点が必要ではあるのでしょうけれど、社会全体の制度設計の部分において、エグジットのところをちゃんとサポートする仕組みがないと、いくらエントリーのところの障壁をあげたところで結局、糞詰まりを起こすことになるのではないかと思います。
──実際のところ、そのハードルが下がると、少し前向きな気持ちになれるところもありそうですよね。
もちろん撤退が楽しいわけはないでしょうけれども、撤退から再起への道筋が選択肢として見えるだけで、判断に余裕は生まれるような気はします。もっとも、これは従業員などもさして多くない小規模事業者に限っての話だとは思いますが。
──なるほど。
そういえば前回触れようと思いながら触れそびれたのですが、確か昨年の暮れだったと思うんですが、パリのシャンゼリゼ通りの再開発プランというのが発表されまして、これは、自動車の交通量を減らし、歩行者が優遇され、緑豊かな公園のような空間にするという、グリーンリカバリー的なアジェンダがふんだんに入った計画で、世界最大の都市農場をつくるといったアイデアもあるそうですが、ビジネスについて言いますと、通りに面したテナントがいわゆるメガストアだらけになってしまわないようにグローバルチェーンの参入を規制しつつ、むしろパリの生活文化を反映したものにしていくそうなんです。
──いいですね。
これはシャンゼリゼ通りが商業主義によって独占されてしまったことで、地元の人たちからすっかり敬遠されるものになってしまったことへの反省から出てきたアイデアだそうですが、観光政策とローカルコミュニティの活性化とがトレードオフなっていた状況への解としては正しいと思うんです。
──観光政策としても、ローカルなスモールビジネスの振興は重要だということですよね。
だと思いますね。自分の国にもあるチェーン店だらけのモールみたいな街を歩いて楽しい観光客なんていないわけですよね。
──その国、その都市なりの日常性にアクセスしたいわけですもんね。観光客しかいない街を観光客として歩いても楽しくないですよね。
だと思いますよ。そういえば、以前「Sónar」(ソナー)という音楽イベントを観にバルセロナを訪ねたことありますが、何に一番感心したかといえば、犬のお散歩をしている方を街中で多く見かけたのですが、その犬たちの表情がびっくりするくらい良くて驚いちゃったんですよね。
──って、いきなり本題に突入しましたね。
自分はわりと動物が好きなほうなので、街中にいる犬や猫にはそれなりに注意を払っているつもりですが、バルセロナの犬は、衝撃を受けるくらいの溌剌さで、「ああ、これはいい街だなあ」と感心してしまいました。なんか「わが町!」って感じで、もう自信満々に闊歩してるんですよね。市民感があるんです。
──へえ。面白いですね。
変な話、一度、ペットを通して都市のウェルネスを測ってみた方がいいんじゃないか、と思ったりしたくらいです。

The pet industrial complex
ペットビジネスの反命題
──今回の〈Field Guides〉のお題は「ペットの複合産業」(The pet industrial complex)でして、コロナ下のロックダウンでペットを飼い始める人が急増したことを背景にした特集なのですが、ここでの大きな論点のひとつはいまおっしゃったようなところで、もはや「ペット」というものが、ただの「愛玩物」のようなものではなく家族のようなものとして認識され始めていることです。
はい。今回の特集のメイン記事「アメリカ人の犬猫への愛は、いかに巨大産業をつくりあげたか」(How America’s love for its cats and dogs built the pet industrial complex)には、ペットと人間の関わり合いの歴史を簡単に素描したパートがありますが、そこでは現状がこう説明されています。
「ペットは経済的な理由から家族や子どもをもつことを諦めたミレニアル世代にとって、ますます子どもの代理のようになりつつある。ペットがいかに子どもの代わりになりつつあるかについて研究をしているロラン・シンプソンは、こう語る。『わたしが行ったインタビューで「犬や猫が子どもの代わりだと思っている」と答える人はひとりもいません。けれども、彼らの行動はそのことばを常に裏切っています』」
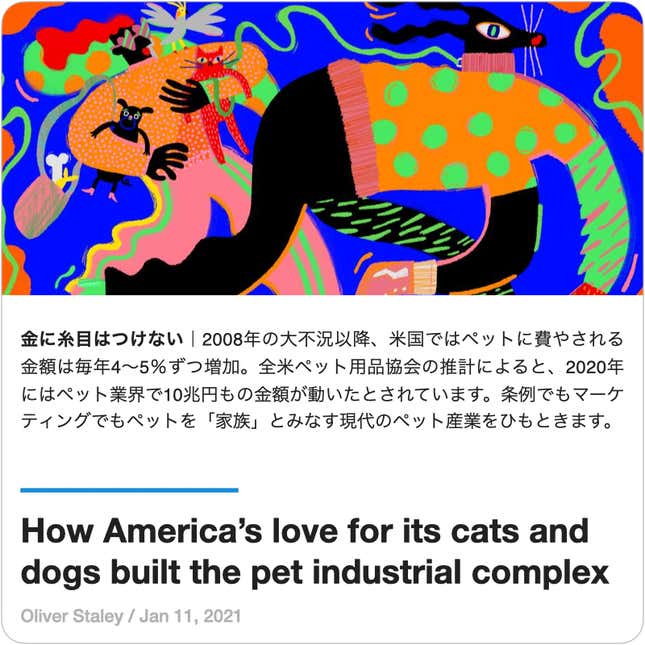
──ふむ。
特集は、ペット産業の巨大化がペット用の食事、玩具、医療、保険からペット用の精神科医のような存在までを含む多種多様なビジネスに及んでいることを明かしていますが、産業の巨大化の背景には、明らかに「人と動物の境界が曖昧になる」状況があるとみられています。「アメリカ人の犬猫への愛は、いかに巨大産業をつくりあげたか」の記事は、こう書いています。
「人にとっていいものと、ペットにとっていいものとの境界は曖昧になりつつあります。自分が食に気を使うなら、ペットの食べるものにも同じように気を使います。自分がサプリメントを服用するなら、自分の犬もそうすべきだと考える人は増えています。自分よりもペットに対してお金を使う人も少なくありません」
──記事のなかにはペット向けのCBD製品なども紹介されていましたね。
そうなんです。こうした状況を「ペットフード業界を図表化」(The pet food industry, charted)という記事は、こう説明しています。
「今年新たにペットを飼い始める人はさらに増えるだろう。けれどもペットフードの需要をドライブしているのは、それではない。マーケットリサーチ会社Euromonitor Internationalによればペットは年々小型化しており、小型犬のブリーディングがいまやトレンドだ。ペットの数が増えたとて、ペットの小型化という現象を考慮すれば、それがペットフード産業の成長を後押ししているとは言えない。
むしろ、ペットのオーナーたちが、自分の愛しい赤ん坊たちに何を食事として与えているかが変わってきている。オーナーたちはペットを家族とみなすようになり、であればこそ、家族の一員にふさわしい食事を与えたいと考えている。この傾向によって、ふたつの市場が目立って成長をしている。『”自然”食』と『ペットごとに応じた科学的食品(消化器官の弱いペット向けの食品やプロバイティックな処方など)』だ。
これらの食品は製造業者が『プレミアムフード』と名付けるものだが、ことば自体はマーケティングのためのものだFDA(アメリカ食品医薬品局)は、ここでいう『プレミアム』ということばに明確な定義は与えていない」
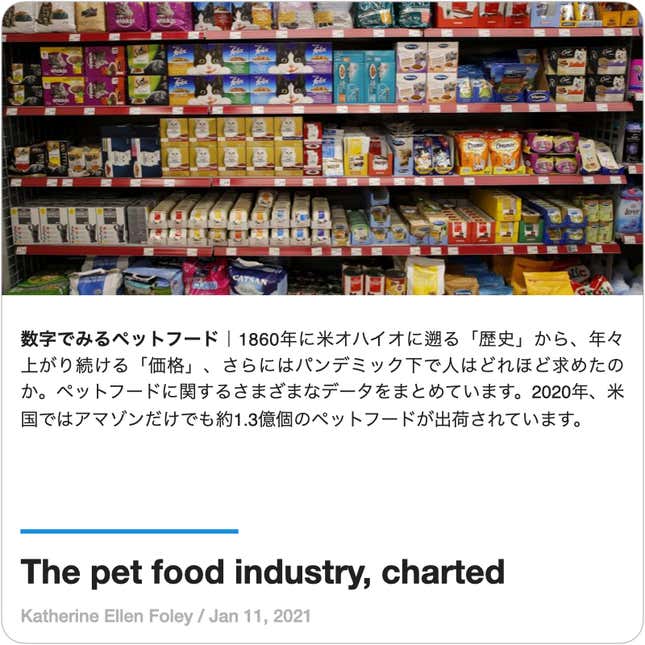
──なるほど。うーん。自分がペットの飼い主であれば、自分もそうなるだろうなと思いつつも、ペットのほうが自分よりいいものを食べていると思うと、なんだか、ちょっと問題があるような感じもしてきますね。
そうなんですよね。「ペットは家族」という考え方は、それはそれとして心情的にはその通りなのですが、ここから先、それが社会に何をもたらしていくことになるか、と考えていくと、実は相当難しい話になってきます。
──ですよね。
さきの「アメリカ人の犬猫への愛は、いかに巨大産業をつくりあげたか」の記事の最終章は「ペットの未来」と題されていますが、ここで論調が突然暗転します。引用しますね。
「(人がペットを家族としてみなすようになってくることは)ペット業界にとっては歓迎すべきことだ。人びとがペットを人間のように扱えば扱うほど、多くの人が食品やサービス、ヘルスケアにお金を使うことになる。けれども、仮に社会全体が犬や猫を人間と同等のもの、市民権をもった存在として扱うようになれば、従来の産業は深刻な打撃をこうむることになるだろう。
なぜならペット産業は、ペットが家畜と同様の『財』であり、であるがゆえにそれを売り買いし、安楽死刺させることもできる。『人格化』(personhood)は、そうした力学を破綻させてしまう。ペット製品協会のキング氏は、「『ペットの親』ということばは避けるべきだと思います。それは飼い主が『オーナー』であるという、そもそもの関係性を変えてしまうからです」
──うう。なるほど……これは、ぐっと重たい話になりますね。
これに、さらに獣医学の協会も、ペットの「人格化」は、医療ミスが起きた際に法的責任を負うことになるといった事情から慎重な立場を取っているとされています。
──それが取引可能な「財」であればこそ、そこをめぐって巨大な市場も生まれますが、その前提が崩れるとすると、社会というものの大きな前提が崩れてきてしまう怖さがありますね。
これはかなりヘビーな問題になるものでして、あまり迂闊なことは言えませんが、この問題が厄介なものとなるのは、そもそも「人間とは何か」ということに深く関わっているからです。というのも、「何が人間で、何がそうでないのか」という線引きは、歴史的に「人間」というものに対しても適用されてきたものですし、それもある意味恣意的に線引きされてきたからなんですね。
──奴隷制度みたいなことですよね。
はい。例えばですが「未開人は理性というものがない」というロジックによって、西洋化されていない文明のなかに生きる人たちを、「財」として扱い、売り買いするといったことが過去にはあったわけですし、昨年から今年にかけてのアメリカの大統領選をめぐる問題のなかでも、そうした状況は、実はいまでも続いているという認識が絶えず確認されていたわけですよね。もちろん制度や道義上のコンセンサスとして、あらゆる人を人として認めるということは、第二次大戦以降の世界では一般化してはいますが、実際にそれが社会において反映されているのかという問題が提出されていますし、そもそも「人間としてみな平等だ」というときに、その根拠は何なのかというのは、実はそれほど確固たるものではない可能性があるということもあるんですね。
──どういうことでしょう。
人類全体を見渡して「人間に共通する資質とは何か」と考えたときに、人間とその他の動物をわかつ根拠は、もちろん生物学的には特定できると思いますが、その違いをもってなぜ人間だけが、他の動物に対して「主人」として振る舞うことが許されるのかの根拠に、果たしてそれがなるのかは疑問じゃないですか。
──人間には知性や知能があると言ってみても、最近の研究などでは、おそらく他の動物にもかなりの知性が見出されているといったこともあるでしょうしね。
そうなんです。そう考えていくと、これまでの人間と動物とを明確に分断していた「人間至上主義」と、例えばいま世界で問題になっている「白人至上主義」は、相似形の問題であると考えることができてしまうわけですね。そこから例えば動物愛護団体などは、動物にも市民権が与えられるべきだと考えるようになり、実際、これまでに象やチンパンジーが市民権を与えるべく法廷闘争が行われていたりするんです。
──うーん。
例えば捕鯨をめぐる論争などでも、「鯨は知能がある動物なんだ」といったことが言われたりするかと思いますが、この論法でいきますと「じゃあ知能の劣った他の動物はどうなんだ?」という疑問がすぐさま出てきてしまいますよね。「知性」という人間が持ち出した価値基準で動物界を序列化するのは、結局「人間中心主義」でしかないということになってしまうわけですね。

──難しいですね。
この問題について、めちゃくちゃ鋭く描いた本がありまして、南アフリカ出身のノーベル賞受賞作家のJ・M・クッツェーの『動物のいのち』という大変込み入った本なのですが、とても面白いです。
──どういう本なのですか?
これは、ある講演会にクッツェーが呼ばれて講演の代わりに書いた小説でして、このなかで「エリザベス・コステロ」という名の老いた女性作家が、ある大学の講演会に呼ばれて講演を行い、哲学者などとディスカッションをする状況を描いた、言ってみれば仮想の対話によって織り成されたものなのです。
──入り組んでいますね。
はい。クッツェーは、議論と対立を明確にするために、老作家を菜食主義で、人間による動物に対する扱いを堪え難いものだと感じている人物として描きます。その主張を一言に集約させるなら、こうなります。
「私たちが認める意識のどこがそれほど特別だから、その種の意識をもった者を殺せば犯罪となり、動物を殺しても罰せられずにすむというのでしょうか?」(『動物のいのち』J・M・クッツェー、森祐希子・尾関周二訳、大月書店)
──ふむ。
それに対し、クッツェーは、その問いに反発する哲学者を多数登場させて、例えば、こんなふうに反論させます。
「貴女はご自分の目的のために、ヨーロッパで殺されたユダヤ人と屠殺された家畜という、ありふれた比較を借用しておられました。ユダヤ人は家畜のように死んだ、したがって家畜はユダヤ人のように死ぬ、と貴女はおっしゃる。これは言葉によるごまかしであり、私はそれを受け入れるつもりはありません。貴女は類似性というものを誤解しておられる。意図的に。ほとんど冒瀆と言ってもいいまでに誤解しておられるとさえ申しましょう。人間は神に似せて創られましたが、神が人間に似ているということではないのです。もしユダヤ人が家畜のように扱われたとしても、家畜がユダヤ人のように扱われていることにはならないのです。たんに置き換えることは、死者の霊にたいする侮辱です。それはまた、収容所での恐怖に安っぽいやり方でつけ込むものです」
──めちゃ重たいですね……。
老作家は、問題点をクリアにするためにあえてナチスによるジェノサイドを問題にしたのですが、彼女は、当然予想された、上記のような批判に、こう答えています。だいぶ長いのですが、引用させてください。
「私たちは他の動物たちと何かを、理性や自意識や魂を、共有しているのだろうか、というのは正しい問いではありません。(もし共有するものがないとしたら、私たちは他の動物を好き勝手にする権利──監禁し、殺し、死体を穢す権利──を与えられるという推論に至るでしょう。)死の収容所の話に戻りましょう。死の収容所特有の恐ろしさ、そこでおこなわれていたのは人間性に反する犯罪であったと確信させる恐ろしさは、犠牲となった人びとにも人間性はあったのに、殺戮者が彼らをシラミのように扱ったという点ではありません。そんなことは抽象論にすぎません。恐ろしいのは、殺す側が犠牲者の立場に立って考えることを拒絶したし、他の人もみな同じだったという点なのです。彼らは『がたがたと通りすぎていく家畜車のなかにいるのは、やつら(原文は傍点)なんだ』と言いました。『その家畜車のなかにいるのが自分だったら、どうなんだろう?』とは言いませんでした。『あの家畜車のなかにいるのは自分だ』とは言わなかったのです。(中略)
言いかえれば、彼らは心を閉ざしたのです。心とは、ときどき他の存在を共有できるようにしてくれる共感という能力が宿る場所です。共感は主体とことごとく関係するものであって、客体、つまり『他のもの』とはほとんど何の関係もありません。客体というのをコウモリではなく(『コウモリの存在を共有できるか?』)別の人間と考えれば、すぐにわかるでしょう。自分が誰か別の人間だと想像する能力をもっている人もいますし、そんな能力はない人もいます。(能力のなさが極端な場合、彼らは精神病質者と呼ばれますが。)そして、能力はあるけれども、それを使わないことを選ぶ人もいるのです。
(中略)トマス・アクィナスやルネ・デカルトがなんと主張しようと、他の存在の立場になって考えてみられる範囲に限界はありません。共感的な想像力に限界はないのです。証拠が欲しいのなら、次の点を考えてみてください。数年前に私は、『エクレス通りの家』という本を描きました。その本を書くために、私はマリオン・ブルームの存在に入りこんで深く考えなければなりませんでした。うまくいったにせよ、うまくできなかったにせよ、です。(中略)いずれにせよ、重要なのは、マリオン・ブルームは存在しなかった(原文は傍点)ということです。マリオン・ブルームはジェイムズ・ジョイスの想像の産物だったのです。もし存在しない生き物の存在に入りこんで考えることができるのなら、それならコウモリであれチンパンジーであれ牡蠣であれ、根源的に私と同じく生命をもっている生き物ならなんでも、その立場に立って考えることができます」

──うーん。なんとも言えませんけれど、感動的な感じもします。
ここだけ取り出すとさすがにちょっとナイーブに読めるかとも思うのですが、彼女はここで、理性や論理や道徳といった回路でなく文学的な想像力、哲学者ではなく詩人の心を通して、世界を感じるよう促しているんですね。
──えーと。共感する力っていうのは、詩人の心に宿るということですかね。
おそらくそういうことだと思うんです。彼女がこうやって「動物のいのち」というものにどうしようもなくこだわってしまうのは、道徳的信念からではなく、「自分の魂を救いたいから」だと言うんですが、おそらく、詩人の心っていうのは、その願いとともにあると感じられているのではないかと感じます。
──うーん。なんだかわかったような、わからないような。
結局、この本にも結論はないんです。ただ、この本で言われる「共感」というものはとても大事なものだと思うんですね。突然話が飛ぶようで申し訳ないのですが、演歌歌手の藤あや子さんって、この間、ソーシャルメディアで飼い猫の投稿ばかりしていて、そのアカウントが非常に人気なことから猫たちを主人公にした写真集が出版され、2匹の猫の飼い主として、藤さん自身がやたらメディアに出ていますが、インタビューなんかを読むと、捨て猫になるはずの猫たちを救ったつもりが、結局救われていたのは自分だった、といったことを盛んに言われているんですね。
──デカルト批判から藤あや子って、すごい飛躍ですね。
この手の話は、ペット語りにおいてはある意味クリシェのようなものなので、そんなに重きをおくべきものでもないのかもしれませんが、なんというか、そうした相互性みたい部分は、なんだかとても大事なような気はするんですね。
──どっちがどっちを助けているのかわからないような状態ですよね。
そうなんですよね。これもかなり雑な話になりますが、「ケア」といったテーマ系における大きな問題は、ケアする側とされる側の関係性が明確に固定化されて、しかもそれが社会のなかにおいて階級化されていってしまうところにあるような気がするんですね。その関係性が固定的であればこそ、そこで行われる「ケア」が専門化・サービス化されていくことも可能になるのだと思いますが、それが産業化していけばいくほど、より階層が固定されることにもなるんだと思うんです。
──どっちがケアをする側で、される側かがわからないみたいなことだと、ものごとの捉え方もだいぶ変わってきそうですよね。
相互依存性(intedependece)という考え方は、おそらくこれからの社会を考えていく上では重要な観点なのではないかと思うんです。それこそデカルトあたりから発生する、いわゆる自立した近代的な「個人」という観点から、動物との関係を考えていくと、相当に困難な議論にならざるを得なくなりますが、そうではなく、ある環境のなかにおいて相互依存している関係であるというところから、それこそ身の回りの動物や植物との関係性を把握していくことができるようになると、「動物に理性はあるのか?」といったひたすら分断を生むことにしかなりかねない議論を、少しは和らげることができるのかもしれないと思ったりします。
──どうなんでしょう。
そういえば、昨年の4月にコスタリカのクリダバトという市が、蜂と木々に市民権を与えたらしいんですよ。
──ええっ。そんなことできるんですか!?
「市民権」といったときの範囲はよくわからないのですが、これは市の都市開発の一環として発動されたもので、市内の緑地をインフラとして捉え、その持続に不可欠な存在として蜂を位置付けたということらしいです。
──そう考えると、最初の方に出てきたバルセロナの犬なんかも、街の活力やサスティナビリティを維持する上で立派に役割を果たしていると考えるのであれば、十分に市民権を得る資格がありそうにも思えてきますね。
メンタルヘルスの問題が前景化しているなか、ペットというものが「人をケアする存在」としてクローズアップされているのだと考えれば、犬や猫やその他の「ペット」というもの存在の公共的な価値が高まっているということでもありますよね。それがさらに進行していった先に、人と動物との関係性にどんな未来が待っているのか。考えてみるのはちょっと面白いですね。
若林恵(わかばやし・けい) 1971年生まれ。『WIRED』日本版編集長(2012〜17年)を務めたのち、2018年、黒鳥社を設立。NY在住のジャーナリスト 佐久間裕美子さんとともホストを務める「こんにちは未来」をはじめさまざまなポッドキャストをプロデュース。これまでの本連載を1冊にまとめた『だえん問答』、好評発売中です。
🧑💻 世界各地で活躍する日本人VCが現地の声で伝える月イチのウェビナーシリーズの第3回は、シンガポール。1月28日(木)、Rebright Partnersの蛯原健さんをお招きして開催します。お申込みはこちらのフォームから。
🎧 月2回配信のPodcast。「ワイルドサイエンティスト」として生物学の民主化をテーマに研究を続ける片野晃輔さんを迎えたトーク、後編の配信もスタートしています。Apple|Spotify
👀 Twitter、Facebookでも最新ニュースをお届け。
👇 のボタンから、このニュースレターをTwitter、Facebookでシェアできます。ニュースレターの転送もご自由に(転送された方へ! 登録はこちらからどうぞ)。