A Guide to Guides
週刊だえん問答
週末のニュースレター「だえん問答」では、世界がいま何に注目しどう論じているのか、米国版Quartzの特集〈Field Guides〉から1つをピックアップし、編集者の若林恵さんが解題します。今週は、TikTokが音楽業界に巻き起こしている現象を追います。
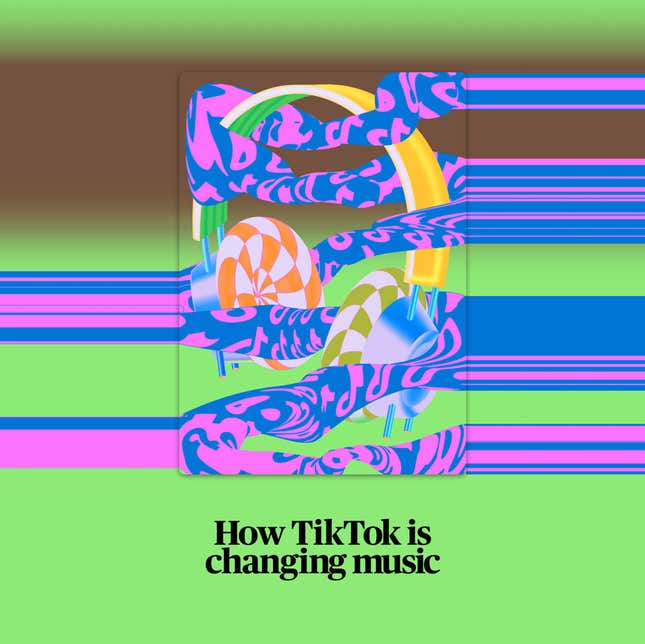
──今回のお題は「『TikTok』はいかに音楽を変えているか」です。得意なジャンルですよね?
え。そうですか? TikTokなんてまったくわからないですよ。
──あれ。そうですか。
はい。かなり自信あります。
──わからないことに(笑)。
ええ。むしろ教えて欲しいくらいです。
──困りましたね。
基本的に、「バズる」ものに特に興味がないのだと思います。
──そうですか。
事務所や家にある本などを改めて見直してみても、いわゆるベストセラーってまったくといっていいほどないですし。
──ないですか。
先日、ちょっとした仕事の用事で50年代の日本のベストセラーのリストを見ていたところ、有吉佐和子さんの『恍惚の人』や『複合汚染』が入っていましたが、それであればおそらくどこかにあるはずです。
──あはは。
あと、橋本治さんの『桃尻娘』とか。
──まあ、たしかにベストセラーではありますが(苦笑)。
といっても、基本リアルタイムではないんです。流行りものは割と後から追いかけることが多いかもしれませんね。
──昔からそうですか?
どうでしょう。思い返してみますと、時代とちゃんとシンクロしていたのって、中学生時代だけだったかもしれません。音楽についていえば、その時代だけはポップチャートのトップ200に入っていた曲の90%近くはわかるんじゃないかと思います。
──それ以降となると。
うっすらとはわかるんですが、メインストリームとシンクロしていた感じはないですね。ただ、当時はまだショップも含めたメディアの存在が安定していましたので、自分から熱心に追わなくても、なんとなく何が流行っているのか、メインストリームで何が起きているのかは、それとなく察知できた気がします。
──そうなのですね。
MCハマーなんて、日本人全員が知っていたんじゃないですか。
──たしかに(笑)。
How TikTok is changing music
ティックトックの訓戒
ところが、自分でもあまり意識はしていなかったのですが、2000年くらいを境にして、「海外の動向がなんとなくでも漠然とわかる」みたいな感じが、なくなっていったんですね。それは実は、インターネットの一般化を境にして起きたような気がしなくもありません。正確なところは、よくわからないんですが。
──へえ。
おそらく2000年代の中頃だったと思うのですが、自分が「あれ?」と思ったのは、あるときグラミー賞のノミネートを見ても「どの曲もわからない」ということがありまして、自分としては結構ショックだったんです。それなりに音楽をずっと追いかけていましたし、それがメインストリームのものではなかったにせよ、一応、視界の片隅では押さえていたつもりだったんですね。
──なのに、まったくキャッチアップできていなかった。
そうなんです。そこで感じた「おれら、気づかずに閉じちゃってない?」という感覚は、自分にとってひとつの大きな転換点にはなっています。ちょうどその後『GQ』という海外のメンズカルチャー誌をお手伝いするようになったのですが、その仕事をする上で大きな問題意識となっていましたし、それは『WIRED』というメディアでの仕事にもつながっていたと思います。
──いわゆる「ガラパゴス」ってことですよね。
おっしゃる通りなのですが、「ガラパゴス」ということばの問題は、そのことば自体が日本でしか流通していないことばだというところですよね。つまり、そのことば自体が閉じているので、取り立てて批判性もないんですよね。
──たしかに。自分たちで言っているだけで、外からそう批判されているわけでもないですもんね。
不思議なんですよね。自分の肌感覚に従うなら、インターネットという世界とつながることのできるツールが広まっていくことと同時進行で、閉じていくわけです。これが、どういうメカニズムで起きたのか、うまく説明ができないんです。その一方で、経済の分野における「グローバル化」というのは着実に起きていたわけですし。
──謎ですね。
なんにせよ、ちょうどそのころから、当たり前といえば当たり前なのですが、「やっぱり自分には見えていない領域というのがいっぱいあるのだな」ということは強く感じるようにはなりまして、特にデジタル空間にあらゆる活動の軸足が移っていきますと、それなりの規模感になっているムーブメントであったとしても、まったく見えなくなってしまうんですね。
──「あれ、バズってましたね」みたいな会話が、どんどん成立しなくなっていますよね。
使っているツールによって、見えている景色がまったく違うのだろうと思いますし、そのなかでもクラスターごとにセグメントされているのだとすれば、よそのチャンネルのよそのクラスターで起きていることは、まずもって見えませんよね。
──たしかに。
さらに、時代の趨勢がマスメディアからデジタルメディアへと移行していくなかで何が変わっていったかについては、この連載でもたびたびお名前を挙げている池田純一さんという方の面白い指摘があります。
──ほお。
かつては「世代」というものが「コンテンツ」によってセグメントされていたけれど、デジタルメディア以降は、「世代」は「アプリ」、つまりは使っているツールによってセグメントされる、ということを池田さんはおっしゃっていて、これは面白いな、と思います。
──ははあ。「ミクシー世代」なんていう言い方ありますもんね。
池田さんのこの指摘は、実は今回の〈Field Guides〉で何度か指摘されることでもあるんです。
──あ、そうですか。
例えば、「TikTokはいかに音楽産業を変えつつあるか」(How TikTok is changing the music industry)という記事には、こんな記載があります。
「ジャスティン・ビーバーはYouTubeで見出された。ショーン・メンデスはVineで存在感を発揮した。カーディ・BはInstagramの女王だったし、アークティック・モンキーズはMySpaceから名を挙げた」
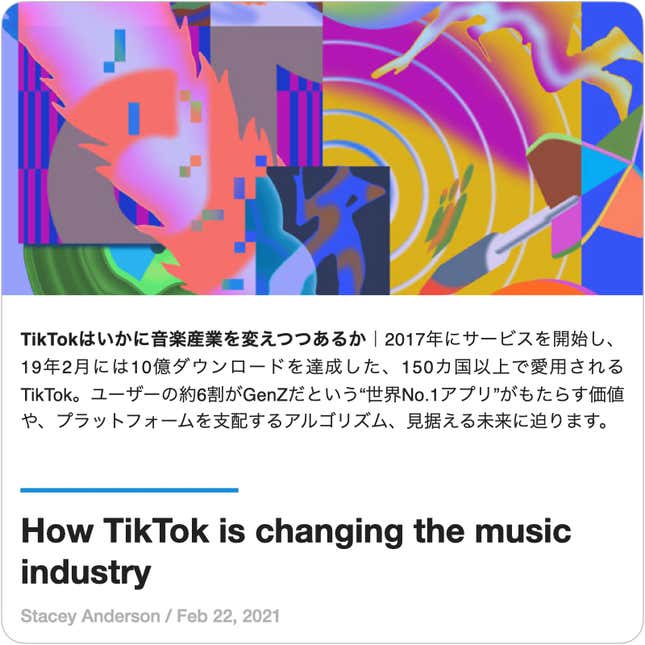
──なるほど。
さらに別の記事「ティックトッカーがレコーディング契約を結ぶまで」(How TikTokers get record deals)では、Soundcloudとビリー・アイリッシュの関係性についても言及されています。
──面白いですね。プラットフォームというか、アプリに対応するかたちでスターが輩出されていく、という構造になっているわけですね。
はい。ここで重要な点は、やはりそこにあるんですよね。つまり、フィルターバブルの構造を考えれば、それぞれのプラットフォーム内で終息していておかしくない「バズ」が、あるクラスターのみならずプラットフォームからもはみ出して「社会的な現象」になって、社会的に認知される「スター」が継続して輩出されているのは、当たり前のように見えるんですが、本当はそんなことはないんですね。
──ん。どういうことでしょう。
今回の特集は、記事としては3本しかないのですが、そのうちの2つがミュージシャンの「レコード契約」を話題にしていることからもわかるように、ソーシャルメディア空間って、結局のところ、いまも昔も、それ自体としては経済空間になっていないんです。
──ん?
それこそMySpace全盛の昔から、ミュージシャンのソーシャルメディアからのエグジットの仕方って、さして選択肢がないんです。「TikTokはいかに音楽産業を変えつつあるか」の記事は、こう指摘しています。
「TikTokが音楽産業を本当に変えるためには、単にミュージシャンの『露出』を増やしてあげるだけでは足りない。ミュージシャンたちが自分たちの作品をマネタイズする方策がそこにはなくてはならない。どうマネタイズするかは個々のアーティストの選択になるが、いまのところ、選択肢はさしてない。ストリーミングの収入を増やすべく露出を稼ぎ続けるか、レコード会社との契約を取り付けるか、さもなくばブランドと提携してスポンサードコンテンツをつくるかだ」
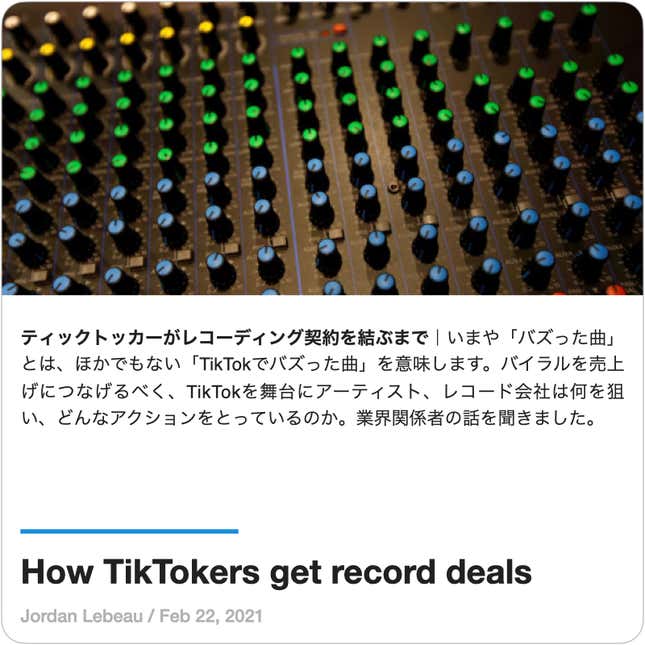
──ははあん。なるほど。
今回の特集は、要は、いかにTikTokが、音楽産業──特にメジャーレーベル──にとって新人アーティストを発掘する草刈場になっているかを明かしたもので、実際、2020年にTikTokを通じて、70組以上のアーティストがメジャーレーベルとの契約を得たことを、TikTokは自社のレポートで誇っています。ただ、これも、なんというか、割と「だから何?」って気持ちになってしまうところもあるんですよね。
──そうですか。いい話なのではありませんか?
ある一面においては、もちろんいい話なんです。ソーシャルメディアを通じて地道にファンベースを構築してきたアーティストが大手レコード会社と契約を結び、その存在が社会化され、時代の空気をアップデートしていくことは重要なことですし、リスナーとしても楽しいことだとは思うんです。ただ、その一方で、いまあるビジネス構造のなかにおいては、先の指摘の通り、自らの手で自分がつくりあげたファンベースをマネタイズすることができないんですね。自分のファンベースを換金するためには、ストリーミングプラットフォームに頼るか、レコード会社に頼るか、どこかの企業に頼るか、原理的には、この3つの選択肢しかないわけです。
──自分でせっせとつくったお客さんたちを、他人の土俵にせっせと送客することで、そのおこぼれに預かる、という構図になっちゃっているわけですね。
そうなんです。例えば、ストリーミングプラットフォームの問題について言いますと、先の記事はこんなことを指摘しています。
「昨年11月、ミュージシャンたちの組合が『Spotifyに正義を』というキャンペーンをローンチしました。そこで1万8,000人の組合員たちは、Spotifyに対して、せめて再生1回にあたり1ペニー(1.3円)がアーティストに支払われること、権利料をめぐる訴訟を取り下げること、さらに財務の透明性を求める要求書を提出した。現在のところ、Spotifyの支払いは、ユーザーのサブスクリプションからの売上げと広告で得た収益を、全体の再生回数ににおける各アーティストの再生回数の比率に応じて分割する「プロ・ラタ」方式に基づいている。結果、上位10%のアーティストに、収益の99.4%が分配されることになっている、と『Rolling Stone』誌は指摘している」
──ああ、そうか。聴かれた分に応じて支払いがなされるわけではないのですね。
そうなんです。これは結構ツラいですよね。1回でも多く再生されるように努力しても、それに応じた収益にならず、むしろ、上位10%の人たちが全体のパイを増やしてくれた方が収入が増える、という構造ですから、実はかなりいびつなシステムなんですよね。別の言い方をするなら、こうしたストリーミングプラットフォーム自体が、TikTokなどの他社プラットフォームで起きる「バズ」をアテにしている構図なんですよね。
──うーん。
それはレコード会社も一緒なんです。数年前にあるイベントで日本の大手レコード会社のディレクターの方が、若いインディアーティストの人に「どうやったら音源を聴いてもらえるんですか?」と訊ねられて、「まずフォロワーを5万人以上にしてから連絡いただけたら」といけしゃあしゃあと答えていまして、「おー、搾取する気まんまんじゃんか」と思ったものでしたが、記事を読む限り、このマインドセットはあまり変わってはいないんですね。
もちろん、その5万を50万、500万に増やすのが、大手レコード会社の仕事だというのはその通りだとも思いますし、それを実現すべくそれなりの投資もするわけですから、言い分はわからなくもないのですが、とはいえ、TikTokは、2020年だけでも再生回数が10億回を超えたものが176点もあったと言いますから、「バズったヤツを捕まえて商売したれ」というやり口は、どんどん横柄・横着になってきているように見えます。
──「TikTokのスターたちは名声への道をどのように再発明しようとしているか」(How TikTok stars are reinventing the path to fame)という記事は、Tai Verdesというアーティストが、自身がつくったデモ曲をクルマのなかで歌った動画が450万再生を超え、Spotifyの「ヴァイラル50チャート」にランクインした時点で、数社から契約のオファーを受けていたことを明かしています。
アーティスト側も、すでにこうした「搾取」の構図については、だいぶ意識的になっているそうで、記事で取り上げられたTai Verdesは、Aristaという大手と契約を結ぶ際に、通例であるアルバム複数枚の契約ではなく、EP1枚分の短期契約で収益はレコード会社と折半、原盤権についても本人が保持という契約を勝ち取ったそうです。これだけアーティスト側に有利な契約の前例は、ジェイ-Zやリアーナ、U2やフランク・オーシャンといったほんの一握りのアーティストしかないんですね。かのテイラー・スウィフトですら、自分で原盤権をめぐって熾烈に戦った結果、負けています。彼女には、2018年以降の作品についてしか原盤権がないんですね。
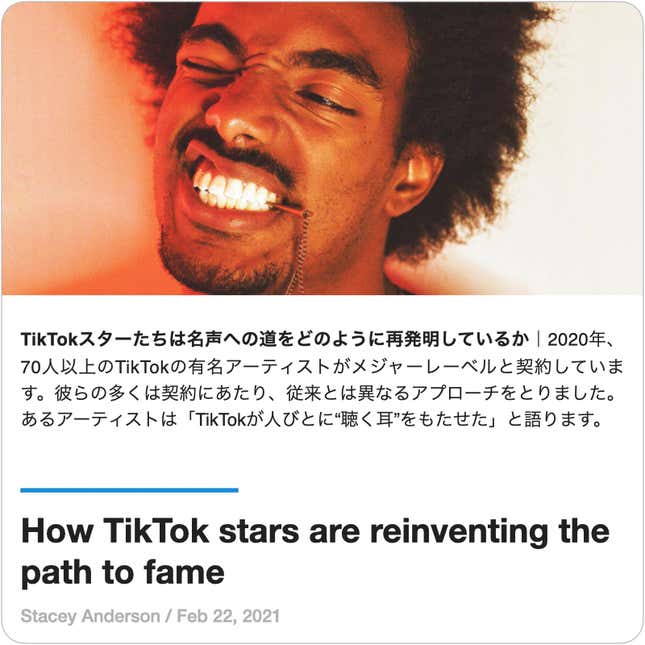
──そう考えると、このTai Verdesの契約は快挙ですよね。
アーティストがTikTokでのフォロワー数や再生回数を武器に、自分たちに有利な交渉をできるようになったことは、たしかに喜ばしいことだとは思うのですが、こうした状況が、むしろ危ういのは、やはり根本のところで、「バズ」というものが、ひたすら予測不能なものでしかない、というところにあるんですね。
──すべてがまぐれ当たり、みたいなところがあるということですよね。
「ティックトッカーがレコーディング契約を結ぶまで」の記事では、マネジメント企業のエグゼクティブが、「TikTokでのバズは非科学的なものです」と語っていまして、「バズるための戦略」というものは、基本存在しないとされています。おっしゃる通り「当たるも八卦、当たらぬも八卦」なんですね。
──ですよね。
かつ、TikTokのように30秒以下の動画でユーザーを引き止めておかなくてはならないとなると、自分の音楽よりも、自分自身を売りにすることとなってしまい、そうなると今度はいざ音楽をマネタイズしようとしても、誰もそこにはお金を払ってくれなくなります。「どうやって自分のファンベースを耕していくかを、アーティストはよく考えておかないといけません」と、記事は戒めています。
──記事内に「ヴァイラルするスキルと、音楽家として成功するためのスキルはまったく違うものだ」という一節もあります。
難しいところですよね。最終的には「やっている音楽が大事だ」というのはその通りだとしても、必ずしも「ヴァイラルすること」を求めなかったとしても、現状の環境のなかで地道にファンベースを積み上げていくためには、チャンネルやプラットフォームに合わせて最適な「伝え方」を模索することは最低限必要にはなります。ただ、音楽家自身が必ずしもそうしたことに長けているわけでもないでしょうから、やっぱり、マネタイズの道筋まで含めた包括的なビジネス戦略を描けるパートナーがどうしたって必要になってくるような気がします。
──本来は、レコード会社がそれをやってくれるものだと思っていましたが。
レコード会社は言ってみれば、もはや投資家かVCの役割に近いものですから、投資対効果(ROI)が見込めないと見れば、すぐにでも契約をドロップする立場なんですね。いまお話したように、音楽家を音楽家として持続的なやり方で成功に導き、それに向けて伴走すべきはずなのは、どちらかというとマネジメントの方だと思います。
──ああ、そうか。

そういえば、つい先日、ポール・ウォッチャーという元インベストメントバンカーに関する面白い記事を『Fast Company』で読んだのですが、この方がやっているMain Street Advisorsというのは、基本的には財務コンサルをやる会社なのですが、そのクライアントはレブロン・ジェームズからドレイク、ビリー・アイリッシュ、ボノ、ジミー・アイオヴィン、ドクター・ドレー、88 risingと多岐にわたっていまして、彼のユニークなところは、アーティストやスポーツ選手を単に、「音楽をつくる人」「スポーツをやる人」とみなすのではなく、一種の「スタートアップ」もしくは「社会起業家」のようなものとみなして、共にビジネスをしていくパートナーとして投資を行うだけでなく、ビジネスの構築を手伝っているところなんですね。
──へえ。そんな会社があるんですね。
もちろん、アーティスト側がこうした動きができるのも、そもそも大きな名声をもっているからで、名声のはるか手前にいるアーティストがいきなりやれるようなビジネスモデルではないとは思うのですが、アーティストの社会的な価値を、レコード会社やサブスクリプションプラットフォーム上でただの「商品」として消費・換金しているだけの現状を、面白いやり方で突破しているような気はします。
──たしかに。それこそビリー・アイリッシュが2019年の「Where do we go?」ツアーで、Reverbという非営利環境保護団体やGlobal Citizenとパートナシップを組んでいましたが、当時はぼんやりと「ダイナミックなことをやるなあ」と思っていましたが、アーティストの意向や価値観をダイナミックなビジネス/ムーブメントへと転換していくような策士が背後にいたというわけですね。
すごいんですよね。レブロン・ジェームズとマーヴェリック・カーターのふたりが設立したSpringHill Companyというプロダクション会社 は、昨年1億ドル調達し、数カ月のうちにアマゾン、ネットフリックス、ユニバーサルなどと契約を結び、ディズニーからは「ダイバーシティとインクルージョン」についてのアドバイスを求められていたりもするそうで、コンテンツづくりを通して、人種的公正について発信していくことを目指しているとされています。
──ははあ。
レブロンは、自身の会社の設立の理由を「プラットフォームをもっている者として何をすべきか考えた結果」だと語っているのですが、彼は、自分の名声や知名度、動員力を「プラットフォーム」として理解しているんですね。ここは面白いところだと思います。ビリー・アイリッシュにしてもおそらくはそうで、こうした観点に立てば、もはや「ファンベース」と呼ばれているものは、そこからお金を搾り取る対象としての「消費者の群れ」ではなく、共に何かを実現していくパートナーとして認識されていくことになるように思うんです。
──なるほど。面白いですね。
この連載でも何度か、K-POPのファンベースの話をしたかと思いますが、あるアーティストとそのファンベースの関係性は、もはや「生産者」と「消費者」の関係性ではなく、それが一体となった「プラットフォーム」とみなすべきものになっているんですね。であればこそ、ブランドから非営利団体、さらには国連のような国際機関までもが協力を求めるようなことが起きるんですね。
──ふむ。でも、それって従来のセレブビジネスと違うんですかね?
これまでと違わないようでいて大きく違うのは、活動のオーナーシップがアーティスト側、アーティストの能動性・主体性にあることかなと思います。これまでは、やっぱりメディア側の意向にアーティストが乗っかる、もしくは「乗らされる」という格好だったのが、いまでは完全にベクトルが逆になっているように感じます。
──アーティストの活動に向けて、メディアなりが動員される、と。
そうですね。こうした動きの重要な点は、まず前提として、アーティストとファンが「意味」というものにおいてつながっていることにあるのだと思います。平べったいことばで言えば「価値観」ともいえますが、そうしたものでつながった信頼関係が「フォロワー数」を単なる数字以上の価値へと変えているんでしょう。もちろん、多くのミュージシャンやアーティストは、ビリー・アイリッシュのような「巨大プラットフォーム」にはなりえませんし、すべてのミュージシャンやアーティストが、「地球環境」や「社会正義」といったお題目を掲げる必要もまったくないと思います。ただ、ちゃんとしたファンベースをもつことは、たとえそれが小さなものでれ、きちんと「意味」や「価値」に立脚していれば、それ自体が、社会的にも経済的にもビジネスの源泉になりうるということは、大きな発見であるような気はします。

──先ほど、日本の大手レコード会社のディレクターの「フォロワーが5万人を超えたら音源もって来なよ」という発言を挙げられていましたが、こうして考えてみると、このことばの残念さは、結局のところアーティストをただの商品制作者、フォロワーをただの消費者としてしか見ていないところにあるのがよくわかりますね。
〈Field Guides〉の話に戻って「ティックトッカーがレコーディング契約を結ぶまで」を読んでみますと、こんなことが書かれているんですね。
「アーティストがさまざまなSNSプラットフォームで必死にヴァイラルしフォロワーを稼ごうとしているのを横目でみているマネジャーは、数を増やすことが必ずしも価値になるわけではないことに気づくはずだ」
──面白いですね。アーティストの価値は、そのアーティストがどういうファンベースをもっているかによって変わるということですよね。
でも、それって特に新しい話でもないですよね。やはり、ちゃんとお客さんを選んでいるブランドって強いですよね。「ファンをつくる」って、別の言い方をすると「ファンでない人をちゃんと排除する」ということでもあります。そこには、明確に「排除」の論理が作動しているはずで、そうでない限り、「ファンでいること」はちっとも楽しくないですよね。
──「お金払ってくれるなら誰でもいい」っていうコンテンツには、そもそも「ファン」っていう概念すら成り立たないですもんね。
自分のお客さんのことが好きでもなんでもない、というビジネスは、基本的に「不幸なビジネス」なんだと思います。で、せっかくいいファンベースを築いても、ひょんな「ヴァイラル」のおかげで客筋が荒れたりしてしまうと、やっている側も楽しくないですよね。ですから、「バズ」を取りにいくにしても、その辺はとても注意した方がいいと思うんですね。なかには、「それでもおれはとにかくバズりたいんだ」っていう人もいるでしょうが、そういう人はどうせたいしたコンテンツはつくれないので、別に無理して追っかけなくてもいいですよね。
──そうですか。
と、思いますよ。
──冒頭にトレンドについては後追い、という話がありましたけど、その辺を見極めるために後追いするということなのですか? つまり淘汰されて残ったものだけ知ってりゃいいじゃん、と。
どうでしょうね。それこそひと昔前に、「MySpaceからすげえのが出てきた!」という触れ込みで、あるバンドがメジャーレーベルと契約して、それこそサマソニかなんかにも来たことがあったんです。たしか佐々木俊尚さんという方が書いた『電子書籍の衝撃』という本のなかでも、そのバンドのことが紹介されていて、うろ覚えですが、これからはこうしたソーシャルプラットホームが新しいスターをつくり出していくのだ、これによって音楽業界は変わっていくのだ、といったことが書かれていた気がするのですが、それを読んで「こんなクソバンドしか輩出できないなら、ソーシャルプラットフォームもたかが知れてるな」と思ったんですよね。
──あはは。なんてバンドですか、それ。
「ハリウッド・アンデッド」というバンドですが、知ってます?
──すみません(笑)。
ほんとにひどいんですよ。
──そう言われると聴きたくなります(笑)。
たしかに、こうしたデジタルプラットフォームが、突発的に世界的な才能を生み出してきたのは、その通りではあるのですが、じゃあ、それが、それぞれのプラットフォームで活動しているアーティストの何%を占めているのか、あるいは、世間で売れていると言われているアーティストの何%いるのかを考えてみれば、そっちの方がよほどの特殊事例なわけですよね。ところが、そうした「成功」だけが、あたかも「成功」だというふうに常に喧伝されるので、うっかりそう思い込む人も多いんじゃないかと思いますが、そんな天文学的な確率しかないようなチャンスを追うことは、よほど遠回りのような気もしてしまうんですけどね。
──この連載も、全然バズらないですが、それも意図してのことだから、それでいいんですよね?
いえ。正直もう少し反応は欲しいところです。
──おい。
わたしだって、たまにはバズりたいと思わなくはないんですよ。
──こら。
すみません。
若林恵(わかばやし・けい) 1971年生まれ。『WIRED』日本版編集長(2012〜17年)を務めたのち、2018年、黒鳥社を設立。NY在住のジャーナリスト 佐久間裕美子さんとともホストを務める「こんにちは未来」をはじめさまざまなポッドキャストもプロデュース。2020年に配信した本連載を1冊にまとめた『だえん問答』も好評発売中。
🎧 Podcast最新エピソードのゲストは、世界8カ国を移動しながら都市・建築・まちづくりに関する活動を行う「アーバン・ジャーナリスト」の杉田真理子さん。多様な「都市」がもつ魅力、トレンドとなりつつあるその価値にせまります。 Apple|Spotify
👇 のボタンから、このニュースレターをTwitter、Facebookでシェアできます。ニュースレターの転送もご自由に(転送された方へ! 登録はこちらからどうぞ)。
