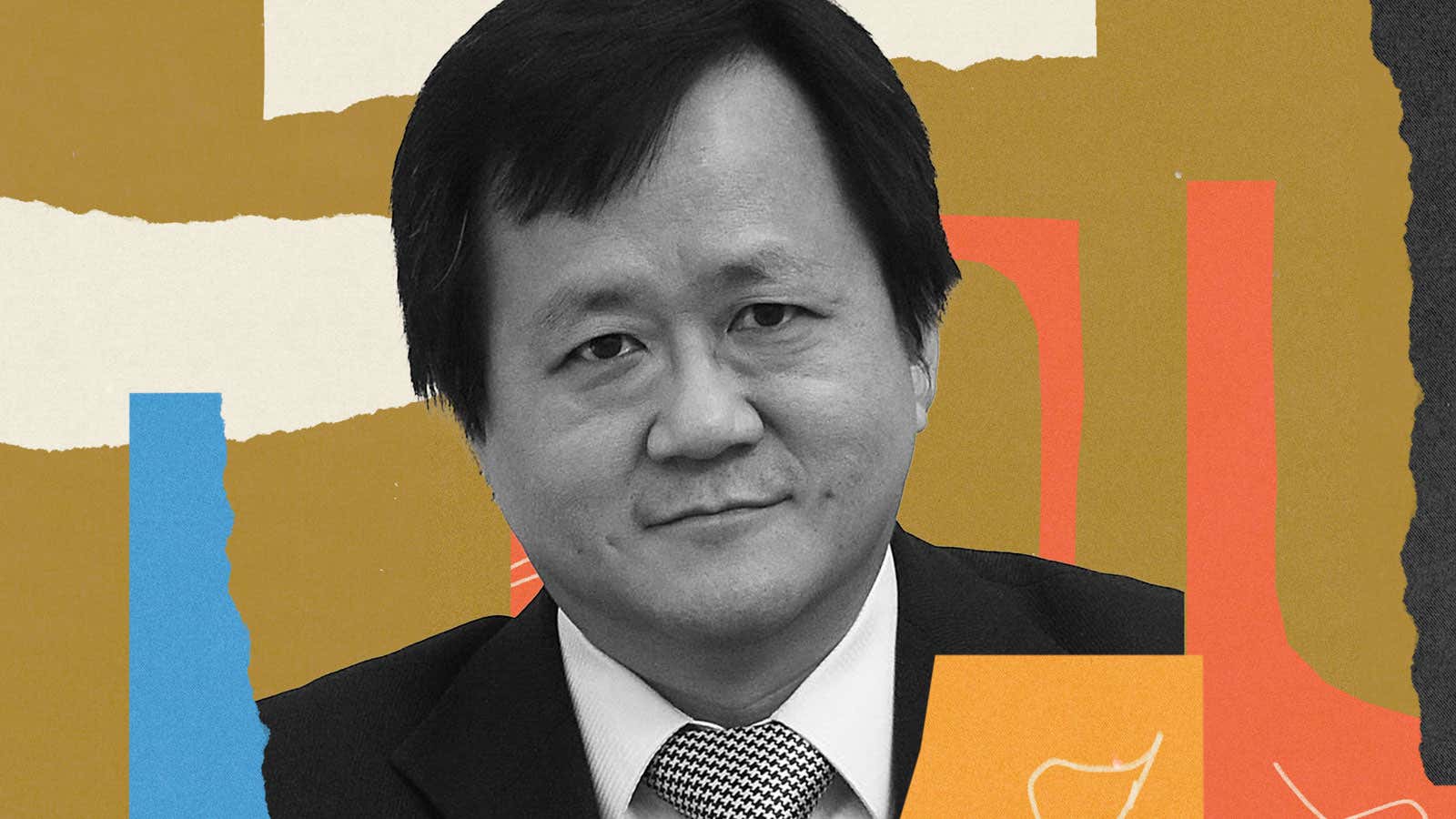Special Feature
中国ウォッチャーに訊く
Quartz Japan読者の皆さん、こんにちは。今週は、1週通してワンテーマで午後のニュースレターお届けする特集週間。4日目は、香港出身の政治史家が中国の歩んできた道とこれからの接し方を語ります。
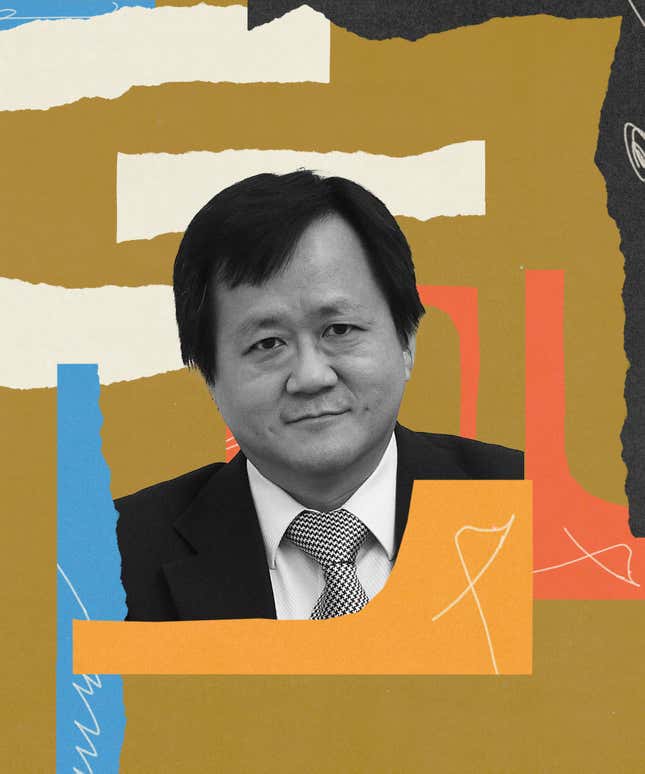
今週は…[中国ウォッチャーに訊く]
ワクチン外交やコロナ後の世界復興、あるいは人権問題から途上国のインフラ整備、さらには気候変動まで。あらゆる問題で世界が避けては通れない国、中国と、わたしたちはどう向き合えばいいのか。今週(21〜25日)お届けするニュースレター特集「中国ウォッチャーに訊く」は、対中政策のキープレイヤーである英国の視点から、さまざまな分野の識者のインサイトをお伝えしていきます。第4回の今回は、中国研究の政治史家が登場します。
スティーブ・ツァン(Steve Tsang)は、政治史家であり、ロンドン大学東洋アフリカ学院(SOAS)の中国研究所の所長を務めています。香港出身で1981年に渡英、オックスフォード大学で学び、博士号を取得したのち、30年近くさまざまな役職に就いてきました。
香港が中国政府に返還された際には、セント・アントニーズ・カレッジの学部長を務め、オックスフォード大学香港プロジェクトの一環として、その歴史を保存するための記録文書の収集や植民地時代の役員へのインタビューを担当しました。
現在は、中国の習近平国家主席の政治思想を記録し、分析する長期プロジェクトに取り組んでいるツァンは、中国と香港に関する複数の著書があり、中国の外交政策と台湾、米国、英国、EUとの関係に詳しい人物です。
Interview with Steve Tsang
中国の優先順位
──香港での生い立ちは、あなたの中国研究にどのような影響を与えましたか?
香港で育ったわたしが初めて中国を訪れたのは1978年、香港の大学の学部生だったときです。毛沢東時代が終わり、鄧小平時代が始まったころですが、「母国」がどのようなものかを知りたいという強い気持ちもあったんですね。
そのときの中国滞在は1週間ほどでしたが、非常に印象的な経験でした。当時は、羅湖(ローウー)で電車を降りてから橋を歩いて渡って中国側に入ったものです。中国の地を踏むのを待ちきれない想いのまま、深圳から広東に向かう列車の車上で窓の外の景色を眺めていたのを覚えています。
そして1週間が経ち、再び国境を越えるために深圳に戻ってユニオンフラッグを見たときには、「ああ、ここが自分の居場所だ」と思いました。1週間の冒険は、まさに目からウロコでした。
──その1週間で、いったい何があったのですか?
それはもう、いろいろと。ヌードルレストランで食事をしていたら、店の外から子どもたちがわたしたちをじっと見ていたことがありましたが、ものすごく居心地の悪いものでした。彼らはわたしたちの口元を指差しお腹をさすり、「お腹がすいた」とアピールするのです。
社会主義の姿を求めて訪れた中国で目にしたのは、貧困以外の何物でもありませんでした。
美しい風景で知られる陽朔での川下りを楽しもうと桂林を訪れた際、わたしたちは地元の人たちと同じ体験をしようと人民服を買って船に乗りました。下甲板から上甲板に行こうとすると、「上甲板は外国人と香港・マカオの同胞のためのものだ。あなたたちは下にいなさい」と言われたこともありました。
──どう感じましたか?
まるで自分が1920年代の上海の公園にいるような錯覚を覚えました。「犬・中国人の立ち入り禁止」なんて注意書き(*1)が貼られるような世界は、共産党によって打破されたはずだと思っていましたから。若者に特有の理想主義は、あのときの体験で完全に打ち砕かれました。
*1:1928年以前の上海では、外国人居留地の公園への中国人の出入りは禁止されており、「中国人と犬」の立ち入りを禁止する看板が設置されているといわれている。もっとも、Robert BickersやJeffrey Wasserstromなどの歴史家によるとこれは事実ではなく、中国共産党が「帝国主義の搾取の象徴として広く利用した」ものだという。ただし、両氏は、そうした看板は存在しなかったかもしれないが「その標識の説明が典型的に想起させるような偏見が、確かに存在したことは明らか」だとしている。
──いまの中国は極度の貧困から抜け出したとされますが、中国政府に対する印象は変わりましたか?
香港の学部生だったわたしは、当時、「毛沢東語録」(Little Red Book)を持ち歩いていたものです。大学で学んでいたわけではなく、自分でそれを買いに行ったのです。共産党のプロパガンダにどっぷり浸かり、党の発言を信じていました。だからこそ、中国に行ったのです。しかし、それはウソでした。それこそが問題であり、貧困も子どもたちの行動も船上の人びとの行動は問題ではありません。
この40年間の中国の経済的な奇跡は、疑いようもなく現実です。上海は利便性でみればニューヨークのマンハッタンに匹敵するほどで、それをみれば、中国が大きな進歩を遂げていないとは言えないでしょう。しかし、それは問題ではないのです。
──つまり、あなたにとって大事だったのは、宣伝されていたシステムが現実ではなかったということですか?
ええ、真実ではなかったということです。
──香港が中国に引き渡された当時、オックスフォード大学で研究をなさっていましたが、イギリスに住む香港人として、どう受け止めていましたか?
それで言えば、物事とは変わるものですね。当初、わたし自身の香港への関心は高く、オックスフォードに来た当時は、香港人としてのアイデンティティを強く感じていました。それから数年が経ち、結婚をして定住し、英国の市民権を得ました。わたしのアイデンティティは変わり、いまは香港人というよりも、香港出身のイギリス人だと自認しています。わたしの未来はもはや香港にはなく、家族も香港にはいません。
──イギリスでの中国の受け止め方は、ここ数年でどのように変化していますか?
中国への関心が高まっていると実感できるようになったのは2010年前後ですが、そもそもの出発点は非常に低いものでした。
キャメロン/オズボーン時代(2010〜2016年)は「英中黄金時代(*2)」ともいわれますが、実のところ非常に一方的な関係で、かつお互いへの理解のなさが露呈していました。イギリス政府は非常に熱心に取り組んでいるのに、中国政府はそれに付き合う素振りもみせなかったでしょう? ただし、その結果として、中国に対する一般の関心は高まりましたし、中国は豊かで強力になるなかで英国に多くの学生や観光客を送り込むようになったのは事実です
*2:デーヴィド・キャメロン首相とジョージ・オズボーン財相(当時)が2015年に始めた中国へのアプローチでは、中国からイギリスへの投資を可能な限り増やし、毎年の対話を通じて金融・経済関係を深めようと試みられた。
その後、2019年には香港での抗議活動とそれに対する中国政府の対応をめぐって。また、2020年にはパンデミックをめぐって状況が変化したと、世間一般は捉えているでしょう。もっとも、わたしにとって真の転換点は2017年にあります。第19回党大会で習近平は中国の新しいビジョンを掲げて自身の権力を強化しましたが、その新しいビジョンにおいて、いろいろなことが変わりました。
──それは、例えばどんなことですか?
「中国第一主義」──つまり「中国を再び偉大にする」という政策が事実上立ち上がり、香港に対するパラダイムも変化しました。香港におけるすべては2019年に始まったかのように言われますが、そうではありません。中国の政策が大きく変わったのは2017年で、習近平が「大湾岸圏」(greater bay area)について語ったときに、多くの人はそれを見逃してしまったのです。それまでは、香港はそれ自体が特別行政区だと考えられていました。しかし、この大湾岸圏という概念では、中心にあるのは香港ではなく深圳です。これは、非常に重要なパラダイムシフトでした。
──習近平はイギリスをどう見ているのでしょうか?
中国政府のイギリスに対する見方は、常に道具主義的なものでした。イギリスは非常に重要な国であり、中国はそれを認識していますが、イギリスは“トップリーグ”には入っておらず、中国の視野にあるのはたったひとつの国──アメリカだけです。
ヨーロッパ全体で見ると、中国にとって最も重要なパートナーはイギリスではなくドイツです。ドイツは中国が求めるテクノロジーをはるかに多くもっているからです。ただし、イギリスには、中国に提供できるものがあります。イギリスの規制当局が承認をすれば、それは世界的に大きな影響力をもつということです。
また、イギリスは単独で行動する傾向があります。EUに加盟していたころであれば(イギリスをきっかけに)EUの結束を崩すこともできましたし、アメリカと一緒に行動したくなければ同様にファイブアイズを突き崩すこともできるでしょう。
イギリスは世界で最もオープンな国のひとつです。他のパートナー国が中国からの投資を許可しないような分野への投資を喜んで受け入れています。イギリスは、対中国に限らず、非常に現実的で非イデオロギー的な見方をしているのです。
──この1、2年での変化はありますか?
中国はいまでもイギリスと関わりたいと思っているはずです。しかし一方で、中国政府は実際的なメリットよりも、自らの尊厳や公平性の問題を重視してもいます。たとえば、新疆ウイグル自治区をめぐるEUの対中制裁への対応がいい例でしょう。中国はEUの制裁を想定していたので、事前にカウンター制裁を用意していたほどです。
イギリスがEUの制裁に加わったとき、中国は驚いたでしょうね。対応策を決めるまでに3、4日かかったという話もあります。最終的には、英国を殴り返すことにしました。イギリスからの特別扱いを期待せず、ファイブアイズ(*3)の関係性にくさびを打ち込む可能性もありえます。
*3:オーストラリア、カナダ、ニュージーランド、アメリカ、そしてイギリスで構成される機密情報共有の枠組み。
──イギリスは中国に対してどのようなアプローチを構築すべきでしょうか?
自らが中国との関係に何を求めているのか、考えを明確にするべきです。中国との関係を築く上で譲れない重要な原則とは何なのか、と。
わたし個人は、中国と関わるべきでないとは思いません。むしろ、そうすべきです。イギリスがもつ偉大な伝統のひとつに、「外交は友人を相手にするときよりも、友人以外を相手にするときに最も必要とされる」というものもありますからね。
アメリカには、世界を民主主義国家にとって安全な場所にするというポリシーがあります。イギリスにはそういったものはありませんが、習近平率いる中国政府は明らかに、世界を権威主義にとって安全なものにするというポリシーを有しています。権威主義にとって安全な世界とは、民主主義の価値や民主主義を犠牲にして存在するもの。イギリスは、世界を民主主義国家にとって安全な場所にするというポリシーこそありませんが、民主主義の価値と人権とを信じています。
──もし、あなたが英国の新しい中国戦略を描く立場にあるとしたら、どんな内容にしますか?
中国が国際的なルールや基準を受け入れ、遵守するよう、中国と協力していきたいと考えます。貿易や投資をはじめ、あらゆる種類の交流において、お互いに公平な競争の場を確保したいと考えます。学者や学生が中国に行き、その基本的な権利を侵害するような扱いを受けることは許されませんし、あってはなりません。それはジャーナリストについても同様で、ジャーナリストが中国から追い出されたり、あるいは脅されたりするのは許されることではありません。
同時に、わたしたちは基本的な価値観をどのように守るのかについても取り組む必要があります。つまり、自分たちが購入する商品の製造過程で発生している強制労働を受け入れたくないのであれば、特定の地域や企業からは購入しないようにしなければならないということです。
中国戦略と並行して、「BNOスキーム(*4)」による香港の人びとの再定住戦略も必要です。イギリスのような国に30万規模の人びとが移住・定住する可能性がある場合、彼らがどんなに高学歴で裕福であったとしても、定住して完全に溶け込むためには支援が必要です。これはお互いに利益をもたらすものです。
*4:中国による香港での安全保障上の取り締まりを受け、イギリスは、返還前に生まれた香港人とその扶養家族に英国籍を取得する道をつくった。
もし支援がなければ、彼らは国内の特定の地域に──移民につきものの“ゲットー”に集まることになり、もとから定住している地元の人びととの間に軋轢が生じることになります。いま、イギリスには、香港の人びとに安全な聖域を提供するチャンスが、そして彼らの才能や資源を活用して相互に利益をもたらす大きなチャンスがあります。ただ、そう簡単にできることではありませんが。
(翻訳:年吉聡太)
at this time tomorrow…
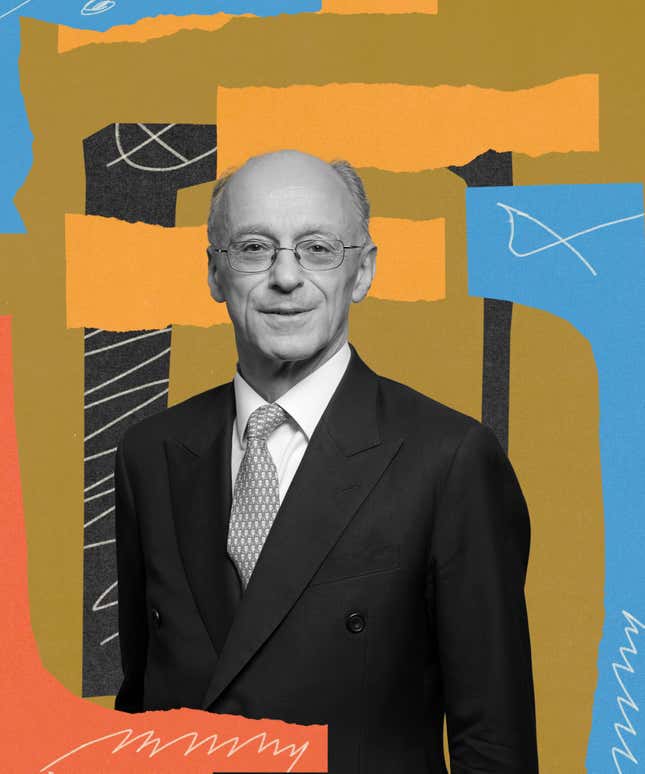
今週25日(金)まで5日間にわたってお届けするニュースレター特集「中国ウォッチャーに訊く」。明日25日の17時ごろにお届けする最終回では、英財界の重要人物、サスーン財閥の一員で元財務商務大臣でもあるジェームズ・サスーンのインタビューをお届けします。Twitterや、このメールに返信するかたちでも、どうぞご感想をお聞かせください。
🎧 Podcastは月2回、新エピソードを配信中。Apple|Spotify
👀 Twitter、Facebookでも最新ニュースをお届け。
👇 のボタンから、このニュースレターをTwitter、Facebookでシェアできます。ニュースレターの転送もご自由に(転送された方へ! 登録はこちらからどうぞ)。