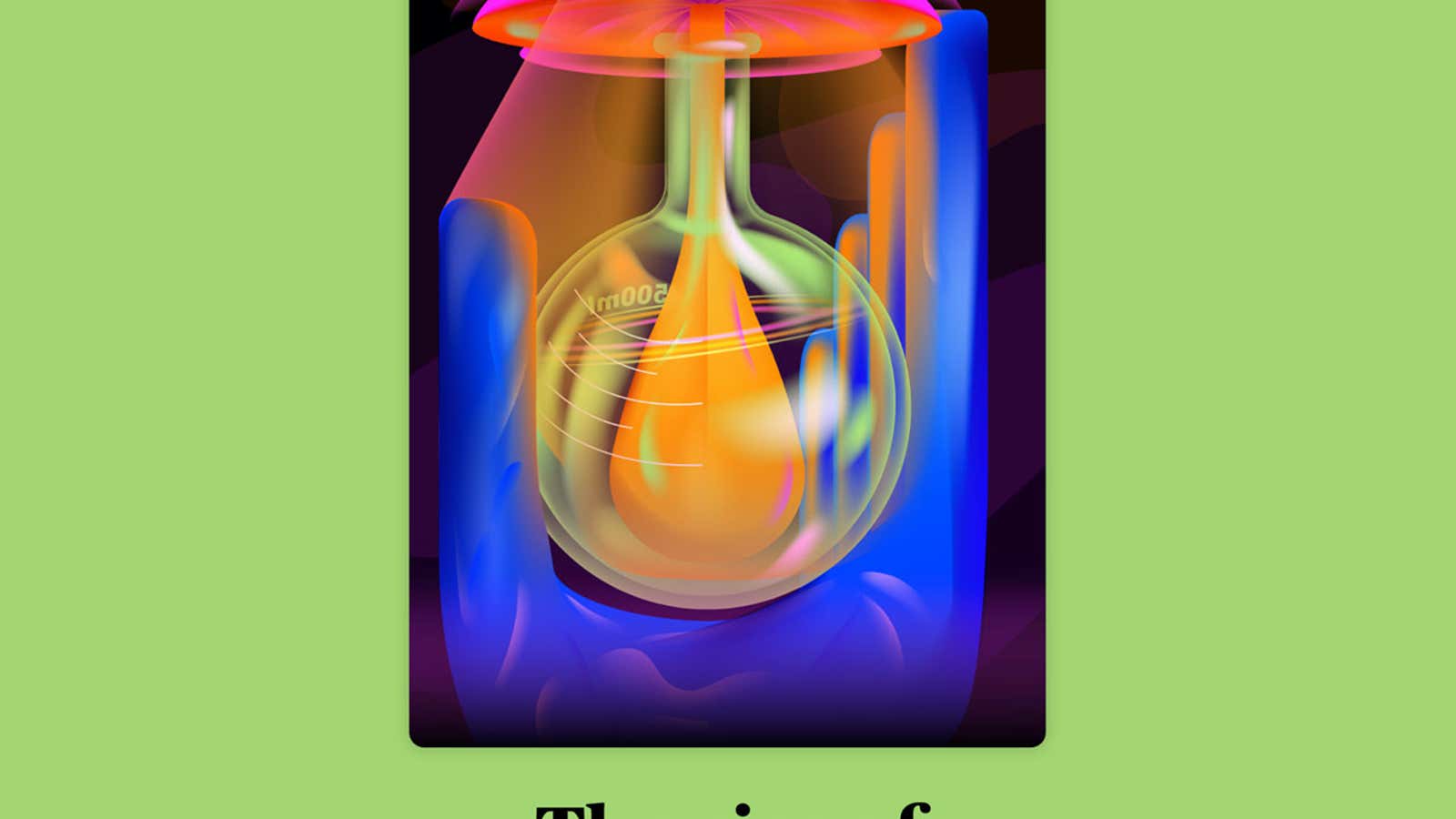A Guide to Guides
週刊だえん問答
世界がいま何に注目しどう論じているのか、米国版Quartzの特集〈Field Guides〉から1つをピックアップし解題する週末ニュースレター。「The rise of psychedelic medicine」と題したQuartzの原文(英語)と、原稿執筆時に流れていたプレイリスト(Apple Music)もあわせてお楽しみください。
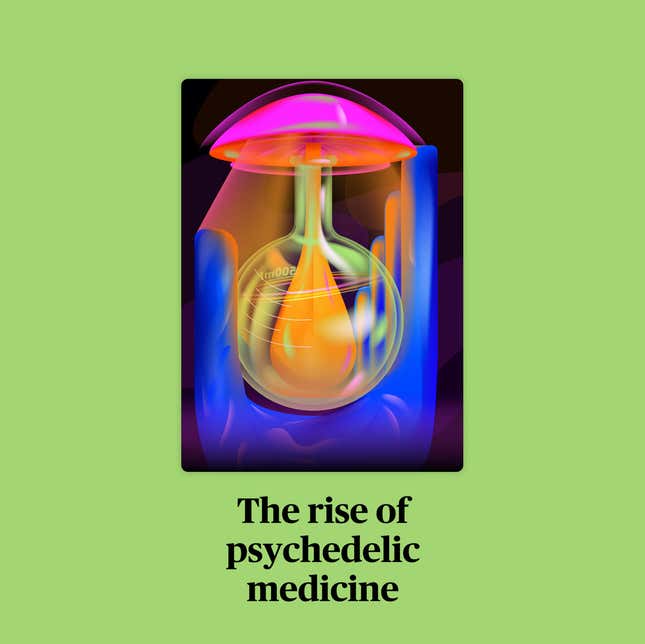
The rise of psychedelic medicine
サイケデリックス再実装
──いよいよ、オリンピックまで1週間を切りましたが、混迷は深まる一方ですね。
コロナ云々とは関係なく、そもそも、もはやオリンピックをやれる国ですらなかったことが明らかになっている感じがしますし、そう感じている人も多いのではないでしょうか。
──昔できたのだから、いまもやれる、と。
それこそ文春に、「『ちゃんと開催しようという努力が感じられない」海外メディアが東京五輪に“大憤慨”ワクチンは自己申告、書類は不備ばかり、取材体制は大学以下…」という記事があがっていまして、組織委員会の運営のデタラメさが海外メディアのスタッフの声を通して明かされていますが、メディア関係者が選手の取材を行う、いわゆる「ミックスゾーン」の設計について、アメリカの事例が紹介されています。「なるほど、そんなふうにやるんだ」と思わされるものですので、紹介しておきますね。
──お願いします。
「ちなみに6月中旬に行われたオリンピック陸上競技のアメリカ代表選考会では、会場となったオレゴン大学でジャーナリズム学を教えるロリ・ションツ教授が陣頭指揮を執り、12人の学生が8台のPCを駆使してリモート取材用のミックスゾーンを整備していた。
記者がチャットで送った質問に選手が答えるシステムで、コロナ禍の取材活動を大いに助けてくれた。現場にいない記者もアクセス権があり、世界中から自由に質問できたほか、インタビュー映像がすぐにアップロードされて発言の確認も簡単だった。記者たちが『すばらしい』と絶賛するほどの体制を、いち大学が整備したのだ。
ションツ教授は来年オレゴン大学で開催される世界陸上でもメディアスタッフとなって記者たちをサポートする予定だ。このように、世界大会を開催するための準備を時間をかけて築き上げている都市もある」
──へえ。大学の教授と学生がシステムを整備した、と。面白いですね。
一方の日本はというと、こんな感じです。
「しかし東京オリンピックでは、リモート取材についての案内はなく、ミックスゾーンでの対面取材がほとんどになる見込みだ。現場での取材を諦めた海外記者が情報を得る方法はほとんどない。
参加選手やチームは、現状、対面取材の有無など知らされていない。もし開始後に不満が出た場合に完全リモートに切り替えられるような準備は必要なのではないだろうか」
──とほほ。
これはもうここで何度も何度も指摘してきたことですが、オリンピックというものもそうですが、こうした国家的なイベントというのは、それが辛うじて意味をもつとすれば、それが、これまでのシステムやインフラを大掛かりにアップデートするチャンスをもたらしうるという点にあるはずです。それはただ単に、これを機に道路工事をして新しい橋を建てることではなくて、例えば、いまの事例で見たように、より効率的でよりオープンな「ミックスゾーンのあり方」をトライアウトするといったことが実は大事なんですね。というのも、そもそもスポーツイベントにおける「取材」の問題というのは、それ自体が大きな問題となっていたりするわけですから。

──どういうことでしょう?
例えば、メディアの取材に関していえば、これまでは取材対象に「物理的に近くに行ける人間」が優位な取材ができるという仕組みになっていて、それ自体が利権の巣窟になっていたことは、例えば日本のメディアにおける記者クラブというもののありようや、御用記者という人たちの存在が何を基盤にその命脈を保っているのかを考えてみればわかりますよね。ところが、オンライン化された先のような仕組みは、そうした空間を、「その場にいない記者」にも開放することによって、そうした利権化を緩和する力学をもっているわけですね。というか、オンライン化による民主化というのは、すべからくそういうダイナミクスをもっているのですが。
──なるほど。それこそ大坂なおみ選手がフレンチオープンで問題化した「記者会見って意味ある?」という議論とも通底しますね。
はい。フレンチオープンでの記者会見を大坂選手がボイコットした際に、『The Guardian』の記者が非常に面白いコラムを書いていまして、それはまさにメディアの立場から、自分たちの仕事がどれほど形骸化してしまっていたかを自虐的に反省する内容でした。「We’re not the good guys」(わたしたちは善の側にはいない)と題されています。
──面白そう。
こんなふうに始まります。
「エミレーツスタジアムのプレスルームで行われる記者会見に集まった者たちは『First Question Man』(FQM/最初の質問男)という神秘的な名で呼ばれる人物について知っている。けれども、FQMがいったいどのメディアで働いているのかは誰も知らないし、ジャーナリストであるのかすら定かではない。それを才能と呼べるなら、彼のただひとつの才能は、会見の最前列に座って最初の質問を発することで、それは大抵、ほかのジャーナリストが席に着こうとガヤガヤしているなか、怒鳴るようにして発せられる。
FQMの意図は定かではない。名を売りたいわけではなさそうだ。なぜなら彼の名前を知っている人には一人として会ったことがないからだ。あるいは何か冴えた洞察を披露して見せようということでもない。なぜなら、彼のほとんどの質問は質問というよりは、世界中の記者会見が愛してやまない、凡庸なコメントに過ぎないからだ。『アルセーヌ、今日の勝利は嬉しいでしょう?』『ウナイ、この勝ちは必然でしたね』『ミケル、タフな試合でした。いまの気持ちを』。
世界第2位の大坂なおみ選手が自身のメンタルヘルスを守るべく、記者会見をボイコットし、フレンチオープンそのものからも辞退することを発表した際に、FQMのことをすぐさま思い浮かべた。記者会見という馬鹿げた義務に何千回も参加し、その度にこれ自体が破滅してしまえばいいという考えを弄んできたジャーナリストからすると、大坂選手の判断には直感的に同情を覚えたものだ。ところが、彼女を襲った非難の怒号と見境いのない憤激を見るにつけ、そこに驚くほど強固な信念があるのが見てとれた。少なからぬジャーナリストたちにとって、記者会見は人生よりも聖なる何かだったのだ。大坂選手は例え彼らの人生を奪ったとしても、アスリートに『今日は試合中どんな気分でしたか?』と聞く時間を奪い取ってはならない、というわけだ」
──もうほとんどただの儀式でしかないということですよね。
はい。つい先ほど、昨日Netflixで配信が開始された「大坂なおみ」というドキュメンタリーを見ていたのですが、そのなかでも記者会見のシーンが何度か出てきますが、基本的な建て付けとして、記者が投げた「いま、どんな気持ちですか?」というもはや質問の体をなしていないような質問に、大坂なおみ選手が一生懸命内実を与えているという図式になっていまして、どう考えても、しゃべる方にだけ負荷がかかっている、まあ、いわばただの見せ物でしかないことがよくわかります。
──選手の中には「それも仕事のうちだ」と語る人もいましたが。
大坂選手は『TIME』に7月8日に寄稿した文章のなかで、こう書いています。
「わたしが問題にしたのはプレスではありません。むしろ伝統的な記者会見というもののあり方についてです。誤解のないよう、もう一度念を押して起きます。わたしはプレスが大好きです。でも記者会見は好きではありません。
メディアとの素晴らしい関係のなかで、中身のある一対一のインタビューをいつも楽しんできましたし、わたしの先達であるノヴァク、ロジャー、ラファ、セリーナといったスーパースターを除けば、わたしは近年のプレイヤーのなかで最も多くの時間をプレスに割いてきた自負もあります。
わたしはつねに心のままに答えるよう心がけてきました。メディアトレーニングを受けたことはありませんから、見たままの姿がありのままのわたしです。メディアとアスリートの信頼やリスペクトは双方向のものでなくてはなりません。
わたしの考えでは(あくまでもわたしの考えであって全てのテニスプレイヤーを代弁する考えではありません)、既存の記者会見のあり方は時代遅れで、全面的なリフレッシュが必要です。プレスと選手双方にとって、もっと興味深く、もっと楽しい、より良いやり方があるはずです。『観る者 vs. 観られる者』(Subject vs. object)という対立ではなく、ピア・トゥ・ピアの関係性がありうるはずです」

──良いですね。「ピア・トゥ・ピアな関係性」って。それがどういうものかはいまひとつわかりませんが、でも先ほどの、オレゴン大学のミックスゾーンのあり方は、可能性として、ひとつのヒントにはなりうるということですよね。
簡単な話なんですよね。身の回りでも「これ、誰も楽しんでないよね」「誰も得してなくない?」という、やる目的や意義が失われた状態で「それをやるためにやってる」だけの仕事はいたるところにあるわけでして、それをグレーバーという文化人類学者は「ブルシット・ジョブ」と名付けたわけですが、それはなにも一生懸命探さなくても見つかるものでして、「死ぬほどつまらん」と感じられたものは、まあ、だいたいそれなんですよね。ですから、大坂さんが、もっと面白いやり方があるはずだと考えるのは正当だと思いますし、それは実際のところ、本当は何も否定してはいないんですよね。
──やめちまえと言っているわけではなく、別のやり方があるでしょ、と言っているだけですからね。
とはいえ、そういう「死ぬほどつまらん」ことの上に自分のアイデンティティを築いてきてしまった人は、それがアップデートされてしまうと自分は用済みになるのではないかと脅威に感じますから、心の底ではつまらんなと思っていたとしても防御的にはなりますよね。お払い箱になる恐怖に耐えるよりも、つまらなさに耐える方が、おそらくは楽でしょうし。
──たしかに。
ただし、大坂選手の動議が喫緊性をもつのは、そうしたブルシット・ジョブが、誰かの大きなコストの上に成り立っている可能性があるからで、大坂選手は、それこそが「観られる側」であるアスリートのメンタルヘルスだとしているわけです。彼女は、記者会見を辞退する理由として、彼女自身のメンタルコンディションを開示しなくてはならなかったわけですが、そのことを彼女は強く問題にしています。
「舞台裏の見えないところでなんらかの困難と戦わなくてならないことはよくあります。アスリートといえども人間ですからさまざまなことが起きます。テニスという階級社会に向けて提案したいことは山ほどありますが、まず提案したいのはプレスに対する義務から理由を開示させられることなく休みを取ることのできる休養日を設けることです。そこから始めることで、スポーツの世界も一般社会とひとしなみのものとなれるはずです」
──理由を言わなくてはいけない、ということが、より大きなプレッシャーになるということですよね。
はい。説明責任を負うということです。大坂選手は、こうも言っています。
「わたしのケースでは、自分の症状を開示することに大きなプレッシャーがありました。正直にいうと、プレスも大会主催者もわたしのことを信じていなかったからです。こうしたプレッシャーが今後アスリート、特に繊細で脆いアスリートにかかることのないよう、保護のための措置を講じなくてはなりません。また個人的な病歴をめぐる狂騒に巻き込まれることは二度とごめんです。プレスのみなさんに次に会うときは、一定のプライバシーとエンパシーをもっていただくことを願います」
──Netflixの「大坂なおみ」のひとつのハイライトシーンは、当時15歳だったココ・ガウフ選手をめためたに破ったあと、ともに勝利者インタビューを受けるようガウフ選手を促すところでした。大坂選手は、「ガウフ選手に誇りをもってコートを去って欲しかった」のだと、そのシーンを回想していましたが、あれは改めて心温まるシーンでした。
言っても相手は15歳ですからね。大坂選手は、その場で即座に、ガウフ選手の胸の内で起きていることを察知して、敗北に泣くのならひとりでシャワールームで泣くのではなくコートでみんなの拍手に包まれて泣くほうがいいと彼女を促すんですね。大坂選手の行為を、試合後にガウフ選手は、こう語っています。
「彼女は真のアスリートであることを証明したと思う。わたしにとってアスリートの定義は、コートの上では人を最悪の敵であるかのように扱うけれど、コートを離れると親友のように接してくれる。彼女がしたのはそれです」
──試合自体は容赦ない勝ち方で叩き潰したわけですもんね。
『NPR』の記事は、大坂選手のNetflixのドキュメンタリーを絶賛していまして、そのなかで、「無慈悲な競技者でありながら、同時に人間として自分自身でありうるのか」が、このドキュシリーズの中心的な問いであると整理していますが、この問いは、何もスポーツに限らないものでもあるように思います。というのも、人は、例えば仕事という領域において、多かれ少なかれ「無慈悲な競技者」(Fierce Competitor)であることを要求されたりすることがありえるからです。別の言い方をするなら、経済というものが、ことさら、そうであるように人に仕向けてくるわけですから。

──そう言われると、これは非常に古典的なテーマでもありますね。なんらかの大義をなす上において、弱さや脆さは、障害になるということですもんね。
はい。ここで唐突に、今回の〈Field Guides〉のお題である「サイケデリック」の話に移るのですが、昨今のアメリカにおけるいわゆる「幻覚剤」のブームは、それが医療分野において改めて、その可能性が見出されていることを受けてのことですが、とりわけそれがターゲットとしている分野は、やはりメンタルヘルスなんですね。
──はい。
こうした状況のなかで、これまで食品に関する著書で人気を集めてきたマイケル・ポーランが、2冊の近著で、このテーマを扱っていましてメディアでも大きく取り上げられています。『How to Change Your Mind』『This Is Your Mind on Plants』という2冊ですが、最初の本は『幻覚剤は役に立つのか』というタイトルで亜紀書房から日本版も刊行されています。ポーラン氏は、言ってみれば昨今の幻覚剤ブームの強力なアドボケイターのひとりと言えるかと思いますが、その彼が『The Independent』のインタビューで非常に面白い歴史観を語っていますので、紹介させてください。
──さっきまで延々お話ししていた大坂選手の話と関係があると良いんですが(笑)。
まずポーラン氏は、一口に「ドラッグ」「ケミカル」と言うけれど、基本的には3つの種類があるとしています。「stimulants」(覚醒剤)、「depressants」(抑制剤)、「psychedelics」(幻覚剤)の3つです。で、彼は、それぞれの代表を「カフェイン」、「オピウム」(阿片)、そしてサボテンから採流ことのできる「メスカリン」としています。そして記事は、こう続きます。
「この3つのうち現代社会の最も深く埋め込まれることになったのはカフェインである。それどころかポーランは、むしろわたしたちの社会はカフェインの助けを得てつくられたものでさえあると語る。1600年代にコーヒーと茶がヨーロッパにいたる以前、特に英国の人びとは朝も昼も夜も酒を飲んでいたと彼は書く。結果、カフェインの到来は薬学的にも社会的にも巨大な影響をあたえることになる。ポーランは歴史家ジェームズ・ハウエルのことばを引用する。1660年あたりを境にして『コーヒーは欧州の国々に断酒をもたらした』。
『18世紀の啓蒙時代の思想家、ディドロやヴォルテールはカフェイン中毒者だった』とポーランは指摘する。『カフェインは理性主義や啓蒙主義、そして産業革命の勃興と絡まりあっている。人が重機器を動かし、夜勤をこなし、複式簿記を取り扱うためには、線的で、一点に集中するタイプの理性が必要だったのです』。
つまるところ、資本主義の燃料としてカフェインは格好のドラッグだったのだ。『This Is Your Mind on Plants』を読みながら、どんな職場でもお茶やコーヒーが無料で振る舞われるのかに気付かされ、まさに目から鱗が落ちるようだった。『資本主義とカフェインのリンクを知るにはコーヒーブレイクが何のためにあるのかを考えればたちどころにわかるはず』とポーランは頷く。『雇用主が従業員にタダでドラッグを配り、それを楽しむ時間に対して給与を払っているところに、すべての答えがある。誰が得してる?ということだよ』。
ポーランは、カフェインが近代化という巨大プロジェクトにおいて果たした役割と、カフェイン・ドリブンな進歩が果たして人間という種のために良いことであったのかという問いを慎重に分けている。『その答えは、近代化をどう考えるかによって変わってきます。近代文明は数多くの至福をもたらしましたがトレードオフもあります。トレードオフとは、つまりそれが生き物としての人間を脅かすものであるということです』」

──なるほど。面白いですね。まず、わたしたちは「ドラッグのない」、ある意味理性的な暮らしを送っていると思っているけれども、そうではなく、カフェインという覚醒剤にどっぷりと浸った世界のなかにいるということですよね。
はい。カフェインは、わたしたちが考える近代文明をつくるあげた重要な物質で、それは「生産性」をもたらすものであればこそ重宝されたわけですが、それが一般化していけば行くほどに、それ以外の「ドラッグ」、つまり抑制剤や幻覚剤は、社会にとって敵対的、破壊的なものだと考えられるようになっていくようになります。結果、アンチドラッグを20世紀の間主導してきたアメリカの、執拗な「対ドラッグ戦争」は、いわばカフェイン文明がそれ以外のドラッグを抑圧していく図式となっていたわけです。また、その「戦争」を主導してきた理念は、科学的なものであるよりは、盲信に近いイデオロギーや人種差別であったり、極めて政治的・経済的なものでした。それがようやく近年になって、科学的な知見が、政策決定に反映されるようになり、マリファナの解禁や、LSDやMDMAの所持・個人使用の合法化といった道筋も開かれるようになってきました。
──はい。
こうした流れのなかで、ポーラン氏は、今度は『The New York Times』に、7月9日に寄せたエッセイで面白いことを書いています。「ドラッグに対する戦争の終焉が見えるところまでわたしたちはきたが、より困難なのはドラッグとの平和というものがどういうものであるかを見通すことだ」。
──ドラッグとの平和的共存。
ポーラン氏は、「こうした物質を社会や人びとの生活のなかに織り込み、リスクを最小化しながら、それをいかに建設的なやり方で扱えるか」が問題だとしています。
──ふむ。
そうした課題を乗り越えるために、彼は、こんな見方を語っています。今度は『GQ』のインタビューからです。
「わたしたちはドラッグがコミュニティを破壊するものだと考えてしまいます。ドラッグの使用は人を破壊します。わたしたちの文明におけるドラッグの使用はとても個人主義的なのです。でも、そうである必要はないのです。ドラッグがコミュニティを結びつけるものとして存在する文化が世界にはあります。そうした文化において、人はひとりでドラッグを使いません。これは目覚ましい考え方です」
──ああ、面白いですね。わたしたちは、ドラッグというものをあくまでも個人主義的な観点から理解し、その善悪や有用性なども、あくまでも個人主義的な観点から論じていたわけですが、そうでない考え方のなかで、ドラッグを別のやり方で社会のなかに置くことが可能だということですよね。
はい。ポーラン氏は特にそうしたあり方をアメリカやメキシコの先住民族たちの知恵のなかに求めていますが、もちろん懸念もあります。今回の〈Field Guides〉にある記事「サイケデリックスはいかに製薬業界の寵愛を受けるようになったか」(How psychedelics became a pharma darling)は、MDMAがPTSDに対していかに大きな効果をもたらしうるかが科学的に証明されたことで、今後こうしたドラッグが巨大マーケットを形成していくことを予測していますが、資本主義によって加速させられたドラッグをめぐる新たなゴールドラッシュに対して、ポーラン氏は、こう釘をさしています。
「『わたしたちは先住文化からサイケデリックスの使い方について多くを学ばなくてはなりません。彼らはわたしたちよりもはるかに長い間それを使ってきました。西側がそれを知ったのは20世紀半ばのことですが、それ以前にすでに何千年も使われてきたのです』
ポーランはサイケデリックスが、医療化されすぎたり、あるいは資本主義の気まぐれのなすがままにならないような道筋を探る上で、先住文化の知見は重要だと考える。『いま資本主義はサイケデリックスに夢中です。ゴールドラッシュさながらの投資が行われ、昨年だけでも数億ドルが注ぎ込まれましたが、それだけをもってすべてがうまく行くわけではありません。わたしたちの社会システムのなかにどのようにそれが埋め込まれていくのか、大きなチャレンジとなります」
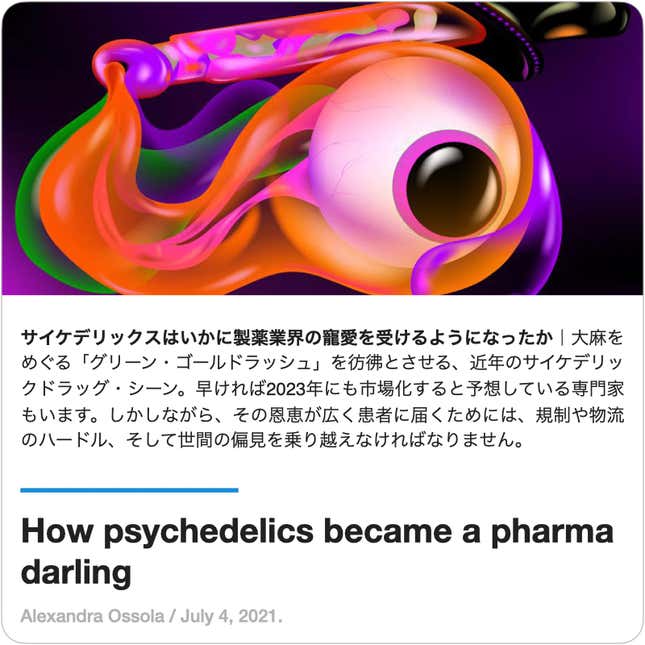
──カフェインドリブンな資本主義経済、あるいは官僚的医療機構のなかで、それらを扱ってしまえば、その本当のポテンシャルは発揮されないままになりうるということですよね。
ちょうど先ほど紹介したポーラン氏の『幻覚剤は役に立つのか』をアマゾンで検索してみたら、レコメンデーションアルゴリズムが、『禍いの科学 正義が愚行に変わるとき』という面白そうな本を薦めてくれました。本の紹介には、こう書かれています。
「誰もが良いことをしているつもりだった。いったいどこで間違えたのか。
新たな科学の発想や発明が致命的な禍いをもたらすことがある。十分な検証がなされず科学の名に値しないまま世に出てしまったものはもちろん、科学としては輝かしい着想や発明であったにもかかわらず、人々を不幸に陥れることがあるのだ。過ちを犯してしまった科学が『なぜ』『どのような』経緯をたどってそこに至ったのかを、詳しくわかりやすい物語として紹介する、迫真の科学ドキュメンタリー」
──ふむ。
ついでに目次をざっと紹介して起きますと、こうです。「神の薬 アヘン」「マーガリンの大誤算」「化学肥料から始まった悲劇」「人権を蹂躙した優生学」「心を壊すロボトミー手術」「『沈黙の春』の功罪」「ノーベル賞受賞者の蹉跌」「過去に学ぶ教訓」。
──面白そうです。
先ほど見つけた本なので、迂闊なことは言えませんが、おそらくこうした過去の事例が犯した間違いは、実験室で証明された「科学的に真」であることが、社会においても真でありえて、しかも、それが「真」であるがゆえに「善」でもあると過信したところにあったのだろうと想像します。というのも、そうした科学主義が繰り返し犯した過ちこそが、20世紀の歴史そのものだったわけですから。わたしたちがいま改めて注意しなくてならないのは、まさにポーラン氏が語っているように、慎重に、それを社会のなかに置かなくてはいけないということで、彼は、『The Independent』の取材の最後で、「わたしたちは、ひとつひとつのドラッグに、ひとつずつ正しい儀式を見つけなくてはならない」と語っています。

──儀式?
というと大袈裟に聞こえますが、習慣ということですね。ポーラン氏は例えばお酒についても、「昼間は飲まない」とか「何か食べながら飲むように」とか、厳密に制度化しているわけではないけれど、それが大きなリスクとならないような歯止めを、非公式なルールというかコード、つまりは習慣として社会化しているわけですよね。それは文化と呼んで良いものだと思いますが、これまで長いこと社会から排除されてきたようなドラッグを、いま一度社会化しようと思ったら、それが文化として定着しなくてはならないということなのだと思います。
──なるほど。文化というのはたしかに、そうやって明文化されていないコードの体系なわけですもんね。
冒頭の大坂なおみさんの話に戻りますと、わたしたちが生きているシステム、もしくは文化は、彼女の「無慈悲な競技者」である側面をサポートしドライブする手立てには事欠かないわけです。
──はい。
ところが、彼女がありのままの「自分自身」であれる時間や空間に対するサポートは、実質的にほとんどないわけですよね。それは大坂選手をはじめとするスポーツ選手に限った話ではなく、わたしたちの生活のあらゆる時間、行動が「生産性」というものに向けて作動させられていることを思えば、これはまったく他人事ではないんですね。
そうした課題に向けて、例えば瞑想アプリのようなものなどが、いま大きく注目されていたりもするわけですが、この連載の第38話「マインドフルネス・ビジネスの不安」で指摘した通り、これも結局、資本主義的ドライブと官僚主義的アルゴリズムと個人主義的な使用法によって、むしろ個々人の間の分断を促すものへとなっていく可能性があり、むしろわたしたちがいま生きている「カフェインカルチャー」を補強しかねないわけです。
──そうですよね。
そうした懸念も踏まえてみると、メンタルヘルスを問題にするにあたって、大坂選手が、医学的なメンタルケアよりも、ただ「休養日をつくりましょうよ」といったことを、まず変革の第一歩として提案したことには妥当性があるように感じます。つまり、彼女は記者会見という「古い習慣」を、リフレッシュするために「新しい習慣」をつくりましょう、と提案しているんですね。
──ああ、なるほど。たしかに。そうですね。いいですね。
はい。これは彼女だけの問題ではなく、社会全体にとって、とても大事な問題であるわけですが、彼女の存在自体が、それをユニークなやり方で射抜くことができるんですね。だからこそ、きっと、これだけの注目を浴びることになってしまうんですね。
若林恵(わかばやし・けい) 1971年生まれ。『WIRED』日本版編集長(2012〜17年)を務めたのち、2018年、黒鳥社設立。7月下旬に発売となる本連載の書籍化第2弾のタイトルは『はりぼて王国年代記』。Amazonでも予約がスタートしています。
👇 のボタンから、このニュースレターをTwitter、Facebookでシェアできます。ニュースレターの転送もご自由に(転送された方へ! 登録はこちらからどうぞ)。