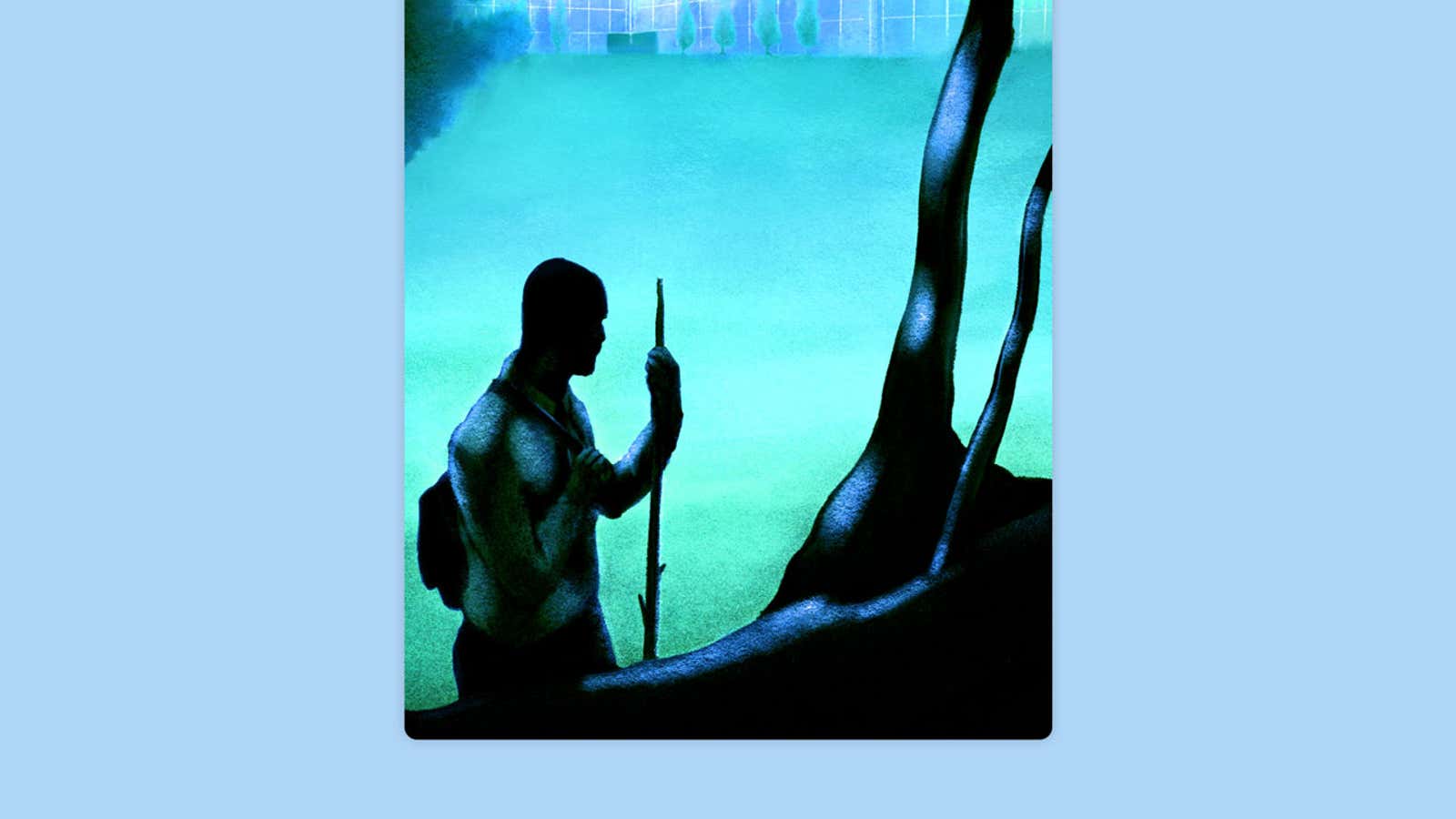A Guide to Guides
週刊だえん問答
世界がいま何に注目しどう論じているのか、米国版Quartzの特集〈Field Guides〉から1つをピックアップし解題する週末ニュースレター。「Can sustainable investing work?」と題したQuartzの原文(英語)と、原稿執筆時に流れていたプレイリスト(Apple Music)もあわせてお楽しみください。

いよいよ発売開始となった『週刊だえん問答・第2集 はりぼて王国年代記』刊行記念イベントを、26日(月)に開催します。参加者のみなさまの質問に、時間の許す限り、若林さんに直接答えていただきます。詳細およびお申込(無料)はこちらから。
Can sustainable investing work?
エシカル投資のことば
──おつかれさまです。
はい。今日は疲れ果てています。
──昨日はずいぶん長いことライブ配信をされていましたね。一応、東京五輪の開会式を観ながらライブ配信を行ったと聞いていますが。
結局5時間近くやってしまいましたが、開会式自体が、そもそも思っていたより長かったですね。
──ひとりで観ていたら相当つらかったと思います。
そこですよね。紅白歌合戦などもそうでしょうけれど、ああいう国家的イベントは、ひとりで観てもつまらないものですよね。かつては、テレビを中心に置いた「お茶の間」というものを通して、その価値が伝播するような建て付けのものだったのだと思いますが、いま「お茶の間」っていうものが何をさしているのか曖昧ですよね。多くの人はソーシャルメディアのコメントを眺めながら観たのではないかと思いますが、もはやこうした「国民的イベント」は、観る側の設定としてどういう構えで観たらいいかわからないようなものになっていることは強く感じますね。ソーシャルメディアを含めたやりとりを基盤としたものになっていれば、もう少し違った接し方もあったのかもしれませんが。もう長年テレビというものデバイスをSVODを観るためのモニターとしか使っていない者からすると、情報の受容という観点から、改めて扱い方に困るものだなとは感じました。個人的には、配信でもしながら観るというようなやり方以外に接し方がわからないといった感じでした。

──情報デバイスを一人ひとりが手にしている状況において、「お茶の間」前提のコンテンツは、たしかに、どうアクセスしていいのか、難しさを感じます。
まったく関係ない話ですが、英国のラッパーのDaveの新作がちょうど開会式の日にリリースされましたが、それがとてもいいタイトルでした。
──はあ。どういうものですか?
「We’re All Alone in This Together」というもので、細かく訳すなら「みんなひとりぼっちで、そのひとりぼっちの状態で、一緒に参加している」となるかと思います。
──ああ、いいタイトルですね。
オリンピックのようなものに、かろうじてポジティブなメッセージがありうるなら、このDaveのアルバムの表題は、その前提というか条件を、うまく言い表していると言えるのかもしれません。音楽もシリアスでメロウでドラマチックでカッコいい高揚感のある、とてもいい内容ですので、開会式をめぐる状況がしんどかった方にはおすすめします。
──Daveと言えば2019年のグラストンベリーで15歳の少年を客席からステージにあげて一緒にラップするという名場面がありました。
開会式で見たかったとすれば、本当であれば、ああいう高揚感ですよね。ちなみに、これを観て思い出したのは、前回ここで語ったことですが、大坂なおみ選手がUSオープンで試合に負けたココ・ガウフ選手を労ってともにインタビューを受けるシーンでした。これは、USオープンでセリーナ・ウィリアムズ選手に勝って初めて優勝したにもかかわらず客席からブーイングを浴びて涙ながらに勝ったことを詫びた大坂選手にしかできない振る舞いだったと思いますが、あのときココ・ガウフ選手は15歳だったんですね。Daveの動画と、このときの大坂選手の動画を改めて観ると、いま「感動」の名の下にどういうものを観たいのか、改めて考えさせられます。未見の方で、なんらかの口直しが必要という方には、ぜひ観ていただきたいです。
──何度見直してもにこにこしちゃいますよね。ところで、開会式は放送で観たんですか? それとも配信?
配信で観たのですが、開会式をウェブなりで観ることができるのかどうかは、自分が調べた範囲ですと当日まで、明確に情報が出ていなかったんですよね。それも非常に不可解でした。最終的にはNHKプラスで観ることができましたが、少なくとも前日まで、開会式が配信されるということは、ちゃんと明示されていなかったはずです。
──テレビで観て欲しかったんですかね。
その辺もよくわからないんですよね。Olympic Broadcasting Serviceはアリババと提携して新たなクラウドサービスをローンチしていて、北京五輪用のソーラー電力を用いた新たなデータセンターをつくったりしていまして、アリババは東京五輪にも協力しているとの報道が過去にもありましたから、オリンピックのストリーミングへの移行は規定路線であるはずですが、東京五輪がそうした潮流にどれだけコミットしているのか、よくわかりませんね。

──なるほど。開会式そのものはいかがでした?
これはどう見るべきかというと、そもそも成功・失敗が無効化されたところで行われているものなので、その質問も意味をなさないんです。そういうふうにつくられているんですよ。このやり口は、現政権のコロナ対策とまったく同じなんですね。
──うん?
つまり、成功を定義しないので、失敗も存在しない、というやり口です。
──ああ。この週末に発売になった『週刊だえん問答第2集 はりぼて王国年代記』の序文で書かれていたことですね。「ゴールの位置を動かし続けたら、やがてゴールの意味が失われるのは必然だが、パンデミック下においてそれは、『これをもって収束』と見なす瞬間が訪れないことを意味している」──。
はい、まさにそれです。オリンピックや万博のような国家イベントは、すでにしてその意義を失っていますので、それ自体に価値を求めるのがそもそもどうなのかという問題はあるのですが、それでもまだ名乗りをあげる都市がかろうじて存在するところを見ると、政治的に利用する価値はある、と少なからずみなされているところはあるのだと思います。
──政治利用以外にはもはや利用価値がない、ということですよね。
はい。実際2028年のロス五輪は、ビッディングが行われることなく、24年の誘致競争に参加していたロサンゼルスにバッハ会長の独断で割り当てたと言われていますから、ほとんどの都市の首長は、オリンピックにメリットはない、もしくはメリットがあったとしても、そのメリットが予算超過のデメリットを上回ることはない、とみなしているわけです。ロサンゼルスのエリック・ガルセッティ市長は「自分から進んで負債を負い、そのコストを公共予算で補いたがるような政府をもっていない限り、ほとんどの都市は二度とオリンピックをよしとすることはないだろう」と語っています。ちなみに1960年以降のオリンピックにおいて予算超過をした割合は、実に100%ですから。
──予算内に収まった大会はないんですね。
メガプロジェクトに関するデンマークの専門家Bent Flyvbjergがオックスフォード大学で「なぜオリンピックは破裂するのか」という非常に面白い論文を発表していまして、これは『ブラック・スワン』のニコラス・タレブの協力を得て書かれたものですが、とても面白いものです。このレポートにクレームを入れてきたIOCに対する返答を記したバッハ会長への公開書簡というのも出ていますので、ぜひ読んでみてください。
──面白そうです。
いずれにせよ、オリンピックを政治目的として利用するにあたっては、それを通して国民との間になんらかのコンセンサスや合意を結ぶということがひとつのゴールになるのだと思いますが、1964年の東京大会には、それが実際どこまで一般化したものだったかは異論もありそうですが、その大会をもって、日本は国際社会に復帰し、民主国家として独り立ちしていくのである、ということを世界に向けて発信すると同時に、国内においても、日本という国の立ち位置を明確化する役割があったわけですね。
──ふむ。
そこには少なくとも「これからの日本」をスタートさせるという意識があったのだろうと思いますし、国民の側にも「ああ、そうなのか」と、ある方向に向けて意識づけがなされたようなことがあったはずです。例えば、五輪の開催は、当時海外渡航の自由化といった政策とセットとなっていたわけですから、こうした制度面での転換・アップデートを、オリンピックを通したマインドセットの転換をもって後押しした、という格好になっていました。
──なるほど。
2024年のパリ五輪についていえば、すでにコロナからのグリーンリカバリーとセットでシャンゼリゼ界隈の大規模なリニューアルプランが発表されていまして、21世紀型の都市への転換をオリンピックに向けた期間を通じて行いつつ、24年にどんと世界にお披露目という絵図が見えていたりするのも、同じようなことです。
──はい。
ところが、東京は当初から、かつての都知事のただの私怨か、せいぜい景気浮揚のための「打ち上げ花火」としての意義しか想定されておらず、しかも日本の経済政策はいつまで経っても土木政策しかありませんから、最初から「成功」の絵図がないんですね。しかも、それが半ば意図的なんです。「コンパクト五輪」から「復興五輪」「コロナに勝った証の五輪」と、次々とゴールを動かし続けることで政府や都なりが発しているメッセージは、「五輪の『成功』は恣意的に、あとから決定することができる」ということでして、そこで起こりうる最も由々しき自体は、「失敗が存在しなくなる」ということです。

──なるほど。
これは昨日(23日)に行われた開会式でも一貫して採用された戦術で、ゴールが明確に設定されていないところで、MISIAさんのレインボーカラーの衣装や、大坂なおみさんの最終聖火ランナー起用が、所詮はただのおためごかしに過ぎないのは、オリンピックを政治利用したがっている人たちが、そもそものところで「ダイバーシティ」といった課題にコミットしてもおらず、それが「これからの日本」の姿を指し示すものであるという約束も、どこでも一切していないからです。
──ほんとですね。
であるがゆえに、そのメッセージに対して、一方からは「え? これが日本がこれからコミットしようとしている道筋なん?」と混乱を来たすことになりますし、逆にもう一方の側から見れば、ただの「tokenization」となって、どの陣営から見ても全体にもやっとした評価になって、せいぜい「ピクトグラムがよかった」といったテレビ番組の感想程度のコメントしか引き出せないことになります。でも、ここで最も重視されているのは「失敗を避ける」ことですから、それでいいんですね。MISIAさんも大坂なおみさんもジョン・レノンも、目指すべきゴールがないところでふんわり差し出された記号にすぎませんので、仮にメッセージ的な部分で突っ込まれても、事後的に「そういう意味ではなかった」と言えるようになっていますので、内容がなんであっても実際なんの問題ないんです。結果、なんらかの非難が出たとしてそれを背負うことになるのは、個々のアスリートやアーティストにということにもなります。
──開会式の何にもやっとしたのか、だいぶわかってきました。本来であれば象徴として記号でしかないはずの天皇陛下が実体性をもったオーセンティックな存在として際立ってしまうところに病理の深さが現れているようにも感じます。
ほんとですね。要は「それっぽいことが言われていればなんでもいい」というやり口で、「それっぽいこと」を適当に貼り合わせて、「日本すごい」「感動」みたいな感じが出せればいいんです。長嶋茂雄さんや王貞治さんにはなんの恨みもありませんが、歩くのもままならない長嶋茂雄さんを引っ張り出してきて歩かせれば、それは心情的に心動かされることにはなりますが、それがいったい、「これからの日本」に向けてなんのメッセージになっているのか、その政治利用は、どういう国家像や社会観と具体的な政策と結びついているのかは定かではありませんし、さらに言えば、松井秀喜さんを使ったあの演出は「高齢者が生き生きと生きていける社会」を表象すらしていませんよね。
働き盛りの世代が、高齢者が表舞台に立つための介助をしている絵図を見せられるのとほぼ同時に、「森喜朗さんを名誉最高顧問に」というニュースが配信されれば、あれが、かなりえぐいメッセージをもった演出であることに間違いないはずですが、それでも記号としての「長嶋」が持ち出されれば、なんとなくポジティブな意味は発動してしまう建て付けになっているわけですね。
──実際、あれを見せられても、どう思えばいいかわかりませんでした。「昔の日本はよかった」というノスタルジーすら喚起されませんでしたし。
これは開会式のディレクターを前日に解任された小林賢太郎さんの騒動をめぐって、どなたかが投稿されていたツイートですが、この指摘は興味深いものだと思いますし、これは開会式に通底する問題を突いているようにも思いますので、引用させていただきますね。
「『君の席』(バナナマン・おぎやはぎ・ラーメンズ)のネタに共通する欠点は、あれだけ緻密に計算された構造を持ちながら『諷刺』に手を出したとたん急に雑になること、つまり笑いのセンスの尖り具合に追いつけない教養不足と通俗性だとずっと思っていたのだが、最悪なかたちでそれが露見してしまった」

──ふむ。小林賢太郎さんの件では、「あれは風刺なのだ」と擁護をする声も多数ありましたが。
ソーシャルメディアなどで出回った情報をなどによれば、ネタは「子ども番組の制作の舞台裏にヤバいヤツらがいる」ということを揶揄したものですから、あくまでも風刺の対象は「子ども番組」です。
ホロコーストは風刺の対象ではなく、ただ「ヤバいヤツら」の「ヤバさ」を表象するためだけに持ち出された記号で、それが「ユダヤ人」や「ホロコースト」である必然性はまったくなく、おそらくほかのことばであってもよかった程度のものです。これは、実際ご本人が辞任の弁のなかで、それを「愚かなことば選び」と呼び、「思うように人を笑わせられなくて、浅はかに人の気を引こうとしていた」と語ったことからも明らかです。つまり「ことばの選択」の過ちだという認識なんですね。
──他のことばでも全然よかったところ、目立ちたくてそれを使った、と。
それが浅はかであったことはご本人も長いこと反省されてこられたのだと思いますので、その浅はかさ自体を責める気はありませんが、間違ってはいけないのは、今回噴出した批判は「ことばの選びが不適切だった」ことではなく、ホロコーストといった相当に厄介な問題を、あくまでも「選択的に選べるネタ」としてしか扱ってこなかった状況をめぐるものだったと思えるところです。
つまり、ホロコーストは、この国では「数あるヤバいネタ」のひとつの表象・記号でしかないということが問題だったわけでして、先のツイートにあった「雑になる」というのは、コンテキストが錯綜して扱うことが本質的に難しい概念を、「ヤバいこと」を表すための記号として無造作に放り込む、その不用意さ、浅はかさを表しているのだと思います。そして、その「雑さ」は、小林賢太郎さんに限らず、開会式全体に通底している浅はかさのように見えました。
──ことばというものの実体性を低く見積もるというか、ただの記号として弄ぶ感覚ですよね。
こうした軽薄さは、結論から言えば、テレビ・広告・芸能が三位一体として支配してきた日本のメディア文化全体を全面的に覆い尽くした浅はかさ、愚かさだと思いますが、こうした浅はかさが罪深いのは、それこそナチの国民啓蒙・宣伝大臣だったゲッベルスが言ったと伝わる「嘘も100回言えば真実になる」という考えに通じているところでして、実際のところ、この原理を日本においては政府も企業もかなり根深く信じこんでいるんですね。これは私が見るところ、端的に「コピーライティング」というものがもたらした大きな弊害です。

──コピーということでいえば、開会式にはたしか「faster, higher, stronger -together」といったようなモットーが掲げられていましたが、おそらく誰も、まったくピンとこなかったように感じます。見た範囲、誰も言及していませんでしたし。
一事が万事それなんですね。つまり誰も本気でコミットしようとはしてない「それっぽいことば」を適当に並べて粗雑なマーケティング感覚のなかで選び取っただけという。言った事実はあるのだけれども、それは約束としては発動されず、それが実現されたのかされなかったのか評価自体がなされませんので、誰もそのことばに責任を取らなくていいんですね。そういう構造を、コピーライティングというのが強化してきたわけで、それが、今なお企業や政府における「ビジョンづくり」の空疎さにおいても踏襲されています。
──オリンピック並に何も約束していないビジョン、多いですよね。
先日、佐久間裕美子さんに面白い話を教えてもらったのですが、ある日本の会社はSDGsへのコミットメントを明確に「約束」というかたちで打ち出したそうなのですが、それを社会に向けて表明するにあたって、その企業は、広告代理店を外したそうなんですね。
──へえ。面白い。
自分たちのことばを実体的なものとして世の中に置くためには、代理店文化から身を引き剥がさなくてはいけない、ということを企業がようやく悟ったということなのであれば、この流れは、ぜひ加速していただきたいものです。
──「代理店文化」ということばで改めて気づきましたけれど、開会式に象徴されたような空疎さは、結局そこで何らかのメッセージを発している主体がおらず、「代理」の誰かが、あたかもそれを誰かが言ったような格好で取り繕っている、言ってみれば「代理文化」が、構造的にもたらす空疎さですよね。つまり、代理店は、頼まれたからことばなりをつくりますが、あくまでも代理としてやっている限り彼らのことばにはなりませんし、企業は、自分たちのものであるはずのことばを社外の人間につくらせている限りにおいて、それは決して自分たちのことばにならない、という。
これはよくオウンドメディアに関する話題において常日頃クソミソに非難してきたことですが、「発信をしたい」と言っている輩が「発信」を他人に丸投げして「代理」させていることのおかしさにそもそも気づかない、そのバカさ加減に企業はいつになったら自覚するんでしょうね。
──企業に限らず政府も同様に「金で買った代理のことば」しかもてていないのだとするとすでにして世の中プロパガンダ=キャッチコピーしかないということになります。
結局ただのプレイスメントなんですね。「MISIA」も「大坂なおみ」も「長嶋茂雄」も「ドローン」も、小林さんの「ホロコースト」や小山田さんの「いじめ」同様、メディア演出上のただの「ネタ」でしかなく、これは代理店が悪いということではなく、彼らはビジネス構造から上も能力上からも「代理としてそれっぽいことを言うこと」しかできませんから、それに任せて主体性を放棄している主体の方こそ、よほど問題だと言えます。
それは文化セクターも同様で、開会式が「日本の文化のプレゼンテーション」と用途として使われるのはいいとしても、昨日見せられたのは、「日本文化のプレゼンテーション」というお題のなかに「文化産業が提供しうるネタ」がランダムにプレイスメントされただけの何かであって、それはメタな視点でみれば「代理文化そのもののプレゼンテーション」でしかなかったということになろうかと思います。実際、次から次へと使い捨てにされた文化従事者が、代理店文化の便利な駒に過ぎなかったことは、この間のゴタゴタを見ても明らかですよね。

──なんとも残念な話です。
それで傷ついた人たちがいっぱい出たのは気の毒でしたが、文化が体現すべきはずの「オーセンティシティ」が簒奪されることがわかっていて、そこに携わったこと自体が浅はかなんです。これは個々人の問題ではなく、個々の産業の矜持の問題だと思いますが。また、「サブカルの敗北」なんて話題もありましたが、「サブカル」と言っていた領域ですら本質的には代理店文化のサブブランチのようなものでしかなかったということでして、ビジネス構造的に見ても広告代理店から自由な文化産業がどれほどあったのかを思えば、そもそもサブカルの自由なんてものがあったのかなとも思いますし、それどころか自分たちで、その自由をみすみす「代理」の手に明け渡してきたというのが、むしろ実態に近いような気もします。広告クリエイターをここまでちやほやしてきた文化セクターは世界的に見てもあまり類例がないでしょうし。
──とほほほほ。産業といえば、ギリギリになって泥舟から逃げ出すように開会式の参加を取りやめた政治家や財界の尻軽さにも呆れました。
誰もコミットメントということを本気で体現しようとは思ってないんでしょうね。風見鶏であることを「ビジネス上の選択」と自分たちを甘やかして正当化してきたような、そういう文化しか日本の経済界には残ってないんですかね。
──うんざりしますね。
とはいえ、そういう尻軽さをもって事業の舵取りをできなくなっているのは、企業は環境へのコミットメントを強く要請されていて、これまでのように「ことば尻」だけで「やってます感」を出して逃げようとしてもそうはいかなくなっていることからも明らかになっています。

──まさに今回の〈Field Guides〉が問題にしているところですね。
はい。今回の〈Field Guides〉は「サステイナブル投資は効くか?」というお題で、メイン記事は「エシカル投資入門」(A guide to ethical investing)というものですが、この記事の冒頭に、化石燃料から脱却しろという株主たちからの声を傲然と無視し続けてきたExxonMobilの、この5月にあった株主総会でドラスティックな動きがあったことを伝えていまして、再生エネルギーへのシフトを要求するEngine No.1という小さなヘッジファンドが4人の役員のうち3人を送り込むことに成功しています。
──へえ。すごい。
これはアメリカの経済界においてはかなりのインパクトがあったようで、それというのも、このEngine No.1が、2020年12月に創設された、生まれてわずか半年のファンドだったからです。彼らは創業すぐに「Re-energize Exxon」というウェブサイトをローンチしてキャンペーンを開始しますが、Quartzの記事によれば、彼らの論点はイデオロギーに基づくものではなく、数字を根拠にExxon Mobilがいかに株主を損させてきたかを説得的に論じ、それをもって株主たちに、企業の再生エネルギーへのシフトを促したと言います。

──ダイナミックですねえ。
若いファンドですが、やっているのは業界のベテランで、「アクティブ・エンゲージメント」と呼ぶべき企業への介入を担当しているチャーリー・ペンナーという人はJana Partnersというファンドで、親が子どものスマートフォンの使用を制限するためのフィーチャーの導入をAppleに対して迫り、それに成功した人物だとされています。
──Exxon Mobilが、こうした動きをもって変化を余儀なくされると、産業全体に対する影響は大きそうですね。
今回の〈Field Guides〉には英国の大手投資銀行HSBCを石炭関連企業への投資から撤退させたShareActionというチャリティ組織のCEOキャサリン・ホワースさんのインタビューも掲載されていまして、投資家と銀行の間で相当白熱したディスカッションを執り行ったとしていますが、こうした小さなアクティビズム・グループが、業界の巨頭を揺り動かしているさまは非常に胸のすくものではありますが、一方で、ESG投資がただのハイプで、気候変動に対する実行的な効力は少ないというレポートもあって、投資行動によって変革を起こすよりも、政府による強力な規制がない限り、ESG投資は「時間の無駄」とする意見もあります。

──ふむ。
そうした意見に対して、先のホワースさんは、こう反論しています。
「そうした意見はシニカルすぎるきらいがあると思います。金融機関のパフォーマンスを向上させることは可能です。それが革命的な変化をもたらしうるかは、これからの推移によりますが、ダイナミックなシェアホルダー・アクティビズムの時代に入ってきたことで、担当役員や社長個々人に対して、責任をきちんと担わせることが始まっています。彼らは、環境ファースト、人権ファーストを実行することを求められるようになります」
──個々人に対して圧力がかかっていくということですね。
こうしたアクティビズムが、会社というもののコレクティブな責任の前に、社長や担当役員といった個々人に圧をかけていくことになるのであれば、それらの人びとが、いよいよ「代理のことば」でやり過ごすことはできなくなっていくでしょうから、こうしたことが日本国内でも一般化していくのであれば、責任を常にうやむやにすることで延命してきた状況が少しは改善すると期待したいところではあります。
──危惧としては、そもそも仕事をするなかで、一度も自分のことばで話したことのないような人たちに、それができるのか、というあたりでしょうかね。
不思議ですよね。日本における仕事というものは、自分たちのことばで語るものではなくなっていて、それで仕事が成り立ってきたわけです。自分たちのやっている仕事のゴールやミッションを、自分たちのことばで語ってみる、というようなことをロジックモデルを用いたワークショップで時々やってみるのですが、少なくとも大きな企業において、これをまともに語れる人に会ったことがないんですね。
どこかから借りてきたような、嘘っぽいことばしか出てこないのがほとんどで、会社で用いていることばが、そのような腹落ちのしない、ほぼほぼ空虚なものでしかなく、それを内面化することでしかその環境にサバイブできないのであれば、その環境に適応してしまった人こそが、おそらくメンタル的に重要な問題を抱えているはずです。
──そんなに重症ですか。
こうしたことばの問題が、特にESG、SDGsといった文脈で大きく問題となっていくのは、すでにしてアメリカでは、『Allure』というメディアが「“地球に優しい”“環境に優しい”“エコフレンドリー”“生分解性”といった表現も雑誌内での使用を禁止にする」ことを発表していまして、実体のないところで、なんとなく雰囲気で「優しいことやってます」という企業は取り合わない姿勢を明確化しています。また、これは非常に面白いレポートなのですが、「ダメなサステイナビリティ・ライティング」を問題にしているものでして、『Forbes』誌が「Most Valuable Brands」としている50の企業のウェブサイトの98%が「地球に優しい」とか「わたしたちはコミットしています」といったダメなクリシェをコーポレートサイトに掲載していると指摘しています。

──面白そうではありますが、とすると企業はいったい何を書けばいいんですかね?
やってることを書けばいいんですよ。「わたしたちはコミットしています」と書くスペースがあるなら、その「コミットした内容」を明かせばいいだけなんです。そっちの方が「コミットしていること」が伝わりますし、語るべき内容がないところで「コミットしてます」なんて言ってみたところ意味ないですからね。といった当たり前のことがわからないのだとすると、それは相当の重症ですよ。やっぱり。
──ほんとですね。
この間何度もここで語ってきたことですが、オードリー・タンさんが言うように、デジタル社会の原理というのは、リテラシーよりもコンピテンスを基軸としたものなんです。つまり、「何を知っている・何を考えている」ではなく「何をやっている・何ができる」に移っていまして、ソーシャルメディアというものがそのインパクトを最大限に発揮するのは、知識の伝播においてではなく、むしろ行動の連鎖という点においてなんですね。
ですから、「わたしたちはこう考えます」みたいなことは、少なくとも企業活動においては、どうでもいいんです。そもそも事業や経済活動というのは、「何かをつくる」とか「何かを売る」という行動において価値を生み出すものですから、企業の語る「わたしたちはこう考えます」なんて、それが商品やサービスとして表出されていない限り、意味ないわけですよね。
歴史的に見れば、サービスや商品のスペックで差別化することが困難となり、多くの企業が代理店の「コミュニケーション技術」に差別化・価値化を預けっぱなしにしたことで、いまの体たらくとなったわけですが、そうした時代もひとめぐりしてコミュニケーションの技術で差別化できる時代はとっくに終わってしまっているんですね。先のレポートは、日本企業に限らず、世界中の企業が、この間、いかに人まかせのクリシェをもってビジネスしてきたかを、わかりやすく示しています。
──先に紹介した日本企業のように、自力でことばを回復できた企業が、この先勝っていく企業になっていくということなんでしょうね。
日本の組織におけることばの貧しさは、お話にならないレベルの酷さだと思います。それは、ことばを外に丸投げしてきたことの当然の帰結ですが、それがもたしたさらに根源的な問題は、それが自分のことばではないので、誰も、そのことばを支えるべく行動をしないことです。つまり、このやり方をしている限り、どこにも「やましさ」や「後ろめたさ」が発生しないんですね。
──やましさ?
自分で言っちゃったら「言った以上やらないとな」となるじゃないですか。
──まあ、そうですね。
でも、やらないんですよ。
──自分のことばじゃないから。
お金を払えば、そのやましさを自分の負債とせずに、人に売り渡すことができるわけですね。まったくもって便利な世の中をつくったもんです。
若林恵(わかばやし・けい) 1971年生まれ。『WIRED』日本版編集長(2012〜17年)を務めたのち、2018年、黒鳥社設立。いよいよ発売! 本連載の書籍化第2弾『はりぼて王国年代記』のお求めは全国書店のほか、Amazonでも。
👇 のボタンから、このニュースレターをTwitter、Facebookでシェアできます。ニュースレターの転送もご自由に(転送された方へ! 登録はこちらからどうぞ)。