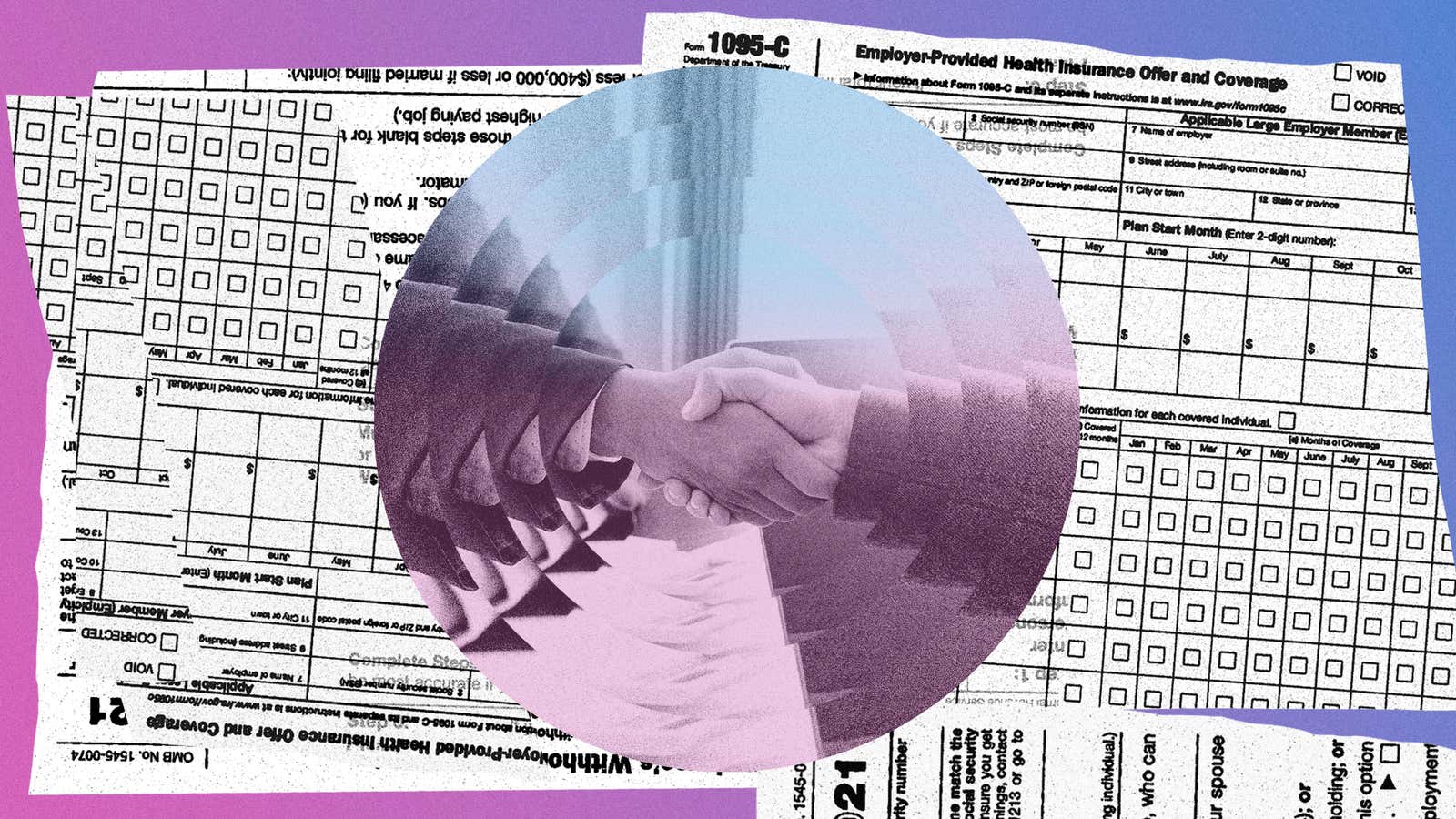Deep Dive: Future of Work
「働く」の未来図
Quartz読者のみなさん、こんにちは。毎週木曜午後のニュースレターでは、「働くこと」のこれからについてのアイデアや出来事をお届けしています。
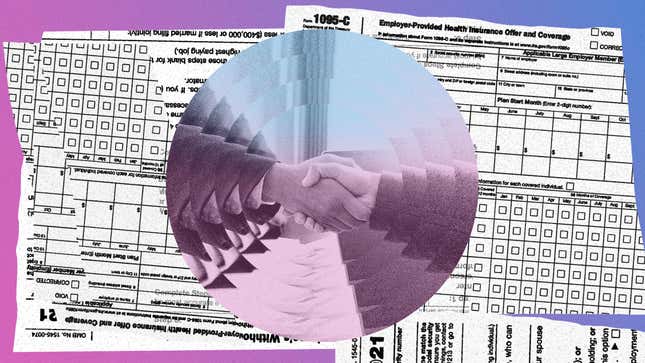
30代で独身のサイラ・ラーマンには、新しい仕事を探すにあたって明確な優先順位がありました。給料をいくらもらえるかというポイントはもちろんですが、金銭以外の──家族をもてるような条件を求めていたのです。
彼女が確認したかったのは、十分な育児休暇と自己免疫疾患の治療に必要な健康保険が完備されていることでした。
サイラは、コロラド州デンバーにあるアルパイン銀行でアシスタント・バイスプレジデントとして働いていました。退職の2週間前に辞表を提出したときには、いくつかの企業の採用面接を受けており、うち1社からはオファーを受けていました。彼女は、数週間かけて自分の選択を考えようと思っていました。
しかし、彼女は忘れていたのです。医療と雇用とが結びついているこの国では、パンデミックの最中でも、“空白期間”によって保険が適用されなくなることを。
このことに気づいたとき、彼女はパニックに陥りました。「わたしの頭の中にあったのは、『もしコロナに感染したらどうしよう』ということだけでした」
彼女が受けていたオファーはフィンテック企業のHMBradleyからのもので、条件も悪くないものでした。HMBradleyの役員たちは、入社日以前に健康保険料を支払うことを申し出てくれました。同社は12週間の育児休暇を約束しており、さらにラーマンは卵子凍結を全社員の福利厚生に加えることを求めました。HMBradleyはそれを了承しました。
彼女はそれが高額だと理解していますが、その要求は自分のためだけでなく、ほかの従業員のためにもという義務感からのものだったと言います。「(ジェンダーについての)“フィフティ・フィフティ”のカルチャーを育みたいのであれば、他の女性を擁護したいと考える女性経営者が権力のある立場にいなければならないと思います」と、彼女は語っています。
Hidden benefits
隠れたメリット
ラーマンとHMBradleyのケースは幸せな一例ですが、この話からは、企業の福利厚生がいかに不透明であるか、そして求職者にとって情報を得ることがいかに厄介な作業であるかがわかります。ラーマンをはじめ多くの労働者が競合他社がどのような福利厚生を提供しているかを知るには、実際に面接するか、あるいは裏ルートを使うほかありません(福利厚生の詳細は、公開されている企業ウェブサイトではほとんど知ることはできません)。求職者が企業間の選択肢を比較することは困難なのです。
パンデミックの影響で、米国では企業の労務管理がクローズアップされることになりました。働き手の多くが、子どもが体操をしているのを横目に、病気休暇や家族休暇、保険の加入状況などを調べながらビデオ会議に出席しています。多くの企業が、従業員が病気になった場合やその家族が病気になった場合、あるいは子どもの学校やキャンプの予定がキャンセルになった場合の方針をあらたに追加・拡大しています。いま労働市場の引き締めの兆しが強まっていますが、こうした傾向はより重要な意味をもつようになっています。
米国の雇用者は、優秀な人材を惹きつけ、維持するためのツールとして福利厚生を利用してきました。労働統計局によると、民間企業の場合、福利厚生は平均的な従業員の報酬の30%を占めています。米国で最も“高給取り”な産業のひとつである金融サービス業は、提供される福利厚生の質において他のあらゆる産業をリードしていますが、ほとんどの企業がそれら福利厚生を公に説明することに対して慎重な姿勢をとっています。
かくも不透明であるがゆえに、企業は自由に、働き手によってより条件のよい待遇を与えられます。それは言い換えれば、働き手一人ひとりが個人的なリスクを負い、より多くを求めなければならないということでもあります。
HMBradleyの場合は? CEO兼共同創業者のザック・ブランクは次のように説明してくれました。「わたしたちは入社希望者や働き手と対話することで、彼らの生活をよりよく、より楽にするには何が必要かを知りたいと思っている」。パンデミックに備えて仕事の合間に保険をかけておくことは「あたりまえのこと」で、「働き手を大切にしてこそ、彼らは企業を大切に思ってくれるという考えを強く信じている」
とはいえHMBradleyのような姿勢をとる企業は例外で、Quartzが米国で最も影響力のある大手資産運用会社、銀行、業界団体、会計事務所など101社を対象に従業員の福利厚生に関する情報提供を求めたところ、うち32社が福利厚生制度を提供していませんでした。
企業が自社の方針を開示したがらないことに、ニューヨークのMcDermott Will & Emery LLPで企業の福利厚生パッケージのコンサルティングを行っているスティーヴン・エクハウスは驚きを隠しません。
「自分たちがよい福利厚生を提供しているのであれば、喜んで開示するものだ。企業が情報を開示しない場合、それは注意すべきサインかもしれない」
エクハウスによると、ヘッジファンドやウォールストリートの金融家の場合、報酬総額に占める福利厚生の割合は少なく、特に高位の役職に就いている人は福利厚生をさほど気にしていないのだといいます。「彼らが気にしているのは、7桁のボーナスをもらえるかどうかだ」
しかし、金融サービス食物連鎖の下層部において、福利厚生はむしろ大いに重要です。労働者団体Committee for Better Banksのメンバーであるレイナ・アブラハムソンは、3年ほど前にオレゴン州のウェルズ・ファーゴのコールセンターで働き始めました。採用時に福利厚生について訊ねたものの、詳細はほとんど知らされなかったと言う彼女は、いまとなってはもっと知っておきたかったと語ります。「だって最高のものが提供されているとはいえないから」
トランスジェンダーであるエイブラハムソンは、2020年4月にホルモン療法を開始し、現在、性別適合手術を受けるかどうかを検討しています。彼女の保険では費用の80%がカバーされますが、彼女の予想ではその手術費は5万ドルにも上り、手元には4,000ドルの請求書が残ることになります。
エイブラハムソンの時給は17.67ドル。彼女は言います。「(保険で)かなりの額が支払われるとはいえ、いまの給料ではとても賄えない」「費用次第で、手術を受けるか受けないかが決まってしまう」
Investors also care about…
投資家もみている
一方で環境・社会・ガバナンスに配慮した投資を推進している金融機関が、他方では福利厚生に関する情報を開示しない。それは矛盾していると言わざるをえません。データプロバイダー企業のMorningstarによると、ESG戦略への資金投入の気運は高まっており、第2四半期までに「サステナブル」ファンドのアセットは2.3兆ドルにまで増えています。
これは旧来のファンドからすると約5%程度ではありますが、過去最高の水準で、この傾向はさらに高まることが想定されます。「投資家は、企業、特にリーダーに対して、このあらたな枠組みを受け入れ、ステップアップすることを求めています」と、別のデータプロバイダー企業JUST Capitalの投資商品担当ディレクター、ロレイン・ウィルソンは言います。
JUST Capitalの調査によると、労務関連ランキングで高得点を獲得した企業の株式は、株式市場でも高いパフォーマンスを示しています。同社による格付け対象企業890社のうち、4社に1社が自社の育児休暇制度や託児所の福利厚生を詳細に報告しており、それらの企業は2018年までの5年間で2%多くのROE(自己資本利益率)を生み出していることが報告されています。
つまり「従業員に投資する理由」は確かにあって、企業は「その投資をすることで損をしていない」というのが、ウィルソンの説明です。
トロントにあるHoneytree Investment Managementの共同設立者であるリズ・シミーのようなESG投資家にとって、企業が優れた福利厚生を提供するのは「“やったほうがいい”ことだからではなく、雇用と維持、質の高い仕事、労働市場での競争力のため」。そして、それは投資対象としての企業の評価にも反映されているというのです
であればこそ、金融業界は従業員の福利厚生を提供し、その内容について透明性を高めることで、優れたガバナンスと従業員の公平な待遇の重要性と価値を示すことをリードすべきだと、彼女は語っています。
COLUMN: What to watch for
ワクチン義務は適法か

この数週間、米国ではマイクロソフトから軍までが、働き手に対してCOVID-19ワクチンの接種証明書の提示を求める方針を固めています。米国では、成人の約63%が2回のワクチン接種を受けており、大企業の多くは接種を義務化しています。米国では、1905年に天然痘が発生して以来、企業にはワクチン接種を要求する法的根拠があるという点で大方の合意が得られています。
ただし、世界を見渡せばその適法性はより曖昧です。インドネシアやサウジアラビアなどの一部の国では、政府によってほぼ全面的な義務化が進んでいます。しかし、英国では、ワクチン接種の義務化はもちろん、ワクチンの接種状況に関するデータを収集することさえも「法的にも道徳的にも“地雷原”」だとされています。
(翻訳・編集:年吉聡太)