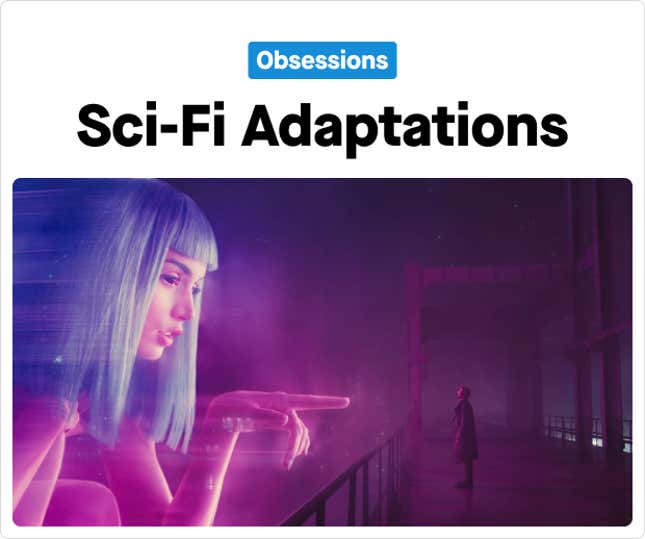
週に一度、夜にお届けする日本版ニュースレター「Obsessions」では、グローバル版の人気シリーズ「Obsessions」の翻訳のほか、力のこもったレポートやインサイトをお送りしていきます。
世のSFファンで、満足している人なんているものでしょうか? 「トレッキー」(「スタートレック」シリーズのファン)にはじまり「ゲーム・オブ・スローナー」(言わずもがなの「ゲーム・オブ・スローンズ」シリーズのファン)に至るまで、SF/ファンタジー大作の一連の作品群を追いかけていったところで、結局のところ、そこにあるのは大きな失望と尽きることない不満でしかありません。
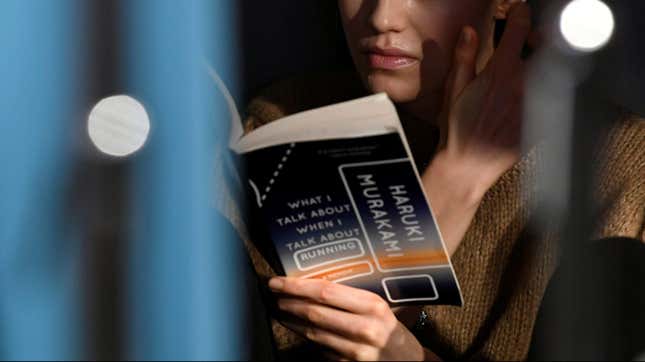
小説にせよグラフィックノベルにせよ、映画化/テレビ化されるとなるとその瞬間には熱い視線が寄せられます。しかし、その脚色には困難がつきまといます。原作に忠実でない、とか、原作者の想像力を具現化させるのに十分な資金がない、とか、あるいは単に異なるメディアでは同じ感動を与えられない、とか……ファンは常に何かしら不満をもっているのです。
いわゆる「翻案」は、そんなにも“悪”なのでしょうか? あるいは、SF/ファンタジーのファンの寄せる期待がそもそも筋違いなのでは? 今日のニュースレターでは、シートベルト着用のうえ、この疑問の答えに向かうロケットの旅に、しばしお付き合いを。
by the digit
数字でみる
- 797:「スタートレック」の全エピソード数。37シーズンも続いた
- 3,000万部:ジョージ・オーウェルの『1984』が1949年に出版されて以来、販売された推定部数
- 100%:2010〜2018年のSF書籍の売上高増加率
- 30万部:中国の月刊定期刊行物『Science Fiction World』の発行部数
- 17時間:映画『アベンジャーズ/エンドゲーム』が興行収入1億ドルを達成するまでにかかった時間。
What makes a great adaptation
「いい映画化」の条件
「最高の映画化」とは「原作をそのまま再現しようとしないこと」に尽きるのかも知れません。それはつまり、原作のエッセンス(主要なプロット、テーマ的要素、ストーリーテリングのアプローチなど)は残したうえで、それら主要な要素を用いて、独自のストーリーと世界を形成する、ということです。
そもそも、映画化それ自体が、すべてのファンを満足させることなどできるはずはありません。そして、それでいいのです。
もっとも、Netflixをはじめとするストリーミングサービスが「エサを必要とするコンテンツモンスター」であり続ける限り、SFの映画化が「だれかの作品の焼き直し」以上のものになる可能性は高まってもいます。
米ケーブルチャンネルのSyfyで放映され、現在はアマゾンが管理している「エクスパンス(The Expanse)」は、批評家からの絶賛と大衆の人気のどちらも得ている好例です。原作に忠実でありながら、その枠を超えるプロットをもった「エクスパンス」が証明するのは、従来の映画化の限界が変わりつつある、ということでしょう。監督をはじめとする制作者は、従来の「30分枠」などのフレームにとらわれず、世界観の構築に全力を注ぐことができるようになったのです。
ジャーナリストでSF作家のアンドリュー・リプタクは、SF専門のニュースレター「Transfer Orbit」において、視聴者は長い目で見ている、と指摘しています。いま、制作者たちの前には、古い世界を生き返らせ、あるいはまったく新しいものをつくる機会が待っているといえるでしょう。
quotable
けだし名言
脚本家以外の作家に、映画における責任を負わせたりしないで。原作本の著者に「どうしてこうなった」なんて聞かないでほしい。だってその人も不思議に思っているのだから。(アーシュラ・K・ル=グウィン、2006年、個人ブログより)
A message for the masses
なにを伝えるのか
数多あるSF作品のなかでも、高い評価を受け、文化的な影響力をもち、広く読まれている作品には、今日の社会経済的な問題が明日どのように解決されるかを想像しているものが多くあります。ウィリアム・ギブソンは『ニューロマンサー』で商業化(commodification)に疑問を投げかけ、マーガレット・アトウッドは『侍女の物語』で家父長制にメスを入れ、アン・レッキーは『叛逆航路(Ancillary Justice)』で誰かを人間以下と考えることの意味を問いかけています。
これらの小説について、SF作家のアーシュラ・K・ル=グィンは「曖昧なユートピア(an ambiguous utopia)」と表現しています。読者がジェンダーや階級、人種の影響に直面して何ができるのかを考えようとするとき、現代の考え方に縛られることのない場所をつくり出すことができるのです。未来を描くということは、「物事がどうあるべきかという願望」を抱くことである、とも言えるでしょう。
これを「映画化」に当てはめるのは、いささか酷なのかもしれません。映画は本ではないし、本だからできることを期待してはいけません。映画は確かに力強いメッセージを伝えられるメディアですが、過激な異世界を大きなスクリーンで実現するには、それなりの労力(そしてお金)が必要です。映画を製作する側からすると、その投資に対する見返りが必要になります。たしかに観客の数だけみれば本よりも映画の方が多いのですが、観客は映画を「楽しむ」ためにやってくるのであって、必ずしも「よりよい未来を想像する」必要はありません……。
Case study: Dune
『デューン』の場合

1984年に公開された映画『デューン』は、SF作家フランク・ハーバートの傑作を実現するために13年の月日が費やされた試みの集大成でした。しかし、同作は興行収入3,100万ドルという結果に終わり、その後、監督を務めたデヴィッド・リンチは、自身に最終決定権はなかったと回想しています。もっともリンチ版『デューン』は、彼独特の徹底したキャンピーな演出もあってカルト的な地位を獲得しています(スティングも出演していますし)。
さて、2021年のドゥニ・ヴィルヌーヴ監督による映画化は、『デューン』を正当に解釈できたのでしょうか? このジャンルにおける名作として、作品の地位を回復できたのでしょうか? アカデミー賞10部門にノミネートされ(6部門を受賞)、公開月には約400万世帯が視聴したという実績をみれば、作品性と大衆の人気の両方において成功している、と言えそうではあります。
DEPARTMENT OF JARGON
用語解説
2021年のヴィルヌーヴ版『デューン』については、さまざまな評価ができるでしょう。「撮影における見事な勝利」だとか、「ゼンデイヤの出番はもっとあったはずなのに」だとか……。ただ、ひとつ明らかなのは、それは「続編」ではない、ということです。
ここでは2つの用語、「続編(sequel)」と「リブート(reboot)」を定義してみましょう。
- 🤖 続編:『ブレードランナー2049』のように、既存のキャラクターの物語を追い、プロットを拡張するもの。
- 🐍 リブート:同じストーリーを同じフォーマットで再演すること。2021年版の『デューン』は1984年版のリブートでした。2023年には『Dune: Part 2』が公開されますが、これは2021年の映画の続編としてカウントされます。
More ways than one
「映画化」だけじゃない
SFは映画化されるだけではありません。バレエやコミック、ラジオドラマなど、さまざまな方法が試されています。1985年、アメリカのSF作家アーシュラ・K・ル=グウィンは『Always Coming Home』という作品を発表していますが、これはル=グウィンと作曲家トッド・バートンが、小説の世界を音で表現した共同制作のアルバムです。
今日のニュースレターはJordan Weinstockがお届けしました。日本版は年吉聡太が担当しています。
one 🚀 thing
ちなみに……
SF作品の映画化は、今日の映画界において、興行収入の大部分を占めています。同時に、映画界最大の失敗作にも。原作から100年を経た2012年に公開された『ジョン・カーター』は、1億2,900万ドル(インフレ調整後:2億2,500万ドル)の損失を出し、歴代最大の興行損失となりました。
🎧 Quartz Japanでは平日毎朝のニュースレター「Daily Brief」のトップニュースを声でお届けするPodcastも配信しています。
👀 Twitter、Facebookでも最新ニュースをお届け。
👇 このニュースレターはTwitter、Facebookでシェアできます。転送も、どうぞご自由に(転送された方へ! 登録はこちらから)。
