[qz-japan-author usernames=”abhattacharyaqz”]
India Explosion
爆発するインディア
Quartz読者のみなさん、こんにちは。毎週金曜日の夕方は、次なる巨大市場「インド」の今と、注目のニュースを伝えていきます。英語版(参考)はこちら。
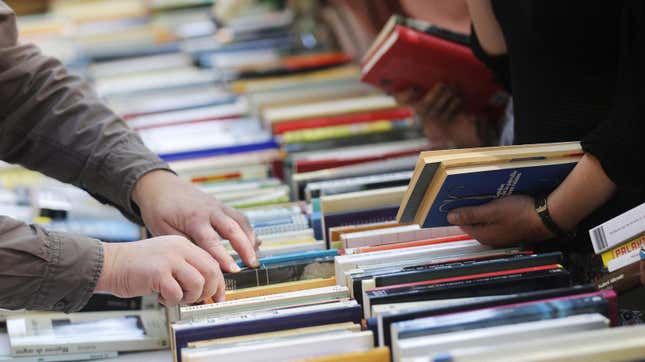
児童文学作家のドクター・スース曰く、学びへの入り口は読書だ。彼は1978年に、「読むほどに、より多くのことを知れる。学ぶほどに、多くの場所へ誘ってくれる」と記した。
インドのスタートアップ界隈の人々は、2019年何を読んだのか── Quartzが彼らに尋ねたところ、人生、マネジメント、また経済など、幅広い分野からお勧めの一冊が挙げられた。
Trillion-Dollar Coach: The Leadership Handbook of Silicon Valley’s Bill Campbell
邦題:『1兆ドルコーチ シリコンバレーのレジェンド ビル・キャンベルの成功の教え』
著者:エリック・シュミット、ジョナサン・ローゼンバーグ、アラン・イーグル
伝説のコーチである故ビル・キャンベルのコーチング手法を、Googleの元CEOらが解説した一冊。私はファウンダーとして、常により良い目的志向型の企業を構築しようとしています。「マネジメントの達人」とされる人たちが書いた指南書は山ほどありますが、これは実在する創業者を導いたコーチングを解説したリアルなストーリーです。

読みやすく、手本にしやすい。本書で得られたのは思考の大きな変化。つまり、自分自身を「勝てる組織を導くコーチ」として認識することです。事業を創る喜びを共有する空気を作りたいファウンダーは必読です。 ──Farooq Adam:ファッションeコマースサイト「Fynd」共同設立者
21 Lessons for the 21st Century
邦題:邦題『21 Lessons: 21世紀の人類のための21の思考』
著者:ユヴァル・ノア・ハラリ
Homo Sapiens(邦題『サピエンス全史』)とHomo Deus(邦題『ホモ・デウス テクノロジーとサピエンスの未来』)の続編で、人類の歴史を振り返った上で21世紀の展望が論じられています。本は、倫理、価値、技術と人間との関係をテーマに掘り下げています。
この本は、現代の社会、経済、政治的問題に焦点を当てながら、私たちの生活へのテクノロジーの影響について、モノを見るレンズを提示しています。ここに書かれた全てに同意するわけではありませんが、著者のユニークな見方を通し、現代に生きる人々の心のフレームを広げさせる大胆且つ挑発的な一冊です。明確な答えはありませんが、多くの疑問を投げかけています。──Rajan Navani:「JetSynthesys」副会長兼マネージングディレクター
AI Superpowers
著者:Google China前社長カイフ・リー
他に読んでいる最中の本があったら中断してでもこっちを読んでいただきたい。最近のディープラーニング技術の進歩は、電気の発見と同じくらい重要なものです。とてもパワーのある発明であり、且つ新しい世界への扉を開くきっかけになる技術です。
この本は、人工知能(AI)がどのように進化するか、さらにどのセクターと仕事が影響を受けるかについての実用的な見解を示しています。

AIが引き起こす混乱は、社会を変革を媒介する可能性があり、AIと人間の思いやりの心が組み合わさることで愛のある社会が創造されるという未来を著者は思い描いています。彼は、AI実装の国際競争でアメリカを追い抜くと目される中国の絶対的な存在感について説得力のある考察を展開しています。今後20年は働きたい人は必読。彼らが進むべき方向を理解し、選択することです。 ──Sandeep Murthy:「Lightbox VC」パートナー
Everything is F*cked—A Book About Hope
著者:マーク・マンソン
この本はとても美しく書かれています。皮肉とユーモアは筆者の強みです。これを読めば、自分自身に正直、誠実にならずにはいられない気持ちになるはずです。 ──Arpita Ganesh:ランジェリーブランド「Buttercups」CEO兼ファウンダー
The Hard Thing About Hard Things
邦題:『HARD THINGS』
著者:ベン・ホロヴィッツ
タイトルの通り、この本はビジネスでうまくいかない可能性のあるすべてのこと、そして強い気持ちでアクションを起こすことの必要性を筆者は語っています。

会社の寿命を確保するために、スタートアップが積極的に導入しなければならないことを網羅して提示しています。中でも私が印象に残っているのは、カスタマーサービスを向上させるために、自分自身とチームに「していないことは何か」を問うことです。 ──Chirag Jain:「Ashika Capital」CEO
Will My Cat Eat My Eyeballs?
著者:ケイトリン・ドーティ
私が読んだ(正確にはAudibleで聴いた)中で一番面白かった本です。著者は葬儀業界で働いた経験から「愛と死」を哲学したSmoke Gets in your Eyes(邦題『煙が目にしみる 火葬場が教えてくれたこと』)で知られており、今回の作品でも科学的事実と歴史を巧みに組み合わせて、長年、信念をもち執筆に取り組んできました。
私たちの祖先の代から、迷信や概念が浸透することで、私たちはトラブルから逃れることができました。たとえば、はしごの下を歩くとアクシデントに見舞われるから、そもそもそういう場所を歩かないとか。でも私たちはこういった一見、非論理的な推測には疑問を持つべきです。
なぜ会社はユニコーンである必要があるのか、なぜコストをかけずにビジネスを拡大することが重要であるのか?…私は今、こんな疑問に答えるエッセイを心待ちにしています。 ──Upmanyu Misra:「Cianna Capital」CEO兼共同設立者
Poor Economics
邦題:『貧乏人の経済学』
著者:アビジット・V・バナジー、エスター・デュフロ
私はノーベルが発表される前にこの本を読み、バランスが取れていることを発見しました。都市の消費者経済以外の「経済」を理解しようとする人にとっては素晴らしい読み物です。

貧困のさまざまな側面に対し、実現可能な解決策を分析するためにとられた科学的アプローチは、非常に興味をそそられます。特に、貧困トラップという文脈での持続可能な開発に焦点を当てることは、私やビジネスのような起業家にとって、長期的な思考に役立ちます。 ABテストで見られた因果関係は、文化的および社会的な人間の行動の側面と、他の多くの複雑な根本的現象を説明するのに有用でしょう。
この本は一般的にグローバルな観点から誤解されている複数のタッチポイントについても掘り下げています。たとえば、教育では、学校教育は学習と平等化されるべきではなく、教育を1年追加するごとに収入が大幅にアップするというデータ駆動型の解説に興味をそそられました。インドのほか、開発・発展の課題に直面するにとって大きな関連性があり、応用できる部分があると思います。 ──Ditainam Goel:「AttainU」CEO兼共同設立者
An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations
邦題:『国富論』
著者:アダム・スミス
これまで私は、たくさんの歴史や経済などの本を読んできましたが、これは多くの事象に通ずる古典です。
『国富論』の一部は理解するのに骨の折れる内容ですが、意外にもそこまで難しくはありません。この本を読んでいる間、数世紀前に書かれたものだということを忘れそうになります。すべてが、急速に変化する今の世界の状況にも、かなりフィットし関連があるように思います。仕事と賃金、貿易と政治、さらには倫理など多くのトピックをカバーしたこの本を読むだけで、まるで学位を取得するかのようです。 ──Akash Gehani:「Instamojo」COO兼共同設立者
This week’s top stories
インド注目ニュース5選
- アマゾンAWSがインドのドローン業界と提携。インドのドローンの業界団体インドドローン連盟(DFI)は、国内のドローンエコシステムの開発促進のため、Amazon Web Services(AWS)を優先クラウドにすることを発表した。地場ドローンメーカー、アプリ開発などの企業と協力して、インドでのドローン本格運用への期間を短縮したい考え。
- 魚粉、魚油産業で海洋資源が根絶やしに。インドでは、食用ではないいわゆる「雑魚」を世界の水産養殖市場に飼料として供給する魚粉・魚油(FMFO)産業は、寛容に受け止められていたが、状況が変わりそうだ。手当たり次第に海洋資源が漁獲されたことで、魚種の絶滅、海洋生態系の崩壊につながっていると指摘された。
- UPI決済が爆増。統合決済インターフェース(UPI)を活用したオンライン決済取扱高が、2019年12月に前年同期比100%増の2兆ルピーを突破。2016年にUPIが開始されて以来の最高額を記録した。
- 国営航空エア・インディア売却がついに…。2017年に民営化の方針が決まりながら、買い手が付かずに頓挫した計画がやっと動き出す。インド政府は月内に意向表明書(EOI)の募集に取り掛かる予定。ちなみに前回は応札者から1件もEOIは提出されなかった。
- デモ隊襲撃で市民の怒り加速。首都ニューデリーにあるジャワハルラルネルー大学(JNU)で5日、イスラム教徒を差別していると批判されている改正国籍法(CAA)に反対するデモの最中に謎の暴漢たちが学生たちを襲う事件が発生した際、居合わせた警官たちは暴漢の侵入を黙認したとされ、与党の関与も疑われる。しかし学生によるデモの勢いは止まない。米コロンビア大、英オックスフォード大の学生らも連帯を表明するまでに。
【今週の特集】

今週のQuartz(英語版)の特集は「The birth of geriatric cool(クールな高齢化の誕生)」です。日本だけでなく、多くの先進国で高齢化が大きな課題となる中、いかに老年をミレニアルズのような躍動ある産業として捉えるのか、大きな変化の兆しをQuartzがレポートしていきます。
(翻訳・編集:鳥山愛恵、写真:SINOVATION VENTURES、ロイター)