A Guide to Guides
Guidesのガイド
Quartz読者のみなさん、こんにちは。週末は米国版Quartzの特集〈Guides〉から、毎回1つをピックアップ。世界がいま注目する論点を、編集者・若林恵さんとともに読み解きましょう。

──先週「メンタルヘルス」をお題にお話したところでして、若林さん、かなり強い口調で、こうおっしゃっていたわけです。
木村花さんの事件にかかわらず芸能人が社会的な事件として取り上げられたときに、自分がいつも思うのは「いったいマネジメントはなにをしてたんだ?」ということでして、コミュニケーションが基本一方通行である従来のマスメディアに関わるときのやり方では、双方向メディアであるインターネットやソーシャルメディアによってかたちづくられた環境は御しきれないということは、随分前からわかっていたことでもあるはずなのですが、有名人のマネジメントを管轄するはずの組織が、自分たちのメシの種であるはずのタレントやアーティストを防御するための手立てを、システマティックに講じているのかどうかは非常に疑問に思う
はい。
──加えて、こうもおっしゃっていました。
いくら加害者を排除し、罰することができたとしても、彼女の場合のように、その前に被害者当人が自殺してしまっては元も子もない
ええ。
──そのちょうど1週間後の今日(7/18)、三浦春馬さんという俳優さんが自殺されたことが報じられたわけで、ここで提起された問題が、そのまま露呈してしまったという感じで、改めて怒りとともに非常に強いやり切れなさを覚えました。
わたしも同様です。わたしは三浦さんの活動についてはまったく存じ上げてはいませんが、それでも、それなりに実りのあるキャリアを積まれている方だという認識はうっすらとありましたから、より衝撃がありました。また、三浦さんほどの著名人ともなれば、それなりの事務所に所属していらっしゃるはずですが、マネジメントがみすみす、このようなかたちでスターを失うのであれば、その人道的・社会的な責任はもとより、経営責任、ビジネス上の責任もまた非常に重いと思います。
アーティストの自殺は、それを資本としてメシを食べている人たちすべての責任であるはずですが、責任主体である企業のみならず、業界からも、こうした事態に対するコミットメントの表明が、まったく行われていないように見えることに、個人的には非常に大きな憤りを覚えます(編集部註:三浦春馬さんのスタッフによる公式Twitterアカウントは自殺のニュース以後、記事配信時点でも完全に沈黙)。
──結局のところ、アーティストが矢面に立って、世間の愚かさと対峙し、その背後で企業がそうした軋轢を「バズ」の名のもと商売にし、換金しているという構図です。
おっしゃる通りです。加えて、その責任は、あくまでも個人としての被害者と、個人としての加害者の自己責任の範疇で戦え、という格好になっていて、さらに言えば、それを周りで見ている野次馬も、そうした構図をある意味受け入れちゃってるんですね。なので、加害者をなんとかしろ、プラットフォームをなんとかしろ、という法規制の話ばかりで、それしか実効的な手立てがないとみなが信じ切っているのは、それ自体がいかにほとんどの人がこれを“自己責任”の範疇で理解しているかを表しているように思います。
──その事態のほうが、よほどヤバい気がしますね。
そうなんです。もちろん、この間起きた自殺や、いわゆる“誹謗中傷”の問題は、ソーシャルメディアの問題ではあるわけですが、といって、ソーシャルメディアがこの世に登場して、もうとっくに10年以上経っているわけですし、特段新しい事態でもなんでもないわけですね。むしろ問題は、例えば芸能や音楽、TV、映画といった関係業界が、すでにソーシャルメディアがデフォルトの環境になっているにもかかわらず、それに適応するかたちで、自分たちの組織やビジネスモデル、ビジネス上の価値定義を再定義し、再編成することを怠ってきたことで、ビジネスセクターのもたつきと世間の進行速度のズレとの間で、そのインターフェイスになっている“個人”、つまりアーティストや、俳優さん、タレントといった人たちが、すりつぶされて行っているということなんだと思うんです。
で、やはり腹立たしいのは、結局のところ“業界”の人たちはお給料もらって安閑としていても別にさして困らないというところで、そうした非対称性がおそらく事態を悪くしているようにしかみえないんですよね。
──いやな話ですね。
例えばですが、法規制の話の手前で、各業界がやれることは実際いくらでもあるわけです。まず現状認識の話から言いますと、これは弊社でつくった簡単な資料を元にしていますが、スウェーデンのデジタルディストリビューション会社Record Unionによる調査(2019)、国際プロサッカー選手会(FIFPro)による調査(2017)、ジョンズ・ホプキンス大学による調査(2019)によると、アメリカの一般成人でうつ病を経験したことがあると回答した人は26%であるのに対して、プロのサッカー選手は38%、インディペンデントのミュージシャンに関しては73%が、うつ病や不安障害などに苦しんだ経験があると回答しているといいます。
──なるほど。73%ってすごいですね。
つまり、ソーシャルメディア云々以前の話として、社会的なスポットライトのあたる著名人にとって、メンタルヘルスが深刻な問題となっていることは明らかなんです。
──ほんとですね。
という問題意識のなかで、音楽イベント最大手のLive Nationは、24 時間365 日、ツアー関係者がセラピストとオンラインでコンタクトを取ることができるプラットフォーム「Tour Support」を支援したり、ヘヴィメタルバンド・ゴッドスマックのボーカルが、アーティストへの啓蒙活動やメンタルヘルスの社会的認知を上げる活動を行う非営利団体THE SCARS FOUNDATIONを立ち上げたり、音楽フェスティバルやイベントを通じて、メンタルヘルスの認知の向上、 コミュニティビルディングを目指すSound Mindという非営利団体ができていたりします。またプロバスケリーグのNBAには、「メンタルヘルス・ディレクター」という役職が置かれてもいます。

──なるほど。業界全体として取り組んで行く姿勢が感じられますね。
そうなんです。メンタルヘルスの問題は、前回もお話した通り、公衆衛生、社会厚生上の問題であるのみならず、ビジネスのサステイナビリティにまで関わる危機なんです。という認識が、おそらく日本の企業には圧倒的に欠如しているように思います。
──そうですか。
経済空間は、新自由主義の聖域であって、そこは適者生存、弱肉強食の原理がむき出しの格好で、存在していいのである、と、なぜか日本のビジネス空間は、アメリカ以上に信じてしまっているところがありまして、これはすでに前に書いたことがあるかもしれませんが、自己啓発に基づく自己責任論を、最初に日本で提出したのは経団連だといわれていまして、それが、経営の合理化による非正規雇用の増大といった施策とセットで持ち出されるわけです。
そして、“財界”の言わば言いなりになる格好で、ワーカーも自己責任という理屈をどんどん内面化していくというのが、おそらく90年代から進行してきた事態だと思うのですが、それが極めて深刻なのは、例えば会社からドロップアウトさせられたとしても、そうした極めて新自由主義的なロジックを内面化してしまっているワーカーたちは、それを自分の“弱さ”のせいであると感じて、“自分の問題”として受け止めてしまうというところなんです。
──木村花さんの「遺書」にも、「ごめんね」のことばがありましたね。
そのメッセージが痛切なのは、「強い者以外は、この世に存在してはいけない」ということが自明のこととしてコンテキストとしてもっているからですよね。
How to build an anti-racist company
「反人種差別」の訓練

──今回の〈Guides〉は、〈アンチレイシスト企業のつくり方〉というお題で、ちょっとこれは日本の読者のみなさんには遠い話かな、とも思ったのですが、いまお話いただいたこととは、ものすごくシンクロする話ですね。
だと思います。この特集は、主に、ブラック・ライヴス・マター運動(BLM)を受けて、企業が「アンチレイシスト」、つまり「反人種差別」を標榜しなくてはならなくなっている状況のなかで、どうすれば企業がよりダイバースでインクルーシブなものとなれるのかを考察したもので、おっしゃる通り、日本の企業は言っても、アメリカほどには人種的多様性がないので一見無関係な話のように見えますが、これをもう少し俯瞰したところから、「ビジネスの社会的責任」という視点で捉えると、アメリカ企業における人種問題と、日本企業におけるさまざまな不平等は、まったくもってパラレルな関係にあると言えると思います。
──話の流れでいきますと、まず一番大きな争点は「女性」といったあたりでしょうか。
もちろんそれも大きな問題ですが、そこに無理にフォーカスしなくてもいいかと思います。例えば〈How to have more productive conversations about race in the workplace〉という記事に、以下のような事例が出てきますが、これを読むと、読まれた方は「ああ、うちの会社でもあるわー」となるのではないでしょうか。
Daily Beastの記事によると、最近行われた米国コンデナスト社の全社員ミーティングでCEOのロジャー・リンチは全社員に向けて、多様性やインクルージョンに関わる懸念についてもっと声を上げるべきだと促し「社内のチャンネルをみながもっと使って、問題についてもっと早く声を上げてくれていたら、われわれももっと早くに対処できたはずだ」と語ったという。前回行われたミーティングでも、人種差別、給与の不均衡、役員クラスにおける人種的多様性の欠如などを指摘した社員には、CEOのこのことばはまったく刺さらなかった。

──“あるある”ですね。
おそらく、これはどこにでもある話なんだろうと思います。上にいる人は「もっと声を上げてくれ」というわけですが、いざ声を上げても、その肝心の“上の人”がそもそも聞く耳をもっていなかったら声をあげる意味もないですし、声をあげることでなんらかの報復にあったり嫌がらせを受けたりすることが想像される環境であれば、“声を上げる”ことは決して簡単ではないはずです。そこに目を向けずに、「声を上げろ」「聞く耳はある」といくら言っても、声は上がってきません。そして、結果として、そのことをもって「うちには問題がない」となってしまうわけですね。
──それはまさに、有色人種が警察を呼ぶと、かえって自分が捕まってしまうので、警察を呼ばないようになって、有色人種が被害に遭った事件がないことになってしまうのと似ていますね。
こうしたことはよくあるんだと思います。やや事象を矮小化するキライはありますが、私はこれを「混浴温泉問題」と言っていまして、それはどういうことかと言いますと、「うちは混浴温泉です」って言ってはいるんだけれども、実際のところおっさんがずっとトグロを巻いているから女性は非常に入りにくい。結果、“混浴”は名ばかりで、実態としては“男湯”になっているのだけれども、運営する側は女性の出入りを禁止しているわけではないので“混浴”を実施していると言えてしまうし、なんなら、そこに入っていかない女性は“自ら選択的”に入らないだけなので、それは女性の側の問題だと言えてしまったりもする、というそういう構図ですね。
──わかりやすいです。
〈Why diversity initiatives fail〉という記事を見ますと、職場における人種平等をめぐってどういう法整備が過去に行われてきたが年譜としてまとめられています。それは1964年のジョンソン政権下での「Civil Rights Act」の法制化にはじまり、さまざまな裁判などを通して、職場におけるダイバーシティと不平等の是正は、名目上は進んできているわけです。
この記事の冒頭には、2020年6月の調査によれば、アメリカの3分の2以上の企業が公式に「ダイバーシティとインクルージョン」をめぐるポリシーを設けており、S&P500インデックス企業のうち半数近くが「チーフ・ダイバーシティ・オフィサー」を置いているとも書いています。
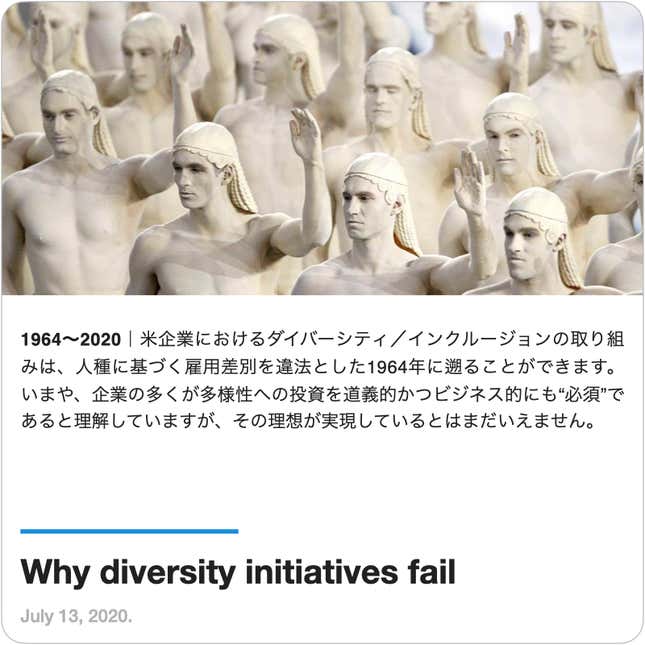
──”制度上”はずっと改善されている、ということですね。
そうなんです。ところが、BLM運動を通して浮き彫りになったのは、制度的には解決しても、実態としてはまったく解決していないということなわけですよね。たしか、以前どこかの日本企業で女性のための相談窓口をつくろうとした女性幹部が突然解雇されるとか、ある男性社員が育休を取って会社に戻ったら突然転勤を命じられたといったことが話題になったときに、会社側の対応で共通するのは、基本的に「法的には問題ない」という一点張りだったところで、これは判で押したように、政治家でもこうしたことは言うわけですが、そもそも問題に対して声を上げた人は“法”を問題にしているわけではなく、もっとウェットな部分で「それは理不尽だ」と感じているわけですし、強いて“法”の問題にするのであれば、「その法はおかしい」と言っているわけですから、議論が噛み合わないというか、議論そのものに非対称性があるんですね。
で、これはいうまでもないことですが、現行の“法”によって信任されて“上”のポジションについた人は、その“法”によってその権力が認められ、守られているわけですから、その法を変えるインセンティブは一切ないわけです。
──暗澹たる気持ちになってきますね。
先の記事の年譜は、それでも果敢に法廷に持ち込む人がいて、その結果裁判で権利の拡張を手にしてきた闘争の歴史でもあるわけですから、法治国家としては、法の内部での手続きに訴えるのはとても大事なことだとは思いますが、とはいえ、巨大企業を相手に従業員が法廷で争うということ自体、非常に大きな非対称性のなかでの争いになりますから、法廷が公正な場なのかといえば、それもすでにしてあやしいところはあるわけですね。
──そうだとすると、社会も企業も、なかなか変わっていかないですよね。
その点で、企業というものは、市場の信任を失うことになれば命脈を絶たれることになりますので、変化をレバレッジするためのターゲットとして狙いやすさはあるのだと思います。実際、BLMを受けて、市民、国民からの猛烈な批判、視線に晒されているのは企業で、それこそFacebookから数百社以上の企業が広告を引き上げたのは、やはり市民の厳しいプレッシャーがあってのことでしょうし、人種的バイアスをめぐる批判に直接晒されている企業は銀行からエンタメまで、あらゆる業界におよびます。
──そうしたなか、ある意味生き残りをかけて、真剣に変革に取り組まなくてはならないと企業は感じ始めているんでしょうかね。
おそらく出てき始めていているんだとは思いますが、とはいえ、これまで語ったように、企業の偽善的な態度に対して「制度だけをアップデートしてもダメだぞ」という圧も非常に強いですから、「今回はちゃんとやれ」というメッセージをもって今回のGuidesも編成されているようにみえます。
──実際、どんな手立てが紹介されているのでしょう。
これは非常にソフトなものですが、例えば、〈The case for using literature to kickstart conversations about race at work〉という記事では、企業内でレイシズムに関する理解をきちんと広めていくために、文学作品を用いて社員教育を行うBooks@Workという組織が紹介されていますが、記事のなかでは、こんなことが書かれています。
これまで企業がやってきたDEI(Diversity, Equity, Inclusion)プログラムは、システミックレイシズムについて語り合うか、必要なスキルやツール、言語を身につけるといったものに終始してきました。それらは単なるお勉強だったのです。一方、物語を用いて行う対話は、それぞれ違った立場にある人たちがデリケートなトピックについて語り合うことを可能にします。

──さっきでてきた話の流れでいえば「声を上げろ」というだけでなく、ちゃんと言いにくいことでも声を上げることのできる環境をつくれということですね。
はい。この記事も非常に面白いのですが、〈Lessons on building an inclusive culture from the writers’ room of HBO’s “Watchmen”〉は、HBOドラマ「ウォッチメン」の脚本チームが、いかにダイバースな人たちの視点を取り入れているかを明かしたものですが、ここでも言われていることは同じで、「女性の視点を入れたいから女性をチームに入れる」「黒人の視点を入れたいから黒人を入れる」だけではまったくダメで、むしろ重要なのは「出されたアイデアを決して否定しない」といったことだと語られています。
あるショーランナーは、たくさんの人がいる前でアイデアを出し、それがいいアイデアか悪いアイデアかを論じられるのは、そこにパーソナルな感情をいかに持ち込むなと言われても難しいもので、自分のアイデアが批評されることで傷つくことは少なくない、と語っています。
──そうでしょうね。
わたしも身に覚えがありますが、例えば雑誌の編集会議でアイデアを出すのは、やはり勇気がいるんですね。自分が面白いと思っていることを、つまらないと言われるのはさすがに凹むわけです。ただ、何が面白くてそうでないのかを客観的に判断していこうという場ですから、いちいち感情的になっていても仕方がない場所でもあるわけで、その辺のさじ加減をどのように差配するのか、というのが難題であるわけですが、前提として、まずはアイデアがたくさんでてこないことには始まらないわけですから、「どんなアイデアでも出していいんだ」と思える環境を、どうやってつくっていくのか、ということが大事だと思います。

──そうですね。
ありきたりといえばありきたりな話なのですが、わたしたちは「人の話に耳を傾ける」ということを実はちゃんと訓練されてきていないように思うんですね。つまり先のコンデナストのCEOのように、チャンネルや場所を用意すればいろんな意見があがって議論が可能になる、とシンプルに思っている人は多いと思いますが、人がしゃべるためには、こちらが相手の言っていることを、相手の関心領域に沿って理解しなくてはいけないわけですが、多くの場合、人は、自分の関心領域に沿って人の話を聞いてしまうんですね。
──ああ、言われてみればそうです。
これは前回でも語った話かとも思いますが、政府だろうが、企業だろうが、あらゆる組織は、自分たちが発信することばかりにリソースやコストを割いていますが、実は“聞く”ということにまったくリソースを割いていませんし、そうであるがゆえに聞く能力がないんです。それは外に対してもそうですし、組織の内側に対しても同様なんですよね。
──たしかに。
たしかジミヘンだったと思うんですが、「知識はしゃべる。智慧は耳を傾ける」ということばを残したらしいんですが、社会全体がひたすら前者に偏っていますが、メンタルヘルスの問題も、今回の組織内におけるシステミックな不平等というものと向き合うときにはほとんど役に立たないということは肝に命じてほしいなと思います。

──習ったことないですもんね、人の「話の聞き方」って。
そうなんです。加えて、そうした聞く力の欠如は、現状の問題の認識を誤らせることにもなります。つまり、さきほどお話したように、数字上は何も問題がないように見えているから問題がないのかといえば逆にそれが水面下に潜ってしまっていることに問題の本質があるわけですから、「本人に聞いて、本人が問題ないと言ってるから問題はない」というのは誤りなんです。
──目に見えなくなっている問題をどう可視化するか、ということですね。
最初に紹介した〈How to have more productive conversations about race in the workplace〉のなかで、「レイシズムの改善を当事者にやらせるな」というティップスが出てきますが、そのアドバイスはまさに、人種の問題について有色人種のワーカーに「どうすればいい?」とか、女性のワーカーに「どうすればいい?」といくら聞いてみたところで、必ずしも改善につながらないのは、上記のような問題にぶつかるからですよね。
──ふむ。どこから始めるのがいいんですかね。
それについては、2つの記事が同じことを語っています。先に挙げた〈Why diversity initiatives fail〉と〈Is your business model anti-racist?〉ですが、こちらで言われているのは、過去の施策に何が問題だったかをきちんと理解しろ、ということなんです。
──ほお。
というのも、企業でも、政府でも、すでにさまざまな施策を打っているわけですよね。にもかかわらず、状況が改善してないのであれば、前の施策に問題があったということで、その評価をせずに、さもいま気づいたことみたいなフリしてスクラッチからやっても、基本同じことの繰り返しなわけです。制度化すればいいわけではなく、制度の運用がうまく行ってないわけですよね。そこにおそらくなんらかのトリックがあるわけですから、それを無視して、ただ制度を書き換えても意味がないんだと思うんです。
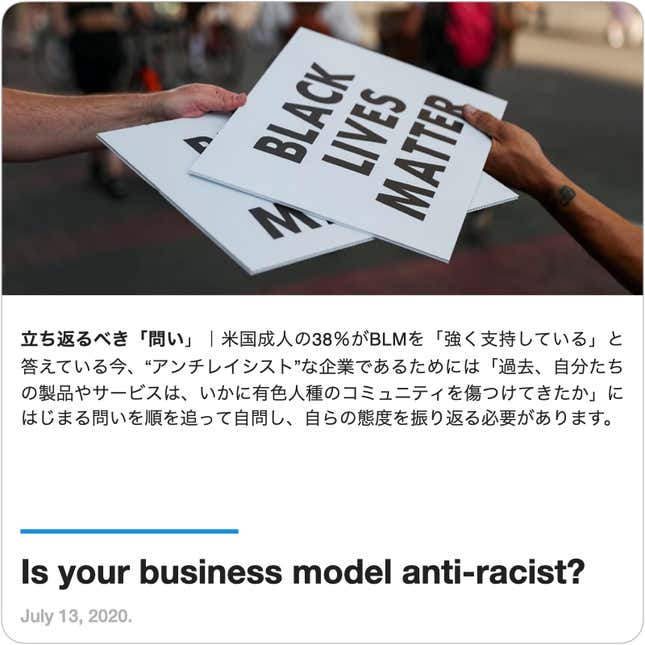
──たしかに。
失敗した施策の背後には、おそらく埋もれている声がたくさんあるはずで、それをまずは取り出さないことには意味がないじゃないですか。
──ほんとですね。冒頭の俳優さんの自殺の話に戻りますと、おそらくですが、ごくごく初歩的な問題として、いったいどの程度の人たちが、どのような労苦のなかに置かれているのか、数値もなければ、なんのインサイトもないわけですよね。そんな状態のなかで、制度を変えろ、という話をしても、じゃあ、どう変えるのか、それを変えることで誰をどういうふうに救えるのかということにもなりますね。
そうなんです。ソリューションの構想には、それなりに精緻な課題の特定が必要なはずですが、特に日本では、きちんとしたリサーチを見ることは本当に稀です。なので、ほとんど空想でしかないような「ソリューション」が幅を利かすこととなります。イノベーションのような話ひとつとってもそうなんですが、冴えたアイデアは、インサイトのユニークさに基づくんです。面白いソリューションは、そのソリューションが面白いのではなく、その前提としてあるインサイトが面白いんです。
──言われてみればそうですね。
企業にはいい加減、そのことに気づいてほしいですね。そのことに気づいていない時点で、自分たちの“耳”がいかに退化しているかを表しているようなものですから。受信感度の低い企業なんて、死ぬほどダサいじゃないですか。
──ダサいですね。
市場や社会のちょっとした動きに最も敏感であるべきなのが企業ってもののはずじゃないですか。それを察知できなくなったような企業はとっとと退出、というのが本当の意味での市場原理なはずなんですけどね。なんでそうならないんでしょうね。
──なんででしょうね。
さあ。困ったものです。
若林恵(わかばやし・けい) 1971年生まれ。『WIRED』日本版編集長(2012〜17年)。2018年、黒鳥社(blkswn publishers)設立。著書『さよなら未来』のほか、責任編集『NEXT GENERATION BANK』『NEXT GENERATION GOVERNMENT』がある。NY在住のジャーナリスト 佐久間裕美子とともホストを務めるポッドキャスト「こんにちは未来」のエピソードをまとめた書籍が8月5日に発売。
✍️若林恵さんによる本連載は、毎週末お届けしています。Quartz Japanメンバーには、過去の配信記事もご希望に応じてお送りしています。下記フッター内のメールアドレス宛てにお問い合わせください。
🗳Quartz Japanを、皆さんにとってさらに価値あるサービスとしていくため、ぜひ声をお聞かせください。ご回答いただいた方には、抽選でプレゼントも。アンケートフォームはこちらから(所要時間10分程度)。
📩このニュースレターはSNSでシェアできるほか、お友だちへの転送も可能です(転送された方の登録はこちらから)。
🎧Podcastもスタートしました! 👍Twitter、Facebookもぜひフォローを。




