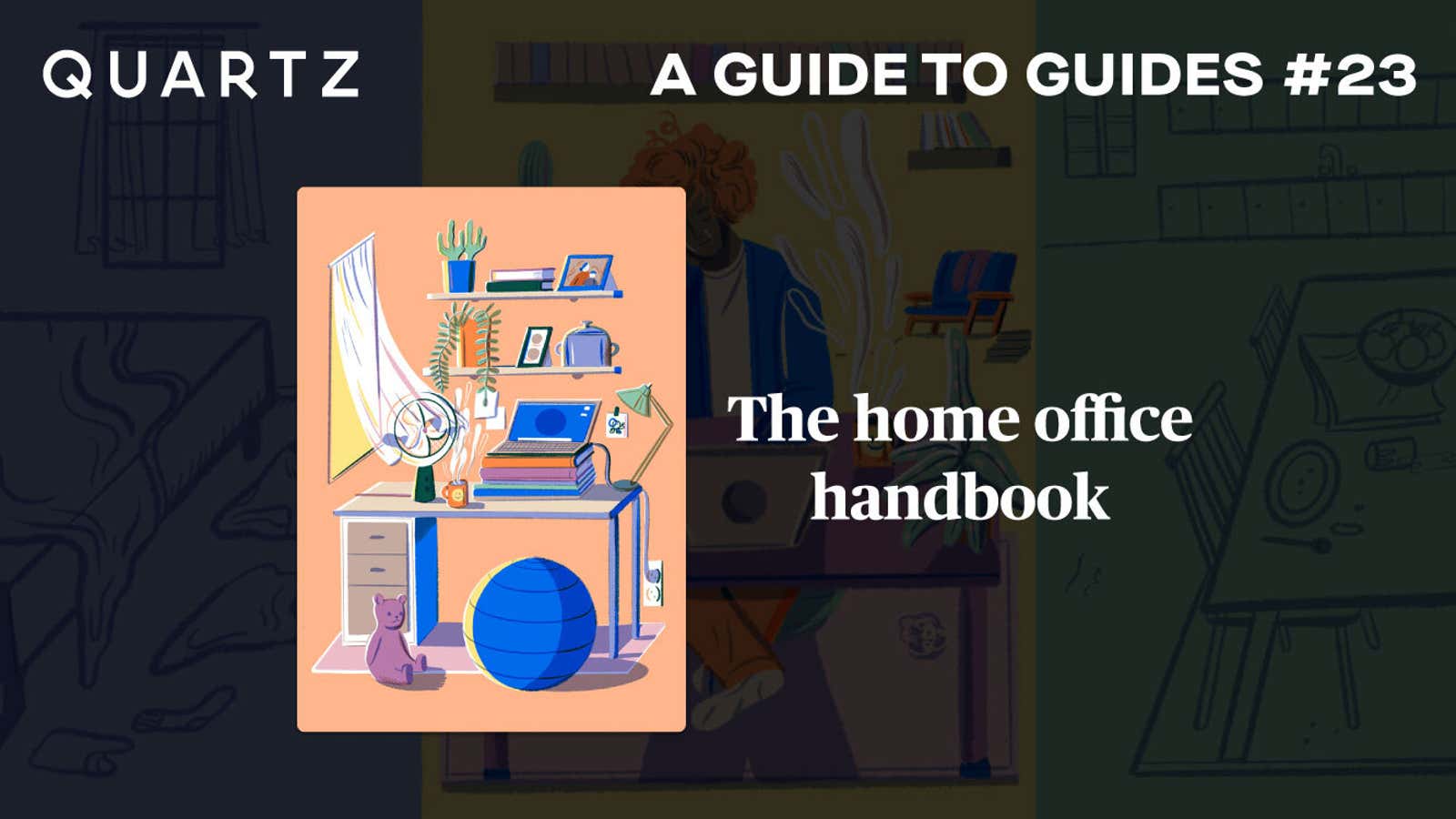A Guide to Guides
Guidesのガイド
Quartz読者のみなさん、おはようございます。世界はいま何に注目し、どう論じているのか。週末ニュースレターでは毎回、米国版Quartzが週ごとに組んでいる特集〈Guides〉から1つをピックアップし、編集者の若林恵さんに解題していただきます。今週は、WFHの話題から、そもそも「家」とは何かまで。

──お疲れさまです。調子はいかがですか?
元気ですよ。
──先週の九州出張はいかがでした?
朝からずっと缶詰で、ワークショップのお手伝いをするといった仕事でしたので、とくに九州だからどう、ということもないのですが、4連休だったこともあって、往復の飛行機がぱんぱんに満席だったのは驚きました。というよりドン引きしたのですが、航空会社はなに考えてるんですかね。すし詰めですよ。
──というより「Go To」とやらの問題のような気もしますけどね。
往復ともに国内線で、行きが赤い鶴の会社で、帰りが青い会社でしたが、「さすがに問題じゃない?」と地上スタッフの女性に行ったら、「減便してますので」と言われたんですが、感染ということを考えたら、ほんとは逆であるべきですよね。
──コストのことは度外視して考えるなら、増便して各機の客席を減らすという方が、ソーシャルディスタンス的な観点からいえば、まあ、正しい感じはしますよね。
よくわからないんですよ。飛行機のなかで、「Care Promise」なんていう安全を謳うキャンペーン映像を流してはいるんですが、基本線が「スタッフからの感染が起こらないよう万全の注意をしています」という内容で、「おい! そこじゃねえわ!」と思わずキレそうになってしまいましたが(笑)、まあ、乗客同士の感染は、管轄外といえばそうかも知れなくて空港側で体温測定やらはやってくれないという話でしょうし、せっかくお上がゴリ押しして実施してくれた「Go To」にタテ突くわけにもいかないでしょうから、まあ、苦しいところではありますよね。
──空港では体温測定とかはやるんですか?
いや。なかったですね(苦笑)。というか、コロナ以後に訪れた空間で、あれだけハンドサニタイザーやプラスチックのスクリーンなんかが設置されていない空間も初めて、というくらいパンデミックとは無縁の空間になっていまして。飲食店や映画館、ライヴハウス、スポーツ競技場などが、席を相当数間引いて細心の注意を払って対策を講じざるをえなくなっていることと比べると、ちょっとヒドすぎるのではないかと思いますね。ひどく不公平だと思うんですけど、「文句言う人、いないの?」と聞いたら、自信満々に「いないですね!」と返されまして(苦笑)。
──クレーマー扱い(笑)。
そうですね。
──クラスターが発生したらどうするんですかね?
知り合いは、「“出ないこと”になってるんじゃないですか」と穿ったことを言っていましたが、まあ、実際そんなところなのかもしれません。

──それでオリンピックを本当にやろうとしているんですかね?
さあ。「なかったことにする」という戦略をひたすら推し進めることでなんとかなる、と思ってるんですかね。海外を見ていると、大型イベントもオンラインでどう実現するかという実験もさることながら、オフラインでどう実施するのか、ということについてもさまざまな実験がされているように見えますが、そういう実験がダイナミックに行われているという感じはしませんよね。
──「バーニングマン」のバーチャル版が面白かった、とか、NBAやF1が無観客でゲームをどう実施しているかといったことも話題になっていますよね。
ですよね。実際にスポーツなどは、いま本当に大きな分岐点にあるように思います。というのも、自分はまったく観ていないのですが、サッカーのチャンピオンズリーグも、NBAのファイナルも、大坂なおみさんが優勝したテニスの全米オープンも、無観客だからといって特段選手たちのパフォーマンスが落ちたかというとそうでもないそうで、逆にむしろ向上しているかもしれないと観戦した知人たちは言っていますので、「現場に客がいる」ことの重要性は、本気で再検討されることになるんじゃないかという気もします。
──それは大胆ですね。
そうですか? そもそもスポーツ自体がここまでのビッグビジネスになったのはテレビのおかげですし、オリンピックでいえば、1984年のロサンゼルス大会を契機として、放映権料ビジネスに傾斜していった時点で、すでにバーチャルなものになっているわけじゃないですか。スポーツ視聴は、体験としてはとっくに「現場中心」でなくなっているはずですし、ビジネスにしたって、相変わらずチケット収益はバカにならないとはいえ、そのオペレーションコストと、オンライン化することでアクセスできる視聴者の数の莫大さを考えたら、どっちが優先すべきかは割と明確に結論が出ちゃいそうにも思うんですけどね。
──まあ、そう言われたらそうかもしれないですが。なんだか残念な気もしますね。
自分は、最近はスポーツ中継をあまり観なくなってしまいましたが、子どものころから相撲も野球もサッカーも、そこそこは観てきましたし、サッカーもワールドカップは全試合のうち半分くらい頑張って観たりもしますが、一生のうちのスポーツ視聴体験って、もうおそらく99%以上がメディア経由ですよ。逆の言い方をするなら、スポーツの面白さというものを、メディアを通して教化されてきたわけですから、むしろそっちがデフォルトの環境で、「現場視聴」はむしろオプションなんですよ。物心ついたころからスポーツは現場で観戦してきて、その習慣のあとでテレビ中継を発見したという人もいないとは思いませんが、そちらが優勢だということは、さすがにないと思うんですよね。
──たしかに。
もっとも、現場は現場で面白さがないとは思わないのですが、その手の「現場大事」といった言説は、音楽フェスの擁護論においてもそうなのですが、多くの場合「現場の楽しみは、コンテンツをじっくり観るというところではなくて、飲食だったり、仲間と一緒にいることだったりするんで」といったものになりがちでして、結局のところ、その体験価値が「コンテンツをじっくり味わう」というところにないのだとすれば、「コンテンツはなんでもいい」ということにもなってしまったりしますよね。

実際コンテンツの解像度は現場では下がるわけですから、そもそも高解像度を要求するコンテンツである必然性が本当はないということでもあって、本当は、ずっと、ここに矛盾があったわけですよ。
──まあ、F1なんかは現場で観ていても、レース自体の推移はよくわかりませんしね。お祭りに行くようなものですよね。
そうなんです。これは別にお祭りを否定しようという話ではないんです。ここで言っているのは、そうしたお祭り的なものの価値とコンテンツ的な価値というのを、これまでのイベントは不分明のまま興行化してきたということでして、コンテンツのオンライン化によってそうやって不分明だったものが徐々に分離していくことになっていきますので、そのイベントなりが「コミュニケーション価値」に比重があるのか、それとも「コンテンツ価値」に比重があるのか、イベントをやる側が策定し直さざるをえなくなるのではないかという感じがするんです。
──現場で観るなら草野球でもいいわけですよね。
だと思います。随分前に、ベルリンのウニオンベルリンというチームに関する記事をつくったことがあるんですが、そこに出てきたある英国人サポーターは、プレミアリーグの拝金主義と、それに伴って必然的に起きる「現場の劣化」、つまりライトユーザーばかりになっていくことに嫌気が指して、毎週末にわざわざドイツに行って、下部リーグのチームを観に行くんですね。
そこで問題になっているのは、スタジアム体験の濃密さ・クオリティであって、それは試合を行っているチームや試合自体のクオリティとは別のものなんですね。その彼はスタジアム体験というものを高い解像度でもって認識しているわけですが、それとチームが強いとか戦術がいいといったサッカーの試合そのもののレベルをめぐる解像度とはまったく違うものなんですよね。
──面白いですね。スタジアム体験の解像度をあげることと、コンテンツの内容を上げることは必ずしも一致しないということですよね。
もちろんコンテンツは重要なんですが、トップクラスのコンテンツをただもってくればいいということではないという意味では、その通りでして、要はコンテンツを測るときの尺度が違ってくるということだと思います。
一方で、オンラインに完全に移行したものは、それとは逆に、コンテンツそのもののクオリティの勝負になってきちゃうように思います。草野球を配信したとして、それを面白く見せるためには、相当の設備投資が必要になる可能性がありますし、映像としての解像度が上がっていけばいくほど、それに耐えうる内容が求められることになるようにも思います。もっとも、それをコミュニケーション価値の方に振れば、そこには別の価値提案もありうるとは思うんですが。
──難しいですね。
難しいですよ。結局、ものごとがどんどんオンライン化していくと、それまで対面とかリアル空間に集ってやっていたことって、なんの意味があったんだっけ?といちいち問い返されることになりますし、それをよくよく考えていってみると、「それ以外にやりようがなかったからそうやっていた」だけのことでしかなかったりするんです。
で、いま、あらゆる領域で問い直されざるをえなくなっているのは、人がいかに空間によって縛られていたかということなのですが、それが明らかになることで一層明確になってくるのは、そうした空間への固定化によって、わたしたちの社会生活が、いかに不動産ビジネスに囲い込まれているかということでもあるんですよね。

The home office handbook
ホームオフィスの含意
──たしかに。今週の〈Guides〉のお題は「ホームオフィス」なのですが、コロナ対策として一般化した、いわゆるテレワークによって、まさにそうした根源的な問い直し作業が求められることにもなっています。
面白いですよね。「家で仕事をするなら昼寝に罪悪感をもつのはもうやめよう」(Why you shouldn’t feel guilty for napping while working at home)という記事は、就業時間中に昼寝をとることをタブー視してきた社会と、その規律を内面化してしまったワーカーたちをその軛から解放すべく、昼寝の効用を盛んに謳っていますが、これなんかも今にして思えば、そもそも「なんで昼寝ってダメなんだっけ?」という問いを発動してくれるわけですし、「家から仕事するときに楽な服を選ぶのはやめよう。喜びをもたらしてくれる服を選ぼう」(Don’t dress for comfort when working from home—dress for joy)という記事は、仕事場のユニフォームであるところのスーツやジャケット、ブラウスやハイヒールなどが不要になったときに、“家着”を選ぶ基準が「楽だから」しかないことを問題にしていますが、そう言われると、家着って、オンの時間の対比のなかで、それに対する補足的な役割しかもっていなかったことが明らかになりますよね。

──家着って、言ってみれば、ただ下着の延長みたいなことですもんね。
それはそれでいいと思うのですが、「家ではだらっとしてていいじゃんか」という論拠を支えていた「その代わり、外ではバチっとキメるんで」という状況がテレワークによって消滅すると、ただ「だらっとした服を着ている人」になっちゃうわけでして、それもなんだかな、と思い始めると「家にいるわたし」にふさわしいルックというものを自己開発していく欲求が出てくるのも必然的なことですよね。で、記事は、まあ、大した解決ではないのですが、なるべき自分がときめく服を着るようにしよう、と勧めるわけです。
──「こんまり」じゃないですか(笑)。
そうなんですよ(笑)。とはいえ、だからといってバカにするのも違うと思うんです。近藤麻理恵さんのブームが明かしたのは、そもそも自分が何かを選ぶときに、自分の内発的な欲求で選んでいるというよりは、実は、外からの要請や外に対する適応戦略をさも自分の欲求であるかのように自分を偽っていたことが結構ある、ということだったと思えるのですが、そうした心理の機微を「ときめき」ということばで少し揺さぶってみると、実は不要な欲求に基づく選択に気づくことができたりするのは本当だと思うんです。

──自分もあります。気に入ってはいるんだけど、あんまり着ないTシャツとかありますね。それってきっとときめいていないんでしょうね。
わかります(笑)。で、逆に、ときめくもののときめきの理由を探してみると、色やデザインよりも、素材やサイズに要因があったりするじゃないですか。そういう発見って、小さな発見ではあるのですが、解像度がちょっとでも上がるという意味では大事なものだと思うんですよね。
──ということでいえば、「ホームオフィス」を自分なりにどう快適化していくかというお題は、言うなれば、自分の仕事にどうときめきを再び見出していくか、というプロセスでもあるのかもしれませんね。
「ハッピーなホームオフィスをいかにデザインするか」(How to design a happy home office)という記事は、例えば「ノイズキャンセルヘッドホン」や「メディテーションアプリ」の活用や、部屋の「緑化」に務めること、あるいは「壁をブラウンにするといい」といった具体的なアイデアを提供していますが、まあ、それをやったからといって、そもそも「クソみたいな仕事」が耐えられるようになるというものでもないとは思うのですが、この記事において注目すべきは、そもそも、「家で仕事をすることはいつから当たり前になったのか」と問うている点かなと思います。
──そうか。テレワークはオフィスの再定義と同時に家というものの再定義も促しているわけですよね。
そうなんです。記事は『Easy Living: The Rise of the Home Office』という新刊を紹介しながら、家から仕事を排除していく「当たり前」が一般化するのは、19世紀後半のことであると明かしていまして、それまでのイギリスには住居とワークショップと呼ばれる仕事場がある、「ワークハウス」というものが一般的だったとしていますし、記事は、「workhome.com」という、まさにそのワークハウスに特化したウェブサイトを紹介しています。そこに掲載された論文は、「ワークホーム/ワークハウス」と呼ぶべきものに関する研究は驚くほど少なく、分類学の父と呼ばれる植物学・博物学の父祖カール・フォン・リンネは、住居と仕事場が同居する家は「呼び名もなく、それに関する知識はすでに失われている」と書いたほどだそうです。

──なんだか不思議ですね。いま聞いても、取り立てて珍しいものだとも思えないですが。
記事によれば、産業革命によって大量の男性が工場労働に駆り出されることで、家と仕事場の分離は始まるとしていますが、それでも「家仕事」がなくなったかといえばそんなことはなく、小売店や自営職人や教師、聖職者といった人たちは家を仕事場にしていたといいます。
ところが、19世紀後半になると「空間が人の表象になっていくことが進行し、公共圏は生産活動に、私圏は生殖、子育て、消費の空間として切り分けられていく」のだと『Easy Living: The Rise of the Home Office』は説明しています。次いで、そのことによって、「”家庭第一主義”あるいは”真の女性性”というカルトが、ヴィクトリア朝時代の中産階級の家のありようはかたちづくられ、そこは危険に満ちた都市生活・近代生活における安全な避難所として、男性女性双方の居場所となっていった」としています。
──ふむ。つまり、都会生活、あるいは近代化された生活が、家族という観念をより強化し、家のありようを「仕事をする場所がない私圏」へと変えていったということですね。面白いですね。
この記事は、ひとつ興味深い記事を紹介していまして、『The Conversation』というメディアの「『家で働く』をめぐる空間の奪い合いにおいて、女性はノマド化させられている」(In the work-from-home battle for space, women are the reluctant nomads)という記事なのですが、ここでは、上記で記したような「都市家庭」において、男性にはまだかろうじて20世紀初頭まで「書斎」という空間をもてていたとされているのですが、それが多くの中産階級の家からなくなっていったとしても、家に書斎らしき場所をつくるという流れは20世紀を通じて、通信業者や不動産業者によってずっと温存されてきたとされています。
──お父さんの本棚のある部屋とか、趣味の部屋みたいなものは、いまだに結構ありそうですよね。
その対比として女性がたとえば家計簿をつけようとか、共働きのお母さんがどこで仕事をするかといえば、主にキッチンや食卓だったり、寝室にある小さなテーブルだったりするわけですよね。
──テレビや映画とかでも必ずそうですよね。
記事はそうした状況をして、家が20世紀を通じてすでにずっと「ジェンダー化」されてきたと書いています。
──いま、テレワークによって変更を迫られているのは、実は、そうした「家」というもののあり方そのものなのかもしれませんね。
これらの話を見ていくと、アメリカにおいてもそうですし、日本でもそうだと思うのですが、家というものの構成・編成自体が、リモートワークはおろか、「共働き」というものにすら対応していないことが見えてきます。

──あまり関係のない話かもしれませんが、つい先日、鳥取選出の衆院議員の杉田水脈という問題発言の多い方が、またしょうもない問題発言をしてまた話題になっていましたが、この人なんかは典型的な「『家族第一主義』『真の女性性』のカルト」みたいな存在だと思うんです。つまり女性の価値はその「生産性」に宿るという考えのことですが、これらの話を聞いていくと、右派のそうした「家族が大事」みたいな考えは、いかにも伝統を重んじているように見えて、典型的に20世紀的なものであるようにも思えてきますね。
どうなんでしょうね。これはきちんと最新の歴史学を踏まえた検証が必要だとも思うのですが、よく歴史ドラマなんかで「お世継ぎ」の問題が話題となって、大奥における女同士のドロドロが喜んで取り上げられますけれど、「家の存続」が重要だったのはそうだとしても、かなり融通無碍に養子縁組制度もあったような気もしますので、「家が第一」が即「女の価値は『生産性』」というドラマなどにありがちなナラティブが、20世紀的な家族観によるバイアスによって強調されている可能性はあるかもしれませんね。あまりうかつなことは言えませんけれど。
──まあ、そうですね。
今回の〈Guides〉で気がかりなのは、とはいえ、まさにその点でして、先に挙げた「ハッピーなホームオフィスをいかにデザインするか」(How to design a happy home office)という記事そのものが、どうもやはり20世紀型の従来の「家族」「家」というものを当たり前のものとして前提にしすぎている嫌いはあるんですね。
──ですよね。デザインで共働きでも働きやすい「家」につくり変えようという話は、それ自体としてはいいんですが、家と家族を自明のものとして一体化しすぎているように見えなくもないです。
とりわけ、テレワークのブームが、首都圏郊外に新たな住宅需要を生み出す可能性がある、とドイツのエコノミストたちは喜んでいるといった記事を読むと、これは、まさに20世紀的な家族=家のモデルで郊外を再開発しようという話で、これは、放っておくと、ただの20世紀モデルの繰り返しですよね。
──ほんとですよ。
それこそ最近「デジタル田園都市国家構想」なんていうものが提案されていまして、これはかつてあった大平正芳首相時代の「田園都市構想」のリブートで、行政のDXに向けたそれなりに真摯な提言だとは思うものの、都市ワーカーの分散をもって地方や非都市部エリアの不動産開発という発想が根っこにあるような気がしなくもありません。
さらに言えば、これには経済政策がほとんどなくて、発想が大都市の大企業のワーカーを地方に住まわすというだけのことで、日本全国が「通勤圏」としてより広域に大都市に従属させられるということにもなりかねないですよね。
──ふむ。
これは単純な思考実験でどれほど有用か検証できると思うのですが、リモートワークで地方や非都市部に「家族」で暮らすということが、たとえばシングルマザーと子どもの「家族」で安心安全に実行できるのかを考えてみたら、色々と落とし穴が見つかりそうにも思います。非正規雇用で都会の会社に雇用されて、それで家賃や生活費の安い地方に住めっていう話だとすると、これ、都市の大企業をただ守るためだけの施策にすぎませんよね。
──そういえば、昨日だかに政府が、都市の企業に勤めていて地方移住する人に100万円支給するといった政策が発表されていましたね。
これもなぜか「単身」だと減額されるといった縛りがありまして、やはり「家族での移住」が前提になっている感が拭えませんよね。家族と家が1セットで、しかもそれが1カ所に固定されないといけないという発想が、そもそもデジタルがもたらす可能性と矛盾しているはずなんですけどね。
──ほんとですね。
それこそかつてあった「ワークホーム/ワークハウス」が、ジェンダーや家族といった観点からどういった編成をされていたかといったことを検証してみると、もしかすると新しい「ホームオフィス」のヒントが見つかるかもしれませんし、「ハッピーなホームオフィスをいかにデザインするか」(How to design a happy home office)で紹介されていたモバイルワークプレイスなんていうアイデアは面白いと思います。
──移動小部屋みたいなものですよね。
記事内ではモジュール型のスモールスペース「KitHaus」とサンフランシスコのスタートアップ・Vitalが提案しているモバイルワークスペース、って要は仕事用に特化したバンなのですが、こうしたモジュール形式のソリューションは、家族という固定した観念を柔軟化する上でも、いいアイデアだと思いますね。

──女性にとってもありがたいものになる可能性がありそうです。
2018年にIKEAが出したレポートによると、世界中の30%の人が「家にいるのが落ち着かない」と感じているそうなんです。
──驚かないですね(笑)。
加えて、落ち着く場所としてアメリカ人の45%は「クルマのなか」と答えているそうなんです。さらにミレニアル世代になると「ソーシャルメディア」と答える人も20%近くいるといいます。
──ああ、面白いですね。最初の方の話としてもリンクしてきますね。「家」もまた不動産から離れていくという。
まさに。
──「家」がソーシャルメディアにあるなら、田園も都市も関係ないですもんね。
デジタルデフォルトの環境っていうのは、そもそも場所は関係ないはずですから。最初の話に戻りますと、オリンピックが配信オンリーになるなら、毎回開催都市という概念も意味ないですし、変える意味も無くなりますよね。
──ほんとですね。
これは、畑中章宏さんの『五輪と万博』という本に書かれていたことなのですが、かつて90年代半ばに「世界都市博」という万博もどきの開催を鈴木俊一都知事が構想したことがありまして、これは青島幸男さんによって中止になってしまいます。この都市博の主眼は、新しい通信・IT技術の見本市とすることでお台場を、来るべきIT産業の集積地にするというところにありまして、お台場を開発することで新たに9万の雇用を生むことができると鈴木知事は語っていたそうなのですが、ここでいう「9万の雇用」って、要はオフィスの床面積の話なんですよね。
──不動産開発。
当時から、このことに疑義を呈していた人がいたことを本は明かしているのですが、この批判は、いま一層有効だと思うんです。デジタル技術の進展を不動産開発に結びつけるしかできない発想の貧しさは、いまなおオリンピックや万博や「田園都市構想」に執心する政治家や官僚を見ればなにも変わっていないことがよくわかります。最後に引用しておきますね。
──ぜひ。
「都市博には、先述したように『高度情報社会に向けて、マルチメディアの実験をする博覧会』という側面があった。これに対して、Ⅲ章で丹下健三論を紹介した松山巌は、都市博中止決定の直後に、こんなふうに語っていた。
〈都市博以前の、テレポート構想についても、これは情報化社会の中で新しい都市をつくる必要性から出てきたのですが、現実にオフィスは今や余っている。それに、本当の情報化社会であれば、必ずしも固定された土地にオフィスをつくる必要性はないのではないか。つまり、土地・建物という土木的な政策と、情報化との間には、矛盾があるのです。(「世界都市博覧会とは、いったい何だったのか。」)〉
松山が抱いた、情報化社会の到来と土木的イベントとの矛盾、あるいは新しい時代にオフィスは必要であるのかという問題提起は、四半世紀近く経ったいま、いっそう現実的なものとなっている。しかし一方で、都市博が開催されるはずだったお台場は順調に発展し、楽天的で空虚な歓声が聞こえてくるばかりだ。そして、鈴木が抱いた開発の夢はかなわずに終わったが、博覧会の誘惑は人々を捉えて離さず、都市博が中止になったあとも繰り返し浮上していくのである」
若林恵(わかばやし・けい) 1971年生まれ。『WIRED』日本版編集長(2012〜17年)を務めたのち、2018年、黒鳥社を設立。NY在住のジャーナリスト 佐久間裕美子とともホストを務めるポッドキャスト「こんにちは未来」のエピソードをまとめた書籍が発売中。
ニュースレターの転送はご自由に(転送された方へ! 登録はこちらからどうぞ)。
👇 のボタンでニュースレターをTwitter、Facebookでシェアできます。Quartz JapanのTwitter、Facebookでも最新ニュースをお届けしています。
🎧 Quartz JapanのPodcast、ミュージシャンの世武裕子さんをゲストに迎えた最新エピソードをお楽しみください。