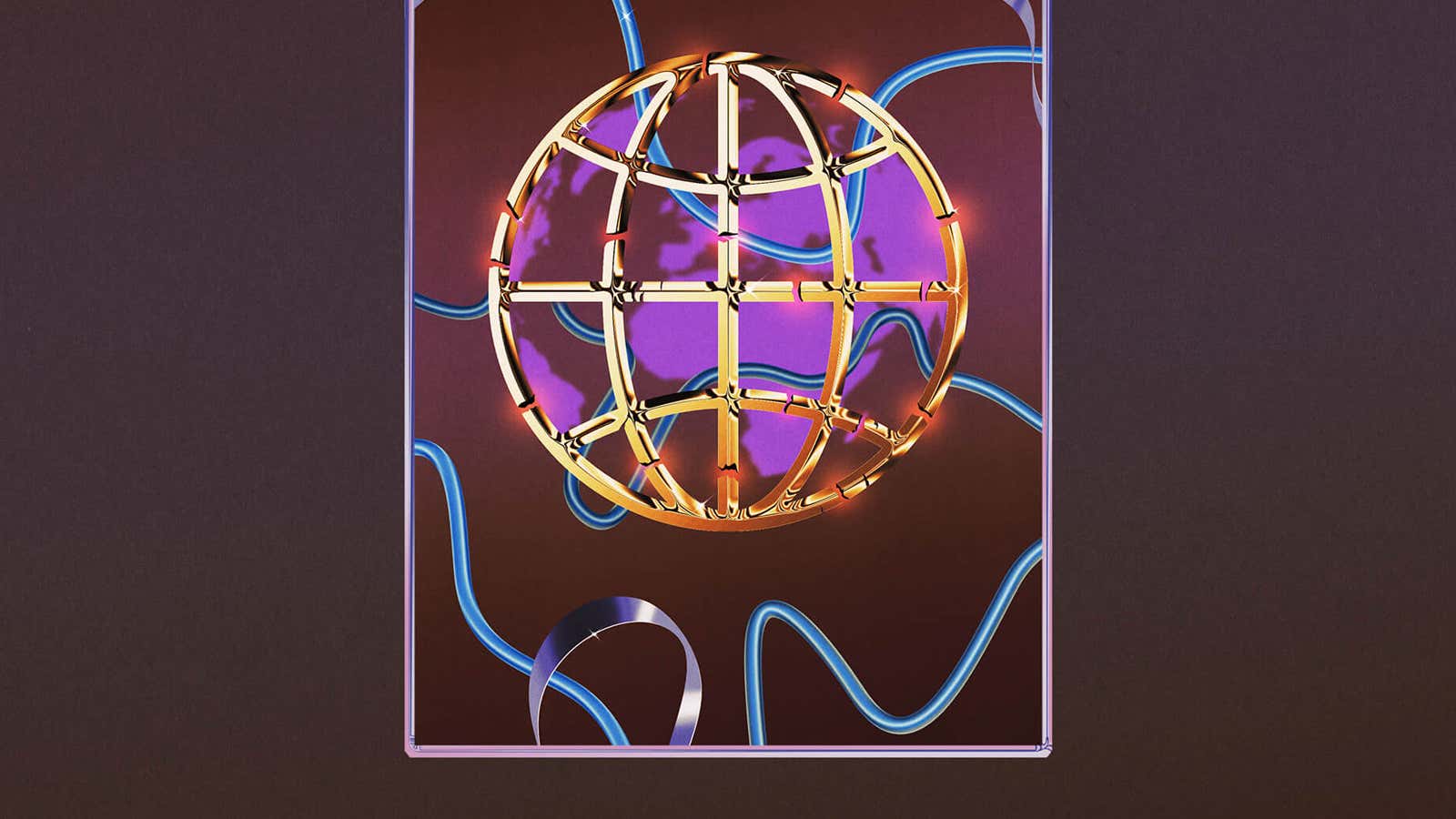A Guide to Guides
週刊だえん問答
Quartz読者のみなさん、おはようございます。世界はいま何に注目し、どう論じているのか。週末ニュースレターでは、米国版Quartzの特集〈Field Guides〉から1つをピックアップし、編集者の若林恵さんに解題していただきます。前回までとは、タイトルが変わったようですが……。
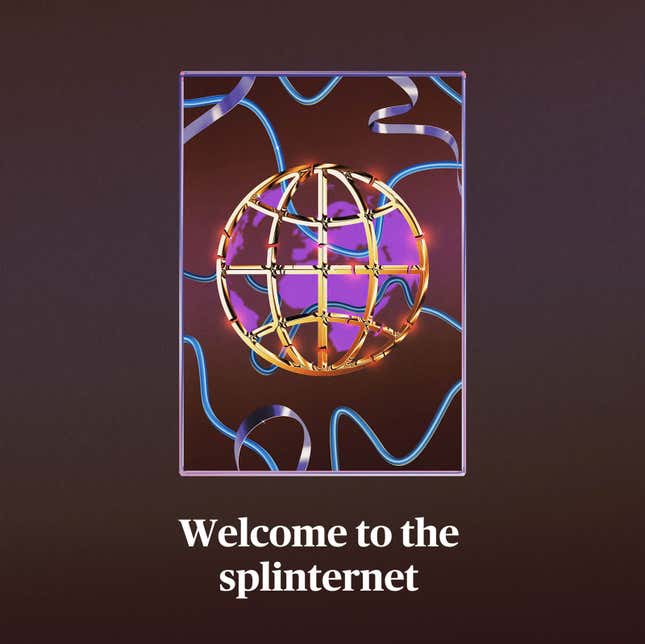
──こんにちは。2週間ぶりですが、お元気ですか?
いえ。まったく。
──どうしたんですか?
この連載の単行本化の作業がまだ続いておりまして、死にそうです。
──大変ですか。
ページ数が膨大にありまして。
──何ページあるんですか?
400ページ近いですね。
──え、そんなに?
あるんです。
──わずか半年で、よく書きましたね。
ほんとですよ。張り切りすぎました。
──これからも張り切ってくださいよ。
そうですね。
──本のタイトルは決まっているんですよね?
はい。『週刊だえん問答 コロナの迷宮』というタイトルです。
──は。なんですか、それ。
連載自体はずっと「〈Guides〉のガイド」でしたが、友人と駄話をしていたときに、ここで用いている「仮想対談」という形式を「だえん問答」と呼んではどうかとなりまして、そのまま採用しました。個人的にはかなり気に入っています。
──だえん、ですか。
中心点がふたつある、という含意です。ふたりによる対話になっているという構成において、まず視点がふたつありますし、米国版の『Quartz』の〈Field Guides〉と書き手である若林の応答になっているという企画の建て付けの点でも、中心点がふたつあると言えるのではないかと。
──なるほど。それで連載のタイトルも今回から、「週刊だえん問答」に変更されたということですね。
はい。そういうことです。

Welcome to the splinternet
テクノナショナリズムの逆襲
──では、改めて「週刊だえん問答」としての第1回、通算で数えますと28回目ですが、今回のお題は「テクノナショナリズム」です。
はい。原題は「Splinternet」(「Welcome to the splinternet」)となっていまして、「スプリンター」は「破片」「裂片」を意味する英語ですから、今回の特集は、当初麗しき「グローバルビレッジ」をつくりだしてくれるはずだったインターネットが、国家の管理下におかれ、ナショナリズムと結託しながら断片化していっている流れを追ったものとなります。トランプ大統領が中国産のアプリ「WeChat」や「TikTok」をアメリカで禁止しようとしていることが、特集の底流にある直近の問題ですが、こうした断片化は、起こるべくして起きているとも言えます。
──そうですか。
中国がGoogleやFacebookを筆頭に国外のサービスを排除し、デジタル空間を明確に「国家の領土」とみなしたのが、いまにしてみれば、やはりひとつの重大な転換点だったように思います。これは、2009年の出来事です。
──はい。
当時のインターネットは、基本シリコンバレー由来のアメリカのテック巨人の独壇場でしたし、中国のテック企業が世界化するなんていうことはまったく想定されていませんでしたから、“アメリカ寄り”の立場からすると、「あらあら、中国がまた自分の殻に閉じこもっちゃったよ」「まあ、いずれ外に出てくるから気にしないでおこう」といった対応だったように感じます。少なくとも自分は、そんな印象でした。「グローバル」といえばもっぱら「アメリカ」のことを指すと思い込んでいる日本から見ると、アメリカのグローバル覇権はデフォルトの環境ですから、デジタル空間においてもその盤石性を疑うことがなかったのだと思いますが、ところが、中国に限らず、世界の多くは必ずしもそう思っていたわけではないんですね。
──そうなんですね。
アメリカ産の巨大テック企業によって、ただでさえ強大なアメリカのパワーがさらに強化されることを嫌ったのは中国だけでなく、欧州もそうです。彼らは、2000年代の初頭からデジタル空間においてアメリカ企業が独占的な地位を占めることをことさら警戒しており、ベルリンなどの都市を中心に、アンチ・グーグル、アンチ・フェイスブックのキャンペーンを長らく展開してきました。それが制度として結実したのが2018年に施行された「一般データ保護規則」(GDPR)というもので、これは明確にアメリカのテック巨人をターゲットにしたものでした。
──はい。
そうやって、デジタル空間におけるアメリカの影響力を相対化しようとする動きは、目立つところでは中国と欧州で動いていたわけですが、ことが複雑になるのは、国家としてのアメリカと、アメリカ産のテック巨人が、必ずしも一枚岩ではなくなり、むしろ時を経るにしたがって敵対的になっていったことでした。
──なぜでしょう?
いくつか契機があったとは思いますが、スノーデン事件(2013年)によって、まず政府と市民の間に決定的な溝が生まれ、その後、ソーシャルメディアの力を最大化することでトランプが大統領になってしまったことで(2016年)、「デジタルテクノロジーは社会を破壊している」といった言説がアメリカでも広く流布されるようになりました。『WIRED』のようなテックメディアからも、こうした声が上がってくるほどでしたから、これは大きな潮目でした。さらに大統領選挙がFacebookを通じて操作されていたという「ケンブリッジ・アナリティカ」のスキャンダルが出てきたことで(2018年)、政府もいよいよ本腰で規制に動かざるを得なくなりました。
──下院の公聴会にGAFAのお歴々が呼び出されていましたね。
はい。そして、ここからさらにややこしくなるのは、デジタル空間における覇権は安泰だろうと思っていたアメリカで、知らぬ間にミレニアルズ・Z世代を中心に、あろうことか中国産のアプリが大人気になってしまっていたからです。これはアメリカに限らずどの国もそうだと思いますが、要は中国をナメていたんですね。アメリカもここにきて慌てて使用禁止を打ち出してはいますが、これが意味するのは、アメリカ自体が、インターネットのグローバル性を否定するということですから、その影響は甚大です。
──中国がアメリカ企業を禁止したのと同じことをやろうとしているわけですもんね。
そうなんです。これは、中国の戦略の方が、結果的には当たっていたということを暗に認めてしまうことになりかねません。おそらく世界中には、インターネットをより強固に国民を監視・管理する装置として利用したいと考える指導者や官僚はいたはずですが、アメリカが一応体現していた民主主義や個人主義といった理念がある意味歯止めになって、あからさまな監視や管理は表向きには進行していなかったはずですが、アメリカ自身がそのタガを外してしまいますと「なら、うちも」となる国は結構出てくるのではないかと予想されます。

──なるほど……。
今回の〈Field Guides〉にある「インターネットの未来を勝ち取るべく戦う最も重要な企業・政治家・アクティビスト」(The most powerful companies, politicians, and activists fighting for the future of your internet)という記事では、「人権」を主題に「サイバーピース」を謳うヨーロッパの政治家や団体が紹介されている一方で、そうした勢力と真っ向から対立するであろう「強権派」として、インドのモディ首相のソーシャルメディア部隊や、ウガンダのムセベニ大統領が紹介されています。

──ヤバい人たちなんですか?
ムセベニ大統領は、Twitter、WhatsApp、Facebookなどのソーシャルメディアを何度も遮断しており、「ソーシャメディア税」なる政策も打ち出しているそうです。彼の強硬な態度は、アフリカ諸国のリーダーたちからは賞賛され、レソトやジンバブエといったアフリカ諸国でのソーシャルメディアの利用は徐々に厳しく規制されるようになってきていることが、10月に『Quartz』に掲載された、「アフリカ諸国政府はソーシャルメディア規制を静かに強めている」(More African governments are quietly tightening rules and laws on social media)という記事でも明かされています。
──ふむ。
この問題は、ソーシャルメディアで政府批判をした人が逮捕されるような事態を生み出しているということで、ソーシャルメディア規制の大きな目的は、何よりも市民が自由に声をあげることを恣意的に封殺することです。
──怖いですね。
一方インドのモディ首相は、世界のなかでも最もテックサヴィーなリーダーとして知られており、InstagramとTwitterに約6,000万人ものフォロワーを抱えていまして、これはトランプ大統領の約2倍だそうですが、これを主導してきたのがモディ首相の所属政党BJPのソーシャルメディア部隊です。通称「IT部屋」(IT Cell)は、元々は若い有権者を獲得するために組織された部門ですが、手っ取り早くフォロワーを獲得するために、イスラム教徒に対するヘイトを撒き散らしており、それがインドのネット空間を汚染していると記事は指摘し、「インドはオンラインナショナリズムを煽ることで、自分たちが中国を羨ましく思っていることを明かしている」とも語っています。
──うーん。お話を聞きながら日本のことを思うにつけ、「デジタル庁」なんていう話も、いよいよきな臭く聞こえてきますね。
「テクノナショナリズムが形づくるインターネットの未来」(Techno-nationalism is shaping the future of your internet)という記事は、こうした現状観を、こんなふうにまとめています。
「中国が提唱する『サイバー主権』という理念は絶大なる影響力をもつにいたっている。よその国の政府も、その理念をもってインターネットを、指導者が考えるところの国益に従って規制すべきだと考えるようになっている」
「資金力のあるいくつかのプラットフォームに権力が集中する一方で、全体主義的な政府が次々と、そのテクノロジーを自国民を管理するために利用するようになってきている」

──ひえー。なんとも暗黒な未来ですね。
先述の「インターネットの未来を勝ち取るべく戦う最も重要な企業・政治家・アクティビスト」には、「人権」という盾をもってこうした状況と戦っているグローバルノンプロフィット組織などが紹介されています。一応羅列しておきますので、興味ある方にはぜひ見ていただきたいと思います。

──心強いですね。ところで、アメリカの大統領選は、終わったのか終わっていないのか、もはやよくわかりませんが、大統領がトランプからバイデンに変わることで、今後のインターネットの行方が多少でも変わることは起きるんでしょうか。
ちょうど今週の月曜日の11月9日に、「バイデンのホワイトハウスはテック政策どう変えるか? 知っておくべきこと」(How Will Tech Policy Change In The Biden White House? Here’s What You Need To Know)という記事が『NPR』に出ていましたが、とにかく話題が多岐にわたります。
──そうですか。
まず、言及されているのが、トランプが投票日間際に、独禁法でグーグルを訴えた件です。記事は、この裁判がこの数十年におけるテック企業に対する裁判で最も重要のもので長期化は必至としながらも、バイデン政権は、この裁判を継続はしないだろうと見ています。
──なぜでしょう?
この裁判自体が選挙選を睨んだアドバルーンだったという見方から、この裁判自体を継続しないということですが、といって民主党がグーグルを見過ごすかといえばそうではなく、むしろ新たな裁判をスタートさせるのではないかという見方が有力ですから、アメリカ政府とグーグルの戦いが始まるのは、おそらく間違いなさそうです。「もし、この裁判に政府が勝つと、グーグルはその帝国の分割を余儀なくされるだろう」と記事は書いています。
──ふむ。
次に問題となっているのは、ユーザー投稿型のプラットフォームの規制です。これらのプラットフォームは、ミスインフォーメーションやディスインフォーメーションの温床になっていることから、どの国でも政府は頭を悩ませている問題ではありますが、アメリカで争点になるのは、テック企業をこれまで守ってきた「通信品位法」(Communications Decency Act)の「Section 230」という条項でして、この法律が認めた「legal liability shield」というものがあることで、テック企業はユーザーが投稿したコンテンツに対する責任を負わずに済んできました。これをオーバーホールすることについて、バイデンは、副大統領時代に「至急やる」と語っていたそうですから、特にTwitterとFacebookなどのソーシャルメディア企業に対して、誤情報や偽情報の取り扱いをめぐって規制をかけて行くのではないかと見られています。
──それは、いい話ですよね。
テック企業がここで一番恐れているのは、上記の「legal liability shield」を失うことで、それが温存される限りにおいては、規制はむしろウェルカムなのではないかというのが記事の見立てです。
──そうなんですね。
ユーザーが投稿したコンテンツをめぐって裁判地獄に陥るよりは、政府が言う通りにユーザー投稿に規制をかけていくほうが、彼ら的にははるかに楽ですから、Facebookあたりは、それをむしろ歓迎するのではないかと専門家は見ているようです。
──ザックらしいといえば、ザックらしいですが。
とはいえ、ここでの懸念は、何が投稿され、何が削除されるかの判断を政府が担うことになる、という点です。自政権に有利な投稿だけが許可されるということになれば、中国や先のウガンダと何が違うのか、ということにもなりかねません。
──といって、この間の選挙戦を見ている限りでは、企業の自助努力だけでは、制御しきれないようにも見えますから、この判断は難しいところですね。
もっとも「legal liability shield」がなくなることで最も痛手を被るのは、TwitterやFacebookよりも、むしろRedditやYelp、あるいはWikipediaなどのサイトだろうともされています。
──Wikipediaがなくなったりしたら困りますね。
まったくです。次いでの話題は「中国テック」ですが、バイデン政権は、トランプが指摘していたように自国民のデータが中国に盗まれているのではないかという疑念は共有しているようですが、「全面禁止」のような強硬策ではない、もっと戦略的なやり方で中国と対抗していこうとするだろうと見られています。これはTikTokやWeChatのようなサービスだけでなく、5Gをめぐるファーウェイの処遇なども含まれます。

──うまく中国を御することができるんでしょうかね。
どうなんでしょうね。記事には具体的なアプローチは語られていませんが、どんな戦略がありうるのか興味ありますね。そういえば「中国テック」については、この原稿を書いている11月13日の『日本経済新聞』に「テンセント、動画投資倍増」という記事が出ていたのですが、それによるとテンセントが2023年までに映画やドラマのコンテンツ制作に対して、なんと、1兆6,000億円相当の投資をしていく予定なのだそうですよ。
──1兆6,000億!それもコンテンツにですか!
すごいですよね。記事は主にバイドゥやバイトダンスへの対抗策として国内コンテンツの拡充を狙っているとの見方ですが、個人的に気になるのは、その資金がどの程度ハリウッドに流れていくのか、という点でして、テンセントが保有する映画制作会社「Tencent Pictures」が、これまで出資してきた作品を見ますとハリウッドでの展開は、今後さらに強まるようにも感じます。
──え。テンセントが関わっているハリウッド映画って結構あるんですか?
ありますよ。並べてみましょうか。『ウォークラフト』『キングコング: 髑髏島の巨神』『ワンダーウーマン』『ラ・ラ・ランド』『レディ・プレイヤー・ワン』『ヴェノム』『バンブルビー』『メン・イン・ブラック:インターナショナル』『ターミネーター:ニュー・フェイト』などがこれまでのもので、来年以降にはポール・トーマス・アンダーソンの新作や『トップガン』『ヴェノム』の続編なども控えているそうです。
──ちょっと! ほとんど観てますが! テンセントのお金が入っているとは知りませんでした……しかも名だたるIPばかりじゃないですか。
自分は『ヴェノム』を観たときに、冒頭に「Tencent Pictures」とあったのに気づいて「えっ?」と思ったのですが、調べてみて改めて驚きました。
──ディズニーが『ムーラン』で中国寄りの態度を取ったことで世界中から批判を浴びましたが、そう考えると、すでにアメリカのコンテンツビジネスは、チャイナマネーにどっぷりという可能性もありますね。そこに来て、コンテンツ予算「1兆6,000億円」とくれば、うーん、バイデン政権はこの辺も気にしないとなのかもしれません。
大変ですよね。話を戻しますと、バイデンが直面しなくてはならない「テック問題」はまだあります。
──まだあるんですか……。
はい。『NPR』が中国問題に次いで取り上げているのは、いわゆる「データプライバシー」の問題です。これについては来年には、プライバシーをめぐる連邦法が制定されるのではないかと専門家は見ているそうです。
──テック企業の反対はないんですか?
むしろテック企業側がそれを望んでいると記事は書いていまして、なぜかと言えば、カリフォルニア州が独自にデータプライバシー法を施行したように、50の州が個別に法をされるよりは、連邦レベルで法制化してもらったほうが彼らとしてはありがたいですし、どうせ欧州において「GDPR」を遵守しなくてはならないわけですから、GDPRと同等の厳しさの法規制であれば、すでに対応済みだということもあるようです。
──ふむ。まだ、あります?
ありますよ。お次はギグエコノミー対策です。これについては、つい先日、ギグワーカーを雇用者ではなく個人事業主としてとどめおくことを求める「Proposition 22」という法案が、カリフォルニア州で可決されまして、ワーカーたちのみならず労働組合などにも大きな落胆をもたらしました。
とはいえ、テックプラットフォームに対して、ギグワーカーたちをもっと公正に扱うべきだという世論は根強くありますし、独占企業が同業のSME(Small & Medium Sized Enterprise)を圧迫することへの反発も強くありますし、一方のテック企業も、より柔軟でフェアな労働環境を生み出していくことの必要性を認識していると、あるベンチャーキャピタリストも語っていますので、バイデン政権は大統領令をもって規制を発動してもよいのではないか、とする声があることを記事は紹介しています。

──なるほど。
飽きてきました? ご安心を、次が最後です。
──はい。
最後は移民の問題です。
──テックと関係あるんですか?
シリコンバレーは長いこと外国生まれのワーカーたちによって牽引されてきましたし、記事によればテック業界における外国生まれのワーカーは実に60%にも上るそうです。
──イーロン・マスクやピーター・ティール、セルゲイ・ブリンをはじめ、マイクロソフトCEOのサティヤ・ナデラなどなど、外国生まれのスターには事欠きませんね。
そうした優秀なワーカーたちを呼び込むために用いられてきたビザが「H-1B」というものでして、これをトランプ大統領が廃止しようとして、連邦裁判所に止められるという悶着がありました。トランプとしてはアメリカのワーカーに職を与えるための施策だったようですが、バイデンは、高技能をもったワーカーについてはさらに増やしていく方針だと見られています。
──この問題については、先週の〈Field Guides〉で特集されていましたが、ここは、今回のお題である「テクノナショナリズム」の問題とも直結していますね。
ナショナリズムと排外主義は、コインの裏表のようなものだと思いますが、その根底にあるのは、やはり労働・雇用の問題です。この3月には、ドイツで高技能ワーカーの条件を緩和する新しい移民法が施行されたそうですが、移民の増加が社会の不安定さを増すのは知りながらも、それでも優秀なワーカーを呼び込みたいとどこの先進国も思っているのは、おそらくそうしないと国の未来がつくれないと考えているからなのだと思います。排外主義を抑えながら、国の経済を支えていくであろう外からの新しい人材を、どうやって社会のなかになじませていくのかは、非常にデリケートなバランスが必要とされる難題ですね。
──票取りという観点から言えば、敵を特定して排除を謳うのが一番効率が良さそうですから、そこに陥らないためには、よほどの自制が必要に思えます。
そうですね。今回の〈Field Guides〉は、インターネットの夢であった、ヒューマニスティックにつながったグローバル世界が、粉々に砕け散っている状況を反映した特集ですが、そのなかでもとりわけ面白かったのは、「インターネットをあらゆる言語でアクセスできるようデータサイエンティストたちが格闘中」(Data scientists are trying to make the internet accessible in every language)という記事です。

──ほお。
そのなかには南アフリカのデータサイエンティストの、こんなことばが紹介されています。「インターネットは情報を民主化したというけれど、そうじゃない。インターネットが民主化したのは『英語の情報』だ」。
──おー。冒頭にあった「グローバルといえばアメリカのこと」ともつながる話ですね。
わたしたちはアメリカの覇権のなかに長いこと暮らして来ましたから、グローバルというとそれが「アメリカ化=英語化」を意味していると、あまりに自明のこととして思ってきましたし、テックイノベーションを主導したのがアメリカ企業だったことから、デジタル化がもたらす「グローバルビレッジ」もまた自明のこととして英語の世界だと感じていたように思いますが、本当は、もっと想像力を働かせて、そうでない世界を思い描くべきだったのかもしれません。
──そこでは中国語が話されている、とか?
それもひとつですよね。これは以前に書いたかもしれませんが、J・J・エイブラムズ製作のNetflixオリジナル『クローバーフィールド:パラドックス』では、宇宙ステーションにおける公用語が中国語だったことに驚き、感心もしたのですが、いま起きていることは、これまでの「英語の覇権」が、ほかの言語に置き換わっていくということでもないのかもしれません。
──どういうことでしょう。
それこそ、いま挙げた記事は、ローカルな言語が多数あるインドやアフリカ、あるいはバスクなどで自然言語処理の専門家が、翻訳AIを用いて、インターネットにおける言語の多様化を推進している状況を描いていますが、すでにしてわたしたちは、かつてないほどマルチナショナルでマルチリンガルな環境に接していることは、この原稿を書きながら、ずっとブラックピンクを聴いていても思います。
──好きですね。
どんどん好きになってきてしまいましてお恥ずかしい限りですが、言語という観点でいえば、ブラックピンクの動画は絶えず、ハングルと英語とタイ語と日本語がランダムに入り混じっていますし、いわゆるファン動画はもはやナショナリティという概念自体が意味をもたない様相でもあります。そのなかで、英語は、やはり相変わらず優勢にある言語ではあるのですが、つい先日、『Virtual English: Queer Internets and Digital Creoliziation』という面白いタイトルの本をみつけまして、「なるほどそうか」と思いました。読んではいないのですが。
──えーと、訳すと「バーチャル英語:クイアなインターネットとデジタルクレオール化」という感じでしょうか。
ここにある「デジタルクレオール」ということばはいいなと思いまして、もしかすると英語の専制は、クレオール化されながら相対化されていっているのかな、と思ったりします。ブラックピンクのLisaが母国語のタイ語を話している動画を、意味もわからないなりにたくさんの人が観ているような状況は、かつてないものだと思いますし、そうやって未知なる言語に絶えず晒されながらも、それでも何かしら共有できるものを皆が探り当てようとしているさまは、非常にポジティブなことのように感じます。
──それこそブラックピンクやBTSが、アメリカの4大ネットワークの番組で韓国語の歌を歌っているのをみると、時代も変わったものだなと思いますよね。
今朝、ちょうどアヤ・ナカムラというフランスをはじめ欧州で大人気のマリ人の女性シンガーの新譜を聴いていたところでして、彼女の名前の「アヤ・ナカムラ」は、調べてみるとドラマ「Heroes」のヒロ・ナカムラさんからとった、ただの芸名なのですが、日本人名を芸名にしたフランス語で歌うアフロポップの歌手って、やっぱり相当面白いなと思います。彼女の作品は、今作で初めてアメリカでディストリビュートされることになるそうですが、アメリカもすでにして、出自の不明な、こういったものを聴くことができるだけの耐性を得ているのかと思うと、興味深いですね。
──ナショナリズムや「一国による覇権」といった観念を鮮やかに無効化していく感じがありますね。
地上の国家がいくら壁を立て、人びとを自分たちの領土に閉じ込めようとしても、デジタル空間のなかには、すでに摩訶不思議なやり方でクレオール化した別の領土がすでにできているのだとすると、少し痛快な気持ちにもなります。だいぶロマンチックな見方かもしれませんが。いずれにせよ、「国家」というものを強く統治したい側にとっては、その新しい領土は目障りなものなのでしょうね。
──今後世界がどう転んでいくのか、よほど注視しないとですね。
どうなりますか。
若林恵(わかばやし・けい) 1971年生まれ。『WIRED』日本版編集長(2012〜17年)を務めたのち、2018年、黒鳥社を設立。NY在住のジャーナリスト 佐久間裕美子さんとともホストを務める「こんにちは未来」をはじめさまざまなポッドキャストをプロデュース。本連載をまとめた単行本の発売が12月8日に決定! 同じく黒鳥社から、今月末にはメディア美学者・武邑光裕さんの単著も発売されます。