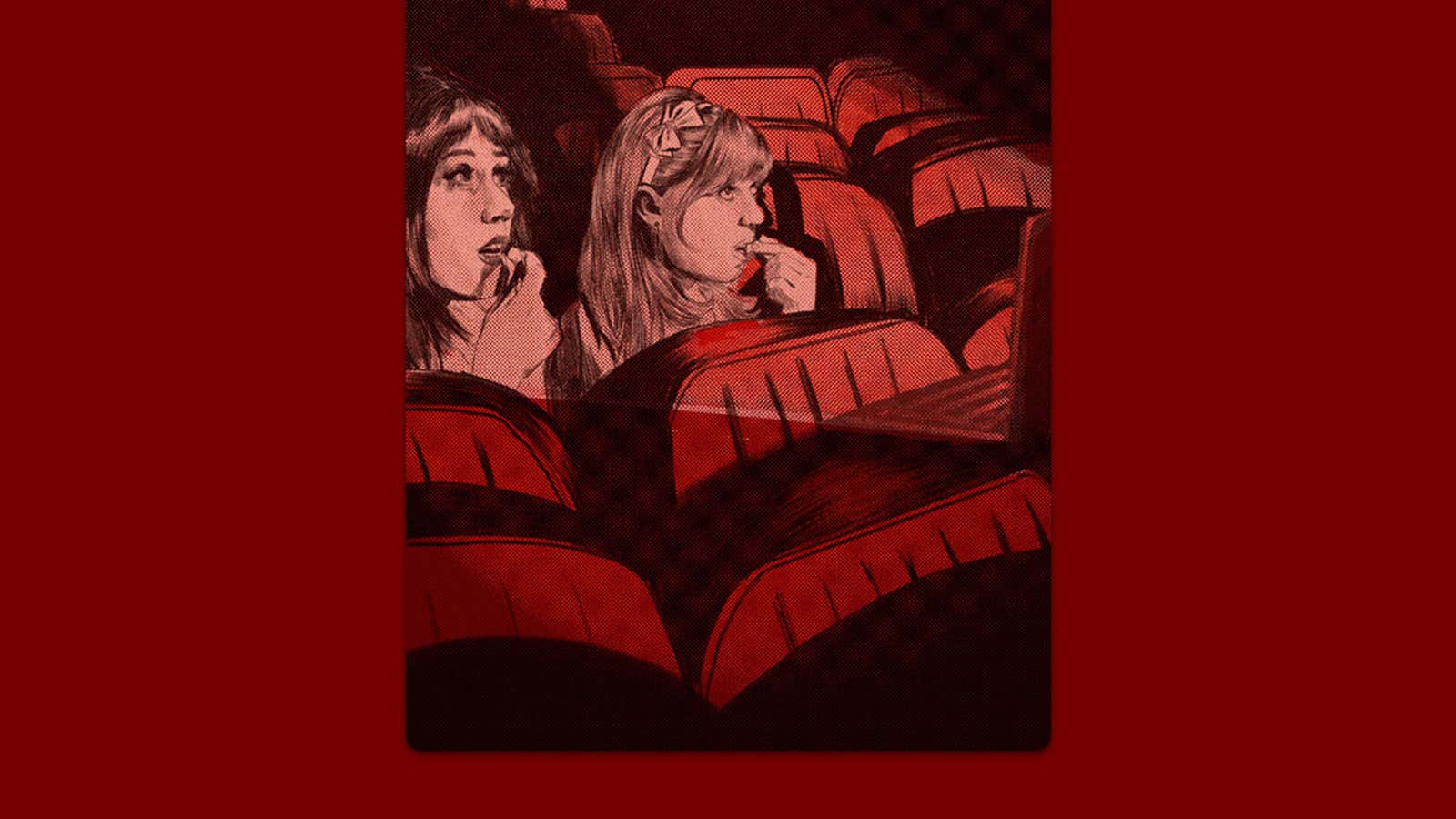A Guide to Guides
週刊だえん問答
Quartz読者のみなさん、おはようございます。週末のニュースレター「だえん問答」では、世界がいま何に注目しどう論じているのか、米国版Quartzの特集〈Field Guides〉から1つをピックアップし、編集者の若林恵さんが解題します。2021年最初の「だえん問答」は(昨年末と同様に)メール1通には収まりきらない文字量に。上・下2通のニュースレターに分けて、1分違いでお届けします。

──あけましておめでとうございます。今年もどうぞよろしくお願いします。
はい。よろしくお願いします。
──お正月はどうされていましたか?
いや、特にこれといったことはなかったですよ。読書したり、音楽を聴いたりする気にもあまりなれず、ネットフリックスをぼんやり観ていたりしましたね。
──なにか面白いものありました?
どうでしょうね。たまたま観た『#Rucker50』というバスケットボールをテーマにしたドキュメンタリーが、作品の出来はめちゃくちゃ悪いんですが、内容はとても面白かったです。
──へえ。どういうものなんですか?
ハーレムに「Rucker Park」という、バスケ史における伝説的な公園があるそうで、その50周年につくられたドキュメンタリーなのですが、この公園で毎年夏に開催されていたトーナメントが、いかにその後のバスケの隆盛を下支えしたかが主題でして、この公園と、そこで行われていたアクティビティの意義を確認してみると、スポーツというものをめぐるわたしたちの認識が、大きく間違っているかということに気付かされます。
──どういうことでしょう。
公園の簡単な歴史は、スニーカーを中心としたカルチャーメディア『Complex』のいい記事がありますので、それを参照いただくといいかと思うのですが、60年代に始まったこの夏のトーナメントというのは、当時のNBAのプロも参加するような大会だったんです。というのは何を意味するかと言いますと、公民権法が制定される1964年以前のNBAは、アフリカンアメリカンもいるにはいたのですが、チームに数名程度だったそうなんです。ちなみにNBAは、1946年に創設されたそうですが、NBAで初めてプレイした有色人種は、ワタル・ミサカさんという日系の方なんだそうですよ。
──へえ! そんな話、聞いたことないですね。
そうなんです。わたしもいま調べ物をしていて初めて知ったのですが(笑)。ミサカさんについては、例えばこの記事を参照いただくといいと思うのですが、どうもドキュメンタリー映画もあるみたいですね。

──面白いですねえ。
ほんとですね。で、話を戻しますと、夏のハーレムで行われるトーナメントにプロのNBA選手が参加しているというのはどういうことかというと、当時の選手たちの間では、バスケの最高峰はプロリーグではなく、むしろハーレムのストリートにあった、ということでもあったんですね。いわば、プロが腕試しをしに行くような場が、ラッカー・パークのトーナメントだったということなんです。
──ははあ。なるほどなるほど。
いまもそれはあまり変わっていないとは思いますが、それまでのバスケは大学リーグの延長線上にあって、大学が選手を輩出していたわけですが、そこから遠く離れた都市の貧困エリアにバナキュラーなバスケットボールカルチャーがあって、それがいわば、エスタブリッシュメントであったメインストリームのバスケを脅かす存在になっていたということを、ラッカー・パークのトーナメントは表しているわけですね。
──ふむ。
そして、そこでストリートの技術やプレイスタイルなどが、徐々にNBAに影響を与えていくということになるわけですが、そうした影響は、ゲームのルールなどにも及んだと言いますので、選手たちだけでなくNBAの運営・経営自体が、このストリートトーナメントに多くを負っていると言えるほどでして、実際、ラッカー・パークは、のちにNBAの審判や運営スタッフなどを多く輩出しているとも言われています。
──すごい影響力ですね。
そうなんです。そうしたストリートの文化をダイナミックに導入して行くことで、バスケというスポーツはグローバル化していくことになるわけですから、その後のメガエンタテインメントとしてのバスケは、実際はハーレムにおける、ローカルなコミュニティ活動にひとつの大きな基盤をもっていることになります。
──というのは?
このラッカー・パーク・トーナメントを創設したホルコム・ラッカーという人は、ニューヨーク市の公園管理部門で働きつつ、学校やコミュニティセンターで英語を教えていた教師でして、彼が、このトーナメントを始めたのは、あくまでも若者たちを都市犯罪などに巻き込まれるのを防ぐためだったんです。そうやって始まったアクティビティが、やがて選手たちを輩出し、かつNBAのなかに雇用をさえ確保していくことになったわけですから、このトーナメントは、いまのことばで言ってみれば、スポーツを通じたコミュニティビルディングの模範例とでも言えそうなものでもあるんですね。
──ははあ。なるほど。
かつ、このハーレムの事例は、シカゴやフィラデルフィアなどにも伝播して行くことになり、ある時期からは都市対抗で試合が行われたりもするようになります。というふうに考えてみますと、その後極端に商業化され、純然たるエンタメとみなされるようになった、とりわけアメリカのスポーツというものは、その基盤に、周縁化させられたマイノリティコミュニティの草の根のアクティビティがあったわけで、それは、根本のところで公共をめぐる社会活動であったという意味において「政治」的なものなんですね。
──そうなりますか。
前回に書いたように文化人類学者デイヴィッド・グレーバーが、「自分たちの問題を自分たちで解決する」ことを指して言うところの「政治」を、ここでは意味していますが、そもそもスポーツがそういうものとしてコミュニティで機能していたということであれば、スポーツは最初から政治的なんですね。
──ふむ。
ところが、80年代のレーガン政権以降、テレビ中継のグローバル化によってスポーツがグローバルエンタメ化していくなかで、こうした出自が一切見えなくなっていくんですね。特に日本では、マイケル・ジョーダン/シカゴ・ブルズの全盛期をもって、グローバル化の波に飲み込まれていくこととなりますが、ハーレムから遠い日本のお茶の間には、プレイの凄さとその快楽性ばかりが、エアジョーダンというプロダクトとセットで伝わってくることになり、ひたすら消費主義的な快楽のなかでそれが受容されてしまうことになってしまいます。だからといって、ジョーダンによって洗練の極点に達するプレイがどこから生まれてきたものなのか、おそらくアメリカの現場では、忘れられたことはないはずなんですね。
──そうなんですね。
これは、つい先日気づいたことなんですが、こうしたハーレムのストリートバスケのレガシーは、意外なところに流れついていまして、実は「B Corp」というアメリカ発祥の企業認証制度があるのですが、これが、ハーレムのバスケと関係があるんですね。
──B Corpというのは、パタゴニアやユニリーバといった環境や人権意識の高い企業に与えられる認証ですよね。
はい。最近ですとESG、SDGsといった文脈で改めて注目されている認証制度ですが、この認証を授与しているB Labという非営利組織は、実は、AND1というバスケットボールシューズをつくっていたベンチャーの創設者が、AND1を身売りしたあとにつくった組織なんです。
──へえ! 面白い!
『The B Corp Handbook』という本の冒頭には、このAND1というブランドのことが書かれていまして、この会社は、ハーレムなどで撮影されたストリートバスケのトリックプレイばかりを集めたミックステープを制作・配布していたことで知られていたと書かれています。加えて、社員に対するフェアな扱いなどでも知られていた企業だったとも書かれているのですが、企業というもののなかにいま一度、「社会性」や「公共性」といったものを埋め込み直そうという運動の中心にいるプレイヤーが、ハーレムのストリートバスケに源流をもっているというのは、非常に示唆的な話なんですね。
──ほんとですね。
この間、BLMなどの流れの中で、スポーツ選手が何かを発言するたびに、「スポーツに政治を持ち込むな」というような横槍が入ってきましたが、『#Rucker50』という作品を観て感じたのは、「スポーツに政治を持ち込むな」という言説は、実は「スポーツ」のことをいっているのではなくて、「経済」もしくは「ビジネス」に政治を持ち込むなと言っていたのだな、ということです。
──はあ。
つまり、スポーツは、いま見てきたように最初から政治的な活動としてあったわけです。ところが、メディア産業が、それを巨大エンタメへと仕立てあげていくなかで、そうした政治性を、いわば脱色するかたちで広めていくことになったおかげで、「スポーツが非政治的なものである」という錯覚が生まれるようになっていったわけですが、それはいわゆる新自由主義的なビジネススタイルが発動したイデオロギーであって、スポーツの特性ではないんですね。スポーツはいつだって政治的だったはずなんです。それを遠い極東のお茶の間でも見ることができるように中立化していったのは、むしろ娯楽産業の要請であるはずなのですが、その娯楽産業の根幹には、ローカルな「政治」がいまなお常に存在しているわけですから、それを消そう消そうとしても、表出してくるわけです。
──それは音楽でもまったく一緒ですね。
ですから、せっかくごきげんな気分でスポーツを見ていたところ、突然政治的なメッセージを見せられて不愉快になる人は、スポーツの中立性を侵害されたことではなく、むしろ新自由主義的な観点から、ビジネスというものが無政治的であると信じているところに水を差されたことにむしろ憤慨しているんですね。それは、ちょうど、新自由主義的な企業のあり方やそれを支えてきた価値観が、それこそESGといった観点や、「B Corp」のような考え方によって、水を差されて防御的になるのと完全に同じ心性のように思います。

──「ビジネスの中立性」は、もはや存在しない、ということは、前回でも指摘されていたことでした。前回は、それこそ、「ビジネスであれば、どんなクライアントからの仕事も受ける」という経営者の考えと、「世の中の害悪と思われる企業や組織とは仕事をしたくない」とする従業員との対立が問題として取り上げられていましたが、ことここに及ぶと、なんと言いますか、「ビジネスに善悪はない」「クライアントが喜べばそれでいいのだ」というような論理が、なんでこうまで世の中に深く根付いてのさばるようになってしまったのか、そのこと自体が不思議でなりませんよね。
ほんとですね。ちょうどいま、トランプ大統領のソーシャルメディアのアカウントが凍結されたことが話題になっていますが、ツイッターは社内において内部からの突き上げが、かなり強くあったことが報じられていますし、フェイスブックについては、社内のメッセージボードをなぜか会社側が一時封鎖したことも明かされていました。経営者にとっては「社内の声」は、もはやかつてないほど大きな影響力をもつステークホルダーになっていることが見えてきます。
──ほんとですね。あのザッカーバーグがついに強硬措置に出たのは驚きました。
そうですね。ここは本当に難しい判断だと思います。
──言論統制だ、という声が日本でも大きく上がっています。
そうですね。ツイッターもフェイスブックも、トランプのアカウントを凍結するにあたっては、それが大統領という公共性の高い人物のアカウントであることから特例的に「規約」の適用を免除してきたわけですし、十分に時間的な猶予を与えてきたということもありますので、これが突然起きたことではない、ということは前提として理解しておくべきでしょう。かつ、重要なのは、どちらの社も、トランプ大統領の発言内容に対して是非の判定をくだしているわけではない、という点かと思います。
──あ、そうですか。
そうだと思います。というのも、どちらの声明にも登場しているのは「リスク」ということばでして、これ以上放置しておくと社会的リスクが高い、という理由からの凍結であって、トランプが間違ったことや間違ったメッセージを発しているからという理由ではないんですね。
──そこは結構重要なことですね。
「修正第1条」というのは、やはりとても重いものでして、これだけ公共性の高いプラットホームであればなおさら、そこに投稿されたある言論を正しい、ある言論は間違いだ、と判定すること自体、原則許されないということは、おそらくジャック・ドーシーもマーク・ザッカーバーグも相当強くキモに命じていたはずです。ですから、ここにいたるまで強硬策を講じることはしてこなかったはずですし、それはとても正当なことだと思います。というのも、人には嘘をつく自由もありますから、何が真実か、そうでないかをある強大な主体が、それを一方的に抑圧することはできないのが原則です。
──ふむ。
ところが、世の中には、それが嘘であると困る類の嘘もあるわけですね。
──ははあ。
というのも、その嘘が、社会の安全を脅かすものになるものであった場合、そこにおいては、その嘘の重大性が測られなくてはならないという議論は、これは古くからあるものでして、100年前のアメリカの判事でアメリカのプラグマティズムの発展において非常に重要な役割を果たしたオリバー・ウェンデル・ホームズという人が言った名言がいまもよく参照されるようで、それはこういうものです。
「言論の自由を最も厳格に擁護したとしても、劇場でウソをついて火事だ!と叫び、パニックを起こす自由は誰にも保障されない(The most stringent protection of free speech would not protect a man in falsely shouting fire in a theatre and causing a panic.)」(「権利章典 – 言論の自由」アメリカンセンターJAPAN)
──なあるほど。
これは1919年のことばだそうですので、問題は100年前からまったく変わっていないとも言えますね。ツイッターやフェイスブックの措置は、おそらく、このことばを念頭に考えるべきものかなと思うのですが、要は、ここでの判断の基準は、嘘の内容そのものではなく、それが発せられる状況と、それがもたらしうる被害をめぐるリスク計算に基づいている、ということになるのではないかと思います。自分の見るところ、この判断の仕方は、とてもプラグマティックなものなのだろうと思います。
──プラグマティズムってそういうことなんですね。
宇野重規先生の解説によれば、プラグマティズムは、「人々の『信じようとする権利』を最大限に重視した」思想なのだそうです。
──へえ。
宇野先生は続けてこう解説しています。
「問題は、人間が行動するにあたって選びとった理念が正しいことを、神学的・形而上学的に論証することではない。すべての人間には、自分の選びとった理念を追求する権利があり、重要なのはむしろ、そのような理念が結果として何をもたらすかである。
(中略)人間は考えがあるから行動するのではなく、行動する必要があるから考えをもつと彼らは説いた。(中略)プラグマティストたちは、ある理念がそれ自体として真理であるかどうかには、ほとんど関心をもたなかった。というよりも、それを真理であると証明することは不可能であると考えていた。そうだとすれば、ある理念に基づいて行動し、その結果、期待された結果が得られたならば、さしあたり(傍点原著者)それを真理と呼んでもかまわない。彼らはそのように主張したのである。
重要なのはむしろ、各自が自らの理念をもつことに関する平等性と寛容性である」(宇野重規『民主主義のつくり方』2013、筑摩書房)

──面白いですね。読みながら、議会に突入した人たちの姿を思い浮かべてしまいますね。
もちろん彼らの行為は法的に査定されることにはなると思いますが、それでも、彼らの「理念」が正しいのか間違っているかどうかは問わないというのが、プラグマティズムの重要なところだと思うんですね。「やつらはアホだ」というのも、それを言う人間を詰るのも簡単なのですが、そこで発動された理念の真理性をいくら論じても泥仕合にしかならないわけですから。
──まあ、そうですよね。
随分昔にある本のなかで、「表現の自由と言うものは、あなたのためにあるのではなく、あなたと真反対の意見をもつ人のためにある」ということばを読んだことがありまして、それがアメリカのある判事のことばだと書いてあったのは覚えているのですが、おそらくきっと、これもホームズのことばなんじゃないかと思っています。プラグマティズムが説く「信じるようとする権利」と、それをめぐる「寛容性と平等性」をよく表しているように思います。
──いま聞くと、非常に身につまされることばですね。
これは、自分の好きなことばなんですよね。
──なんかわかる気がします。
というような話をですね、つい先日ある知人にしましたら、最近公開になった『ワンダーウーマン 1984』が、まさにそんな内容でしたよ、と言われました。
──あ、そうなんですか。
いや自分も観ていないからわからないのですが、そう言われるとちょっと観てみたくなりましたが、最近は映画館に行くのも何かと億劫ですし、いまは緊急事態宣言中ですしね。
このニュースレターの続きは、1分違いでお送りしている「Guides:#35 ムービーシアターの絶滅・下」でお読みいただけます。
若林恵(わかばやし・けい) 1971年生まれ。『WIRED』日本版編集長(2012〜17年)を務めたのち、2018年、黒鳥社を設立。NY在住のジャーナリスト 佐久間裕美子さんとともホストを務める「こんにちは未来」をはじめさまざまなポッドキャストをプロデュース。
🧑💻 世界各地で活躍する日本人VCが現地の声で伝える月イチのウェビナーシリーズの第3回は、シンガポール。1月28日(木)、Rebright Partnersの蛯原健さんをお招きして開催します。お申込みはこちらのフォームから。
🎧 月2回配信のPodcast。編集部の立ち話のほか、不定期でお送りするゲスト回の最新回では古川遥夏さんをお招きしています。Apple|Spotify
👀 Twitter、Facebookでも最新ニュースをお届け。
👇 のボタンから、このニュースレターをTwitter、Facebookでシェアできます。ニュースレターの転送もご自由に(転送された方へ! 登録はこちらからどうぞ)。