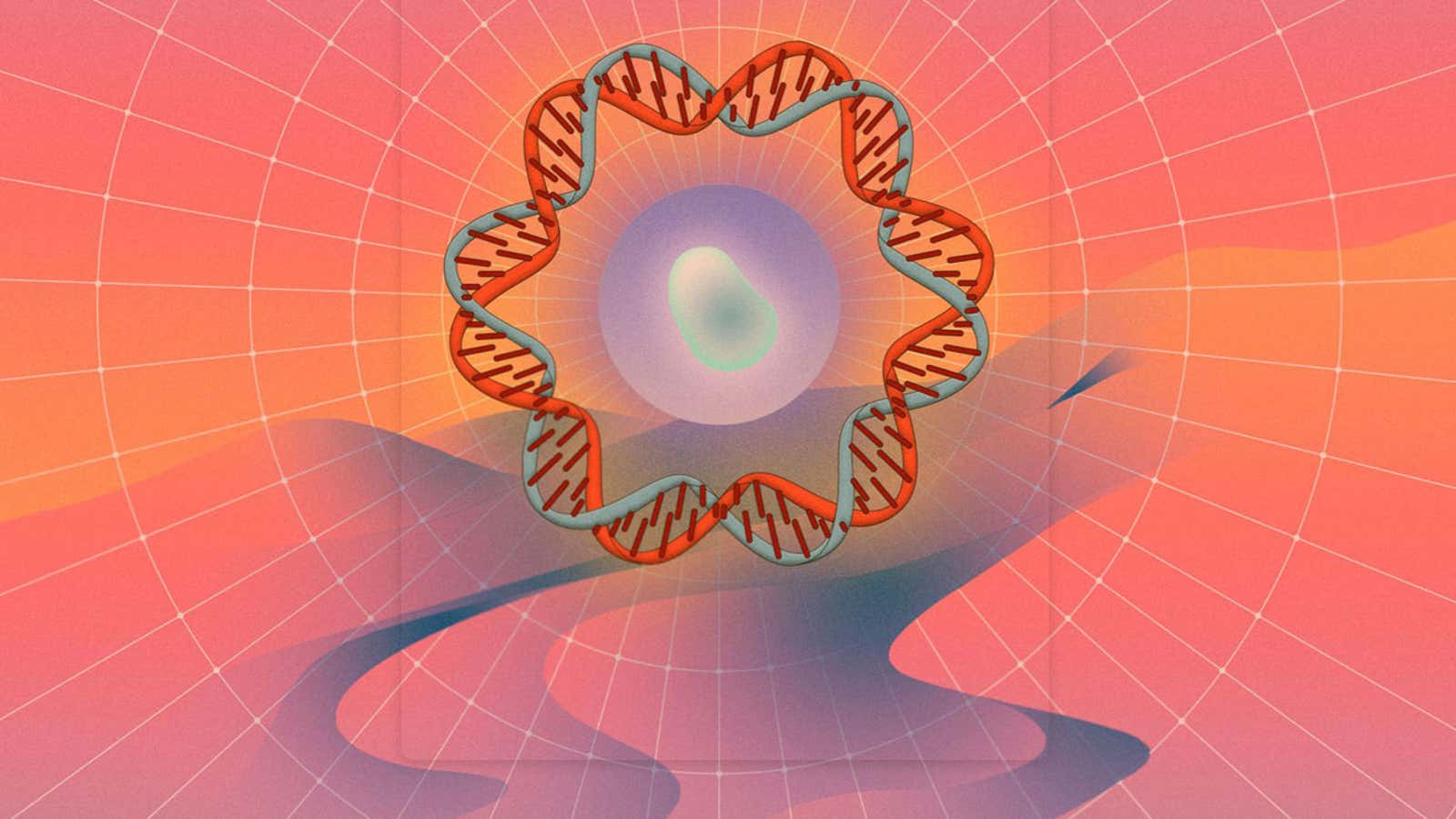A Guide to Guides
週刊だえん問答
世界がいま何に注目しどう論じているのか、米国版Quartzの特集〈Field Guides〉から1つをピックアップし、編集者の若林恵さんが解題する週末のニュースレター「だえん問答」。Quartzの原文(英語)と、原稿執筆の際に流していたプレイリストとあわせてお楽しみください。
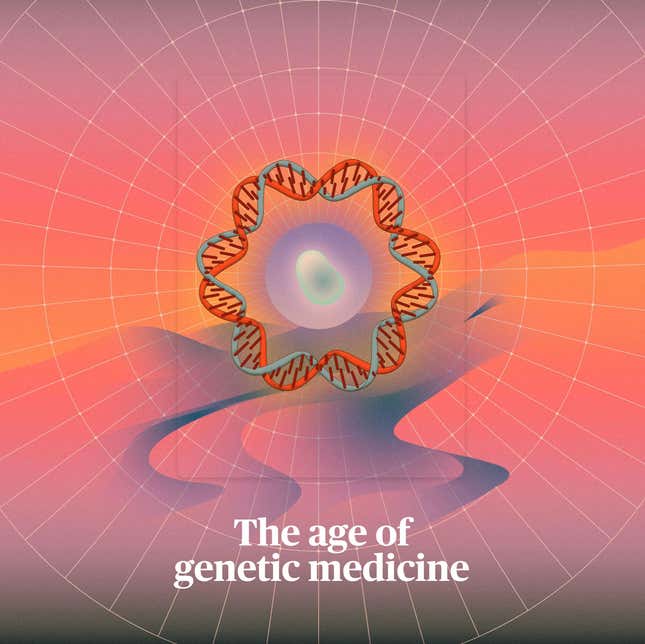
このニュースレターは、現在、期間限定で配信から24時間、ウェブ上で無料で閲覧できます。ニュースレター末尾のボタンからぜひシェアしてください。連載バックナンバーはこちらからお読みいただけます(会員限定)。
The age of genetic medicine
バイオテックの革新
──もう6月です。6月3日で、オリンピックまであと50日を切ったとのことです。
どうなるんでしょうね。この連載をまとめたものを7月には刊行したいと思っていまして、タイトルをどうしようか迷っています。
──前作が『週刊だえん問答 コロナの迷宮』でした。
当初は『週刊だえん問答 消えたオリンピック』としたかったのですが、なかなか消えませんのでどうしたものかずっと考えていたのですが、制作進行の都合からもそろそろ結論を出さないとでして、まだ変わるかもしれませんが、ひとまず『伝説のオリンピック』にしようかと思っています。
──開催前からすでに「伝説」ではありますからね(笑)。かつ、フレディ・マーキュリーへのオマージュ、ということでいいですか?
そうですね。
──オリンピック、ほんとにやるんでしょうかね。
つい昨日あたりはスポンサー企業が組織委員会に「延期」を進言・提案した、というニュースもありましたが、数カ月延ばしたところで、という気もしますね。ほとんどの人が感じていることだと思うのですが、現状の苛立ちというのは、オリンピック開催そのこと自体ではなく、オリンピックがあるせいで、政府なり自治体の意思決定やコミュニケーションが、捻じ曲げられているのではないか、という点にあると思うんです。しかも、「オリンピックがあるから他国よりもよほどちゃんとやらないと」という方向で準備に邁進してきたようにはとても見えず、むしろ、「オリンピックが問題なく開催できるように”見えるよう”に取り繕おう」という方向でしか考えていないように見えるので、多くの人が苛立っているわけですよね。
──そうですね。
国内のメディアを操作して、うまくやっているように見えるようにすることは、これまでの体制でできると踏んでいたとしても、ここに来て海外メディアによる批難もかなり高まっているように、そんなハリボテの「やってる感」は、すぐに見透かされることは最初からわかっていたじゃないですか。つまり、海外ではPCR検査の拡充が、コロナ対策の一丁目一番地とされていて、それをもって「コロナ対策」としているわけですよね。その実効性を疑って違うやり方をするのは、それはそれで特に悪いことだとは思わないのですが、それをもってして諸外国に対して日本がいかに安全なのかを説得するのは、相当の成果とエビデンスがない限り、よほど手間がかかるとしか思えませんよね。だったら、海外に足並みを揃えて、これだけPCR検査やって、これだけの感染者数に抑えていますよ、とやったほうが、普通に考えると説明コストも低いわけですよね。
──それをしてこなかった結果として、慌てて選手の検査拡充をするはめになっているわけですしね。
そもそも国際イベントなのですから、正体のよくわからない「日本モデル」をもって「安心安全」を確保すると言ったところで、それが、参加者する外国の方々が考える「安心安全」と合致していないのであれば、安心安全を確保したことになりませんよね。わたし自身は、科学的にみて、PCR検査が何よりも大事なのかどうかという点については、正直よくわからないところがあるのですが、オリンピックをそこまでどうしてもやりたい立場であったなら、どれだけ結果が出せるものだとしても、日本独自のやり方にこだわるような道は取らないような気もするんですよね。というのも、有り体に言ってしまえば、「ちゃんとやってる感」を出そうと思うなら、そっちのほうが、ずっと説得的に見えるはずだからです。それは非常に日和った考え方ですが、世界的なイベントが控えている以上、世界的なスタンダードにあわせないで物事を進めても、無駄に労力がかかるだけとしか思えないんですよね。

──なるほど。
日本は国際社会において、なんとか独自性を出そうと、やたらとコンセプトだけ出すんですよね。みんなが「スマートシティ」というお題を議論しているところ、自分たちだけ「ソサエティ5.0」と言ってみたりするわけですね。で、その中身が何なのかというと、特に何かがあるわけでもなくて、普通にみんなが議論しているところで、同じことばを使って議論したらいいじゃん、という程度のことなんですね。
──なんとなくわかります。
とはいえ、スマートシティについていえば、日本は欧州型とも中国型ともアメリカ型とも違うコンセプトを打ち出せる可能性のある、非常に面白いポジションにあるのは、そうだと思うんです。さりながら、国際的な規格やルールづくりという場面において、なかなか自分たちのアイデアをそのなかに押し込むことができず、結局自分たちにとって必ずしも有利ではないルールメイクをされてしまう、というところに苦慮してきた焦りもあるのもわかるはわかるんです。
──国際柔道などでも、いつも日本に不利なかたちでルール変更が行われる、といったボヤきは聞きますね。
同じことだと思うんです。独自のコンセプトを打ち出して、自分たちがルールメイクにおけるイニシアティブを取りたいという気持ちはわからなくもないにせよ、さりとて国際機関が決めたルールに抗って、自分たちだけで「新しい柔道をつくるんだ」と、新しい連盟なりを立ち上げたところで、それはそれでイバラの道でしょうから、なかなかツライところですよね。
──プロレスならありえそうですけどね(笑)。
そうやって見ると、中国はやはり周到でして、国際的なルールメイクのところでどんどん声を大きくしていきたいという野心に従って、どんどん影響力を強めているんですね。例えば、中国問題の専門家である遠藤誉先生が書かれた記事「トランプ『WHO拠出金停止』、習近平『高笑い』──アフターコロナの世界新秩序を狙う中国」に、こんな記載があります。
「現在、国連には15の専門組織(国連憲章第57条,第63条に基づき国連との間に連携協定を有し,国連と緊密な連携を保っている国際機関)があるが、その内の4つの専門機関の長は「中国人」が占めている。その4つの機関名と職位、中国人の名前および就任時期を書くと以下のようになる。
- UNIDO(国際連合工業開発機関)事務局長:李勇 (2013年6月~)
- ITU(国際電気通信連合)事務総局長:趙厚麟(2014年10月~)
- ICAO(国際民間航空機関)事務局長:柳芳(2015年3月~)
- FAO 国際連合食糧農業機関 事務局長:屈冬玉(2019年8月~)」
──なるほど。決定権のあるポジションに人員を配置していっているわけですね。
はい、で、ここからすごいんですよ。
──ほお。
「それだけではない。国連専門機関のトップ以外の要職や、国連傘下の関連国際組織あるいはその周辺組織にも、以下のような中国人が着任している。
- WIPO(世界知的所有権機関)事務次長:王彬頴(2008年12月~)
- IMF(国際通貨基金)事務局長:林建海(2012年3月~2020年4月)
- WTO(世界貿易機関)事務局次長:易小準(2013年8月~)
- WB(世界銀行)常務副総裁兼最高総務責任者(CAO):楊少林(2016年1月~)
- WHO(世界保健機関)事務局長補佐:任明輝(2016年1月~)
- AIIB(アジアインフラ投資銀行)行長(総裁):金立群(2016年1月~)
- IOC(国際オリンピック委員会)副会長;于再清(2016年8月~)
- IMF(国際通貨基金)副専務理事:張涛(2016年8月~)
- WMO(世界気象機関)事務次長:張文建(2016年9月~)
- UN(国際連合 国際連合経済社会局)事務次長:劉振民(2017年6月~)
- ADB(アジア開発銀行)副総裁:陳詩新(2018年12月~)
- UN(国際連合=国連 事務次長補佐):徐浩良(2019年9月~)
こんなに圧倒的な数の中国人が、国際組織の要職を占拠している。
これはチャイナ・マネーで買収された(という言葉が悪ければ『心を奪われた』)人々によって『選挙で公平に』選ばれているメンバーたちだ。戦略的な中国は、着々と水面下で『仕事』をしてきた。
特に注目すべきは、今般問題になっているWHOは事務局長のテドロスだけではなく『WHO(世界保健機関)事務局長補佐:任明輝(2016年1月~)』にあるように、事務局長補佐の一人は中国人自身なのだ。WHOは中国によって牛耳られていると言っても過言ではない」
──うげげ。IOCの副会長まで。水面下で着々と仕事してきた感、ハンパないですね。
そうなんですよね。昨年はコロナ対応において、WHOが中国に日和っているとして、トランプ大統領が盛んに非難をし、日本でもテドロス事務局長は「親中」との批判が持ち上がりましたが、遠藤先生の指摘によれば、まったく同じことがIOCとの関係でも起きているわけですね。「バッハ会長らの日本侮辱発言の裏に習近平との緊密さ」と題されたコラムで、こう断言しています。
「IOCの裏には中国があり、IOCにとっては日本国民の命などはどうでもいいことなのである。金が入り、権威を保つことができればそれでいい」

──ほんとに困ったもんですね。
ですね。そういえば、IOCが、オリンピックの開催都市を決める選考において、候補都市にどういった条件を課しているのかを明らかにした腹を抱えて笑ってしまうほどに面白いニュースをつい先日を見ましたので、それ紹介させていただいていいですか?
──あ、ぜひ。
これは2014年に『Slate』というメディアに掲載されたものなのですが、タイトルはこういうものです。「ノルウェーを冬季五輪から辞退させた、噴飯もののIOCの要求」(The IOC Demands That Helped Push Norway Out of Winter Olympic Bidding Are Hilarious)。
──面白そう。
オスロは、2022年の冬季五輪の開催地に、北京とカザフスタンのアルマティと並んで立候補していたのですが、IOCがローカルの組織員会や開催都市に対して要求していた「開催条件」が、ノルウェーのメディアにすっぱ抜かれ、それがあまりにもくだらないものだったので、国民が爆笑+激怒した結果、入札から降りたという顛末なのですが、Slateは、IOCを「詐欺師と天性の官僚が運営する悪名高きおバカ組織」(notoriously ridiculous organization run by grifters and hereditary aristocrats)とディスり、その要求を「ディーバもどき」(diva-like demands)とくさしています。
──わはは。
で、IOCの要求はこちらになります。
- 開会式前に国王との面会を要求。開会式後にはカクテルパーティ。飲食代は王室か地元の組織員会がもつこと。
──え、マジすか? それを書面で要求しているんですか?
らしいですよ。続いてこうです。
- すべての道路にIOCメンバーが移動するための専用レーンを用意すること。このレーンは市民や公共交通の利用は不可。
──ひ、ひどい……。
- IOCメンバーが到着する際には地元組織員会のボスとホテルの代表が部屋で歓迎をすること。部屋には季節のフルーツとケーキを用意。
- ホテルのバーは『超深夜』(extra late)まで営業時間を延長し、ミニバーはコカ・コーラ社製品がストックされていること。
- IOC会長の到着時には式典をもって出迎えること。
- IOCメンバーの空港の出入りにあたっては特別な出入り口を用意すること。
- IOCメンバーのホテル到着の際には笑顔で迎え入れること。
- 開会式・閉会式中には、酒が完全に補充されたバーが用意されていること。競技中のスタジアムラウンジはビールとワインで大丈夫。
- 会議室の温度は常に摂氏20度に保たれていること。
- ラウンジや競技会場で提供される温かい料理を一定の時間で入れ替えること。なぜならIOCメンバーは同じラウンジで何度も食事をしなくてはならないリスクがあるからだ。
──ビヨンセかよ!って、ほんとに呆れ果てますね。これはオスロ市民は辞退を心から喜んでいるでしょうね。ほんとにホテルオークラさんが気の毒としか言いようがないです。
せっかくの「おもてなし」の相手がこれだとすると、滝川クリステルさんにすら同情したくなってきます。

──ほんとに。ところで、今回の特集って「遺伝子創薬の時代」(The age of genetic medicine)というものなのですが、関係ある話ですか?
いまのIOCのディーバたち話は関係ないですね(笑)。あまりに面白いので、公共の益のために一応出しておこうということでしたが、その前のルールメイキングの話は、もしかしたら関係ある話になるかもしれません。
──今回の特集は、特集といっても2本のストーリーしかなく、ひとつは「COVID-19がもたらした創薬の新時代」(Covid-19 vaccines have triggered the next wave of pharmaceuticals)、もうひとつが「遺伝子創薬を変える20社」(20 companies changing genetic medicine)というリストです。
もちろん、これは興味深いお題でして、今後の創薬のあり方を変えていく潮流だと思うのですが、技術的なことをわたくしはさっぱりですので、どうしても文化的な話になってしまいそうです。そうした観点から見ると「COVID-19がもたらした創薬の新時代」の記事にあった「創薬の歴史」をめぐる年譜は面白いなと思いました。そのなかで触れられていますが、いま「メッセンジャーRNA」を用いた創薬という流れは、創薬の歴史で言いますと「第4波」(fourth wave)ということになっていまして、そうだとすると、つい直近までの時代は「第3波」つまり「サードウェイブ」のなかにあったということになります。

──コーヒーみたいですね。
創薬における「ファーストウェーブ」はいつかと言いますと、記事は18〜19世紀に、ヨーロッパで製薬会社が誕生しはじめたころをさしているそうです。グラクソ・スミスクラインの親会社に当たるPlough Court Pharmacyが1715年創業、おなじみのファイザーが1849年、ブリストル マイヤーズ スクイブが1887年だそうでして、このころの創薬は、植物から成分を取り出して薬にするという、いまから見ますと非常に素朴なものでした。
──ふむ。
その後、バイエルがアスピリンを1900年代に発売を開始したほか、1929年にペニシリンの発見などがあるのですが、第2波、つまり「セカンドウェーブ」が来るのは1970年代まで待たなくてはなりません。1970年代になると、いわゆる「ブロックバスタードラッグ」というものの開発に製薬会社が注力しだすようになります。バリウムや避妊薬といったものがこの時期生まれ、化学療法が広まります。この時代に生まれた薬は「低分子(小分子)化合物」を用いたものだと言います。この辺りは、わたしはよくわかりませんが。
──同じくです。
で、同じく70年代に新しい創薬の考え方が生まれまして、これが抗生物質を用いたもので、カリフォルニア州バークレーに初のバイオテック企業シータス(Cetus)が生まれています。この会社は、のちに大手のノバルティスに買収されていますが、シータスの創業を皮切りに、76年にジェネンテック(Genentech)、80年にアムジェン(Amgen) 、81年にジェンザイム(Genzyme)といったバイオテック企業が生まれています。これが「サードウェイブ」にあたるのですが、こうした企業が、いまやってきている第4波の礎を築いたとされています。

──言ってみればスタートアップですよね。
そうなんですね。今回の対コロナのワクチンをめぐる情報のなかでも、「ファイザー」や「ジョンソン&ジョンソン」といった名前は、すでに見聞きしていたものですが、「モデルナ」(Moderna)なんていう会社なんて聞いたこともなかったわけですよね。
──ですよね。なんだかみんな、さも知っているような感じで「モデルナ、モデルナ」と言っているので、「その会社、有名なん?」って聞くのも憚られる感じでしたが、普通知らないですよね?
知らないと思いますよ。わたしも去年初めて知ったのですが、調べてみたら2010年創業の会社ですから、ほんとうにスタートアップなんですよね。『TIME』が、ファイザーとともにワクチンの開発を行なったバイオンテック(BioNtech)とともにモデルナのワクチン開発のバックストーリーを紹介していますが、2020年1月の段階でモデルナは20のワクチンのプロジェクトを動かしていたものの、まだ最終テストにいたっているものはひとつもなかったそうです。
──そうなんですね。
モデルナは、スイス人のStéphane Bancelと、ベイルート生まれのアルメニア人のNoubar Afeyanのふたりで創業された会社で、2020年1月に武漢で起きている状況を耳にしたBancelがAfeyanに「ワクチン開発をやろう」と言って、プロジェクトに乗り出したことが記事に明かされています。そこからアメリカのCDCのアンソニー・ファウチに掛け合って経済的な支援も取り付けたとされています。
──めちゃアジャイルですね。
これはバイオンテックとファイザーの場合も同じでして、2020年1月に、中国の新型ウィルスに関する論文を読んだバイオンテックのファウンダーの指示で、社内で「クラッシュプロジェクト」(突貫計画)を立てて、そこで一定の成果が見えたところで、ファイザーの担当者に電話をし一緒にワクチン開発をやらないかと持ちかけたそうなんです。
──素早い。
その電話で、ファイザーの担当は「まさに同じ提案をしようと電話をかけようと思っていたところ」と答えたそうで、3月に両者間で契約が結ばれたそうです。
──面白いストーリーですね。ワクワクしますね。
つまり、コロナワクチンの開発の物語は、言ってみればバイオテック・スタートアップの物語でもあるということなんですね。ちなみに、バイオンテックの創業者は、Ugur SahinとOzlem Tureciという夫婦でして、ふたりともドイツのトルコ系移民の家系だそうですから、モデルナとバイオンテックの物語は、移民とイノベーションをめぐるものでもあったりするわけです。

──いいですね。
今回の特集で個人的に注目したのは、このあたりのことでして、要は大企業ドリブンな「開発」が、すでにして形が変わってしまっているということなんですね。これは先ほど見たように、創薬の世界でもそうで、第3波の登場から、これまでの産業構造が変容し始めていまして、第4波にいたると、そちらがむしろ主流になりつつあるわけです。こうした流れについて、今回の特集は、そこまで深くは突っ込んではいないのですが、こんな言い方で、その転換を語っています。
「(サードウェイブの新たな企業は)既存の製薬大手と比べると、規模ははるかに小さくアジャイルで、ブロックバスタードラッグを生み出すことではなく、さまざまな治療薬を開発することに注力している」
──モデルナやバイオンテックは、まさにそうした企業ですね。
はい。この記事には『Nature』に掲載された非常に面白い記事へのリンクが貼られていまして、この記事のなかに、いまお話したような移行の経緯が説明されています。記事は「市場化された科学は信用できるのか?」(Can marketplace science be trusted?)というタイトルで、歴史家のPaul Lucierという方が書いたものですが、主に科学の信憑性とビジネスの危うい関係性にフォーカスしているのですが、科学の進展と、その財政的な資源の出どころの時代ごとの変化を概観していまして、とても面白いものです。
──へえ。
論考は、1873年に起きたある事件から始まっていまして、これは、ある科学者が企業からお金をもらっていたことが判明したことで、「米国科学アカデミー」(NAS/US National Academy of Sciences)内部で、その科学者を除名すべきか否かで争議が持ち上がったというものです。
──へえ。科学者っていうのは、アマチュアじゃないといけないというコンセンサスだったんですね。
ところが、問題とされたその科学者は「企業こそ科学が必要だ」と猛然と反論し、その結果除名を逃れるんです。すでにNASは企業のファンディングなしでは生き残れないことも大きな理由でしたが、いずれにせよ、このことをきっかけに、ビジネスセクターと科学の関係というのは、どんどん深まっていくこととなります。
──はい。
記事によりますと、最初に一般化した関わり方は「コンサルタント」モデルでして、企業に対して科学者が助言者やアドバイザーの立場として関わるというもので、これは19世紀には一般的なかたちだったそうです。それが20世紀に入りますと、企業による「インダストリアル・ラボ」というモデルが生まれ、そこでお給料をもらいながら研究にあたる新しいタイプの科学者が生まれます。こうした「R&D」ラボの嚆矢となったのは、言わずと知れたエジソンのラボでして、ここでの研究成果がゼネラル・エレクトリック(GE)に電球市場における独占に近い優位をもたらしたことから、ほかの企業もマネをするようになります。エジソン/GEにインスパイアされてR&Dラボを設立した企業には、以下があるそうです。
- デュポン (1903年設立)
- ウェスティングハウス・エレクトリック(1904年設立)
- アメリカン・テレフォン&テレグラフ(AT&T/1909年設立)
- イーストマン・コダック(1912年設立)
──面白い。
こうした企業ラボは、技術ドリブンなコンシューマープロダクトを生み出すようになり、また同時にノーベル賞受賞者なども生み出すようになっていきます。企業科学者・産業研究者で初めてノーベル賞を受賞したのは、カール・ボッシュとフリードリッヒ・ベルギウスのふたりのドイツ人で、1931年に化学賞を手にしたそうです。
──ふむ。
そこから時代は第2次大戦へと突入していくことになるのですが、それを受けて、科学のドライバーが「軍=ミリタリー」に移行していくと記事は書いていまして、戦時中、ヴァネヴァー・ブッシュが主導した「Office of Scientific Research and Development」は、2,300件もの研究を発注していまして、その受け手のうち140がアカデミックな機関であったのに対し、企業は320あったとしています。
──戦時体制ですね。
はい。ただヴァネヴァー・ブッシュは、戦争後もそうした体制が必要であると考え、冷戦下における科学研究と企業R&Dに関する政策をルーズベルト大統領に提言します。それが「Science – The Endless Frontier」というレポートですが、このレポートにおいて提出されたアイデアの根底にあったのは、基礎科学がイノベーションの基本にあって、それがベルトコンベアのようなかたちで、発明・開発、生産へと至るという流れでして、これは俗に「リニア・モデル」と呼ばれる考え方だそうです。

──ほほう。つまり、基礎科学がすべての源だ、とするわけですね。
はい。ですから、こうした考えのなか、企業ラボは、応用科学ではなく、基礎研究にどんどん携わるようになっていったと記事は明かしています。これは、財政的なバックについていた軍の意向が強く働いていたせいでもありますが、こうした基礎研究ラボの代表格としてベル研究所、IBM、ウェスティングハウス、デュポン、RCA、ゼロックスパロアルト研究所(現パロアルト研究所)などが挙げられています。
──ベル研究所にゼロックスのパロアルト研究所といえば、のちのITの先駆となった研究所ですね。
はい。こうしたラボは、「第2次産業革命」とまで謳われ、大きな成果は挙げたのですが、70年代のオイルショックから、80年代のグローバル経済化などの影響によって、これらのラボを支えてきたアメリカ企業が、経済競争から遅れを取り始めるようになってきてしまいまして、80年代以降、ラボを縮小したり、売却したりするようになっていきます。つまり、ビジネスのお荷物になってしまったということですね。
──基礎研究ばっかりやっていても儲からん、と。
はい。そうした状況のもと、先の「リニア・モデル」も放擲されるようになり、その代わりに注目を集めるようになってきたのが、自前のR&Dラボを持たずにビジネスのメインストリームに躍り出てきたインテル、マイクロソフト、アップル、サン・マイクロシステムズ、シスコシステムズといった企業だったというわけです。このうちマイクロソフトはのちに、この世代の企業としては最大のリサーチラボを設立しますが、そのミッションは「基礎研究」ではなく「イノベーション」にありまして、もちろん「科学」を軽視するということではないのですが、それは社内ではなく、むしろ外部で行われるのが望ましいと考えるようになっていると記事は解説しています。
──面白い。「イノベーション」の対義語は「基礎科学」だったんですね。
ここで起きた転換が実は大きいんだと思うんですね。そして、この転換による最も目覚ましい成果が「バイオテック」だったと記事は書いています。
「バイオテックの勃興は、新しいビジネスプラン(アントレプレー科学者とベンチャーキャピタリストがパートナーとなって研究成果を販売)とイノベーションの新しいモデルの台頭を表していた。これによって産業は、ひとつの主体が閉鎖した内部で行うリサーチから、多数の開かれたリサーチ、あるいはオープンソースのものへとシフトした。このモデルにおいて、アカデミック・アントレプレナー、商業化された大学、グローバルなリサーチ機関、そして数知れない小さなスタートアップが基礎科学やIPを提供し、大手企業は、それを製品として開発し商用化することを担うようになった」
──ああ、面白いですね。バイオンテックやモデルナの事例というのは、まさにこのモデルが花開いたものだと言えるわけですね。
ちなみに、こうしたモデルが基本的には「第3次産業革命」と呼ばれるものだそうでして、記事は、このモデルは、19世紀のコンサルタントモデルへの先祖返りとも言えるとしていますが、とはいえ、このモデルが果たして、この論考の主旨であった、お金と科学の問題を解決するものではないと釘をさしています。
──基礎研究やIPを、サードパーティからどんどん買おう、というモデルですもんね。商業化がより進んだモデルとも言えそうです。
そうですね。この先にいったいどういう問題が待っているのかは、目を凝らしていないといけないのかもしれません。

──とはいえ、こうやって概説されると、日本がなぜ「ワクチン敗戦」と呼ばれる事態に陥ったのか、ちょっと見えてくるような気もします。
日本の創薬・製薬が、現在どんな状況で、どういう取り組みをしているのか、よくわかりませんが、少し関わりのあるメーカー企業のR&D部門の所在なさを見るにつけ、企業としても、「これをどうしたものか」を考えあぐねている感じはとてもします。製薬会社なども、もしかしたら似たようなことなのかもしれません。
──あと、無理やり話をこじつけるわけでもないのですが、科学者とビジネスセクターとの関わりという話は、スポーツ選手とビジネスセクターとの関わりとも重なりあう部分があるようにも感じました。
それは面白い指摘ですね。先ほど「科学者はアマチュアだったんですね」というコメントがありましたが、言われてみればスポーツ選手も同じで、特にオリンピアンと呼ばれる人たちは「アマチュア」であることが、強く重視されていたわけですよね。それが、ちょうど80〜90年代を境に、プロ化が進む流れは、あるいは他の産業とも近いのかもしれませんし、そのアナロジーを現在に当てはめるのであれば、スポーツ選手は、科学者同様に「アントレプレナー化」して、自分のIPをそれこそ大会主催者や企業に売っていく「スポーツアントレプレナー」へとビジネスモデルがシフトしているということになるんでしょうね。例えばJay-Zが設立したRoc Nationのスポーツマネジメント部門などは、そうしたモデルの尖兵と言えるのかもしれませんし、フレンチオープンを辞退した、大坂なおみ選手の動きとテニス連盟との問題も、そうやって考えると、新旧のビジネスモデルの間で起きている軋轢に起因していると見ることもできそうです。
──面白い綱引きですよね。
大手はすでにして自社R&Dができず、アカデミック・アントレプレーのイノベーションをあてにするしかない状況において、サービスやプロダクトの主導権は一体どちらにあるんだ、という綱引きですよね。大坂なおみ選手にしてみれば、「いったい誰のおかげでメシ食えてると思ってるの?」と思っているでしょうし、一方の連盟サイドも、おそらくそう思っていると思うのですが、でもテニス連盟などが想定している旧来ビジネスのほうが圧倒的に分は悪いと思いますよ。
──そうですか。
と、思いますよ。だって、「だれのおかげでメシ食ってんだ」と言ってふんぞり返っている旧ビジネス側の人たちは、自分が泊まるホテルのバーの営業時間とか部屋の温度とかフルーツにしか興味ないんですよ(笑)。
──あ、ちゃんとつながりました(笑)。
おあとがよろしいようで。
若林恵(わかばやし・けい) 1971年生まれ。『WIRED』日本版編集長(2012〜17年)を務めたのち、2018年、黒鳥社設立。責任編集を務めたデジタルガバメントについてのハンドブック「GDX:行政府における理念と実践」の序文がこちらで公開されています。
🐦 Quartz JapanのニュースレターをTwitterでシェアいただいた方を対象に、ステッカーとご友人招待用クーポンをプレゼント! 対象の方のうち、ご希望の方はこちらのフォームにご記入ください。
🎧 Podcastでは月2回配信しています。Apple|Spotify
👀 Twitter、Facebookでも最新ニュースをお届け。
👇 のボタンから、このニュースレターをTwitter、Facebookでシェアできます。ニュースレターの転送もご自由に(転送された方へ! 登録はこちらからどうぞ)。