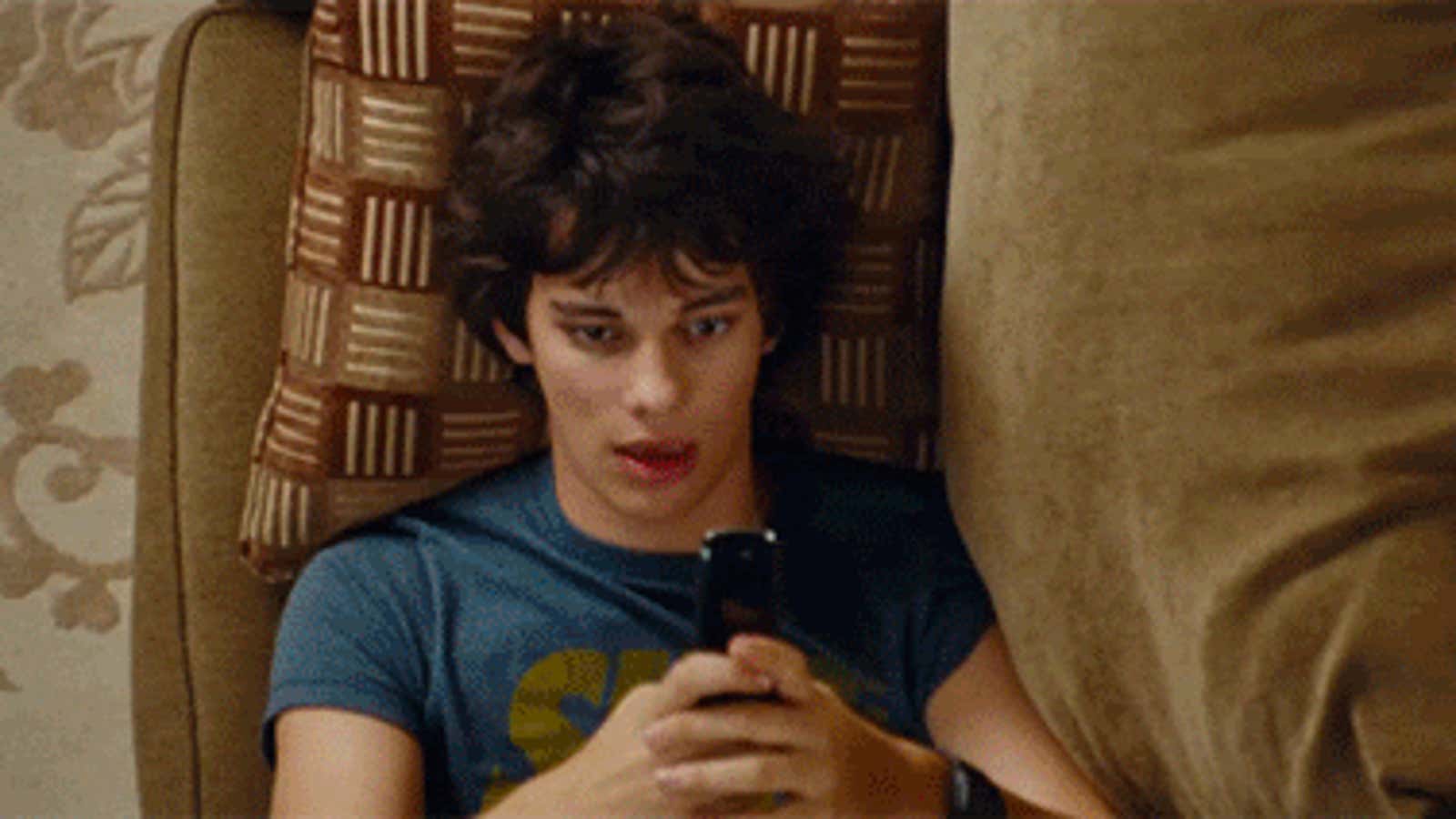A Guide to Guides
週刊だえん問答
世界がいま何に注目しどう論じているのか、米国版Quartzが取り上げている「世界の論点」を1つピックアップし、編集者・若林恵さんが「架空対談」形式で解題する週末ニュースレター。毎週更新している本連載のためのプレイリスト(Apple Music)もご一緒にどうぞ。
Super apps: What you need to know
アジアンテックの起源
──お疲れさまです。調子いかがですか?
昨日寝違えたのか、首が痛くて、微妙につらいです。
──えー。大丈夫ですか。ただでさえ不摂生しているんですから、気をつけた方がいいですよ。
ほんとですね。今年は、体調に不安を抱えることに、どうもなりそうです。
──病院嫌いですしね。
はい。まあ、こんなところでわたしの不健康自慢をしても仕方ありませんので、ここまでにしておきますが、先週、語り忘れたことがありますので、そこから今回はお話を始められたらと思っています。
──ほう。先週は、タングステンブームという謎の事象についての話題でしたが、語り忘れたこととはなんでしょう。
まさに鉱物資源と権力というものに関わる話で、おそらく何の役にも立たない話かと思いますが、日本についての話をし忘れたな、と思っていまして。
──日本における鉱物資源の権力の関係ということですか。
はい。
──パッと思い浮かぶものがないですが、何なんでしょう。
これは、水銀なんですね。
──あ。そうか。へえ。
日本の伝統色として馴染み深い「朱」の色は、水銀から取り出したものでして、これは特に神社の鳥居などで使われていることからもわかるように、極めてパワフルな色なんですね。
──宗教権力と結びついている、と。
はい。これは、わたしが20年以上も前に『太陽』という雑誌の編集部に在籍していた際に、「四国八十八ヶ所遍路」をテーマにした特集をした際に、松岡正剛さんから教わった話で、いまだに印象に残っているものです。
──遍路と水銀って、関係がよくわかりません。
ですよね。この話をするためには、まずその前提として四国八十八ヶ所をめぐるお遍路がどういうものなのか、を知っておく必要がありますが、ことを簡単に済ませるために、まずはお遍路の歴史を「松山観光コンベンション協会」というところのウェブサイトから拾ってみたいと思います。このサイトの信憑性については、よくわかりませんが、ひとまず「四国八十八ヶ所 歴史」でgoogle検索したところ、一番トップに表示されたのがこれでした。オフィシャルな見解として一般的なものの代表として理解いただくのがいいかと思います。
──はい。
その記載はこうです。
四国八十八ヶ所は、弘仁六年(西暦815年)に真言宗の開祖である弘法大師・空海によって開創されたと伝えられています。四国遍路がいつ頃から、何をきっかけにはじまったのか定説はありませんが、弘法大師の遺跡を遍歴した弟子の真済であるか、または自らの悪行を反省し、一目弘法大師にお目にかかり懺悔したい一心で四国を巡った伊予の長者・衛門三郎が最初であると言い伝えられています。
元来、四国遍路は修行僧が行うものとされていたようですが、弘法大師に対する信仰が高まった江戸時代中期頃より、日本全国の人々が四国を訪れ、弘法大師ゆかりの地を巡るようになりました。
──そうか。弘法大師=空海が関係するんでしたね。
はい。簡単に言いますと、「空海が遍歴した四国の土地土地を辿りなおす」というのが「お遍路」というものの基本的なコンセプトとなっているわけですが、松岡先生がまず注意を向けられていたのは、「じゃあ、空海はいったい何のために、そうやってさまざまな土地を遍歴していたのか」という点でして、松岡先生は、空海は水銀の鉱脈を探していたのではないか、とおっしゃるんですね。
──ほお。
空海が訪ねたと言われるいたるところで、数多く残っている言い伝えは、空海が井戸を掘り当てたというものでして、空海の井戸伝説というのは、本当に数多くあります。空海は唐から土木技術を持ち帰ったことでも知られていまして、なかでも農業用の貯水池として空海が改修を施した「満濃池」は、現在でも農水省のウェブサイトにまで記載されるなど、レジェンダリーな偉業として語り継がれています。
──へえ。
ですから、最新の土木技術をもった先端エンジニアとして空海を見るという見立ては間違いではないとは思うのですが、とはいえ、それだけでは一体なぜ、空海があちこちで井戸ほりをしていたかの説明にはならないわけです。もちろん、それによって衆生を救うことがあったとは思いますので、それはそれで大事なことだったかもしれませんが、ただの福祉事業だったのかというと、そうでもなさそうだ、と。
──ふむ。
そこで弘法大師と水銀の関係に着目すると、弘法大師が、自身が打ち立てた真言密教の総本山として最終的に選んだ場所はどういう場所であったかが問題になってくるんです。
──それって、高野山のことですよね。
はい。空海の真言密教を打ち立てるにあたって、高野山を選ぶことになるわけですが、そこが誰の管理下にも置かれていない無垢な土地だったのかというとそうではなく、当然、周辺地域にはその土地の有力者もいましたし、先行する「神様」もいたりしたわけです。
──ああ、そうか。
伝説上では、空海は高野山を拓くにあたって、ふたりの神様の道案内を得ていたとされていまして、ひとりが高野明神、もうひとりが丹生明神だったと言われています。つまり、地元に元々いた神様──これはすなわちその神様を崇めていたローカルな有力者を意味しますが──と空海は、ある時点で手を結んだか、あるいは配下に収めることで、高野山を自分のものにすることができたと見ることができるわけですね。

──そう聞くと、新しい企業に古い地場の企業が買収されていくような話にも聞こえて、なかなかダイナミックですね。
はい、まさにそういう観点から面白いんですよね。折しも、空海の生きた平安時代は、日本が統一的な国家としてかたちづくられていく途上にある時代でして、それと同時にローカルな神さまがあちこちにいて、土地土地の部族が個々に自分たちの神様を信仰している状況から脱しながら仏教へと収斂していくようなことが進行していまして、その過程で起きた新旧の価値体系のハイブリッド化は「神仏習合」の名で呼ばれることとなります。
──日本史の授業で習いましたね。
日本における「神仏習合」の歴史において、空海は、とても重要な役割を果たしてと言われていますが、それは真言密教が、日本の神道と強い親和性が見られるからなのですが、仏教学者の末木文美士さんは「空海の宗教理論は日本の宗教観を理論化したものであると言える」とさえ指摘している、と、あるブログでは語られています。
──ローカライゼーションですね。
はい。もちろん空海は教理においてもそうしたローカライゼーションを行っていったのですが、水銀との関係に戻しますと、そうしたローカライゼーションは、政治的なものだったとも言えるわけですね。つまり、既存の旧勢力を取り込みながら、新興勢力である自分の圏域を拡張していく上で、水銀というものが権力の源泉になることを、空海は見て取っていたのではないか、というのがわたしなりが理解した松岡先生の話の概略なのですが、そもそもなぜ水銀が権力の源泉になるかというと、水銀が「朱色」の原材料だからです。
──言われてみると朱色は神社には欠かせない色ですね。水銀から取れるんですね。
日本で水銀から朱を採ることは縄文時代から行われてきたそうで、日本ではそれをずっと「丹生」(にう)と呼んできました。万葉集に見られる「青丹よし」という枕詞にある、「丹」は水銀(朱沙)から採れた朱色のことを指しているのではないか、と『古代の朱』という本には書かれています。
──へえ。
話を思い切りすっ飛ばして空海のところに繋げますと、先に高野山を開山した際に空海が手を結んだのが、まさに丹生明神という神様で、これはお察しの通り、水銀の神さま、しかも女神なんですね。日本の水銀文化研究の第一人者である松田壽男先生の『古代の朱』という本は、ニホツヒメという名のこの女神と、それを崇めていた丹生族というトライブの動きを丹念に追い、それが関西はもとより関東、東北にまでその痕跡があるとしていますが、松田先生は、この丹生族が集団移住を繰り返すことで「植民的進出」を行っていたのではないか、との仮説を語られています。
要は、それなりに大きな勢力をもっていたトライブなのではないかということですが、とすると、空海はその有力トライブと手を組むことで、真言密教の勢力拡大を目論んだとも考えられます。
──なるほど。それなりに影響力のローカル企業と組むことで外来の新しいパラダイムを日本で広めるということですね。
それは、言うなれば政治的なコンテクストですが、水銀は一方で神社と密接に結びつく不可欠の資源であると考えれば、それを抑えることには当然経済的メリットもありえます。また中国では「丹」が薬品として利用されてきた歴史もありますので、そこにも経済的な鉱脈としての意義は考えられます。
──スマホに不可欠なレアメタルを抑えるに似た話ですね。
さらに、水銀が薬であったということにつながるかたちで、水銀がもっている「霊的」なコンテクストもあるわけです。
──中国では不老不死の薬としてみなされ、楊貴妃が飲んでいたなんて話を聞いたことがあります。
まさに、そこはとても重要なポイントです。真言密教では生きたまま仏になるという秘術がありまして、この秘法は「即身成仏」と呼ばれるのですが、要はミイラになるということです。松田先生はこのミイラ化の秘法を日本に持ち込んだのが空海だったのではないかと推察していますが、この秘法を執り行うにあたって、必要とされたのが水銀だったんですね。
──ああ、面白い。
これには物理的に水銀の防腐作用が期待されたこともありますが、中国において水銀が不老不死をもたらす重要な鉱物であったことが深く関わっている可能性もあります。環境省のウェブサイトに「不思議な水銀の話」というレポートがありまして、そこに「空海と丹生明神」という章があるのですが、そこにはこんなことが書かれています。
空海が留学した唐では、神仙思想が盛んであった。唐代は、不老長寿を信じて何人もの皇帝が水銀を飲んでいた時代であり、空海もまた、水銀に関する知識を持って帰国したに違いない。水銀は、朱の顔料として絵画や建築物に使われるとともに、鍍金(めっき)の材料としても利用されていた。また、中国の煉丹術(不老長寿の薬を作る術)では、金や銀より価値があるものとされており、高価な材料であった。西洋的価値観であれば「金・銀・銅」の順になるところが 、中国では「 朱・金・銀」の順であったため、朱を求めて山に入るというのは、当時の人にとっては自然な感覚だったのかもし れない。
空海は、生まれ故郷である四国から奈良末期の平城京に上った。若い頃の空海は、 吉野(和歌山県)や出生地である四国で山林修行をしつつ勉学に励んでいたとされる が、中央構造線上のこのあたりは水銀の産地で、縄文時代から朱を採掘していた記録 が残っている。修行中の彼が、山中で朱に関して見聞していたとしても不思議ではないし、その経験から、中国的価値観を受容できたであろうことも頷けるのではないだろうか。
──なるほど。しかし、なんでこんな話が国のウェブサイトに掲載されているのか謎ですね。
なんにせよ、水銀には、政治的な力、経済的な力、霊的な力、さらに上記の環境省のレポートには、「丹生明神が、鉾や舟を赤く染める土を与えて軍威を高めたとの言い伝えもある」と記載しているように、それがひいては軍事的な力をも表す、非常に重要な戦略資源であったことは間違いなさそうなんですね。
言うなれば、空海という留学帰りのイノベーターが日本で新事業を旗揚げするにあたって、水銀というものがもつパワーを戦略的に味方につけることで一気に一代で一宗派を立ち上げることができた、と言えなくもないのではないか、というわけです。
──高野山がアップルやフェイスブックのキャンパスのように思えてきました。
そんなふうに宗教者や教団施設などを、世俗化して捉えるのは、もちろん大変失礼なのですが、空海がもたらした新しい技術やパラダイムが、極めて革新的なものであったとするなら、それがもたらしたインパクトを想像するには、そうしたアナロジーも少しは役立つのではないかと思います。

──いまで言うと、これまでの組織運営のパラダイムが「DX」という名の元で、180度の転換が迫られていることとも対応させたくなりますね。最新技術によって社会の劇的なトランスフォーメーションが進むなか、既存のプレイヤーに変わる勢力が台頭し、そこにかつてのエスタブリッシュが吸い込まれていくという物語ですよね。
と言いましても、これはあくまでも仮説でして、実際はこんな雑な話ではないとは思いますが、鉱物と権力ということでいうと、この話は、仮説とはいえ、面白い話ですし好きな話なんです。
ちなみに、鉱物のもつパワーという話を現代に移しかえると、言うまでもなく「レアメタル」は相変わらず戦略物資として極めて重要なものですし、ブロックチェーンやビットコインの基盤となる営為が「マイニング」、つまり「採掘」ということばで語られるのはとても象徴的なことだと思います。
──言うなればブロックチェーンのマイニングにおける「ナンス(nonce)」もしくは「ハッシュ値」といったものが、現代における「水銀」だと言えそうですね。
ブロックチェーンの「採掘者」が「掘っている」のかは、説明されてもいまひとつわかり切れないところがありますが、それを「現代の水銀」と呼ぶのかどうかは、文化的なコンテクストが大きく関わってきますよね。
アメリカの鉱物採掘の歴史で言えば、「金」の採掘が歴史的にも文化史的にも重要なのだとは思いますが、先に見たように、中国の神仙思想に基づけば「金」よりも「朱」のほうが優位性が高いといったこともあるので、こうした文化コンテクストの違いが、例えば現代のテクノロジーをめぐるわたしたちのパーセプションに少なからぬ影響を与えていることもあるのではないかと思ったりはします。
──デジタルテクノロジーは、どこに行っても同じ原理で同じように作動するものだと思いがちですが、案外そうでもない、と。
というのも結局それを使うのは人であり、ある固有の習慣や文化をもった社会ですからね。それこそ今回のお題は、#86に続いてまたまた「スーパーアプリ」なのですが、それがなぜ世界に先駆けて中国で開発され、欧米においてまったくアイデア化されることがなかったのかというのは、もちろん現実的な条件の結果ではありながら、同時にそこには文化的なコンテクストもあるようには思うんです。
これは自分的にはずっと気になっていることでして、中国のサービスの方が欧米のアプリよりもうまくデジタルテクノロジーのネイチャーに適合できていることには、経済・政治環境のような条件だけでは説明しきれないところがあるように思えてならないんです。
──ふむ。
例えば、以前、中国の音楽アプリがいかにSpotifyやApple Musicと違っているかということを、この連載のなかで紹介したことがありますが、そこで中国のアプリは基本「中課金」のビジネスモデルになっていて、であればこそ、音楽をめぐって「聴く」だけではないさまざまなサービスが開発されていくことになり、結果として音楽アプリ自体が、動画視聴もでき、ソーシャル機能もあり、ゲームやカラオケもできたり、友人とパーティができたりと、多種多様な機能を搭載したスーパーアプリ的なものとなるわけですが、エンタメを中心とした中国ビジネスの専門家の陳暁夏代さんにお伺いしたところ、それもまず大前提として、中国ではそれ以前に「音楽にお金を払う」という慣習がなかったのが大きな理由だったそうなんですね。
──「音楽を聴く」がビジネスになっていないところで、音楽を聴くために月々1,000円払えと言われても、「なんで?」となりますよね。
ですから、まずは無料でサービスを開放して、「何かをしたい」という欲求がユーザーのなかに生まれてくるポイントにペイウォールを設けるということになりますので、必然的にサービスを拡張せざるをえなくなるんですね。
──それは、もう明確に合理的な説明ですね。
はい。ただ、このことを今度は逆に、「なぜ欧米で音楽は有料が当たり前となっているのか」というふうに問うてみると、この答えを出すためには、かなり歴史を遡らなくてはならなくなるような気もするんですね。あるいは、これを「日本において「音楽に金を払う」という行為は、いつからどこで当たり前になるのか」と問うてみたとすると、そもそも近代以前に、「音楽を音楽だけで消費する空間」があったのかと疑問になりますよね。
想像なので根拠のないあやしい話ではありますが、多くの場合、「音楽」は祭祀に埋め込まれていたり、演劇の一部として提供されたりするのが一般的だったのではないかという気がするのですが、そうであれば、ここ日本においても「音楽に金を払う」行為は、せいぜいここ200年くらいの話かもしれないということになってしまいます。

──若干屁理屈っぽい感じもしますが、とはいえ、音楽を聴くという行為を独立した体験として楽しむということがあったのかと言われると、パッとは思いつかないですね。
カラオケなんていうのは、その最もいい実例だと思うんです。
──ほお。
カラオケは、最近はずいぶん行ってませんが元々は大好きでして、数年前まではしょっちゅう行っていたのですが、とはいいながら、一方で「音楽好き」を自認してきたところもありますので、カラオケというものを自分のなかでどう正当化するのかというところで、わりと葛藤があったんです。
──葛藤?
音楽というものを西洋的な意味で「作品」として理解するのであれば、その正しい受け止め方は、それを静態的に「鑑賞する」ということになるわけですよね。そこでいう鑑賞っていうのは、要はじっと聴いて、自分なり咀嚼することですから、「みんなで歌って盛り上がろう!」みたいなことって、下手すると、その作品性に対する冒涜になるということになりかねないなと思うんですね。例えば、クラシックのコンサートで、お客さんが一緒になって曲を歌い出したら、普通はつまみ出されますよね。
──まあ、そうですね。
ただ、これがロックのコンサートですと許容されますが、それも実際は、音楽の音がデカすぎて、誰が歌っていても気にならないから自由に歌えるだけで、客席が静まりかえったバラードで、大声で歌っている一団がいたら、きっとみんなイラッとするとは思うんです。つまり、「音楽を聴く」ことは、基本的には場の主体である「アーティスト」の表現をありがたく拝聴するところにあるわけですね。ところがカラオケというものは、その作品を、「ユーザー側が勝手に改変して良い」という建て付けになっていて、好きな歌を好きなように歌えちゃっているわけです。
──ある意味、二次創作を許してしまっている、と。
はい。とはいえ、歌というものは、「その歌を歌っていいのは、この人だけ」というふうに権利化するのが難しいもので、人がシャワーを浴びながら鼻歌を歌っているところにまでJASRACが取り立てにくるようなことは、基本できないですし、そんなことすべきものでもないですよね。あるいは人が集まったりしたときに歌を歌うことは普通に起きることでもありますので、そういう意味で、音楽は社交空間における重要な要素でもあったりします。
そういう意味で言いますと、カラオケは、音楽作品というものを、鑑賞する対象というよりは、社交空間を円滑に動かすための通貨のようなものとして「音楽」というものを使っていることになるのですが、これが日本において発達したことは興味深いんですね。
──どうしてでしょう。
というのも、日本における芸術というのは、もちろん全部がそうではありませんが、鑑賞というよりは実際の創作に重きが置かれ、しかもそれがある意味社交空間におけるツールとして発展してきた歴史があると思うんです。これは特に俳句のような文芸においてそうだと思うのですが、「俳句を楽しむ」と言ったときの意味は、芭蕉や蕪村を味読するということではなく、下手でもいいので自分で詠むことを意味していますので、どちらかというと鑑賞型ではなく、参加型のものなんですね。実はカラオケというものも、それに似ているところがあるように思うんです。つまり、本来は1対1で向き合うべき鑑賞型であるべきはずの体験を、参加型の体験に半ば強引につくり替えてしまうことをやっているように思えてならないんですね。
──ある「作品」を使って自分で何かをやってみる、ということですね。って、それっていまで言うところのTikTokじゃないですか。
まさにそうなんです。自分も最初にTikTokというサービスの話を聞いたときに、「なんだそのくだらないサービスは」と思ったんですが、何との対照においてくだらないと感じたのかと言えば、「音楽は作品として鑑賞すべきだ」という観念との比較においてくだらないと感じたんだと思うんです。これは、まさにカラオケが、ちゃんとした音楽鑑賞というものと比べてくだらないとされてきたこととまったく同じなんですね。
──なるほど。
ここでさらに気になるのは、そのTikTokというサービスの発祥が中国で、爆発的な成長を遂げたのも中国をはじめ東南アジアにおいてだったことなんです。また、カラオケということで言えば、中国の音楽アプリにはカラオケサービスもあり、これも中高年層に人気だとも聞きます。
こうした状況を仮に、「音楽のソーシャル化」と呼んだとしますと、それはちょうど、日本において音楽が、どちらかというと社交的機能において重視されていた話とも対応してきまして、なんのことはない、日本におけるコンテンツ消費は、近代以前からずっと「ソーシャル」なものだったということが言えるのかもしれませんし、これはまったく確証はありませんが、これはもしかしたら中国を含むアジア全般に見られる傾向なのかもしれないと思ったりするんですね。

──妙なことを考えますね。
こうしたことを踏まえてスーパーアプリというものについて考えてみますと、スーパーアプリを理解する上で極めて重要なのは、スーパーアプリの基盤として不可欠なのは、お金をやりとりするペイメントの機能と、ソーシャル機能なんだと思うんです。というのも音楽アプリの比較で言いますと、SpotifyやApple Musicが静態的で「ただ聴く」だけのものに留まり、中国のアプリに見られるようなダイナミックなアクティビティが生まれないのは、ソーシャル機能が決定的に欠落、もしくは弱いからなんだと思うんです。
──音楽好きが、音楽サービス内で日常的にメッセージをやり取りするようなことがないわけですもんね。あるミュージシャンが好きなアーティストがコメント寄せ合うみたいなことすらできないというのは、よくよく考えてみると、意味がわからないですね。
本当にそうなんです。Quartzの今週の〈Weekly Obession〉は、スーパーアプリについての解説をこんなふうにしています。
「スーパーアプリ」という言葉は、ブラックベリーの創業者マイク・ラザリディスの2010年のMobile World Congressでのスピーチに起源があるとされる。彼はそこでこう言った。「スーパーアプリとは、一度使い始めると、それ無しでどうやって生きてきたのかと不思議に思うようなアプリケーションのことだ」
このビジョンは、WeChatやAlipayによって中国で完全に実体化した。10億人以上の中国人が、タクシーの注文からテストの点数チェック、鍋をシェアした後の友人へのお返しまで、毎月これらのシステムを利用している。
投資顧問会社「GP Bullhound」の香港エグゼクティブディレクターであるElsa Huは、東南アジアの巨大な人口、比較的若い人口層、携帯電話の高い普及率が、アプリの急成長を促したと述べる。これらの地域はPC時代をスキップしてモバイルコンピューティングに直行したため、イノベーションの豊富な機会が生まれた。
「WeChatが始まった当初は、WhatsAppやFacebook Messengerと非常によく似ていました」と彼女は語る。「彼らはすぐに、ユーザーが毎日WeChatで多くの時間を過ごしているなら、そこから離れずに他のことをしたくなるだろうということに気づいたのです」
──まあ、わかりやすい説明ではありますよね。
これが間違いだとはもちろん思いませんし、この後に語られるように、FacebookとWeChatの道行きを分けたのが、中国はクレジットカード時代をいきなりリープフロッグしてモバイルウォレットを実装できたからだというのも、おそらくはその通りなのだとは思うのですが、自分としてはどうしても何か違うフレームが、アジアでスーパーアプリが勃興した背景にはあるような気がしていて、それが何なのかがずっと気になっているんです。
──ふむ。
なかでも、ひとつ大きなポイントとなるのは「ソーシャル」ということばをめぐる文化的なコンテクストなのではないかと感じていまして、日本では一向にSNSを「ソーシャルメディア」として記述する習慣が定着せず「会員制交流サイト」というまったく意味のわからない訳語が使われるなど、「ソーシャル」の意味がずっと宙に浮いたような格好になっていますが、ちょっと前に気になって山崎正和さんの84年のベストセラー『柔らかい個人主義の誕生』という本を改めて読んだときに、「なんだ、これ、ソーシャルメディアの話じゃんか」と思ったことがあるんですね。
──へえ。
いま手元にないので引用できなくて申し訳ないのですが、ウェブで検索しますと、山崎先生とこの本の功績について論評した「『誰でも表現者』時代の本質は『リズムと社交』:世界を広げる読書案内としての『山崎正和』評伝」なんていう『東洋経済オンライン』の2021年の記事がヒットしますが、ここで筆者の神谷竜介さんは、こんなことを書いています。
高度成長とそれに伴うグローバル化が日本型の地縁血縁共同体(ムラ社会)を解体し、個人化された大衆社会が孤独と不安を内包することでしか立ち行かなくなる時代に、「消費」と「美学(美意識)」に着目することで人々の欲望を他者との交歓、すなわち「社交」へと転化しようとする道筋を見いだしたことはどれほど称揚しても足らない。
あるいは、2018年のインタビューでは山崎先生自身が、この本で立てた見立てについて、こう解説しています。
本の端緒になったのは、時代の変化でした。洋服の有名ブランドや美容院が人気を集めるようになった。カラオケも流行しはじめた。自分を見せる、聞かせるという「自己表現」の欲望に人々が目覚めていったんですね。
私はこれを「表現する自我」という概念で説明しました。それは、近代に西欧から流入してきた「自我」とは逆です。「自我」は欲望の主体であって、他人の持ち分を奪い、他人を手段として使って、自分を大きくしようとする。資本家が労働者を使って資本を増やすように。
「表現する自我」は尊敬できる他人を必要とします。化粧し、着飾った女性は、自らの姿を同性の美女か気に入った異性に見せたいと思うもの。猫に見せても意味がない。猫には評価する能力がないから。(中略)
時間消費を楽しみ、自己表現する自我の登場です。それは、かつての産業社会の硬い個人主義とは区別される「柔らかい個人主義」なんですね。他人に自らを表現し、時間を消費して社交を楽しむんですね。

──社交としての消費、もしくは消費としての社交ということですね。面白いですね。しかも80年代に日本はすでにそこに突入していたと。
ここで気になるのは、近代に西欧から流入してきた「自我」とは逆の、しかも「『表現する自我』は尊敬できる他人を必要とする」という方向性を、なぜ日本人がもちえたかというところなんだと思うんです。
──そこはまさに、インターネットがもたらした双方向性とも呼応しあうところですし、その双方向性を体験する場としてカラオケの登場が言及されているのも興味深いですよね。
そこから先を語るためには、もう一回本に当たらないとダメなので、今日の話はここまでにしたいと思いますが、なんにせよ、スーパーアプリの議論において、その基盤にあるはずの「ソーシャル」という部分が、多くの場合欠如しているのが、自分としてはとても不満なんです。
──「ソーシャル」といったときに、それが一体何を意味しているのか、西欧諸国とそうでない国とではずいぶん違いそうですもんね。
ソーシャルメディアが、ひとつの社交空間であって、その参加者は「柔らかい個人主義」によって束ねられていると考えてみるだけで、向き合い方も少しは変わるような気もするのですが、わたしたちの頭のなかのフレームが、相変わらず産業時代のそれなのかもしれません。
山崎先生は先のインタビューで「かつて『消費』といわれていた多くの部分は、実は『生産』なんじゃないか」と語っていますが、スーパーアプリもそうですし、メタバースに関する議論もそうですが、わたしたちが「消費」を「生産」としてしか考えられない状態にある限り、インターネットが本来拡張しうるユーザー間の相互性、P2P性という、最も本質的な部分が打ち消されてしまうように思うんです。
──山崎先生がおっしゃるところの「尊敬できる他人を必要とする自我」ですね。
この連載で何度も引用させていただいている宇野重規先生の『民主主義の作り方』には、鷲田清一先生のことばが引用されていまして、そこでは「依存」というものの不自由さと「自由」がもたらす不安の間に「他者たちとの相互依存という位相がある」と書かれているのですが、この部分をどう拡張できるのかが、おそらく今後のインターネットのキモになんだと思うんです。そうでない限り、それらはただ単に、より「巨大な依存」へとユーザーをひきこむだけになるはずで、利便性からのみ語られるスーパーアプリの話も、そうした依存性に付け込もうというだけの、うんざりするようなイヤな話になってしまうんじゃないかと思うんですよね。
──#86「スーパーアプリの激震」も同じような終わり方してましたよね。
「わたしたちの未来がSiriやMetaのメタバースによってかたちづくられるものであったとしても、それが必ずしも中毒的で搾取的なサービスの世界である必要はなく、居心地のいい世界であってもいいのだ」という引用で終わっていたと思いますが、まさに同じことですね。アジアで実体化したアプリに何を学びうるのかというところで、自分も含めてですが、わたしたちは基本的だけれども重要な何かを見落としているような気がしてならないんです。
若林恵(わかばやし・けい) 1971年生まれ。『WIRED』日本版編集長(2012〜17年)を務めたのち、2018年、黒鳥社設立。
꩜ 「だえん問答」は毎週日曜配信。次回は2022年2月6日(日)配信予定です。本連載のアーカイブはすべてこちらからお読みいただけます(要ログイン)。
🎧 音声コンテンツもぜひ! 平日毎朝の「Daily Brief」の英語読み上げや、日本語ニュースのPodcastを配信しています。
👀 Twitter、Facebookでも最新ニュースをお届け。
👇 このニュースレターはTwitter、Facebookでシェアできます。転送も、どうぞご自由に(転送された方へ! 登録はこちらから)。