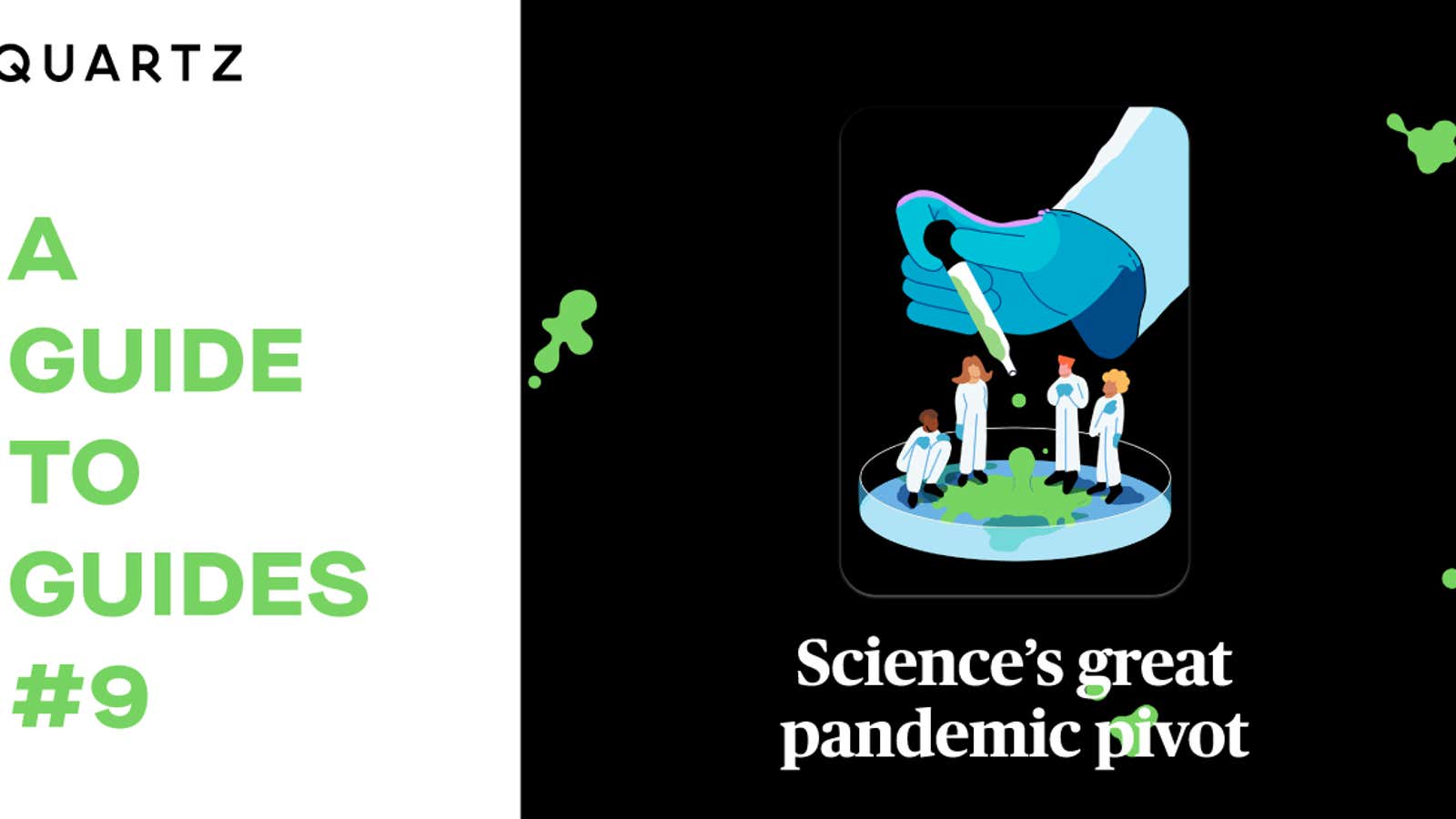A Guide to Guides
Guidesのガイド
Quartz読者のみなさん、こんにちは。週末のニュースレターではQuartzの特集〈Guides〉から、毎回1つをピックアップ。世界がいま注目する論点を、編集者・若林恵さんとともに読み解きましょう。

──緊急事態宣言も取り下げられて、だいぶ平時に戻ってきたように思いますが、生活の方はいかがですか?
そうですね。自分は結局ほとんどステイホームもしないで、事務所に通っていましたから、日々はあまり変わらないといえば変わりませんが、それでも、少しホッとする感覚はありますね。やはり、なんというか、肩肘が張っていた感じはあったと思いますので。
──「ニューノーマル」なんて言葉も出ていますが、新しい習慣になったことなどあります?
日常的にマスクをするようになったくらいですかね。といっても好きなスポーツブランドのマスクが出たので、そのロゴ入りのものを喜んで身につけてるくらいのことなので、ある意味、新しいファッションアイテムという気持ちが強いかもしれません。
──結局、タバコもやめてませんよね。
そうですね。ZOOMなどで会議がリモートになって一番よかったことはタバコを吸いながら会議ができるようになったことだ、なんて喫煙仲間とは不謹慎な冗談を言っていたのですが、そもそも、感染対策として禁煙が有効だみたいな話は本当なのかな、と思うところもありまして。
──え、違うんですか?
これも喫煙者の知人に教えてもらったんですが、タバコに含まれている成分がコロナウイルスに効くという論文が、たしか4月だったと思うのですが、実は出ていたりもするんです。フランスの著名な神経生物学者が、「ニコチンはコロナウイルスが体内の細胞に届くのを防ぎ、体内における拡散を抑止する効果がある可能性がある」と言っていると、これは英国紙Gurdianが報じています。ちなみに、フランスの病院に収容されたCOVID-19患者のうち喫煙者は8.5%だったそうで、フランスの喫煙者は平均して25.4%なんだそうですよ。
──なんと。
もちろん、こうした情報は、喫煙者的には喜ばしいものだったりするんですが、まあ、それはおいておくとして、今回のGuidesのお題が「科学」だということですから、それに即して言えば、よくよく考えなくてはいけないのは、科学というものが、ほんとうにアテになるのか。ということなのではないかと思うんですね。
──え。
いや、科学はもちろん大事なんですよ。でも、おそらく喫煙、もしくはニコチンがコロナウイルスに効くなんていう論文は、いくらプロモートしたところで、これだけ反喫煙が進行しているなかでは、一顧だにされないわけですよね。
わたしも別に、コロナ対策として喫煙をあらゆる公共空間、商業施設内で全面解禁すべき、と叫ぼうとは毛頭思わないのですが、そうだとすると、科学的エビデンスというものは、ハナから社会的なアジェンダ──それは主に経済上のもの、あるいは政治上のアジェンダでもあるわけですが──を補強するものとしてしてしか存在しないのではないか、という疑念は常にあるわけですね。
──要は、社会は自分たちが受け入れたい“エビデンス”しか聞き入れないと。
それは批判でもなんでもなくて、自分だってそうなんです。喫煙が感染症によろしくない、ということがパンデミックの初期に言われていましたが、愛好家の自分からしたら、「あ、そうですか」くらいのもので聞く耳をまるでもたないのはそうで、それはもちろん愚かなことで、たしかに愚かなんですが、じゃあ翻って、愚かでない判断というものが一体どこにありうるのか、ということになると、実際は途方に暮れてしまうことになるわけです。

──福島原発の事故のときもそうでしたね。科学者が出てきてさまざまなことを言うわけですが、微妙な学問領域の違いや、立場の違い、スポンサーの違いなどによって、おっしゃることも違ってくるわけで、それに対して「あいつは専門家じゃない」とか「左翼だ」とか「中国政府に金をもらってる」とか、まあ、本当か嘘かわからないような批判が湧いて出てくるのは、今回のコロナ禍においてもそうでしたね。
そうなんです。科学というものは、客観的で中立な答えをひとつ出してくれるものだというのが専門家ではない素人の願いというか、期待ではあるわけですが、長い目で見れば、コロナウイルスとはどういうもので、どうやって対処できるのかは明確に明らかになっていくのだとは思いますし、ワクチンの開発というのはそういうものであるとは思うのですが、短期的にすぐに「これだ」という答えが出ないのは、それはそうですよね。
ある記事で読んだのですが、それこそ医者だったか疫学の研究者か忘れてしまったのですが、「未知なるウイルスに専門家は存在しないにもかかわらず、われわれは専門家として振る舞うことを要求される」といった言葉を漏らしていまして、それはたしかに大きな矛盾だなと思うわけです。
──そうですね。
新型コロナウイルスの専門家と呼べる人は、自分が知っている範囲では「バットウーマン」(bat woman)との異名をとる武漢の研究ラボの責任者だった女性研究者で、彼女は15年間、コウモリから移る感染症を追いかけてコウモリが巣としている洞窟を探索してまわっていたそうなんですが、その唯一とも言える専門家が、そうであるがゆえに、今回のパンデミックの根本的な原因であると名指しされているのは、この矛盾を端的に表しているのかもしれません。
──バットウーマンですか。
アメリカの科学ジャーナルに彼女に関する非常に面白いストーリーが載っていまして、その記事自体は、彼女がウイルスを世に放った張本人であるとする濡れ衣を晴らそうとする方向で書かれていますので、その記事を紹介したTwitterのリプライ欄は「中国政府の回し者」といった罵詈雑言で、もう大荒れなわけです。
──どっちが正しいと思われました?
自分は記事自体はとても面白く読みましたし、コウモリからの感染症にこれだけの情熱を傾けてきた女性研究者にものすごく感心はしたんです。ただ、この記事の信憑性となると自分は判断ができませんし、パンデミックの背後で、国際政治上のさまざまな駆け引きが起きているのは、おそらくその通りだと思いますので、記事が捏造であるとまでは思わないですけれども、どこかからのファンディング上のあるいは、政治上の後押しがあって記事の掲載にGOサインが出たということはないとは言えないとも思うんですね。
逆に、そういう記事が政治的な配慮から掲載が見送られることが容易にありえることを思えば、1本の記事の背後でどういう力が動いていたのか、あるいは特に何も動いていなかったのかといったところは、想像の域を出ませんから、判断のしようもないですよね。書き手の思いや共感がしっかりと伝わってくる読み応えのある記事だなとは思いましたので、その辺で判断を止めておくしかないのかな、と。
──議論のしようもない、と。
そうですね。そもそも判断するにも、手持ちの情報がないわけですから。

Science’s Great Pandemic Pivot
コロナ下のサイエンス
今回のGuidesのなかでもこの武漢の研究所の話題が1カ所出てきますが、どういう文脈かと言いますと、科学研究における“資金の流れ”という文脈なんですね。〈Why research labs were drastically unprepared for Covid-19, even after SARS〉という記事で書かれているのは、結局のところ、科学研究というのは資金獲得のコンペティションであって、そのコンペティションのルールは研究者が決定するのではなく、ファンディングする側が決定するという問題で、要は政治的な要件に従って、研究者は右往左往せざるを得なくなっている、ということなんですが、武漢のラボについては、こう書かれています。
「結果として、科学研究の助成は党派的な問題に帰着し、政治の短視眼的な決定の対象となっていく。例えば、トランプ政権がSARS-CoV-2がそこから発生したと喧伝したことから、NIH(米国国立衛生研究所)は、コウモリから人へのコロナウイルスの感染を研究していた武漢の研究所への資金援助を突然打ち切った」

──研究所が、ある意味、政治的駆け引きの道具にされた、ということですね。
この記事は、NIHへの助成申請がサイロ化していることで、最も基礎的な研究が、援助対象にあてはまらなくなっていることや、助成の枠組みに合わせて少なからぬ研究者が、自分の研究内容を変更せざるを得なくなっている問題などを指摘していますが、今回の特集のほとんどの話は、結局のところ「資金がどこから流れているか」ということの問題に帰着していまして、そうした観点から言えば、科学にほとんど自律性や自由というものがない、ということなんですね。
──どうしてそうなっちゃったんでしょうね。
これは、若い科学者のキャリアがCOVID-19によって不安定化させられている状況をレポートした〈Covid-19 is destabilizing an entire generation of young scientists〉で書かれていますが、大学や研究室がロックダウンしてしまい、自分も身動きができない状況になると、研究設備にアクセスができなくなってしまうので、研究そのものが中座してしまうんです。要は、科学研究というのは、個人で賄うことが到底不能な高価で巨大な設備を要するので、そこへのアクセス権がないと、手も足も出ないということなんだと思います。
──家にこもって自分ひとりで論文を書くなんてことは、もはやできないわけですよね。
それはもちろん仕方のないことだと思うんです。実際お金がかかるわけですから。ただ、そのアクセス権の有無が自分の未来を決定してしまうという状況は、利権の温床になりますので、そうした構造は、弱者を常に利権側の言いなりにさせてしまうので、若い研究者は、資金もそうですし、設備へのアクセスを絶たれた瞬間に、もうドロップアウトするしかないんですね。
もっとも、資金を提供したり、設備投資をする側からしますと、費用対効果はどんどん厳しく問われるようにもなってきますし、公的援助も減っているなか、より効率的な投資が求められてもいるわけですね。
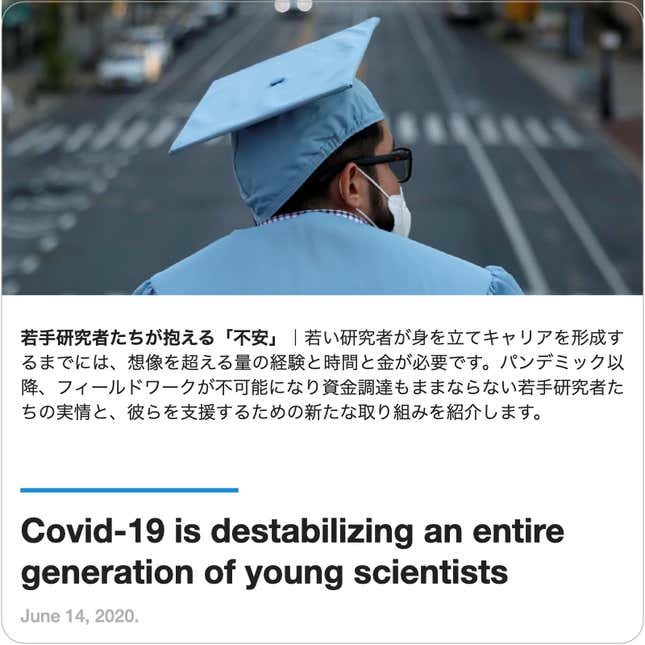
──ははあ。
とりわけ税金が投入されるともなれば、国民側からは当然「それはなんの役に立つんだ」「ほかにもっといい使い道はあるだろう」といった声は上がるわけで、それはそれで正しい声ではありますので、そうなってくるとお金を使う側としては、余白を削り取られていってしまうということにもなるわけです。
先に挙げた〈Why research labs were ~〉の記事の中で、ある研究者が、「我が国の科学研究を援助するやり方は変わらなくてはならない。現在あらゆる研究は、その中身を露ほどもわかっていない政治家によってまな板の鯉にさせられてしまっている」と嘆くわけですが、その政治家の判断というのは、ある意味では国民の判断でもあるわけですから、こうした自体は、国民のせいとも言えるわけです。
──たしかに。
とはいえですよ、じゃあ、国民の科学リテラシーを上げるのが急務だといったところでですね、包括的に科学界を見回して、「これは役立つ/これは役立たない」なんて判断ができるわけないんです。自分の研究領域に隣接する科学者がどんな研究をやっているのかを当の科学者ですらロクにわかっていないというほどに科学の世界は細分化されてしまっていますから、いったい誰が、そんな神のような視点から“腑分け”ができるのかといったら、もうおそらくこれは誰もできないはずなんです。
──できませんか。
と思いますよ。と、加えて、ここがとても重要なところだと思うのですが、今回のパンデミックが明らかにしたように、新型ウイルスというのは、言ってみれば常に“未知のもの”として姿を表すわけですね。それはどういうことかというと、それが襲来するということを予測した上で、それの対処法を予め準備しておくということができないということなんです。
──準備できるなら“未知”ではないということですもんね。
そうなんです。なので、役に立つとわかった上で投資を行うということが原理的に不可能であるということが、パンデミックが明かした不確実性ということになるのだと思いますが、それはなにもパンデミックに限ったことではないはずです。
──そうすると、手立てがないということになっちゃうんですかね。
それは、先の記事でも触れられていることなんですが、そうした不確実性を前にして大事なのは「研究の多様性を確保しておくことだ」ということになるんです。先に挙げた「バットウーマン」のような人が、「いつ、どこで役に立つかはわからないけれども、きっといつかどこかで役に立つはずだ」という気概をもって地道に研究を継続してことがいかに重要であったかは、今回のパンデミックにおいては本来であれば重要な教訓になったはずなんです。
未知の困難に対処する上では、いかに多様なソリューションに賭けておくかはとても大事な戦略となるはずで、実際、〈Why research labs were ~〉のなかでは、研究の多様性を確保するために独立系研究者をもっと支援すべきだとの声が紹介されていますし、政治的・経済的なアジェンダによって資金の分配が恣意的に決定されないよう、抽選にすべきとか、研究者たちの投票で決めるべき、といった提案もなされています。
──抽選ですか。面白いですね。
計画して賭け金を張るよりも、ランダムに貼ったほうがレジリエンスが高い、という考え方なんだと思いますが、不公平・不公正の是正という意味でも、そこまでバカげてるとは言えないのかもしれません。もちろんうまく設計しないとダメだとは思いますが。
──お金の流れということで言いますと、チャン・ザッカーバーグ財団の動きを追った〈Coronavirus is putting the power of private philanthropy to the test〉といった記事もありました。
科学に限らずアートの分野でもそうですが、海外ですと、いわゆる民間セクターと公共セクターの間に入るかたちで、財団などの多種多様なソーシャルセクターが、市場化できない公共財や社会的な価値を守る活動に資金を投入していて、今回のCOVID-19の一連の困難のなかで、こうしたセクターの厚みや資金力が大きな違いを生んだように思います。
記事では、アウトブレイクが起きてから助成の申請が激増したほか、行政府からもPPEの確保への援助などを頼まれてポンとお金を払ったことなどが明かされていて、これまで説明してきたような基礎研究支援からPCR検査の素早い実装の支援といったところまで、公共では動きが遅いところを補完していたことが明かされていて、ゲイツ財団なども含めたこうしたセクターの活動は、やはり不可欠のものとみなされていますね。
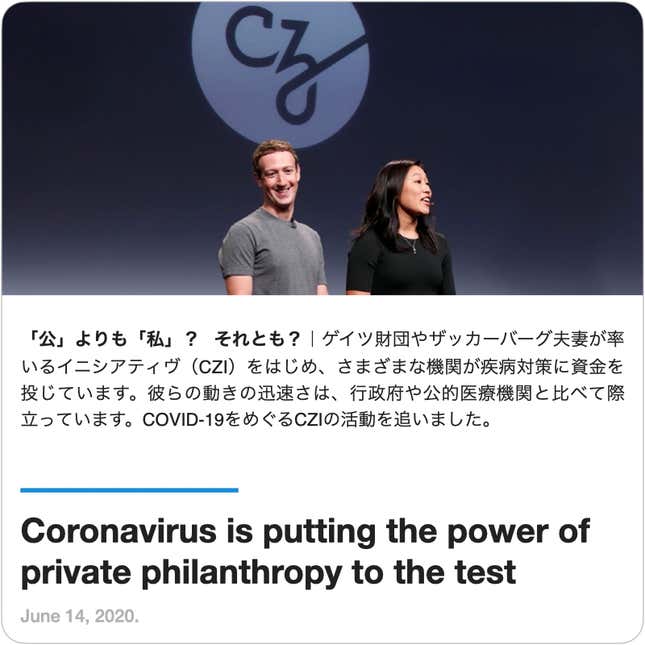
──一方、ビジネスセクターは、いかがでしょう。
〈Coronavirus has upended the profit incentives for pharmaceutical research〉という記事のなかで民間セクターの動き、主に製薬会社の動きが概説されていますが、記事がフォーカスしているのは、シェアホルダーの顔色を常にうかがわないといけない企業というものの限界でして、パンデミックは世界的な公衆衛生上の危機ではあるわけですが、その一方で、企業から見れば格好のマーケットなわけですね。
で、企業は当然そこで利益を得ることができると思えばこそ開発競争にも乗り出すわけですが、とはいえ、どこかが一番乗りでマーケットにプロダクトを投下できたとして、価格が、より多くの人に行き渡るような設定になるのか、どれほどの生産量が担保されるのか、といったあたりは各国政府にとって極めて重大な問題になりますから、国際機関などの介入も必要になってくることになってきます。

──今回の危機のなかで、総じて民間企業の“何もしなさ”はちょっと驚きがありましたね。
そうなんです。そこは本来もっと問題にされていいと思うのですが、有名社長や起業家が、ある種のフィランソロピー(慈善活動)としてマスクを寄付したりといったことはありましたが、総じてぼんやり眺めていたような印象はありますよね。
そういえば、日本人の研究者であり経営者でもある山田忠孝さんという方が、大手製薬会社のグラクソ・スミスクラインで研究開発部門の会長をされていたときに、会社が行おうとしていた倫理に反するような訴訟を取り下げさせた顛末を通して「ひとりの声がいかに組織を変えられるか」を論じたエッセイを、この間たまたまHarvard Business Reviewで読んで非常に感銘を受けたのですが、企業に対してもっとちゃんと社会的責任を果たせという声が今後より厳しくなって行くなか、日本人経営者がそのモデルとして語られるのは、嬉しいことではありますね。
──Black Lives Matterのプロテスト運動においてもそうでしたね。企業への眼差しは非常に厳しいものですよね。
ユニクロみたいな企業が、アベノマスクよりも先にマスクの生産に乗り出すと言い出すようなことを楽しみにしてたんですけど、えらく遅かったですよね。もちろん色んな調整が必要なのだろうとは思いますし大企業になればなるほど、そうしたスピーディな決断が難しいとは思うのですが、それも変えていかないとなのかもしれません。
──ですね。
というのも、さっきの話に戻りまして、いかに“未知”なる状況に対応するのかということで言いますと、〈Science will never be the same after Covid-19〉という記事が非常に面白かったんです。ここではドイツ、ナイジェリア、イスラエル、英国の研究機関が、「コロナ対策」に向けて、いかに研究組織を高速でピボットしたかというところに焦点が当てられています。
──高速ピボット?
つまり、平時において例えばAIDS、エボラ、ジカウイルスから鳥コロナウイルスやラッサ熱などの研究を行っているラボを一気に束ねて、新型コロナウイルスのワクチンの研究に当たらせたという事例がここでは紹介されているのですが、今風の言い方をするなら「アジャイル開発」を行うことのできる組織体へと研究機関をつくりかえるというアイデアと言えるかと思います。
──面白いですね。

オックスフォード大学では200人の研究者がそれぞれの研究をシャットダウンして、ワクチン開発にあたったと言いますが、ほとんど研究者になんらかの役割が与えられていたというんですね。
──すごいですね。
記事によれば、これは数年前から想定されていた事態で、研究所内では緊急事態が発生した際のプロトコルがある程度できあがっていたと言います。結果、この研究所はワクチンのテストが世界で一番進んでいるそうですが、この取り組みが面白いのは、実際のところ“専門家”が誰ひとりいない事態のなかで、近い領域の研究者が集まって、一種の“コレクティブ”として動いているところだと思います。こうすることによって、さまざまな知見が吸い上げられるでしょうし、科学者間の合意形成にもつながると思いますので、より信憑性の高い情報を取り出すことも可能になるようにも思います。
──なるほど。科学者個々人がランダムに発信するよりも、信頼に足る情報になりうるということですね。
いろんな立場の人や視点の人が入ることで、ある特定のバイアスから抜け出ることが可能になるのではないか、と。希望的観測ではありますが。ただ、これまた英国の研究者が書いた面白いエッセイがありまして、そこで今回のパンデミックがもたらしたよかったことをまとめていたのですが、それが結構近いことを指摘していたんです。
──ほお。
Nestaという英国のイノベーションラボの研究員が書いたものなのですが、COVID-19がもたらした良い傾向として、まず「専門家の復権」が挙げられているのですが、ここで重視されているのは、単にひとりの専門家が権威をもつということではなく、広い領域の専門家を集めたグループシンキングで、とりわけ英国ではある科学的知見が政策決定に落とされる際に、心理学者や社会学者、歴史学者、人類学者なども参加したグループのなかで検討されたと書いています。
自然科学と社会科学の専門家がオープンにコラボレーションしていくというやり方を、イギリスは取ったというわけですが、そうしたやり方を取ったからこそ「素早くフェイクニュースを潰すこと」や「エビデンスの素早い精査」「エビデンスに基づく発信・対話」や「メンタルケアの導入」といったことができたと語っています。
──なるほど。最初に指摘されていたように、科学的知見が最も重視される局面ではありながら、一方で、科学者や専門家への信頼や信憑性が低下しているわけですから、そのことにどう乗り越えるのかという課題に真摯に取り組んだ事例と言えそうですね。
さすがだなと思ったのはまさにそこなんです。エビデンスが大事ということは盛んに言われているわけですが、特に日本はそうですが、そもそもそのエビデンスが信頼に足るものかという手前のところで、“科学的手付き”というものの信頼性が崩壊しているのが実態なわけですから、エビデンスベースの政策を執り行うのであれば、それとセットで信頼性の再構築が戦略化されていないと意味がないわけですね。そこにちゃんと目を向けているのは、やはり優れているなと思うわけです。
──お話をお伺いしていると、科学の問題は、情報の問題と深く関わっているんですね。
パンデミックは同時にインフォデミックでもあったわけですが、そもそもソーシャルメディアに関して用いられる“拡散”とか“ヴァイラル”といったことばを見るとわかるように、感染症のアナロジーが用いられてきたわけですよね。パンデミックとインフォデミックはそういう意味ではパラレルにシンクロしているわけでして、とりわけデジタルネットワークにおける感染症が深刻なのは、それが“真実”というものをなし崩しに崩壊させてしまうところで、そこで言われている真実というのは、おそらくは“科学的真実”というもののはずなんです。
──そうですか。
すべての情報が嘘か本当かわからないような状況を「ポストトゥルース」と呼んでいますが、その世界のなかでは、“真実”というものがもはや幻想でしかないということがどんどん明らかになっていっちゃっているなか、その矢面に本当に立たされているのは“科学”だと思うんです。実際、科学者がなんと言おうと、ワクチンなんて打たないと言っている人はたくさんいるわけですし、情報の信憑性なんていうものは、自分の信念に合致するかどうか、の問題でしかなくなっているというのが現実だと思うんですね。
──最初の話に戻っちゃいましたね。
そうなんです。「ポストトゥルース」って本当におおごとなんだと思うんです。初めてそのことばを聞いたき、それは「科学の死」を意味するんだな、と思ったんです。といって、科学は今まで以上に大事になってもいるのはその通りなんですよ。でも、科学的理性をもって人はもはや動かなくなってしまっているのも本当で、そうした状況を、やはり受け入れたところで何ができるのかを考えないとなんだと思います。その意味では、この状況全体が“未知”なんじゃないでしょうか。
若林恵(わかばやし・けい) 1971年生まれ。『WIRED』日本版編集長(2012〜17年)。2018年、黒鳥社(blkswn publishers)設立。著書『さよなら未来』のほか、責任編集『NEXT GENERATION BANK』『NEXT GENERATION GOVERNMENT』がある。ポッドキャスト「こんにちは未来」では、NY在住のジャーナリスト 佐久間裕美子とともホストを務めている。次世代ガバメントの事例をリサーチするTwitterアカウントも開設。
若林恵さんによる本連載は、毎週末お届けしています。先週は「GenZの可能性」と題し、世界の経済を回しているとされるZ世代に寄せられる“期待”の正体に迫っています。Quartz Japanメンバーには、過去の配信記事もご希望に応じてお送りしています。下記フッター内のメールアドレス宛てにお問い合わせください。
このニュースレターはSNS👇でシェアできるほか、お友だちへの転送も可能です(転送された方へ! 登録はこちらからどうぞ)。Quartz JapanのPodcastもスタート。Twitter、Facebookもぜひフォローを。