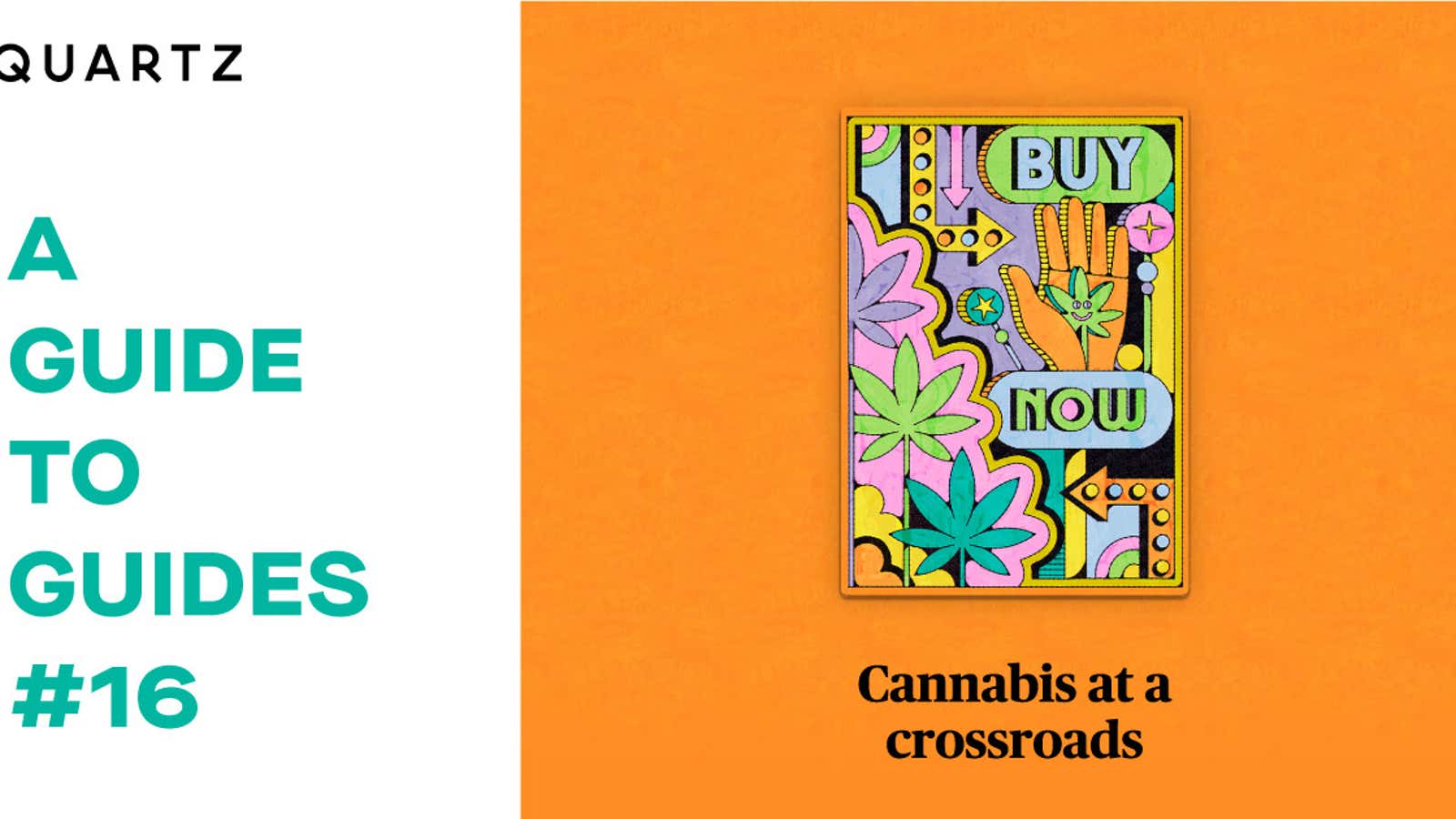A Guide to Guides
Guidesのガイド
Quartz読者のみなさん、お盆休みはどうお過ごしですか? 週末は米国版Quartzの特集〈Guides〉から、毎回1つをピックアップ。今週も、世界がいま注目する論点を編集者・若林恵さんとともに読み解きましょう。
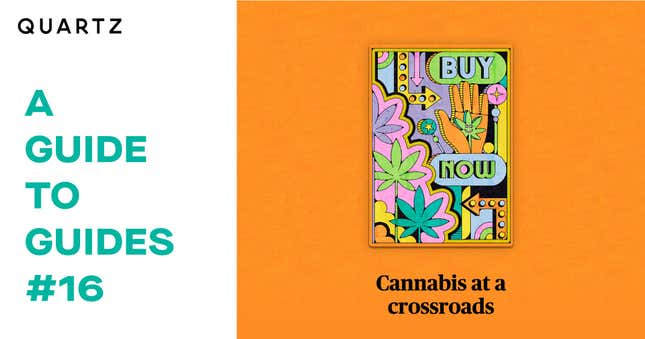
──お盆ですね。休みは取らないんですか?
とくにまとめて休みを取ろうという予定はないのですが、周囲が休みになってますので、のんびりはしています。
──なにか楽しいことありますか?
ないですね(笑)。ないです。
──きっぱり断言(笑)。最近気になっていることはなにかあります?
今回の〈Guides〉に近からず遠からずなところでいいますと、イソジンの話は面白いな、と思ってます(笑)。
──あ、大阪府知事の。面白いですか。どこら辺がですか?
知事が何を思って、何を言いたくて、あの発言をしたのかはよくわからないですし、そこはあまり興味もないのですが、面白いのは、即座に売り切れになるほど、わざわざ買いに行く人がいるというところですね。驚きませんか?
──ほんとですね。日本人、どうしちゃったんですかね。どうしてこんなに踊らされやすいんだろう。
今日たまたま読んだ記事に「『うがい薬買い占め』で露呈する、日本の学校教育の致命的欠陥」というものがありまして、これはまさに今おっしゃったような観点から「なぜ日本人は批判的に情報を検証することができないのか?」を問題にしていて、その根本原因を学校教育に求めています。
──ほお。
例えばOECDがやった調査が引き合いに出され、教師たちが「批判的に考える必要がある課題を与える」かどうかを問うたアンケートの結果が語られているのですが、それがどういうものかと言いますと「アメリカは78.9%、カナダ(アルバータ)は76%、イギリス(イングランド)は67.5%、オーストラリアは69.5%」。
──ふむ。
「アジアではシンガポール54.1%、台湾48.8%、韓国44.8%。イデオロギー的に国民の体制批判に敏感な中国(上海)でさえ53.3%、ロシアも59.7%なっており、48カ国の平均でみると61%だった」
──はあ。で……
日本ですよね。記事によると「47の国・地域が40~87%の範囲におさまっている中で、なんと日本だけが12.6%と、ドン引きするほどダントツに低い」とされています。
──低っ! 引くっ!
ですよね(笑)。加えて、こんな指摘もあります。「ちなみに、これほどではないが、日本の教員がほとんど実践しない指導がもう1つある。『明らかな解決法が存在しない課題を提示する』という項目だ。48カ国平均が37.5%という中で、日本は16.1%。下にはチェコやリトアニアという旧共産圏の国しかなく、ビリから3番目」。
──いやあ、もう、なんか情けなくなりますね。
そうなんですね。この数字はこの数字で、もうほんとに重く受け止めたほうがいいとは思いますし、落ち込んだほうがいいとは思うんですけど、とはいえ、だからといって、それが、みんながイソジンを買いに殺到する理由なのかどうかというのは、自分的にはちょっと腹落ちしないところもありまして。

──そうですか。
わからないんですけどね。イソジンの買い占めに走る人に細かく聞いてみたら、別にそれが「コロナに効く」と本気で信じて買いに行っているわけでもない、ということになるような気がしなくもないんです。
──どういうことですか?
これ、あんまり、うまく言えないんですけど、買い占めに走る人の心理を自分なりになぞってみると、どちらかというと、「なんでもいいから“買いたい”」という欲求が強いんじゃないかと思うんです。

──え。よくわからないです。
うん。あのですね、自分が海外のメディアタイトルを扱う仕事をしていたことから、欧米の雑誌なんかを目に通すことが今も多いんですけど、向こうの雑誌をみていてある時にふと気づいたのは、例えばなんらかのガジェットや服なんかを紹介するときに、向こうの雑誌って価格を載せないことが結構あるな、ということだったんです。
──へえ。
ところが、日本の雑誌って、わたしもヒラの編集部員だったときは、本でもCDでも、雑貨でもインテリアでも、なんでもかんでも「値段を入れろ」って、やたらと言われたんですよ。値段っていうものに異常なくらいのオブセッションがあるんですよ。で、それにいつもうっすらと違和感があったんですよね。
──はあ。
これ、些細なことなんですけど、これ、実はメディアが「何を伝えようとしているのか」というところの根幹に関わる部分だったりするようにも思うんですね。つまり、海外の雑誌は「その”モノ”を知ろう」と言っているところ、日本のメディアは「その”モノ”を買おう」と言ってるんです。これ、実は大きな違いなんですよ。
──言われてみると。
これ、そもそも流通上の仕組みの違いから、本なんかでも、アメリカの場合は定価が決まっていないので、価格を載せてもしょうがないという話もあってのことだとも思うので、理念としてその違いが生まれているということではないと思うのですが、日本のメディアの推移をみていると、「価格の記載はマスト」という、よくわからない行動規範を自分たちに課したことで、とくに雑誌は、ひたすら「商品カタログ」へと堕していくという道筋を辿ったように思うんです。で、これが読者側になにをもたらしたかと言えば、「情報を摂取する」という行為が、自明のこととして“消費”に結びつくはずだ、という条件反射を身体化させていくことだったんじゃないか、という気がするんです。
──ふむ。つまり、餌をみたらヨダレを流す犬のように、雑誌を手にした瞬間に、即、財布を開く準備をするようになってしまった、と。
雑誌に限らず、テレビも、ある時期からは、情報は、多くの場合「消費情報」になっていったように思うんです。「トレンド」と呼ばれるものも、自明のこととして「消費トレンド」のことじゃないですか。で、よくわからない心理構成のなかで、消費することが生き生きと生きることだということもセットで内面化しているので、週末になると意味なく近所の「モール」とかに買い物に行くのが、完全に「人生の一部」になっているわけですよね。で、そこで買っているモノって、実際、特段必要ないモノばかりのようにも思うんですよね。
──ああ。なんかちょっとわかってきました。
情報のインプットが消費という行為を通して解消/昇華・消化するというサイクルが常態になっていると、消費というアウトプットが封じ込められると人は自家中毒を起こし始めるんじゃないか、というのが、この間ずっと感じてきていたことなんです。
とりわけ、エッセンシャルなお買い物以外はダメね、となっている状況下、そうした自家中毒感が昂進しているのだとすると、なんとなくエッセンシャルであるという言い訳も立ちつつ、おおっぴらに消費に走ることを許してくれるアイテムの情報は、みんなが喉から手が出るほど欲しがっているものだったんじゃないか、と思うんです。
──「やったー!」って感じで飛びつく、と。
タピオカがありなら、イソジンだってありなんですよ。タピオカ屋の前で行列していた人に、「タピオカがほんとにイケてるって信じてるんですか?」って聞いても、質問の意味すらわからないと思いますし、おそらくなんの答えも得られないと思うんですが、それとイソジンも同じようにも見えるんです。どっちにせよ、「それを買わなくてはいけない根拠」なんてないんですよ。“買う=消費”自体が目的なので、それを正当化してくれる情報と、それを買える場所があって、そのなかで自己満足感があれば、それでいいんですよ。
──って言われると、もう、なんというか「教育の問題」と言われているほうがまだ救いもあるような(笑)。
いまお話したのはあくまでもわたしの仮説なので、日本人に批判能力がないというのも、もちろんその通りだという気ももちろんするのですが、とはいえですよ、わたしの記憶ですと、自分が中学生のころからずっと、日本人には批判能力がない、なんてことは言われて気もするんです。個性が大事だとか、自分の意見をもつことが大事だ、なんていうことは、それこそ学校でも聞かされましたし、メディアでもずっと言われてきているんですよね。批評精神が大事だ、ってずっと言われてきてるはずなんですよ。
──うー。

とはいえ、この話が、別の意味で厄介なのは、いわゆるフェイクニュースと呼ばれるものとつながっていることで。受け手の心理の問題から話者側の話をしますと、この間に「◯◯がコロナウィルスに効く」みたいな科学的根拠の乏しいことを言ったのはなにも大阪府知事が最初というわけではなく、トランプからブラジル大統領のボルソナロから、「アビガン」って騒いでいた安倍総理まで、それこそ枚挙にいとまがなくてですね、そもそも発信情報の信頼性に疑問符がついているこれらの方々のご意見は、「はいはい」って感じで自然と社会から排除されていくことにもなるわけですが、もう少し巧妙な言説になっていくと「情報の信憑性」というものの特定は、はなはだ困難なものになっていくんですよね。
──「イソジンがコロナに効く/効かない」という話題も、本気で科学的な議論をしようと思ったら、素人にはおいそれとは理解ができない話になっていくでしょうしね。
難しいんだと思うんですよ。というのも、一方に「科学的真実」というものがあって、もう一方にわけのわからん「陰謀論」があって、それが明確にぱっきりと分かれているのかといえば、まったくそういうものではなくて、その間はずっと微妙なグラデーションでつながっているものなんですよね。最近の海外のメディアですと、たとえば「misinformation」と「disinformation」という両方の語が出てくるのですが、前者は「誤情報」、後者は「偽情報」とでも訳すことになるのでしょうけれど、そこには「意図せぬ間違い」と「意図的に捏造された情報」といった区分があるわけですが、これもまたぱっきり明示的に明かされることはないわけで、そこにも精妙なグラデーションがあるわけです。
──たしかに。
『Fast Company』に、「オーガニックな噂」「無邪気なミスインフォメーション」「戦略的なディスインフォメーション」をどう見極めるかといった主旨の論考が掲載されていましたが、「情報の信憑性」という問題は、コロナ禍が推移していくなかで、どんどん前景化しているのが実態でして、インフォデミックこそ核心的な問題であるという感じも出てきているほどです。
──そうですか。
あるいは例えば、これはイギリスの『Tortoise』というメディアの調査報道記事で非常に面白いもので、「5G陰謀論」や「ビル・ゲイツ、コロナ拡散説」といった、いわゆるコロナ陰謀論において、そうした情報拡散の中心にいて最も影響力を与えているのが、ジョン・F・ケネディの甥っ子にあたるロバート・F・ケネディであるとしているのですが、この人、ただの名家育ちの変人かといえばそんなことはなくて、いわゆる環境派の辣腕弁護士として有名な人なんですね。

──へえ。
で、大手石油会社や自動車会社といった、わかりやすい言葉でいうと「巨悪」と戦ってきた人なんですよ。で、アメリカきっての名家であるケネディ家出身じゃないですか。という点ではわかりやすくリベラル側だった人なんです。なので、そうした視点から、仮想敵をたとえば「製薬業界」といった方向に移していけば、おそらくきっと「巨悪」の片鱗はみつかるはずですよね。
──映画『ナイロビの蜂』でそういうの見ました。「製薬会社がアフリカで人体実験をやっている」、とかそういう話ですよね。
ですです。で、これまた心情的な話ですけど、普通に世間的な視点から見ても、今回のパンデミックで世界中のビジネスが大きく打撃を受けているなかで、おそらく鉄板として儲かるのは製薬会社であるのは目に見えているわけで、製薬会社が頑張ってワクチンを早く開発してくれるのは、もちろん応援したい気持ちもありこそすれ、「人の不幸をエサに、こうやってこいつらがまた大儲けすんのか。なんだかな」という思いも、ないわけではないですよね。実際国際機関や各国政府も、不当に値段を釣り上げられたりしないよう戦々恐々としているわけで、そうした状況のなかにあって、一般市民なんていうのはただの“まな板の鯉”でしかないわけですよ。
──映画なんかで観る限り、その手の巨悪と政府はだいたい一蓮托生ですしね、なんらかの副作用があったとか、いわゆる「薬害」と呼ばれる問題があったとしても、もみ消されるのがオチだったりします。
で、もちろん「そんなのは映画の話ですよ」とか言われても、実際にアビガンという薬については露骨な利益誘導だといった批判もあったわけですから、“映画だけの話”ではおそらく済まないんだろう、という感覚は、もう市民側には拭いがたくあるわけで、その不信感は簡単には乗り越えられないようにも思いますよね。
──はい。
というなかで、いわゆる「反ワクチン(anti-vaxxer)」といった運動も起きてくることになるわけで、いわゆるアメリカで問題視されているムーブメントに同調するほどではないにせよ、総論として“ケミカルな薬”は、どこかで信用がおけないなと感じる人は、少なくないと思いますし、そう感じる人のほうがむしろ常識的なんじゃないかという感じすらあるわけですよね。

──ですね。知り合いでも、「ケミカルな薬はできるだけ口に入れたくない」とか「病院にはできるだけ行きたくない」という人は少なくないです。
ですよね。そういうベースのところでは、これまでの医療や創薬の体制というものに対する不信というのはあって、それはまったく正当なものだと思いますし、パンデミックがある意味、そうした既存の体制を強化する方向で動いていくのではないかという恐れも、そこまで不当な恐れだとも思えないのですが、それが先鋭化していくと、なぜかビル・ゲイツなんかが出てきて、「ん?」って話になってきちゃったりもするんですが、そこに論理上の大きな飛躍があるのかといえば、そんなことはなくて、細かくみていくと、どこからが憶測でどこからが事実なのかという境界はおそらく曖昧化しちゃうところがあるんだと思うんですね。
──グラデーションってことですもんね。
たとえば白だったはずの色がいつのまにか赤になっていたとして、色が微妙に推移していくなかで、いったいどの時点から赤が混じりはじめたのかを特定するのは、やっぱり難しいはずなんですよね。だからフェイクニュースの問題を「批判能力の低い人間が騙されている」と断じるのは、あまり現状認識としてもあっていないように感じますし、なんらかの解決にも役に立たないような気がするんですね。

というのも、ようやく今回のGuidesにもつながるのかなと思うんですが、今回トピックとなっている「カンナビス」も、ある部分では、「アンチワクチン的」ともいえる心情に根ざしたところから派生していたりもするはずだからです。
Cannabis at a crossroads
カンナビスの曲がり角
──ああ、なるほど。めちゃくちゃアクロバティックな着地すね(笑)。
今回のGuidesには、あまりコロナがらみの話はないんですが、わたしの知り合いの海外在住の方なんかで、ロックダウン中のストレス解消においてCBDオイルが役に立っているという方もいましたし、それがウイルスに直接効くというわけではないにせよ、数値としてあまり出てきていない有用性はあったんじゃないかという気もするんですね。
数回前にメンタルヘルスのお話をしましたけれども、特にアメリカの場合、メンタルがやられてきたときに最も手近にある“癒し”がアルコールとオピオイドであったと言われていますが、そこにいく手前で、なんらかの手助けになっていたようで、〈The cannabis cowboys are going corporate〉という記事は、5月にアメリカのいくつもの州がカンナビスのディスペンサリー(販売所)を「エッセンシャルである」とみなし、営業停止されなかったことを明かしていますし、パンデミック期間中の売り上げの増加を見るにつけ、多くのアメリカ人が、そう認識していることの現れだと書いています。

──パンデミックの難しさは、なんというか肉体的な病を外科的に“処置する”ことが困難だということでしたよね。つまり、人の身体だけでなく、精神の病みから社会の病みが全体として作用しあっているなかで、どうバランスを取るかがとても難しいというか。もちろん、病いの原因を隔離・切除することで処置するという西洋医学的な「医療」は必要不可欠ではあるのですが、明らかにそれだけでは不十分、という。
ベタな言い方にはなりますけれど、「治癒」というものについて、もっとホリスティックなアプローチが必要なのではないか、ということは医療に限らず、さまざまな分野で言われていることだと思うのですが、今回のパンデミックはほんとうに、これまでの外科的な措置というものの限界を露呈しました。上の記事は、カンナビスをこう説明しています。「カンナビスは、医療、農業、コンシューマーグッズ、食品、飲料、娯楽のユニークな交差点に存在している」。
──面白いですね。全体性があります。
カンナビスのこの位置付けは、日本で馴染みのあるところでいえば「漢方」に近いと思うんです。上記の説明の部分でいうと、娯楽的な要素は薄いですが、医療であり食品であり、飲料でありといった部分ですよね。で、その効用を、自分たちは、単なる「医学的な機能」よりも、だいぶ膨らみのあるものとして認識していますよね。薬膳みたいなものもと地続きなものとしてあるわけですし。
──たしかQuartz Japanの年吉編集長は、最近漢方を飲むのを始めたそうですよ。
実は、自分もコロナ下で、漢方飲み始めたんです。
──おお、奇遇ですね。
自分は、その辺の薬局で販売している市販のものを買って飲んでいるだけで、体がだるかったり頭が痛かったりするときに服用しているんですが、たしかに即効性という意味では、ケミカルな薬品にははるかに及ばないんですが、それでもいわゆる薬を飲むストレスと比べると気分的にも格段にいいですし、もう少しちゃんと処方されたものだったりすると体調を調えていく上では役に立ちそうで、単なる思いつきですが、駅にある生ジュースのスタンドみたいな感じで、漢方ドリンクのスタンドとかやったら儲かるんじゃないか、と思ったりしています(笑)。
──いいですね(笑)。儲かりそう。
コロナに関するこの間の世界のニュースで個人的に非常に面白かったのは、6月5日に香港のメディア『Inkstone』が掲載した記事で、「漢方薬を国家医療システムの重要な要素として位置づける中国政府が、漢方を貶める言動を違法とする法案を提出し猛反発を受けた」というものなんです。
──へえ、面白いです。
政府は、その反発を受けて、「漢方薬は世代問わず広く支持され、COVID-19感染者7万4,000人に処方され90%の患者に効果があり、その処方箋は3世紀のものだ」と語ったそうなんです。漢方をディスったり、その科学的根拠を否定したりする言説を違法とするのはさすがにやりすぎだとしても、中国政府がこういったかたちで、西洋医療とは異なるオルタナティブな医療を、国家戦略のなかで重きを置いているのは、いままでの論点からいくと、決しておかしな話でもないように思うんです。加えて、中国政府は、漢方の重要性は、医学的なものとしてだけでなく、“ナショナルプライド”の源泉であるとみなし、文化政策としても重要であると認識しているそうなんです。もっとも、その部分が、反発を招いたわけでもあるんですが。

──ふむ。
ホリスティックであるというのは、でも、ある意味そういうことでもあると思うんです。
──と、言いますと。
医療って、本来的にはというか歴史的には、食と一緒で、その土地の自然に根ざしたもの、文化に根ざしたもの、社会に根ざしたものとしてあったわけじゃないですか。という意味で、環境的なものであり文化的、社会的なものであったはずが、近代医療のいわゆる「科学的/外科的」アプローチが普遍化していくなかで、そうしたものは迷信にも似たものとして「民間療法」などと呼ばれて、どんどんマージナライズされていったわけですよね。
その結果、何が起きたかというと、その「科学的/外科的」なアプローチそのものによって、医療というもの自体を、医療が自ら、社会やコミュニティといったものから自己疎外していくことだったように見えるんです。って、病院って、いつまで経っても社会のなかにあって、異様な姿の近寄りがたい異物のままじゃないですか。
──コミュニティと一体化して見える大病院って、ないですよね。
そりゃそうですよね。それは一種の隔離施設なわけですから。社会から切断するためにある場所なので、馴染んだら困るというのが、その基本理念なわけですし。で、もちろん、その機能を否定するわけではないですが、近年は、やっぱり、病院っていうものもリデザインされて、コミュニティに開かれたものになって行かなくてはならないという話にはなってきていまして、そうやって、もう一度、その土地の文化、風土のなかに医療というものを埋め込み直さなくてはならないというなかで、これまで“周縁化”されてきた療法なんかも見直されてきているんです。
──なるほど。
2016年に、自分が編集長を務めていた『WIRED』で「BODY & HEALTH」という特集をやった際に、ドイツにある「世界一厳格なメディカルスパ」を取り上げたのですが、そこで採用されていたのは「FXマイヤー療法」と呼ばれる20世紀初頭の自然療法で、いまでいえば予防医学の一種なんです。
「オーストリア出身の自然療法士、フランツ・クサーヴァー・マイヤーが確立した『予防と再生』を第一義とする健康法だ。マイヤー博士の理論では、消化器、とくに腸のデトックスと洗浄が『予防医学の出発点』とされる。博士は現代人の食生活を『過食』と断じ、質のよい食物を自分の身体(の大きさではなく内臓の能力)に合った量だけ食べること、そして、食べる際には、とにかくよく噛むことという、いたって根源的な食事法を患者たちに厳しく課したそうだ」
と、記事では説明されているんですが、こうした施設が人気であるのも、やはり健康や身体を、ホリスティックに捉えるアプローチがあるからですよね。
──ふむふむ。
カンナビスというものについていえば、これはもう単にマージナライズされたばかりでなく、「凶暴な犯罪者が服用するものである」というキャンペーンがアメリカで長きにわたって強固に推進され、しかもそれがある特定の人種の人びとを迫害するための根拠とされ、かつそれによってアメリカの刑務所ビジネスをサステインさせる口実にも使われてきたことによって、強烈にネガティブな社会イメージを植えつけられてきたこともあるので、それを脱違法化するにいたるには長い道のりがありまして、そうしたなか、カウンターカルチャーのなかで、長い時間をかけて、その文化性も含めて回復されつつあるという状況ですが、アメリカの文化風土のなかにおいては、「カンナビス」は根深く人種問題と関わってきているんです。

──そうなんですね。
例えば「カンナビス」という言葉は、これまで「マリファナ」というスペイン語で一般化していましたが、そもそも、わざわざスペイン語が採用されたのも、わたしが観たNetflixのドキュメンタリーによれば、ヒスパニックの移民を抑圧するためだったとされています。
──へえ。
で、人種問題について言いますと、ジョージ・フロイド殺害をめぐる熾烈なプロテストと警察のミリタリー化の背景には、アメリカがこれまで猛然と推進してきた「対麻薬戦争」があると、『VICE』が6月に念入りな論考を掲載していますが、そのなかで、警官によって殺害された黒人がカンナビスを服用していたことを根拠に警官による殺害が「正当防衛」となったとされる事例がいくつも出てきます。そこから、警官と市民の軋轢を緩和する上で、カンナビスの合法化が有効である、との議論も提出されていると、Quartzは語っています。
──複雑ですね。
そうなんです。カンナビスの問題、特にアメリカにおけるそれは複雑に政治が関わっている問題ではありますので、非常に根が深いんですね。と、一方で、アメリカのカンナビス事情を見ていて難しいな、と感じるのは、中国政府が漢方をナショナルプライドの源泉だと語るような、ある意味でポジティブなナラティブを、アメリカ文化、特に、カンナビスそのものによって抑圧されてきた黒人や有色人種の側が打ち出せてこなかったところにあるような気もします。これは先にお話したNetflixのドキュメンタリー「The Grass is Greener」を観ていて思ったことなんですが。
──どういうことでしょう。
アメリカはいわゆるケミカルなドラッグもカンナビスもいっしょくたにして「ドラッグ」と定義していたわけで、カンナビスをめぐる長年の闘争は、そのリストからカンナビスを外せ、というものだったんですが、先のドキュメンタリーを観ていて思ったのは、実は使用している側も、ある時期まで、政府側のナラティブをそのまま“内面化”してしまっていたんじゃないかと感じたんです。
これは、ジャマイカのレゲエミュージックにおけるカンナビス(ジャマイカですとガンジャと呼ばれたりしますが)、との比較でみるとよくわかるんですが、レゲエ音楽のコンテクストにおいて、ガンジャは、ほんとうに特別な意味をもっていて、それが身体にもいいし、魂にもいいし、世界にもいい、ということが明確に歌を通して、別の言い方をすると“文化”として定義されているんですね。
ですから、彼らは、もちろんその他のドラッグにもときに手を染めることもあったにせよ、ヘロインやコカインとガンジャを同じ平面に並べて認識するという発想がないはずなんです。それは聖なる薬草で、まさに「ハーブ」であるという、そういう価値定義があるのが、実は、アメリカの文化においては、葉っぱを吸うことが「反体制の身振り」であるということでしか価値化されずにいたのじゃないかという気がするんですね。
──カウンターカルチャーでしかなかった、と。
そうなんです。カウンターっていうことは先に体制ありきの話なので、逆にいうとその体制に依存してしまうという側面があるわけですよね。でも、ジャマイカにおける「ハーブ」は、カウンターカルチャーじゃないんですよ。で、先のドキュメンタリーにおいては、カンナビスをほかのドラッグといっしょくたにしないで、そのポジティブな面を価値化していく新しいナラティブを導入した人たちとして、サイプレス・ヒルやスヌープ・ドギー・ドッグが重要な役割を果たしたと語られています。
──ははあ。スヌープは、なるほど感ありますね。自分でカンナビス・ビジネスもやっていますしね。
そうなんです。それではたと気づいたのは、スヌープってある時期からレゲエをやる「スヌープ・ライオン」という別ペルソナがあるんですが、おそらくなんですが、カンナビスをカウンターカルチャーではなく、ひとつの自立した文化として立てるために、スヌープはレゲエというコンテクストを補助線として引く必要があったんじゃないか、ということなんです。そうやって、はじめて、カンナビスはピースフルでポジティブな価値をもつんだというナラティブが確固たるものになっていったのではないか、と。

──面白いですね。
ちょっと脱線してしまいましたが、カンナビスは、ボブ・マーリーが歌ったように「ハーブ=薬草」なわけですし、レゲエでは「ブッシュドクター」なんていう概念が頻繁に提出され、ピーター・トッシュの歌詞によればそれで緑内障が治るそうなんですが、そこには非西洋由来の民間療法の痕跡がありまして、それを現状のシステムに対置しつつ、コミュニティの文化的・宗教的・政治的なアイデンティティとして称揚するというナラティブがあるんですが、アメリカには、そういう立脚点がないところが、なかなか苦しいところだな、と遠くからみていて思うのですが、実は、今回のGuidesが、カンナビスの話をしながら、基本ビジネスの話であるというところにも、その苦しさは出ているのかなと感じたりします。
──あ、そうなんですね。いままでの話は枕だったと(笑)。
実はそうなんです(笑)。今回のGuidesは「カンナビスの交差点」というタイトルで、この数年で爆発的な飛躍を遂げたカンナビスビジネスが、曲がり角にきているという話なんですね。
──そうなんですか。
はい。で、その基本的な論旨がどういうものかといいますと、わっと花開いたビジネスが、いま資金力のある会社によってどんどん統合が進んでいっていて、いずれは4社によって牛耳られるビール産業のような道筋をあゆむのではないか、という危惧が寄せられているわけです。
──なあるほど。
〈Curaleaf wants to be the Starbucks of weed〉という記事では、「カンナビスのスタバ」と謳われるCuraleafという会社のCEOがインタビューされていますが、まず驚くのは、この人物がきちんとスーツにネクタイを締め“コーポレートな感じ”の人物だということで、それはそれで、カンナビスビジネスは長髪のヒッピーがやっているというイメージを払拭する上で大事なことだとも思いますし、インタビューのなかで彼も「対麻薬戦争」に触れながら、「カンナビスはソーシャルジャスティスに資するものだ」と言っているのも、その通りだと思うのですが、とはいえ、カンナビスビジネスが、次第にコーポレート主導のビジネスに展開していくのだとすると、ちょっと「なんだかな」となるわけですよね。
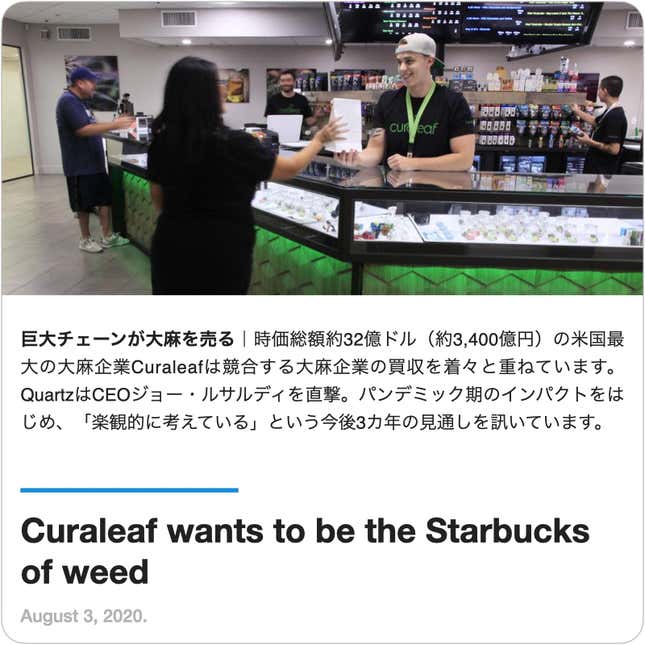
──どうしてでしょう。
これも、先に紹介した〈The cannabis cowboys are going corporate〉という記事に書かれていますが、ウォール街が産業自体に大きな関与をもち出すことによって、これまでのあらゆる産業がそうであるように投資家向けのビジネスへとそれが変わっていってしまうことになってしまっては、“脱違法化”の意味が損なわれてしまうと懸念されています。
結局いくつかの独占企業によって市場が牛耳られてしまうことで、ホームメイドのローカルな農家やブランドが締め出されるのは、脱違法化の主旨にも反するじゃないか、との指摘が記事にはありますが、先に紹介したCuraleafはニューヨーク州のクオモ知事に対して、まさにホームメイドウィードを禁止するよう働きかけているそうなんです。
──なんだかな、ですね。
カンナビスに対する市民側、消費者の期待や欲求は、さっきからお話しているように、あるローカリティに根ざした、ホリスティックな価値の部分だと思うんですが、資本主義/株式会社によってドライブされる産業化は、結局のところ、そうした価値を土地やコミュニティから引き剥がし、機能性や効能の定義によって商品化を進め、その全体性を損なうことになりそうで、不思議とこの特集ではあまり言及されていないのですが、それこそ映画『インサイダー』のなかで描かれた「巨悪」としてのタバコ産業のようなものが再び出現するといった未来図が容易にアタマに浮かんでくるようです。

──どうしたらいいんですかね。
ビール産業が4社独占だったところ、そこにある種の民主化が起きて、地場のクラフトビールがわっと出てきて、そうした選択肢の多さの楽しさに消費者も気づいていく過程がこの間あったわけですから、本当は望むべく産業の先行きとしては、基本が「地ビールならぬ地ヘンプ屋」がわっとたくさんあるという未来が楽しそうに思うのですが、アメリカを見ていると、本当にそうなるのかなという危惧は募りますよね。カンナビスは、本来は、そういう意味での「民主化」の象徴のようなアイテムであるはずですから。
──ふむ。
勃興直前のインドのカンナビス・ビジネスを扱った記事〈India has the world’s biggest cannabis industry that doesn’t exist yet〉は、ヒンズー教文化のなかでシヴァ神の好物と伝えられており、そうした宗教文化における慣習のなかで、7,000万人くらいの人が毎年一度はカンナビスを服用しているといったことをレポートしていまして、ゆえに、インド市場の成長性が極めて高いことを明かしているのですが、そうした話も、カンナビスが、アメリカの大企業が主導するグローバルビジネスになっていった先行きのなかで、グローバル企業のただのサプライチェーンの一環としての位置付けしか与えられないということになると途端につまらない話になってしまいますよね。インドから、むしろ変わったグローバルブランドでも出てくるとまだ面白いですけど。

──なんかあれですね、映画でいうところの『インサイダー』や『ナイロビの蜂』が描いた「巨悪」に対する不審/不信から、ひとつのオルタナティブな可能性として提出されたものが、結局は別の「巨悪」を生み出すような構図になっていて、なんだか最初の話に戻って来ちゃいましたね。
ですね。「コロナにはカンナビスが効く」なんていう話が、いま持ち上がったとしたら、合法化を望んでいる人にとっては、一瞬は朗報のように聞こえるかもしれませんが、そこに巨大産業化を目論む陣営と、その利権にぶらさがろうとする人の結託が疑われなくもないところまで事態は進行しつつある、と、今回のGuidesは明かしているわけですからね。
──とすると、そこがまたひとつの陰謀論の温床にもなりえますよね。
ほんとに、これはもう、ややこしい話です。
若林恵(わかばやし・けい) 1971年生まれ。『WIRED』日本版編集長(2012〜17年)。2018年、黒鳥社(blkswn publishers)設立。NY在住のジャーナリスト 佐久間裕美子とともホストを務めるポッドキャスト「こんにちは未来」のエピソードをまとめた書籍が発売中。
このニュースレターはSNSでシェアできるほか、お友だちへの転送も可能です(転送された方の登録はこちらから)。