A Guide to Guides
Guidesのガイド
Quartz読者のみなさん、こんにちは。週末は米国版Quartzの特集〈Guides〉から、毎回1つをピックアップ。今週も、世界がいま注目する論点を編集者・若林恵さんとともに読み解きましょう。

──こんにちは。いきなりですが、今回は「香港」がお題です。
困りましたね。
──なんで困るんですか?
なんか難しいじゃないですか。
──でも、北京政府のやり方はひどく乱暴じゃないですか。それと戦う香港市民を応援したい気持ちは、そうは言ってもあるんじゃないですか?
心情的にはもちろんそうなんですよ。それはそうなんですが、とはいえ、「頑張れ!」って言った先に何があるのかがよくわからないところもありまして、簡単に「頑張れ!」と言うのも難しいな、と思ったりするんです。
──煮え切らないですね。
いつもそうですよ。ちょっと全然関係ないんですけど、山Pって人のお話していいですか?
──あ、逃げた(笑)。
「遠回り」と言ってください。
──はいはい。で、山Pがどうしたんですか?
つい先日、ある知人から「若林さんは山Pの問題ってどう見てます?」って聞かれて、まず「山P」って誰のことだよ、となりまして(笑)、ちょっと調べてみたんです。
──ジャニーズの山下智久さんですよ。
で、なんか問題を起こしたんですよね。
──高校生と飲んでたという話ですよね。謹慎処分になってましたね。
ですよね。で、私は、もうこの手の芸能スキャンダルはそもそもどうでもいいと思っていますし、基本マネジメントサイドのガバナンスの欠如の問題だと割り切ることにしちゃっていますので、それ以上思うところもあまりないのですが、ちょっと調べていくなかで面白い記事に出くわしたんです。
──ほお。
〈山Pに忍び寄る中国共産党 “ハニトラ”のエジキになる可能性〉という記事でして、これ、出元が『東京スポーツ』なので、その分はすこし差っ引いて読まないといけないとは思うんですが、非常に面白いものです。
──どういう内容なんですか?
まず、ジャッキー・チェンの話が出てくるんですよ。
The global fight for Hong Kong
香港のダブルバインド
──ほお。香港の話ですね。
そうなんです。ジャッキー・チェンって、もともとは言わずと知れた香港映画界のスターですが、ある時期から共産党寄りの立場を取るようになって、香港では「北京の狗」と言われるほどまでに嫌われる存在になっていまして、デモが加熱している最中にあっても、北京政府を擁護するような発言を繰り返しているとされています。
──悲しいですよね。
で、この記事によれば、そうした「転向」のひとつのきっかけとなっているのが、息子のジェイシーが北京で大麻所持容疑で逮捕された事件だそうなんです。
──へえ。
2014年に友人の台湾人俳優とともに逮捕され、6カ月の有罪判決を受けているというんですが、これは中国においては異例と言っていいほどの軽い判決だそうで、香港のジャーナリストのコメントを引用すると、「これほど軽い判決だったのは、父親のジャッキー・チェンが息子を救ったという説がもっぱら。それ以降ジャッキーは、中国共産党がどんなに横暴なことをしても支持する姿勢を貫いている」ということになるそうです。
──言うなれば、息子を人質に取られて、魂を売らざるをえなくなったと。
それが、そもそも共産党の言いなりにならざるを得なくなったきっかけなのか、あるいは、すでに共産党の言いなりになっていたから息子を救うことができたのか、その辺の前後関係はよくわからないのですが、この話がなぜ、山Pさんと関係あるかと言いますと、この逮捕された息子と山Pさんがお友だちだというんですね。
──なんと。
以下、引用となります。
「山下はこのジェイシーと友人関係。11年1月から5月まで、自身初のソロアジアツアーを開催した山下は、ツアー初日の香港公演で、客席にいるジェイシーにスポットライトを当て『He is my friend!』とファンに紹介していたのだ。当時、地元クラブへ繰り出したときのプライベート写真がネット流出したが、山下を連れ出した人物こそ、他ならぬジェイシーだった。
『山下は今回の“未成年スキャンダル”によって、女遊びが好きな日本人スターと見なされた。中国共産党はハニートラップを仕掛けるだろう。仕事で訪中した際に美女を差し向け、それを弱みに中国寄りの発言をさせるよう仕向け、広告塔にするとか。あるいは、日本の芸能界の闇情報を中国共産党に流す役目を負わされるかもしれない』(香港のジャーナリスト ジェイ・シン)」
──むむむ。つまり、中国政府は、有名タレントの弱みを握り、自国に有利なプロパガンダを、それぞれのタレントの母国に流させることを、戦略的にやっているということですね?
少なくとも香港で起きたことはそうだというんです。銭俊華さんという香港出身の地域文化研究者が書かれた『香港と日本 ──記憶・表象・アイデンティティ』という、この6月に筑摩書房から出た新書があるのですが、ここに「集合的記憶と香港芸能人の死滅」という節がありまして、このなかで、香港の芸能人が“裏切り者”へと堕していったさまを厳しく断罪しています。

大規模なデモの最中、10月1日の中華人民共和国の建国記念日に中国のTwitterであるところの『Weibo』上で、本土のファンに向けて「誕生日おめでとう」「祖国を愛する」といった投稿を香港の「多くの芸能人」が行ったことについて、「デモを支持する多くの香港人にとって、それらの芸能人は香港の裏切り者であるだけでなく、道徳がなく、卑劣で、気持ち悪い人間ということになった」と銭さんは書いています。
──なるほど。ツライ話ですね、それ。
今年の3月にキムタクさんと工藤静香さんの長女のCocomiさんがデビューされたじゃないですか。
──今日はやけに芸能ネタすね(笑)。
そのときに、キムタクさんがですね、Weiboで娘さんを紹介する投稿をしたというニュースを見て驚いたのは、「え、キムタク、中国ではSNSやってんの?」ってことでして。というのも、ジャニーズって日本国内で最もデジタル対応に背を向けてきた企業で、画像の掲載すら禁じてきたわけで、それこそジャニー喜多川さんがお亡くなりになってから雪崩を打ったようにデジタル空間に入ってくるようになってきていますが、個人的な見解では、「デジタル」と「ヒップホップ」へのジャニーズ事務所の対応の遅さが、日本のグローバルアップデートを遅らせたと思っているくらいなんですが、なんのことはない、中国本土では、戦略的にやっていたわけですよね。
──日本の芸能人は結構、Weiboやってるはずですよ。例えば、2019年10月のものですが、『日経Xトレンド』に〈木村拓哉や山下智久も 中国SNS「Weibo」に続々参戦する理由〉なんていう記事がありまして、こう書かれています。
「編集部が独自に日本のタレントを調べたところ、最多フォロワー数は、12年にアカウントを開設した福山雅治で534万4819人。13年からスタートした三浦春馬と古川雄輝が、それぞれ376万6508人、339万456人と、Weibo歴の長い俳優が上位を占めた。彼らに共通するのは、中国作品への主演経験だ」
「山下(フォロワー数172万3176人)と木村(同161万3113人)も、それぞれ『サイバーミッション』(19年)、『2046』(04年)で、中国映画への出演経験がある」。
なるほど。ビジネスを考えれば、それは必須事項とも言えることだと思いますので、そのこと自体の是非を一概に問題にするわけには行きませんが、こうした状況を、香港で起きた“芸能人の死滅”という事態と照らし合わせてみると、やっぱり結構怖い話になってくるように思うんです。
──たしかに。
先ほど「弱みを握る」ということばが出ましたけれど、ハニートラップとか、麻薬所持容疑による逮捕という以前に、すでに“経済”というところで、実は弱みを握られているという実情はあって、特に、台湾、香港、韓国、そして日本といった国は、ドメスティックマーケットでのビジネス拡大がこれ以上は望めないというなかで、やはり中国本土というのは目指さざるをえないマーケットにはなっているわけで、ただ、チャイナマネーに依存すればするほど、中国政府に対して厳しい態度を取れなくなるわけですから、「13億の巨大市場」というもの自体が一種のトラップになっていくわけですね。
──怖いですね。
昨年、香港に2日ばかり行って、雑誌『STUDIO VOICE』のアジア特集の編集を担当したスタッフと一緒に地元のヒップホップアーティスト数人に会ったんですが、そのインタビューがちょっと衝撃的だったんです。
──ほお。
というのも、会うなり愚痴なんですよ。20歳そこそこのアーティストが「10代のころから5〜6年ヒップホップをやってきたけど、もうなんのためにやってるのかわからなくなってきた」って、いきなりこうなんです。
──どうしちゃったんですか。
彼が続けて言うには、「もう香港では誰も音楽なんか聴かないんすよ」って。
──どうしてですか?
彼が言うには、「家賃もどんどん上がっているし、みんないい仕事につくことで頭がいっぱいなんだよ」ということだそうで、「音源をネットに上げても、反応してくれるのは本土のリスナーばかり」という状況だそうなんです。
──それは苦しいですね。といって、本土に向けてつくるようになれば、「裏切り者」と言われることになるわけでしょうし。
そうなんです。で、自分は昔、それこそ映画監督のウォン・カーウァイがデビューしたころに学生時代を送ったので、映画を含めた香港文化の活況って、ものすごく眩しいものに見えていた記憶があるんです。なので、「昔はあんなによかったじゃない」って話をしたら、有名な映画会社なんかは「とっくの昔になくなった」と言うんですよ。例えば、カンフー映画を世界化したゴールデンハーベストなんていう会社は、97年の返還前後に苦境に立たされ、スタジオなどを閉鎖し、2007年に本土企業に身売りしちゃうんですね。

──ゴールデン・ハーベストといえば、ブルース・リーからジャッキー・チェン、サモハン・キンポー、チョウ・ユンファといったスターを国際化した名門中の名門じゃないですか。
ジャッキー・チェンはもちろんですが、サモハンの『Mr.Boo!』なんていうシリーズは、それこそ普通に地上波で放映されていましたし、自分は小学生でしたが、クラスの誰もがサモハンは知っているくらいの勢いで、ジェット・リーのデビュー作の『少林寺』なんか、「クラスのみんな」は大げさにしても、「友だちと連れ立って観に行った」というくらいのキラーコンテンツだったんですよね、この日本でも。
それが、気づいたら、中国マネーの軍門に降っていたということになるわけですが、そう考えると、ジャッキーが転向した、といった話は、個々人の道徳心の話では必ずしもない、ということでもありそうで、大きくいえば、文化産業が、20年近い時間をかけて切り崩されていったわけですよね。
──怖いすね。
そういう意味では、先ほどの香港ラッパーのことばは、かなり聞いていて胸が苦しくなるものでもあったんですね。これは銭さんが『香港と日本』で書かれていることでもありますが、かつて国民が憧れロールモデルとしたようなスターや、自分の青春の思い出やアイデンティティの基盤をなしていた音楽や映画作品が、ここにきて自分たちに敵対するものとして立ち現れてくる、というわけですから、これは相当にキツい話なんだろうと思うんです。
──市民と文化が敵対させられている、と。
それこそジャニーズのタレントのすべてが自分たちを抑圧しようとしている機構の擁護者であったり、あるいは宮崎駿さんのような方が“転んで”、『ナウシカ』も『トトロ』も「もう観るに堪えない」とならざるをえない事態を想像してみたら、これは結構厳しい話じゃないですか。
──文化的アイデンティティの崩壊ですね。
まさに。で、それをおそらくなんですが、中国政府は非常に周到に、戦略的に仕掛けているんですよ。去年見た記事ですが、北京政府は、次は台湾をターゲットとして、台湾の映画祭「金馬奨」に中国本土の俳優や監督を参加させない、といった脅しをかけていたりもするんです。で、これは暗に「『金馬奨』に参加する俳優や監督と、本土は一線を引く」というメッセージとなるわけですから、台湾の産業全体も、個々人の製作者や俳優さんも、“踏み絵”を踏まされることになっていくんですね。
映画.comの記事〈大陸からの圧力か?映画賞「金馬奨」授賞結果に台湾人の不満が噴出〉は、2014年のものですが、この時点では、もちろんいまの香港の帰結は、もちろん予測できなかったとはいえ、この時点ですでに“侵攻”が始まっていたのは、今にして見れば明らかなのではないかと思います。
──言われてみると、あれですね、香港のデモには、文化人が登場しないですね。
そうなんです。そのことが、自分もある時期からものすごく気にはなっていまして、それこそBlack Lives Matterの勃興期において、ケンドリック・ラマーがそれを文化化したり、Run The Jewelsのキラーマイクが胸をうつ演説をして素晴らしいアルバムを発表したり、あるいはビリー・アイリッシュやテイラー・スウィフトのようなアイドルが反トランプを明言したりといった、そういう動きが、自分が知らないだけかもしれませんが、ほとんど見えないんですよね。それこそ天安門事件のことを思い出すと、音楽好きの自分としては、崔健(ツイ・ジェン)なんて人の音楽がバックグラウンドに流れていた記憶があるんですよ。
──誰ですか、それ?
中国ロックのパイオニアのひとりで、ライヴのときに赤いハチマキで目隠しをしていて、ポリティカルでカッコよかったんです。一応Wikipediaから引用しておきますよ。
「1989年に、北京で天安門事件が起こった頃、人気の絶頂にあり、『一無所有』はストライキ学生たちの愛唱歌となった。崔健のコンサートは余りに人気があるため、中国共産党によって許可が下りないようになり、2003年まで大きなコンサートは開けなかった」
2012年に本人に『VICE』が行ったインタビューがありますので、興味ある方はぜひ観てみてください。
──今回の香港のデモについていえば、周庭さんという方が、ある意味アイコンになっていますけど、どうなんでしょうね。
もちろんアグネス・チョウさんの信念や献身を疑うつもりは毛頭ないんですが、ただ、欅坂46が好きといった彼女のコメントを見るにつけ自分が思い浮かべてしまうのは香港のラッパーたちの苦渋で、彼らからすると、そういうアグネスさんこそが「音楽なんか聴かない香港人」の象徴のように見えているのではないか、と思ってしまうんですね。
──ふむ。
何が悲しいかといえば、おそらく彼らのようなラッパーこそが本当はデモのナラティブをつくったり、音楽という非言語を用いて、デモの大義を後押ししてくれるはずなのに、アグネスさんがよすがとしているのがおそらく一番“体制側”に転びそうなところにいるアイドルグループだというところなんです。残念ながら、欅坂からは、どこをどう押しても「アグネスさんを支援する」というメッセージは出てこないと思うんです。
──ビジネスとしてアジアマーケットを大事にすればするほど、中国政府にモノがいえなくなる、ということですよね。スポーツでもNBAは一悶着ありましたしね。
あれなんかはまさに典型的で、NBAのヒューストンロケッツのGMが「香港支持」のツイートを撤回させられましたが、NBAのような極めてパワフルなコンテンツホルダーでも、思うことが言えないわけですから、大方の企業や個人が転ばざるを得ないのも仕方ないところはあるんじゃないですかね。
──それこそ、香港の絶大なる味方であるはずのアメリカですら、正面から喧嘩は売れないところはある、と。
今、アメリカがかなり強硬にバチバチとやりあっているのは、トランプがそのことに非常に熱心だからという側面もあると思うんです。それがバイデンになった瞬間、弱腰になっていく可能性は非常に強いわけですし、ヨーロッパでも、こと対中関係においてはメルケル首相ですら煮え切らないところもありますし、その辺、非常に難しいダブルバインドになっているように見えるんです。
──香港のデモを支持するならトランプ支持の方が論理的には妥当じゃないか、と。
そこまで明言はできないようにも思いますが、それでも「バイデンは中国に対して弱腰だ」という言い方をトランプは盛んにして、民主党政権になったら「アメリカで中国語が必修になる」と、うまいやり方で煽ったりしています(CNN.jp〈バイデン氏勝利なら「米国民は中国語習得が必要に」トランプ氏が主張〉)。それに対抗するかたちでバイデンは「強硬姿勢を貫く」とは言っていますが、疑問符をつける声がとりわけ保守陣営からはあがっています。

──むむむ。
『産経Biz』は〈「中国に手ぬるい」批判に対抗 バイデン氏が対中強硬打ち出す〉という記事のなかで、「台湾問題に関しては、台湾支援の立場を明確にするトランプ政権とは対照的に、バイデン氏周辺の外交専門家は『一つの中国を尊重すべき』とする民主党の伝統的立場を打ち出しており、中国に付け入る隙を与える恐れが強い」としていますし、『Newsポストセブン』が掲載するアメリカの保守系メディア『American Thinker』という一見するとフェイクニュースサイトに見えなくもないところからの翻訳記事〈憂慮すべきバイデン親子の中国ビジネス〉には、こんなことが書かれています。
「バイデン氏が大統領になれば、中国の国益にかなうことは間違いない。彼の息子であるハンター・バイデン氏も、それによって恩恵を受けるだろう。彼は過去10年間、中国政府が支援する投資会社BHRの取締役を務めてきた。ニューヨークタイムズの報道によると、ハンター氏は2017年に同社の株式の10%を約42万ドルで購入したという。ジャーナリストのピーター・シュワイザー氏の著書によれば、ハンター氏は父親がオバマ政権で副大統領を務めていた時期に中国を訪れ、同社は中国共産党との間で15億ドルの巨額投資契約をまとめたのだという」
──困りましたね。
上記のような「バイデン・民主党=親中国」という語りは、まあ、保守党の常套句ではありそうなので、全部が全部真に受けていいのかどうかは保留も必要かとも思うんです。ただ、アメリカと中国との香港をめぐる綱引きのなかで、一番気にしておかないといけないのは、今回の〈Guides〉にある記事〈The US-China standoff is turning Hong Kong into a more valuable—and more Chinese—financial hub〉が指摘している内容なのかな、と思ったりしています。

──と言いますと。
要は、経済が結局は政治よりも優先されるということですね。この記事が指摘しているのは、デモや国家安全維持法の施行をめぐる騒乱を経ても、香港の株式市場(HKEX)が停滞しているどころか、急激に伸長しているということなんです。
──え、そうなんですか。
この記事は、「香港市場を見ている限り、米中関係が最悪の局面あることを読み取ることは困難だろう」という一文からはじまっていまして、中国政府による反民主的な管理体制の施行は、香港の金融市場の魅力を決定的に損なうことになるとするこれまでの予測や、この予測に基づく国際的な圧力は、まったく効果を表していないとしています。
──うーん。どうしてなんでしょう。
記事によれば、この間、アメリカで中国企業のビジネス活動や上場を厳しく制限すべきとの声が上がるなか、アリババやJD.comといった大手企業がニューヨーク・ストック・エクスチェンジやNASDAQに代わる資金調達の拠点を求めて香港市場での上場を進めつつあることが指摘されていまして、その大きな誘引力として、ニューヨーク市場やNASDAQといった市場との競争力を高めるために、アメリカではずっと批判に晒されてきている「dual-class shares」(デュアルクラスシェア)を2018年に導入したことが挙げられています。
──なんですか、それ。
自分もこの辺はまったく得意な分野ではないので、よくわかっていないのですが、試しに『M&A Online』というサイトを見てみますと、こう書かれています。
「起業家(創業メンバー含む)に対して、1株で複数の議決権が付与された株式(B種普通株式と呼称されることが多い)を割り当てるもの」
「最も多くみられるのは、B種株式1株当たり10議決権を付与するスキームだ。A種普通株式は当然1株1議決権なので、B種を持つ創業者の議決権割合は発行済株式数の保有割合より高くなる。これにより、起業家が会社の所有権(過半数の維持を狙うことが多い)を掌握することが狙い」
──どういう効果があるんですかね。
簡単に言うと、創業者が株主の意向と衝突することなく会社経営を行うことができるようになる制度なので新興企業やいわゆる”ディスラプティブな”イノベーション企業には願ってもないものなのですが、これを採用したWeWorkの親会社We Companyの暴走が問題化されたように、企業の暴走を防ぐ安全弁であるところの株主の役割が無効化してしまうことが起こるそうです。上記のサイトのこの記述を読めば、だいたいどういうことかお判りいただけるかと思います。
「デュアルクラスといえば、識者がまず思い浮かべるのは、米Alphabet (以下、グーグル)や米Facebook(以下、フェイスブック)だろう。グーグルは創業者のLarry Page氏とSergey Brin氏及び一部の経営陣で議決権の約58%を確保している。一方、Facebookでは創業者のMark Zuckerberg氏が、委任された議決権も含め、やはり約58%の議決権を確保している。
だから、いくら世間が両社の独善的な経営を非難しても、少なくともコーポレートガバナンス(株主統治)の観点で彼らにブレーキをかけることは難しい。
例えば個人情報の問題が明るみに出たフェイスブック。最近の株主総会で、外部株主からこのいびつな資本構造を解消すべきという株主提案がなされた。これに外部株主の実に83%が賛成している。言うまでもなくこの提案は、同社会長兼CEOのザッカーバーグ氏個人により否決されている。
まさに『金は出せ、口は出すな。儲けさせてやるから』というところか」
──ははあ。
イノベーションを加速させる上では有用な仕組みでもありつつ、それが暴走したときに歯止めが効かないという問題点がアメリカで大きく取りざたされているなか、香港が逆にそれに門戸を開いた、というのは想像以上に大きな意味がありそうで、もしかすると今後のイノベーション企業の世界的な中心地として地位を、香港はこれを機に一気に占めることになるのかもしれません。加えて、この制度の導入と同時に、HKEXはバイオテック企業に大きく門戸を開いたとの記載もあります。

──なるほど。
中国の世界覇権を扱った回で、次世代テックの国際スタンダードを握ることを中国が狙っていることに触れ、「China Standard 2035」というまだ全貌が明かされていない国家戦略を紹介しましたが、そうしたビッグピクチャーを睨みながら、香港という場所を見直してみると、香港が重大なピースであることが見えてきそうです。
──深圳の隣ですもんね。
まさにイノベーション都市である深圳をドライブさせる金融装置としての香港株式市場の立ち位置が、ここで明らかになってくるのかもしれません。同じ記事のなかでは、中国政府は、国家安全維持法の施行によって、株式市場を含む経済活動のすべてを中国式のやり方で進めようとしているわけではなく、むしろ香港の金融システムを自分たちのなかに取り込むことで、そのモデルを中国全土に展開することを目論んでいると指摘されています。であればこそ、香港の金融業界は、国家安全維持法に賛同はせずとも、ある意味楽観視しているんです。HKEXのチーフエグゼクティブのCharles Liさんはこう語っています。
「国家安全維持法は、商業活動、契約上の取り決め、金融取引、資本の流れ、係争の解決、人材の移動や情報・データの流れをガバナンスするあらゆる法規制とは無関係である」
もっとも、それが果たして本当にそうなのかは反対意見もありますので、鵜呑みにはできないのですが、少なくともそうプロモーションすることがいかに重要かを物語ってはいそうです。
──このLiさんという方の言われていることを真に受けたとすると、今後、中国企業をめがけてアメリカドルがどんどん流れ込んでいくことになりそうですね。
そうした事態を受けて、アメリカがドルを干上がらせることを想定したりもしていますが、すでに香港が欧米や日本企業などにとって、中国本土にアクセスする上で、重要な拠点となってしまっていることを考えると、そうした施策には現実味がないだろう、としています。
──うーん。なんか、ここでもまた、首根っこをおさえられちゃってますね。
記事の締めは、なかなかに暗澹たるものでして、こう書かれています。
「香港の成功を支えてきた重要な要素の一つである、表現の自由と法の支配が損なわれていることは明らかである。けれども、ドルへのアクセスは安定しており、中国本土とのつながりは一層強化された。中国経済や中国のハイテク企業にビジネスチャンスを伺う欧米の投資家の意欲も衰えていない。ロンドンに本社を置き、香港で多くの業務を行っているHSBCとスタンダードチャータードの2つの銀行が、英国政府の方針に逆らって国家安全法を支持したことは、こうした風向きを端的に表している」
──なんだかな、ですね。香港は、市民の生活空間でもなく、文化空間でもなく、ただの金融空間とみなされ、その意義を一面的に拡張しようと、そういう話ですよね。
今回のGuidesのなかには、香港からの移民の大量受け入れに踏み切ったイギリスの対応をめぐる〈The campaign for Hong Kong’s freedoms has a new base: Britain〉や、天安門期に匹敵するほどの移民が起きるだろうとする〈Hong Kong is about to see a Tiananmen-era wave of migration〉など、これから起きるであろう市民の流出を取り上げた記事がありますが、英国はそもそも移民の流入を嫌がってBrexitに踏み切ったわけですし、そもそも2019年時点では、香港のデモに興味を示していなかったとさえ上記の記事は書いています。

それが国家安全維持法の施行とともに風向きが変わるわけですが、それも2047年まで維持されるはずだった「一国二制度」という英国が敷いた枠組みが反故にされ、ある意味メンツを潰されたからでもあるようです。加えて、そこにコロナ対応をめぐる反・中国の機運が高まったことを受けて、強硬姿勢に突入し、プロテストを首謀した容疑で逮捕され本土で拷問を受けたとされるサイモン・チェンや、ネイサン・ロウといったアクティビストの亡命を認めています。
──英国が、今後のプロテストの前線になるとと書いていますね。
サイモン・チェンは、すでに英国内に亡命政府を英国に立ち上げる構想を語っているそうですし、ネイサン・ロウも英国を戦略拠点として使っていくことを声高にうたっています。
──にしても、英国は、300万人にのぼる香港人が英国籍を取ることができるよう道を探るという方針を打ち出していますが、これは相当な英断ですよね。
ですね。ただでさえコロナによって英国史上最悪の不況とも言われる経済的打撃のなかで、いったいどうやってそれだけの数の移民を養うことができるのかと考えただけで、それがいかに茨の道かは想像できますよね。ビジネスエリートはいいかもしれませんが、そうでない市井のワーカーは、人手が足りていないとされる、いわゆる「エッセンシャルワーク」に従事することになるのかもしれませんが、それが奴隷労働化している状況は、この連載でも度々指摘してきましたし、〈Hong Kong is about to see a Tiananmen-era wave of migration〉という記事のなかでは、トロントやバンクーバーの香港移民の苦闘の歴史が描かれていますが、その苦難がまた繰り返されることになるのかもしれません。
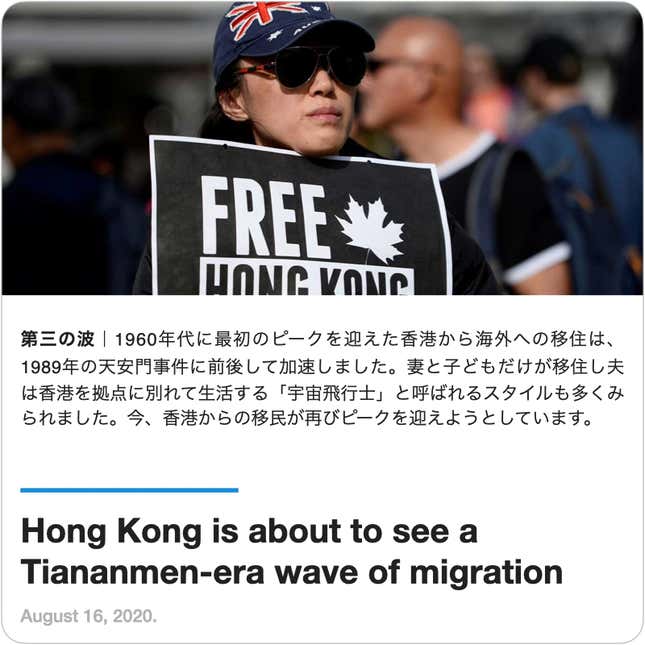
──人ごとのようなことしか言えなくてほんと情けないのですが、やはり前途多難ですね。
そう言えば、つい先日Netflixで『イップ・マン外伝 マスターZ』という映画を観たんです。
──はあ。
これは、英国統治下の香港で、ブルース・リーの師匠でもあった中国武術のグランドマスター「イップ・マン」という人と因縁のある詠春拳の達人が、麻薬の密売をしている組織を叩き潰すという作品でして、最終的に、麻薬密売の黒幕は英国人とそれとグルである英国総督府であることが明かされ、彼らの狗同然だった香港警察も、最後にその真相に気づき、正義の鉄槌が下って終わるという、香港映画にありがちな、非常にオーソドックスな映画なんです。
──ふむ。
ブルース・リーの時代から、ときに英国総督府だったり日本軍であったり、自分たちを支配下に置いてきた権力に素手で立ち向かう存在としてヒーローが描かれてきましたし、香港の警察が描かれる際も、常に外来の権力機構と市民の間に入って苦しい立場に置かれる存在として描かれてきたのが基本線だと思うんです。
──そうですね。
カンフーアクションのヒーローは、武器ももたないで素手で戦うことで、強い声や強い武器をもたない市井の人たちをレペゼンしていたわけで、であればこそ、その精神にアメリカの黒人も非常に感化されることにもなったんです。実際、アメリカで香港映画を最初に受け入れたのは黒人たちで、その影響はいまでもヒップホップのなかに脈々と流れているんですね。

──ウータン・クランがまさにそうですよね。『少林寺三十六房』がモチーフですもんね。
ですです。いま紹介した『イップ・マン外伝 マスターZ』もまさにそういう映画なんです。これを制作した東方電影はレイモンド・チョウという香港映画界の重鎮が2018年に起こした会社で、その第1作目が本作だったんです。その会社の資本がどこから流れているか定かではないのですが、ただ、いまこのタイミングで観ると、やはり非常に微妙な気持ちになるところがあるんです。
──どうしてでしょう。
つまり、英国という悪の手から自分たちの土地を取り戻し、自分たちの中国人としてのアイデンティティを取り戻そうっていうメッセージは、それが香港人の自発的な声のようにも取れる一方、共産党が発するメッセージとしても有効なわけですよね。
──ああ、たしかに。英国に対するネガティブキャンペーンにもなると。
そうなんですよね。で、この作品の難しさは、物語の骨子はいままで通りだということなんです。ただ、その背後に共産党がいることを疑った瞬間、メッセージが反転することになり、権力と素手で立ち向かう男の物語は、下手すると中国への馴化を促す物語にもなりうるんですね。「香港の警察も本当はツライんだ」というメッセージも、ジャッキー・チェンの『ポリス・ストーリー』以来の定番の切り口ですが、いま、この時点で、それにうっかり同情してしまうのは、危険ではあるわけですよね。
──うーん。なんか、もうあんまり無邪気に映画も観られなくなっちゃいますね。
文化というものを市民と敵対させて引き離したり、あるいは近づけたと見せて別の方向へと市民を引っ張っていったり、と、香港ではいまそういう非常にデリケートで、かつ凄まじい文化戦略が展開されているように自分には見えて、正直何がどうなっているのか、まるでついていけていないのですが、ひとつ確実に言えるのは、文化を後回しにして、それを停滞したり瓦解していくのを放置しておくと、あとでひどいしっぺ返しを食らうことになるということなんじゃないかと思います。
──しかも、中国はそれを戦略的に仕掛けてくる可能性があるということですよね。
考えすぎだったらいいんですが、どうもそうじゃないような気がするんです。中国政府がどこでそれを学んだのかよくわかりませんが、文化と政治の関係を、冷徹に見抜いているように見えてなりません。
──日本、どうなりますか。
いやあ、どうでしょう。つまらない話ですが、日本のタレントも、どうせweiboで中国語で発信しているなら、欧米向けに英語でやっておくこととかは、もしかしたら大事なのかもしれませんね。ビジネス上の依存を一国に対して深めすぎないことは、これからますます重要になってくるのかもしれません。
若林恵(わかばやし・けい) 1971年生まれ。『WIRED』日本版編集長(2012〜17年)を務めたのち、2018年、黒鳥社を設立。NY在住のジャーナリスト 佐久間裕美子とともホストを務めるポッドキャスト「こんにちは未来」のエピソードをまとめた書籍が発売中。
このニュースレターはお友だちへの転送も可能です(転送された方へ! 登録はこちらから)。
