A Guide to Guides
週刊だえん問答
世界がいま何に注目しどう論じているのか、米国版Quartzの特集〈Field Guides〉から1つをピックアップし解題する週末ニュースレター。「Welcome to the Hybrid Workplace」と題したQuartzの原文(英語)と、原稿執筆時に流れていたプレイリスト(Apple Music、Spotify)もあわせてお楽しみください。

welcome to the hybrid workplace
ハイブリッドの複雑
──暑いですね。
今日の天気を見るにつけ、今年は暑い夏になりそうですが、その一方で、鹿児島、宮崎、熊本に大雨特別警報が出ています。熱海で土砂災害があったばかりですから、心配です。
──バッハ会長も来日しました。
いよいよ来ましたね。
──都内のオリンピック競技については「無観客」が決定しましたが、これで一応の決着ということになるんでしょうか。まったく盛り上がらなそうですが、その状況を見たさにテレビを見る人もいるのかもしれません。
ずいぶん昔ですが、ジャマイカの女子短距離のスターでマーリン・オッティという人がいまして、その人が結構好きで、たしか「TOTOスーパー陸上」だったと思うのですが、来日したというので国立競技場だかに観に行ったことがあります。
──へえ。意外ですね。
熱心に応援するわけでもないので、客席の一番上で寝そべりながら観ていたのですが、メインスタンドは多少は埋まっていましたが、反対側のスタンドの上のほうなんてガラガラもいいところでした。歓声もさしてあがらずに、粛々と槍投げとかをやっているのを遠くから観ていたのですが、かなり牧歌的な感じでいいものでしたよ。野っ原でやってる感じがあって。
──原風景感ありますね。
この間のオリンピックをめぐる騒動のなかで、「学校の運動会が中止になっているのに、オリンピックはやるのか」という批判をよく見かけましたし、その言説に対して「オリンピックと運動会を同じと思ってるバカ」といった批判もよく見かけましたが、学校の運動会とオリンピックと、どちらが意味あるのかという問いは改めて面白いものだと感じます。
──そうですか。
世界最高峰のクオリティの高いコンテンツこそが価値であるというのは、テレビを筆頭とするマスメディア的な観点においてはたしかにそうなのかもしれませんが、YouTube的なソーシャルメディア的な観点からすれば、もはやシロウト/クロウトの区分けは消えて、ほぼほぼ等価なものとしてすでに存在してしまっていますので、「どちらがコンテンツとして価値があるか」という問いは失効しているようなところもありますよね。
──たしかに。
加えて、最近アメリカでは、たとえばハイスクール・スポーツに特化したストリーミングサービスなんかも発達してきていまして、どんな学校のどんなクラブでも、いますぐに簡単にライブストリーミングを始めることのできるパッケージなども用意されていますから、こうしたサービスの発展を見れば、スポーツ中継は、もはやテレビの占有物でもなんでもなくなっているんですね。

──面白い。といって、それ、誰が観るんですかね?
親や親戚やOBが観るのだと思いますが、それで特に何か問題があるとも思えません。スポーツ観戦が、地元チームの野球やサッカーや、陸上の観戦を意味するようになったとして、特段なんの不都合もないですよね。
──たしかに。
そうしたサービスがちょっとでも収益を生むことができるようになれば、クラブ活動に新たな持続性をもたらすかもしれませんし。どうせ、これまでだって親の寄付などで成り立っていたわけですから、そうしたサービスを通して寄付のハードルを下げることができるかもしれませんし、そこに広告サービスが入れられればローカルビジネスをサポートする仕組みともなりえるかもしれません。ちなみに、Quartz Japanは過去のニュースレターで、ハイスクールスポーツ配信プラットフォーム「Overtime」について、その魅力をこう解説しています。
「まず、アマチュアスポーツそのものの魅力です。普通の高校生やサラリーマンなどの等身大のスターが繰り広げる真剣勝負は人間ドラマにあふれています。『エースで4番』など規格外のヒーローも生まれやすく、試合展開も起伏に富んでいます。Netflixでも最近、高校生バスケの実話ドラマ『バスケが全て(Basketball or Nothing)』が人気を博しました。
次に、Z世代にとって等身大なプレイヤーへの共感です。セレブなプロ選手のテクニックや華美なライフスタイルも魅力ですが、どこか手の届かない他人事で、別世界です。一方、Overtimeに登場するのは、興味も悩みも自分に近く、親近感のもてるスターです。将来のスーパースターを応援し、育てる感覚もあるでしょう。(中略)
さらに、アマチュアスポーツは権利関係が簡素です。放映権ビジネスで巨大になり過ぎたプロスポーツにとって、ネット配信は手が出しにくい領域です。これまでコンテンツとして流通することのなかったアマチュアスポーツなら、しがらみなく自由に事業展開ができます。
そして、『未来のスーパースター発掘』の可能性です。『地元の隠れた逸材』のプレイ動画は、プロスポーツのスカウトマンにとっては大きな魅力です。プレイ動画のデータ解析によるAIスカウトなど、色々な可能性が考えられます」
──それ自体が強力なコンテンツになりうるわけですね。
といって、世界最高峰のプレイが、強烈なコンテンツであることには変わりはないでしょうから、そうしたソーシャルコンテンツがマスメディア的なものと取って変わるということでもないのだろうとは思います。おそらくは共存できるはずで、そうしたメガイベントと、草スポーツめいたものの間に、細かやなグラデーションがつくられていくというのが、あるべき姿であるように感じます。
──二項対立ではなく、グラデーション。
はい。これは以前にもお話ししたことですが、プロスポーツの山の高さが裾野の広さで決まるのであれば、プロスポーツとアマチュアスポーツは、当たり前ですが、関連しあっていますので、オリンピックと運動会、もしくはクラブ活動を対立的に考えるのは、基本的には間違っていると思います。もちろん規模の違いからくるオペレーションの複雑さの違いはありますが、プロもアマもひとつながりとみなすなら、そこには一貫した原則を置きえますし、どうせオリンピックが無観客配信になったのであれば、学校の運動会や部活動においてだって、無観客配信というオプションを行政府としてサポートするという道筋だってありえるはずです。

──そういうときに、先におっしゃっていたような、配信のノウハウを素早くインストールできるような民間サービスがあるといいですよね。というか、それがないところでスクラッチで配信をやったら?と言われても、話にならないですね。
そうなんです。経済再生担当相、もしくはIT担当相とかいう人を置くのであれば、その人たちが本来主導すべきは、そうしたトランジションであるように思うのですが、まあ、そういうアタマはないんでしょうね。もちろん、そうしたアイデアを実装するのが簡単だというつもりはありませんが、ただ我慢しろというだけなら世の中停滞するに決まってますよね。
──西村という大臣が金融機関を通じて飲食店に圧力をかける、と言ったことで大炎上していますが、ああいう発想は、本当にろくなもんじゃないですね。
「ソサエティ5.0」とか言って威張ってる国なんですから、店内の換気や、店内の飛沫の状況などをなんらかのセンサーでも導入して、ある基準値のなかで飲食店が運営されているのかどうかを測定するといったことがあって、はじめて罰則規定の運用もありうると思いますし、仮にそういうデバイスを国が率先して導入を推進していけば、それこそ次に別の感染症が来てもなんらかの役に立つかもしれません。「IoT」だ「ソサエティ5.0」とかいう掛け声ばかりで、役立つところにそういうものを導入しようという発想が、経済再生担当やIT担当にはあって然るべきように思いますが、どうなんでしょうね。こうした取り組みは、調べてみれば、ここやここなど、民間ではすでに少なからずあるんですけどね。
──そういう技術の実装に補助金をつけるとか、そういうアイデアが必要ということですよね。
と、思います。基準も根拠もない緊急事態宣言を発令して、基準も根拠も定かではないプロトコルを適当につくって、あとは、店と客のマナーという道徳問題にすりかえ、店や客の「良心」を試すようなやり方で圧力をかけるのは、法治国家としてはあるまじき最低のやり口だと思います。お酒を提供すると判断した店も、出さないと判断した店も共に、自分たちの「道徳」や「良心」に基づく自己責任において判断させられ、それは、ある種のやましさのなかで「自分の信念」として保持させられるというのは、まずもって心理的に最悪の状況だと思います。
──ほんとですね。
飲食店の「開ける・開けない」「酒を出す・出さない」の是非や、音楽フェスの開催の是非などは、こういう事態にあってはビジネスにおける個々の「自己責任」における責任の範疇を超えています。その判断をするのは、行政の責任においてだと思いますし、その判断に合理性をもたせようとするなら、当然補償は必須ですが、それをしないで、あらゆることを事業者やカスタマーのモラルの問題にすり替えるのは、ただのサボタージュだと考えていいように思います。
──金融機関もさすがに「金融機関は感染警察ではない」といった言い方で反発しています。
もちろん金融機関は、政府の論外なやり口に腹を立てて当然だとは思いますが、とはいえ、そう言っている金融機関自体が、規制産業であることをいいことに、自らをロクにアップデートしてこなかったのは事実だと思いますし、コロナ禍のなかで、いまほんとうに困窮している取引先を、自発的にどれだけサポートしてきたのかは疑問ですし、政府がもっと融資しろと言ってるからやってる程度のことしかやっていないのではないかと疑う気持ちもあります。金融機関が規制で手足を縛られていて、やりたいようなことができていないのは、その通りだとは思いますが、そうした状況が自分たちのメリットになっているところがあればこそ、真剣にそれを打破しようとはしてこなかったのも事実だろうと思います。ずっと言い訳しているだけのように見えたりもしますから。
──手厳しいですね。
ちなみに、西村大臣の「金融機関を用いた恫喝」については、9日には金融庁から全国銀行協会に依頼の通達が行くことが想定されていたとも言われています。
──西村某が単に調子に乗って口を滑らせたわけではないんですね。
これについては、『朝日デジタル』がこうツイートしています。
──なんだ、ひでえな。西村大臣は、自分の発言が大炎上したことで、二階幹事長に詫びにいったと言われていますが、金融庁も連動して動いていた話であるなら、西村大臣はいったい何を詫びたんでしょうね?
わかりません。上記の経緯を鑑みると、黙ってやろうと思っていたのを、うっかり記者会見で口を滑らせたことを詫びに行ったとしか思えなくもなりますが、どうなんでしょう。いずれにせよ、もし仮に、この通達が全国銀行協会に手渡っていたとしたら、全銀協はいったいどうするつもりだったのかが気になるところです。「こんなものには協力しない」と突っぱねるような気概があったかどうかは甚だ疑問です。報道には匿名で銀行・金融関係者の「困惑」のコメントは出ていますが、それだけで、基本ダンマリですよね。そもそも、こういうお達しが金融庁から平気で出されようとしていたこと自体が、全銀協とやらの立場の低さというか、いいように使われるパシリでしかない立場を明かしているように見えてしまいますが、たまには本気で怒ってみせたらどうなんですかね。
──にしても、あの発言は、相当の炎上っぷりでした。西村某、さすがにアウトじゃないかという感じもありそうです。
どうでしょうね。週明けに動きがあるかもしれませんね。

──しかし、オリンピックがいよいよ2週間というなか、まだまだ状況は流動していますね。
情報量が一気に増えているような感じはしますね。それこそ北海道での競技の無観客化、無観客化を理由とした選手の参加辞退、選手の感染、先日名翻訳家の鴻巣由季子さんが翻訳されていた海外メディアのロジ担当のぼやきツイートに見る大会ロジのずさんさといったことに加えて、気候や災害への目配せ、天皇の開会式参加の是非、バッハ会長の広島行き、さらにはオードリー・タンの開会式への参加、英国議会や欧州議会による北京五輪のボイコット勧告など、中国にまつわる問題も複雑化してきています。その状況下で国内はワクチン不足、感染者の増加、都議選での逆風、無観客への後退など問題山積で、そのなか総理はリーダーシップを発揮するどころか、安心安全しか言えないゾンビと化しているわけですから、実際、まだ何が起きても不思議ではない状況のように見えます。しかも日本政府は、何かが起きたらもう「中止」以外に切るカードがありませんし、経済効果はもはやない、と経済担当相が開き直っているくらいですから、惨劇の予感は、むしろ高まっているようにも感じます。
──どうなりますか。
面白いなと思ったのは、そうしたなか、『毎日新聞』が、少なくとも観客の有無について、IOCは「傍観者に徹した」と指摘していることです。
「観客の取り扱いを巡り、リスク回避を最優先するIOCは傍観者に徹してきた。IOC関係者が『ボールは日本側にある』と強調するように、政府、組織委、東京都の決断を追認するにとどまった」
──特にああしろ、こうしろとは言ってないんですね。
はい。それこそ「無観客」については「理解ができない」とおっしゃっていましたが、それこそどういう基準に則って、プロ野球やサッカーは開催され、ロッキンフェスは中止となっているのか、といったあたりは日本国民でもほとんどわかりませんし、緊急事態宣言も、なんの効果を見込んでどういう基準で運用されているのかは日本に暮らしている人にとっても謎ですから、バッハ会長が「理解できない」のも無理ないなと正直思います。
──橋本、丸川、小池といった人たちの、何を言ってるのかさっぱりわからない説明をバッハ会長も聞かされているんでしょうか。
そうだとすれば、当然「理解ができない」という反応になるでしょうね。わたしが個人的に本当に気の毒だなと思うのは、おそらく五者会談と呼ばれるものには通訳が入っていると想像するのですが、日本側のおそらく説明にもなっていないような説明を通訳させられる人です。
──泣きたくなるでしょうね(笑)。
いずれにしましても、IOCは、「理解できない」と苦言を呈することはあっても、こうしろとは言わないんですね。この辺の距離感の取り方はさすがに手練れだなという感じがするのですが、要は地場の興行主たちのお手並み拝見って感じで見ているわけで、実際「一年延期」も「海外客なし」も「無観客」もIOCの発案ではなく、日本側が自らが選んだ選択で、日本政府と都と組織委員会の「自己責任」で選び取った格好になっていて、自らどんどんコーナーに追い詰められていっているわけです。
──IOCとしては、金さえ入ればなんでもいいんでしょうし。
1968年のメキシコ五輪直前のデモで数百人の参加者が射殺されるような事件が起きても「それは開催国の国内問題だから」と言わんばかりに、いけしゃあしゃあと五輪を開催してきた組織ですから、さすがの鉄面皮だなとむしろ感心してしまいます。日本の運営組織は、いいカッコしようとして、出来もしない興行を請け負ったしまった田舎のプロモーターの哀れを一身で体現しているような感じがしてきます。
──あはは。総理はまさにそんな感じです。
これだけ難しい論点が錯綜したイベントをパンデミックのさなかに運営しながら、しかもそれを未来に向けた転換のテコにしなくてはならないわけですから、相当な知恵者でも舵取りは難しかろうと想像はしますが、これが会社で首相がCEOで、その他のCクラスがいまの閣僚という顔ぶれだったら、流石に辞めたいな、と思いますよね。

──あはは。今回の〈Field Guides〉は、その「会社」に関するもので、いわゆる「ハイブリッド・ワークプレイス」がお題ですが、アメリカのメディアは、ここのところ、この話題で持ちきりです。
はい。ワクチン接種も広まったなか、リモート化していたワーカーを会社にどう戻すかは、非常に大きなイシューとなっています。つい最近では、アップルがワーカーをオフィスに戻すことを発表して、ワーカーたちの激しい抵抗に合いましたが、基本的な考え方としては、リモートワークとオフィスでの対面ワークをどうバランスするか、という線で議論が進んでいます。「ハイブリッド・ワークプレイス」ということばが指しているのは、その双方が入り混じっている状態です。
──とはいえ、難しいのは、この1年のように、このままリモートで働くのが望ましいと考えるのか、それともオフィスの対面ワークに戻るのが望ましいのか、ワーカー自身のなかでも意見が割れているところです。
はい。「Zoomが考える仕事の未来」(The future of work according to Zoom)という記事に紹介されているZoomが行った1,500人のワーカーに対する調査では、65%が「ハイブリッドが理想」と答えたとしていますが、そのうちの33%は「オフィスワークがメインであるほうがいい」と言っていまして、32%は「リモートワークがメインのほうがいい」と答えています。
──ちょうど半々ですね。
ただし、その前提として、Limeadeというソフトウェア企業が行った調査によると、「オフィスに戻ることに不安を感じている」ワーカーは、4,500人の調査対象の100%を占めたそうですから、基本、喜んでオフィスに戻りたい、という人はいないわけです。この調査は「ハイブリッドオフィスを有効活用する方法:動画」(How to get the most out of a hybrid work environment)という記事で紹介されています。
──ふむ。
このLimeadeの調査は、面白い事実を明かしています。調査対象のうち56%のワーカーが、オフィス再開の是非について企業側からワーカーの声を何ひとつ聞かれもしなかった、と答えていまして、その結果、「雇用者から大事にされている」と感じるワーカーは16%に下がっています。この数字は、パンデミック前には31%あったそうです。
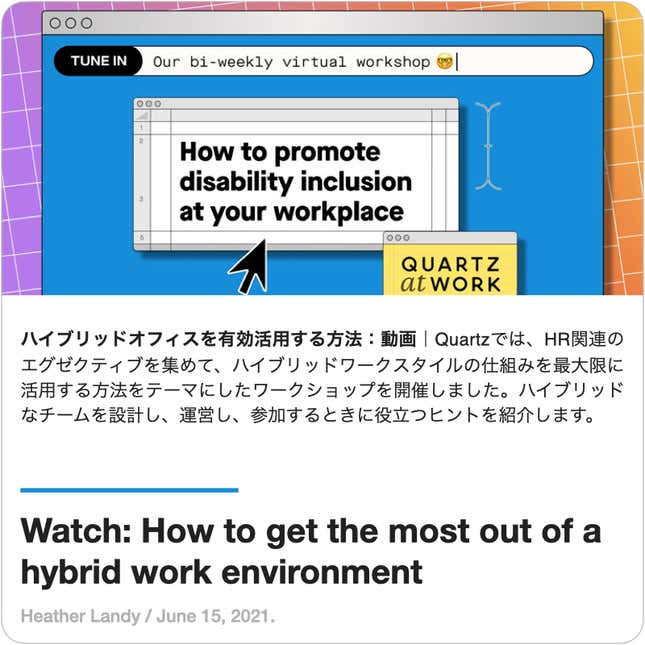
──会社への不信が高まっている、もしくは落胆させられているワーカーが増えているわけですね。アップルの騒動の根幹も、そこにありました。
はい。ワーカーとのコミュニケーションがないところで一方的に「ハイブリッド」が通達され、それが週3日の出社を要求する内容だったものの、なぜ「週3日なのか」について、なんの根拠も明示されていなかったことに一部の従業員が猛反発しました。
──民意を無視、ということであれば、菅内閣とあんまし変わらないですね(笑)。
企業であれば、社員全員の希望を叶えること必要があるのか、と考える人もいるとは思いますが、とはいえ、一方的なコミュニケーションをもって組織を管理することは、どんどん難しくなってはいますから、どこでバランスを取るのかということになります。「Zoomが考える仕事の未来」の記事では、Zoomの創業者兼CEOのエリック・ユアンの、こんなことばが引用されています。
「わたしが耳を傾けた多くのカスタマーは慎重にオフィスをオープンするにあたってハイブリッドなソリューションを採用することを考えていますが、個々の産業、企業、個々人によって最適な働き方のモデルは変わってきます」
「ハイブリッドワークの定義があるとしたら、それはフレキシビリティ=柔軟性ということになるかと思います。従業員にフレキシビリティを与えることです」
──なるほど。
ちなみに、Zoomはここでいう柔軟性をもたらすべく、ダイナミックな機能拡張を行っていまして、「Zoom Rooms」の機能拡張によって、例えばレセプショニストが会社の受付業務をリモートでできるようになるとしています。さらに「Zoom Events」というイベント機能を追加するとされてもいます。
──一口にハイブリッドといっても、まだまだいろんな可能性がありそうですね。
それこそ先日単行本の校了をしていましたが、いまであれば、ライブストリーミングをつなぎ放しにしてリアルタイムで確認作業などを行うことだってできますから、オンラインだけれども同じ時間を共有しながら作業することはそんなに難しいことではないのかもしれない、と思ってしまいました。現状においては、まだ負荷があるかもしれませんが、それこそサービスの機能次第では、ストレスなくやれるようになるのかもしれません

──どうしても対面で集まりたければそうすればいいわけですしね。要は選択肢の問題ですよね。
今回のメイン記事は「うまくいくハイブリッドワークプレイスの17条」(17 principles for a successful hybrid workplace)というものでして、今後の「オフィス」、もしくは「働き方」に関する17のティップスが紹介されていますので、ざっと紹介しておきましょうか。
──いいですね。これは会社に限らず、あらゆる組織に関わる話ですから、なんなら政権運営におけるヒントもあるかもしれません。
まず第一条として「素早く動け。さもなくば人が離れる」とあります。
──ん?
アクセンチュアが行った調査によると85%のワーカーはどこからでも働ける環境を望ましいと感じているそうです。つまり、そうした柔軟性を担保できない会社からはワーカーが流出することになる、ということですが、アメリカの労働市場はワーカーの確保がいま難しくなっていますので、企業に居着いてもらうために、柔軟な対応は必須であるとしています。
──なるほど。
第2条は、「ハイブリッドワークのスケジュールはワーカーやチーム内である程度決定できるようにする」です。
──自己決定できるようにする、と。
はい。基本はそうなのですが、ここでは個々人の裁量を大きくしすぎたりマネジメントの裁量を大きくしてはいけないとしています。あくまでもチームとして試行錯誤をすることが大事だとしています。また、なんらかの意思決定において、理由があって家を離れることのできない女性ワーカーやケアギバーが置き去りにされないよう注意を促してもいます。
──格差や差別、意図的な選別が生まれないような注意が必要だと、と。
はい。第3条は「ランダムな出会いがイノベーションを生む、にこだわりすぎない」です。
──これはありがちですね。「やっぱり対面で合わないと刺激的な会話は生まれないよね」といったことはよく言われますが、会社内での対話なんてほとんど愚痴と噂話だったりしますからね(笑)。
「コミュニケーションの促進がイノベーティブな組織を生み出す」ということについてフィジカル空間が大事だというのは、ほぼ幻想に近いんですね。Anne Helen Petersenというコラムニストは、「スマートでない企業は、廊下でばったり人が会って刺激的な会話が生まれる、という妙な幻想をもっている」と書いています。
──あはは。
まだまだ続きます。第4条は「近所に暮らしているワーカーをつなげよう」です。そうすることで社内のクロスセクターの交流が生まれるとしています。
──なるほど。
以下、ざっと行きますが、第5条は「複雑さを楽しもう」、第6条は「働き手の視点から会社を見直そう」ですが、この第6条で重要なのは、働き手の立場を顧客のペルソナを読み解くように検討することだそうです。続けて、第7条は「とにかく、まず試してみる」です。
──試すためには、そもそも柔軟性が会社に備わっていないとダメですね。
これ、全部やろうと思ったら相当大変ですよね。第8条はさらに大変だと思いますが「マネジメントに正常性バイアスについてのトレーニングを受けさせる」とあります。ハイブリッド環境になるとなおさらフェアな評価が求められるますので、そのためにマネジメントは、客観的な指標に基づく評価ができるようにならなくてはなりません。また、これは会社全体の評価指標に関わるものですので、第9条では「客観的なアウトプット評価に基づいて全ての業務が評価されるべし」としています。

──これ、全部やらないとダメなんですか?(笑)
働き方の文化を変えるというのは、それくらい大変だ、ということですよね。もちろんこうしたことが一朝一夕でなされるとは、誰も考えてはいません。これは大前提です。
──はい。
第10条は「メモを書き残すことを習慣化する」だそうです。これは特に打ち合わせが国境や時差を超えて行われる際には重要で、かつ、チーム内のコラボレーションを高めてくれるそうです。
──音声としてではなく、文字として共有されることで、チーム内の理解が揃うといったことですかね。
だと思います。第11条には「生産性をめぐる期待値を下げる」とあります。これは主に従業員のバーンアウトを防ぐためのもので、特にリモートワークが私生活を浸食していくことを防ぐために必要なマインドセットと考えられています。さらに、これとセットで第12条では、「生産性を監視するソフトウェアの使用を禁止せよ」とあります。
──この連載で散々批判してきた「仕事の見える化ツール」を禁止しろ、と。
はい。記事は、こうしたものを喜んで導入するリーダーは「新しい時代に相応しいリーダーとは言えない」と断罪しています。
──いいですね(笑)。
第13条は、「オフィスとワーカーの居住地の距離について具体的に決めること」です。緊急で社員に参集してもらう必要がある企業は、具体的にどれくらいの距離に暮らす必要があるかを明確化すべきで、記事ではある企業は「24時間以内に来社できること」とされていたそうです。
──なるほど。
第14条は「ワクチン接種状況によってワーカーの分け隔てる必要があるときには注意せよ」です。ワクチン接種は企業がそれを義務化することはできませんし、法的な強制力もありませんから、ワクチンを接種していないワーカーをどう扱うかは、とてもデリケートな問題となります。企業は、接種者と非接種者が混在する環境において、いかにしてワーカーのコラボレーションを促進するかを考えるべきだとしています。
──これは容易に差別、隔離を生みそうな、難しい問題ですね。
はい。あと3つです。15条は「無理にハイブリッドにしなくともよい」です。要は、自社がどういう文化と生産性を基盤としているのかをよく検討しろということですね。ただし、社長が勝手に「うちはこう」と決めるのはダメです。
──そりゃそうですね。めんどくさいからやらないというだけの経営者も多そうですからね。
16条は、「余裕があるならオフィスはもっておけ」です。オフィスの有用性は、ハイブリッドの実験が進むなかで、むしろこれから検討されることになりますので、慌てて処分するには時期尚早との見方を記事は示しています。実際アメリカでは、昨年秋の段階では39%の企業が不動産資産の縮減を考えていたそうですが、今年に入って、それが9%にまで下がったそうです。

──なるほど。次で最後です。
第17条は「やるつもりのない変更について従業員に聞くな」というものです。ワーカーの声を聞くのはいいのですが、それをするにあたって多くの企業が犯す間違いは、やれもしない、あるいはやる気もないオプションをワーカーに提示することだと言います。
──要はコミットするつもりもないオプションは提示するな、ということですね。
まさにその通りです。ワーカーの声を聞くということは、そもそもその声にコミットするという前提があるからやるべきもので、それがないところで「声を聞く」というのは、ただのアリバイづくりでしかありません。
──その手のことってよくありますよね。公募しておいて、一番に選ばれたものが採用されないとか、どこぞの駅のネーミングでも悶着がありました。
最悪ですよね。人の意見を聞くのは、言ってみればそれ自体がリスクや責任を背負うことでもありますから、そこまで軽々にやれるものでもないんですね。相手に対する信頼がないとできませんし、問う側も信頼されていなければ、意味ある意見交換にはなりません。
──人の言うことは何も聞かないくせに「お願い」だけはしてくる人たちに聞かせてやりたいですね。
先に紹介したAnne Helen Petersenさんは、こう書いています。
「社内でフレキシビリティを根付かせようとする企業は、必ず不愉快であったりフラストレーションが溜まったり、混乱に見舞われる期間を経ることとなる。そうしたなかでわたしが見た限り、企業が取るべき最も好ましい姿勢は、とにかく事態を率直に認めることである。『これは複雑で、何度も繰り返しながら、解決せざるをえないものである。けれどもわたしたちは、これがうまくいくことにコミットする」
──「コミットメント」ということばは、それが一般に使われるようになって以来、本当に内実を失っていますよね。
本当はそのコミットメントを行動において示さないと意味がないはずですが、「ことばを言う」ことを行動だと勘違いしている人が多いんですかね。
──困ったものです。
はい。
若林恵(わかばやし・けい) 1971年生まれ。『WIRED』日本版編集長(2012〜17年)を務めたのち、2018年、黒鳥社設立。7月下旬に発売となる本連載の書籍化第2弾のタイトルは『はりぼて王国年代記』。Amazonでも予約がスタートしています。
👇 のボタンから、このニュースレターをTwitter、Facebookでシェアできます。ニュースレターの転送もご自由に(転送された方へ! 登録はこちらからどうぞ)。
