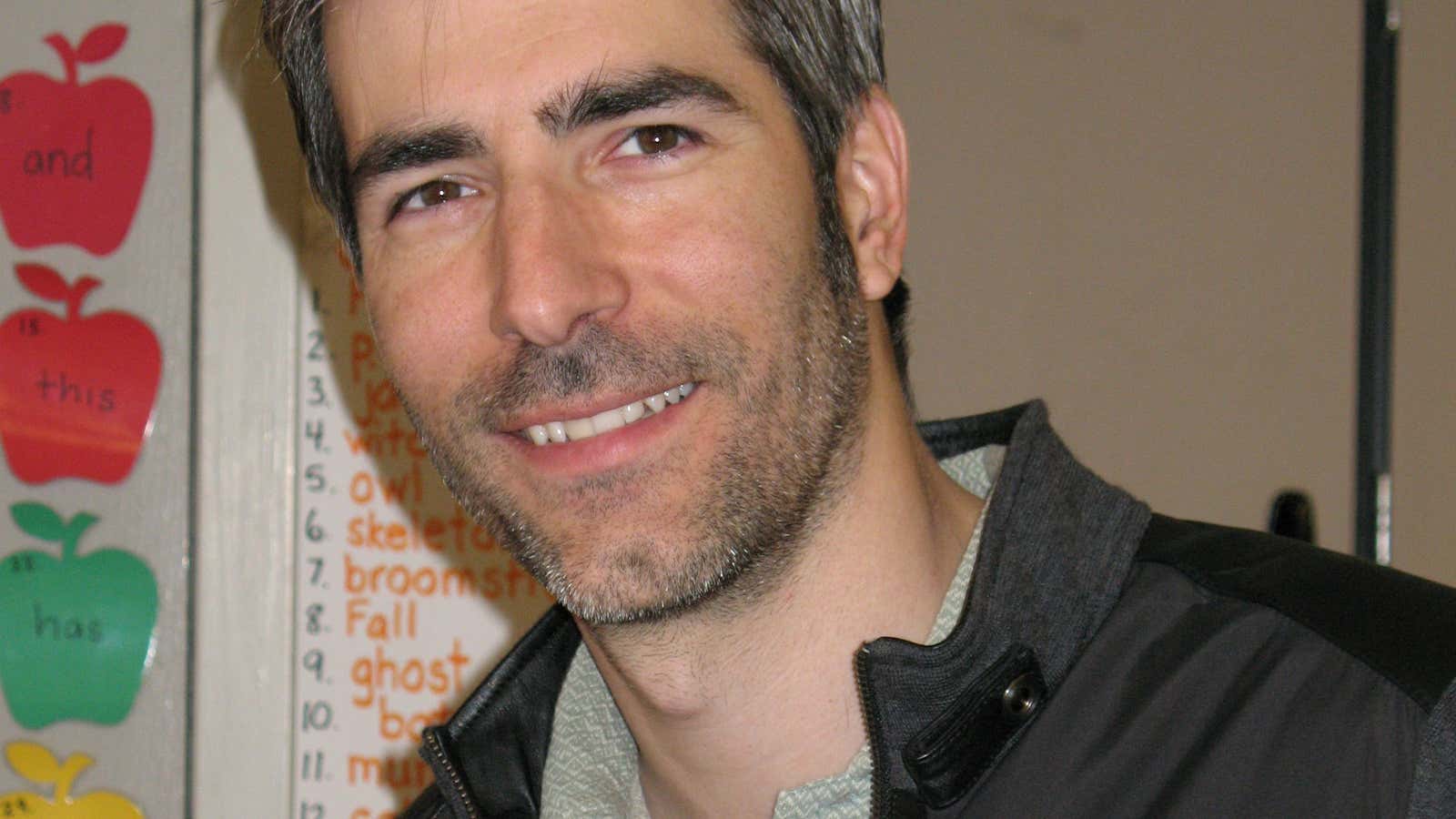Special Feature
だえん問答・番外編
Quartz Japan読者の皆さん、こんばんは。本日は配信が普段より遅くなりましたが、今週のPMメール「Deep Dive」は、いつものように曜日ごとに決まったテーマではなく、1週通して「特集」というかたちでお届けしています。
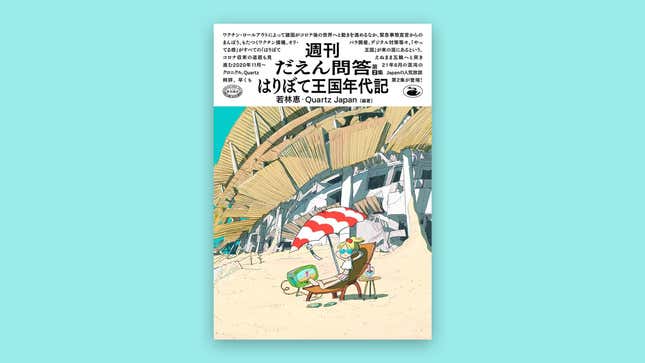
今週は…[だえん問答・番外編]
毎週日曜にお送りしている「だえん問答」は、Quartzの特集「Field Guides」が扱う週替わりの論点を編集者の若林恵さんが解題する人気連載。2020年12月から21年6月までの掲載分をまとめた書籍版(第2集)もついに発売となりました。今週(26〜30日)お届けするニュースレター特集「だえん問答・番外編」では、ネタ元となったField Guidesの内容の一部を翻訳し、論点をより深掘りします。第2回となる今日は、広告だらけのウェブ体験に対するアンチテーゼのようなインタビューをお送りします。
今日「あわせて読みたい」だえん問答:#54 デジタル広告のオルタナティブ(4/11配信)
昨日開催した『週刊だえん問答・第2集 はりぼて王国年代記』刊行記念オンラインイベントは4時間超えのビッグイベントに。急遽決定した来週の「2回戦」の詳細は、改めてお知らせいたします。
The inventor of the digital cookie
ウェブ広告の未来
ルー・モントゥリ(Lou Montulli)が1994年にクッキーを発明したとき、彼は23歳で、インターネット初期に広く使われたブラウザのひとつ『Netscape』のエンジニアでした。当時、彼は初期のウェブが抱える大きな問題を解決しようとしていました──ウェブサイトは「記憶力が悪かった」のです。ユーザーが新しいページを読み込もうとするたびに、ウェブサイトはそのユーザーを見知らぬ他人のように扱ってしまいます。それゆえ、今日のウェブでは当たり前のように使われている「ショッピングカート」のような、ウェブの基本的な機能をつくりあげることができませんでした。
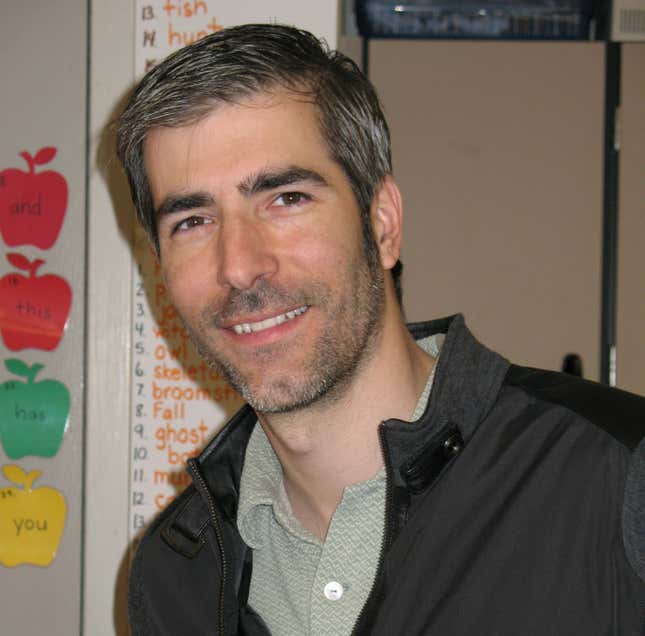
モントゥリは、さまざまな解決策を検討した結果としてクッキー(Cookie)にたどり着いたと、後日談としてブログに記しています。よりシンプルな解決策があるとすれば、それは全ユーザーに固有のID番号を与えることでしたが、モントゥリおよびNetscapeのチームは、第三者がユーザーの閲覧状況をトラッキングできるようになることを危惧し、この方法を不採用に。代わりに彼らはクッキーを採用したのです。クッキーとはユーザーのコンピュータとウェブサイトの間でやりとりされる短いテキストファイルのことで、これであればウェブサイトが来訪者を記憶できると同時に、ユーザーがトラッキングされることはないと考えられたのです。
果たして2年後、広告主はクッキーをハックして、モントゥリらが避けようとしていたことを可能にしました──インターネット上のユーザーを追い回せるようになったのです。最終的にできあがったのが、今日の、クッキーを利用した広告ターゲティングのシステムです。誕生から27年が経ったいま、モントゥリは自分の発明の使われ方に対する不安とともに、それに代わるオルタナティブがよりよいものかどうかについても疑問を抱いています。

──なぜクッキーをつくったのですか?
ユーザーと、そのユーザーが訪問したウェブサイト間でのみ情報を交換するようにクッキーを設計しました。Netscapeの創設者をはじめ、当時のインターネットの住人の多くは、プライバシーを重視していました。ですから、構築するインターネットプロトコルの設計にも、その思想は浸透していたのです。われわれがつくりたかったのは、「自分のことを覚えていてほしいウェブサイトには自分のことを覚えていてもらい、匿名でいたいときには匿名でいられるような仕組み」でした。
──それが一転し、広告主はクッキーを利用してトラッキングに邁進するようになったわけですが、それを目にしてどう感じましたか?
ウェブサイトがそんな振る舞いをするなど想定もしていませんでしたが……もっとも「お金の流れ」を追えば、このようなことになると想像できたかもしれません。われわれがこの問題に気づいたのは1996年のことでしたが、非常に驚いたし、憂慮すべきことだと直感しました。当時、Netscapeはマイクロソフトと(ブラウザ市場の覇権をかけて)殴り合いの闘いをするなど、クッキー以外にも多くの問題が発生していました。みな「こんなことに付き合っているヒマはない。君、これに対処できる?」という感じで、わたしがクッキーへの対処を考えることになったのです。わたしはただの下っ端エンジニアで、利用規約など扱ったこともなかったのですが。
われわれには3つの選択肢がありました。まず、何もせずに広告主がサードパーティ・クッキーを好きに使えるようにすること。次に、サードパーティ・クッキーを完全にブロックすること。そして3つ目は、少しニュアンスを変えた解決策を模索することでした──つまり、クッキーのコントロールをユーザーの手に戻し、広告主がクッキーを使ってユーザーをトラッキングする方法を制御できるようにしようとしたのです。
3つめが、われわれが試みたアプローチでした。ユーザーが自分のデバイス上にどのようなクッキーがあるかを確認し、その用途を管理するための機能をブラウザ内に実装したのです。これでユーザーはサードパーティ・クッキーを完全にオフにしたり、特定のサイトに対してのみオフにしたりできるわけです。
──つまり、その1996年、あなたにはサードパーティー・クッキーを廃止するチャンスがあったということですよね。なぜそうはしなかったのですか?
当時のウェブ業界では、いまほどEコマースが盛んではありませんでした。広告が唯一の収入源だったのです。ウェブ全体が広告に依存していましたが、広告用クッキーを無効にすると、ウェブで収益を上げる能力は著しく低下してしまいます。
ですから、当時の決断が経済から完全に中立であったとは言えませんね。われわれは企業として、オープンウェブの未来を強く信じています。ウェブの収益モデルを確立することが非常に重要で、それでこそウェブの成功があると思っています。ゆえに、ユーザーにクッキーについての選択肢を提供しても、無効にはしなかったのです。
──25年が経ったいま、当時の自分の選択は正しかったと思いますか?
最近思うようになったのですが、ウェブがその収益源を広告に頼ってきたことは、社会にとって大きな害悪だったのでしょう。広告はユーザー体験を変質させます──ユーザーは、質の高さを求めるのではなく、できるだけ多くのインタラクションを得ようとするのです。そして、できるだけ多くのインタラクションを生み出そうとするビジネスモデルは、人の行動を非合理的なものにし、公共の利益を損なうのです。ですから、オンラインでの体験を健全なものにするためには、広告モデルを削減するべきなのでしょう。わたしはウェブ構築に関わってきましたが、歳をとったいま振り返ると、マイクロペイメントや定額制コンテンツの開発にもっと時間を割いていれば、量よりも質を重視することができ、世界はもっとよい場所になっていたかもしれないと思います。
──サードパーティー・クッキーが消えようとしているなか、広告業界はサードパーティー・クッキーに代わるものを用意しようとしています。どう思いますか?
まず「FLoC」について。これは、ウェブ上であなたをくまなく追跡するという従来の手段を使わずに、広告に対する嗜好を表明する代替の形です。そういった形はとても面白いと思います。でも、一般の人はよく理解できないので、最初は少し気味が悪いと感じる可能性が高いとも思います。
次に「Unified ID 2.0」(統一ID 2.0)ですが、これは基本的にクッキーと同じことです。ほとんどの人はこの機能をオフにするでしょうから、普及はしないでしょう。
最後に「ファーストパーティ・データ」について。トップ100に入るような大規模ウェブサイトにとっては有用ですが、小規模サイトでは使い物になりません。そもそもトラフィックが少ないサイトでは、データを収集したところで広告配信の役には立ちません。
──新しい技術によって、消費者が抱いている広告トラッキングへの不安は解消されるのでしょうか。どう捉えていますか?
サードパーティー・クッキーが廃止されると、業界は、クッキーとほぼ同じ機能をもち、かつユーザーの管理外にある(指紋採集のような)オルタナティブに移行しようとするでしょう。それら新しいテクノロジーは、ユーザーを追跡する方法を見つけようとする広告主と、それに対抗する技術的な方法を考え出すブラウザ/プライバシー擁護団体との間で、軍拡競争を引き起こすことになると思います。
最終的には、広告会社とブラウザの間でのいたちごっこを望むのか、それとも、何が許され何が許されないのかを定義する公のポリシーの策定を望むのかということになるでしょうもっとも、この問題を解決できる唯一のテクノロジーを生み出すなんてあまりに困難で、何らかの制限を設けるべきという話になるのだと思います。ただ……これは技術者としては少し言いにくいことですが、法律は、往々にしてあまり的を射ていないものです。しかし技術的に解決できない問題は、政策レベルで解決しなければならないこともあるのです。
(翻訳・編集:年吉聡太)
at this time tomorrow…

本日から30日(金)まで5日間にわたってお届けするニュースレター特集「だえん問答・番外編」。明日28日の17時ごろにお届けする第3回では、全米を覆った労働者のアクティビズムの動きを扱った回(米版Field Guide、だえん問答)から、その発明者の独白をピックアップします。ご感想をTwitterのほか、このメールに返信するかたちでも、どうぞお寄せください。
🎧 Podcastは月2回、新エピソードを配信中。Apple|Spotify
👀 Twitter、Facebookでも最新ニュースをお届け。
👇 のボタンから、このニュースレターをTwitter、Facebookでシェアできます。ニュースレターの転送もご自由に(転送された方へ! 登録はこちらからどうぞ)。