A Guide to Guides
週刊だえん問答
週末のニュースレター「だえん問答」では、世界がいま何に注目しどう論じているのか、米国版Quartzの特集〈Field Guides〉から1つをピックアップし、編集者の若林恵さんが解題します。今週は、「コロナが変えた働き方」と題した特集について、先週に続く後編をお届けします。
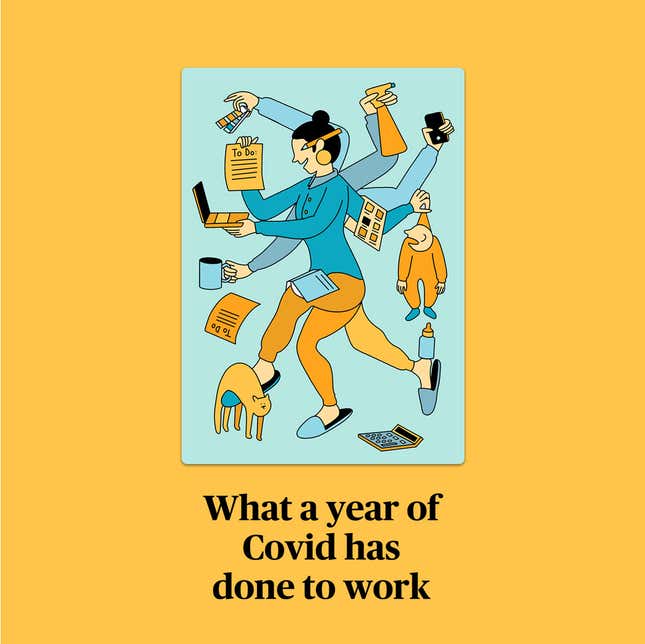
このニュースレターは、現在、期間限定で配信から24時間、ウェブ上で無料で閲覧できます。ニュースレター末尾のボタンからぜひシェアしてください。メンバーシップ読者の方には、先週配信の「前編」をこちらからお読みいただけます。
What Covid has done to work
リモートワークの是非
──それにしても、毎日毎日、いろんなことが起きますね。
今週はずっと騒然としていましたね。
──緊急事態宣言の発令の問題が通奏低音のようにあって、それに絡んでファイザー社のワクチンをめぐって話題や、IOCバッハ会長の発言などもありました。
あと面白かったのは、突然持ち上がって猛反発にあい、すぐさま収束した「欧州スーパーリーグ構想」をめぐる騒動でしょうか。
──2日ほどで帰趨が決したという、あれはダイナミックな動きでしたね。
ちょうど前回、オリンピックに絡んで「いまが分水嶺かもしれない」といったことを申し上げましたが、これも似たようなせめぎ合いのように個人的には見えました。
──「電通的なマスメディアを大量動員した『広告プロパガンダ』の手法がこのご時世にまだ通用するのか、それとも、やはり失効しているのか、それが明らかになる、非常に大きな分水嶺」とおっしゃっていました。
もう少し広い視点からいえば、それこそナチスドイツに端を発する、一方向型のマスメディアによる統治と、その対抗軸としてある、双方型のソーシャルメディアを通じたアクティビズムのせめぎ合いということなのではないかと思います。
──ふむ。
マスメディア型の統治モデルは、かつてであれば主に国家がツールとして有用化していたものですが、いまはもっぱらグローバル経済のビッグプレイヤーたちのツールとなっていまして、国家はすでにして、金融資本をはじめとするそうしたビッグプレイヤーたちの使いパシリのようなものでしかないというのは、われらが総理大臣が、オリンピックに関して「決定権はIOC」と明かしたことからも明らかです。「欧州スーパーリーグ構想」につきましても裏で大手金融機関やファンドなどが動いているそうですから、結局のところ、オリンピックも欧州スーパーリーグ構想も巨大なマネーゲームでしかないはずですが、それを「エンタテインメント」と名づけることで、それがさも「大衆」の欲望やニーズへの応答であるかのように見せかけることにおいて、広告業界およびマスメディアは非常に有効かつ有能な道具として考えられてきたわけですね。

──はい。
従来の状況であれば、おそらくオリンピックも欧州スーパーリーグ構想も、マスメディアを捻りあげて言うことを聞かせていれば、批判はあったとしても黙殺できたはずで、密室で決められた取り決めをゴリ押しできたのでしょう。おそらく森喜朗さんなんかは、完全にそういう前提で動いていたはずなんですね。スポーツというのは、そういう意味では非常に危険な道具で、たしかに選手たちのプレーを実際に見てしまうとほろりとしてしまうところもあって、それによって、その背後に動いている「お金」や「政治的な思惑」といったものがうやむやにされ、うまく覆い隠されてしまうわけです。極端な言い方をすれば、20世紀中葉から後半におけるスポーツというものは、実際はそういうものとして作動してきたとも言えそうですし、だからこそここまで大きいものになったとも言えるわけです。ナチスドイツの慧眼は、スポーツとメディアを掛け合わせることで極大なまでに政治化させる道筋を拓いたところで、それは発明といってもいいアイデアなんですよね。
──スポーツを、国家や経済における支配層にとって便利なツールとして用いるやり方を開発した、と。
はい。ところが、そうしたやり口は、それ自体がもはや秘密ですらなく、巨大スポーツイベントなんていうものが、国家やスポンサー企業と主催者であるところの欧州のエリートのための慰みものでしかないことはことあるごとに暴露され、オリンピックについていえば、ことここにいたって「オリンピックそのものを廃止してしまえ」という意見すら珍しくなくなっているわけです。
──それこそ『The New York Times』が公開したコラムに「オリンピックそのものを見直すときだ」というものもありました。
せっかくですから、少し引用しておきましょうか。
──ぜひ。
「リオはオリンピックを賄いきれなかった。想定の2倍の110億ドルがかかった2004年のアテネは、国家を財政破綻に陥らせる前触れとなった。こうした都市は特例ではない。オリンピックという事業に大きな疑問を呈するときが来ている。『利益はコストに見合っているのか』『これだけの被害をもたらし続けるオリンピックは存在し続けるべきなのか』。
アイデアはある。まず人権侵害をするような全体主義国家に開催権を渡さないこと。オリンピックという運動における対等なパートナーとしてアスリートに大きな権限を与えること。世界中を動き回るのではなく、固定されたベニューで開催する。それによってコストは下がり、環境破壊も止められるし、腐敗した誘致合戦を終わらせることができる。
あるいは分散化。競技ごとに世界中の会場で同時に開催するのだ。当然、選手が一同に介した開閉会式や選手村での選手同士の交歓は失われるが、すでにこれだけつながっている世界において、それが必要なのか?
これという答えになっていないのは認めよう。だが、未来に向けていい加減前に進むべきだ」
──もはや正当化できる根拠がないということですよね。
はい。それはそうなのですが、ところが、この『The New York Times』の指摘は、基本的によい主張だと思うのですが、実は落とし穴があるんですね。というのも、よくよく考えてみれば、オリンピックで指摘されていたような問題をどう解消しうるかということの、ひとつの解決策が「欧州スーパーリーグ構想」のようなアイデアだったりするからなんですね。
──先の主張は言ってみれば一種の合理化の提案だったわけですが、「欧州スーパーリーグ構想」は、たしかに極端な合理化ともいえますね。
ただしこれは、主催者側の利益を減らすことなく、むしろ現状の環境のなかで、さらに最大化するにはどうするかという観点から主張された合理化ですから、結果として『The New York Times』のコラムの提案とは真逆の発想に見えるのですが、誰の欲望を実現するために固定化・分散化するかによって、その主旨は変わってきてしまうんですね。
──そうか。
これも過去にこの連載で触れましたが、スポーツや音楽の事業がサーカス型の巡業モデルを採用しているのは、ことデジタルデバイスが広く行き渡った世界においては、もはや合理性が高いとはいえなくなっているんですね。音楽でも一部のビッグアーティストは、一度の配信ライブだけでツアーをやるのに匹敵しうる利益を生むことができるようになってきてもいますので、ビッグプレイヤーだけを集めてクローズドな環境のなかにファンを囲い込んでビジネスをするほうが明らかに効率的になっていくのは、おそらく間違いないんですね。それこそ5G通信の広がりとともに、スポーツ事業は完全にモバイルを主軸としたグローバルビジネスに移行していきますから、そうした環境に適応しようと思えば、無駄なプレイヤーは排除するに限る、となるのも一定の合理性はあるのだと思います。

──先の『The New York Times』のコラムが提案している内容をオリンピックが採用したとしたら、似たようなことが起きるとも考えられるわけですね。
そうだと思います。これは、今回のお題にも関わってくることになりますが、デジタルデフォルトな環境のなかで、フィジカルな「舞台」の意味がどんどん失われていくようになると、何が起きるかといいますと、実は、主催する主体が置かれている「場所」の権限がどんどん高まっていくということだったりするんですね。
──どういうことでしょう。
先日そういう体験をしたのですが、あるグローバルカンファレンスが日本で開催されることになり、当初はフィジカルな会場が日本に置かれることになっていまして、そうであればこそ日本側が主体的に「おもてなし」をし、そのなかで自分たちなりのアジェンダを埋め込んでいくことができると踏んでいたのですが、それが完全デジタルでの開催となってしまったことで、日本は名ばかりは「主催国」なのですが、あらゆる主導権を「本国」に奪われることになってしまったんですね。
──デジタル会議における「主催国」なんて、そもそも意味のない概念ですもんね。
そうなんです。ただそれによって「主催者」という中心点が消えてなくなるのかというとそうではなく、むしろありとあらゆる権限を、その中心において管理することができるようになりますので、その「中心点」の存在感は、より際立つことになるんですね。
──なるほど。
要は、これまでの興行モデルにおいては「各ローカルのプロモーター・興行主」という人たちの存在は非常に重要で気を遣う相手だったわけですが、「オンライン興行」に移行すれば、その存在は不要になるということで、そうとなれば主催側は中抜きをされなくて済みますから、より多くの利益を得ることができるわけですよね。
──そうか。オリンピックの会場を固定化して配信前提のビジネスに組み替えてしまえば、コストも大幅に削減できて、コンテンツ収益も増大化できると。
はい。グローバルスポーツは明らかに、そうした転回に向けた端境期にありまして、「欧州スーパーリーグ構想」は半ば勇み足のようなかたちでそこに突っ込んでいったように思えますし、一方のオリンピックは旧型モデルを転換できぬまま、昔ながらのシステムと急激に変転する社会環境のなかで破綻しているということなのだろうと思うのですが、このふたつの象徴的事例がともに失敗したのは、双方ともに、これまでのコミュニケーションガバナンスのモデルのまま、事態を推し進めることができると考えていたからだと思います。
──そうですか。
先にお話した通り、これが仮に90年代であれば、国民やファンの側に「ゴリ押しされた」と感じさせることなくゴリ押しできたんですよ。反対意見があったとしても、メディアと警察を使ってうまいこと封じ込められたんだと思うんです。現在も日本政府は、コロナをアリバイにしながら国民に抑圧をかけながら、メディアを利用してなんとか「気運」を持ち上げようと必死ですが、それをやればやるだけ隘路に陥っているのは、ソーシャルメディアに代表される双方向型メディアによるコミュニケーションは従来のやり方ではガバナンスすることができないという現実を、極端に過小評価しているからなのだと思います。
──「欧州スーパーリーグ構想」がわずか2日ほどでポシャったのも、結局のところファンのみならず選手や関係者などが自由に発信できて、しかもそれがあらゆる人たちに可視化され広まっていったからですよね。
はい。ソーシャルメディアを通じて、反対の声が一種の間にアクティビズムとして編成されて、反論や説明する間もないままに参加クラブが謝罪・離脱に追い込まれたというのは、いかに双方向メディアを通じた運動が力をもっているかを端的に示した事例として、あらゆる企業や組織・団体は強く心に胸に刻んでおくべきかと思います。
──バッハ会長もそうですよね。

とはいえ、ここで留意しておくべきは、それが「民衆の勝利」とは一概にはいえないところなんですね。
──あれ。そうなのですか?
重要なのは、双方向メディアは「誰もコントロールができない」という点なんです。これは、TikTokを扱った回でも触れましたが、ソーシャルメディアでバズを戦略的に生み出すというのは、極めて難しく現状まだ定式化もされていないんですね。リーチを稼ぐのがせいぜいで、いくらお金を積めば、どれだけの人の目に触れられるかが定式化されているだけなんです。つまり、あとから「ジョージ・フロイド事件が#BLMの運動に火をつけた」と事後的に説明することは可能なのですが、「#BLMの運動にどう火をつけるのか」を戦略的に実行するのはとても難しいということでして、要は、今回の「欧州スーパーリーグ構想」の反対運動についても、結果論としてうまくいっただけで、声はあがったとしても思ったほど火がつかない、といったことが起こる可能性はあったわけです。
──たまたまうまく行った、と。
あとから見れば当然、成功するにいたった理由や必然性の説明は可能にはなりますが、大事なのは、少なくとも誰かある特定の主体が全体を見渡して戦略的に計画を立てて成功に導くようなやり方で、成功にいたったものではない、というところなのかと思います。そこに秩序立ったように見える構造があったとしても、それは自生的にしか発生せず結果論として構造が生まれただけで、誰かが計画して構造化したわけではない、ということですね。これはハイエクという経済学者が「市場」というものを考えるにあたって提出したもので「カタラクシー」と名づけられたメカニズムですが。
──上から命令したり指示したりしても「バズ」は生まれないし、そのバズを生み出すにいたった本人にとっても、それがなぜバズを生むにいたったのかは謎のままということですよね。不思議なものですよね。
ですから、非常に危険なものなんですね。それは予測ができないかたちで、突然噴出してくるものですから。
──誰もがその予測不能性を甘く見ていているということですね。
はい。
──とすると、どういう振る舞いがありえるんでしょうね。
これも何度も触れてきていますが、結局は透明化するほかないという結論にしかいたらないのではないかと思います。双方向メディアのなかにおいては、相手も自分も対等なプレイヤーにさせられてしまいますので、自分たちの特権性を維持したまま、人を動員させようとしても、これはもう無理なんですね。無限のフィードバックループのなかに自分が置かれているという認識のなかで、隠し立てせずに持ち札をちゃんと開陳しながら、合意形成を図るほかないということになるかと思います。
──それは大変な手間ですね。
そうなんです。ただ、手間だからといって旧来のブルドーザー型で押し切ろうとしても、これはもう無理なんですよ。ですから基本的に諦めるほかないんですが、その際重要なのは、「決定権はもはや誰にもない」と考えることで、先の『The New York Times』の提案で最も重要なのは、まさにその部分なんです。
──「オリンピックという運動における対等なパートナーとしてアスリートに大きな権限を与えること」。ここですね。
そうなんです。これは第48話で「Twitch」のお話をした際にも触れたものですが、こうしたいわば「参加型」の合意形成モデルのなかにおいては、コンテンツの送り手はもはや一元的な「情報発信者」ではなく、どちらかというと「ファンダム」と呼ばれるファンコミュニティをリアルタイムでファシリテートするような存在へと変わっていくんですね。
──「『ユーザー中心』のサービス設計というのは、基本『参加型』という形式になっていくわけですが、そこにおいて極めて重要なのは、参加者の自由を阻害せず、それでも一定方向に、話を潤滑に進めていくことのできるファシリテーションの技術ということになるんだと思う」とおっしゃっています。
こうしたモデルを最大限に活用している事例としては、Twitch上のゲームコミュニテやK-POPが筆頭に挙げられますが、これとまったく同様の動きを取り込んだのはQアノン(Qanon)だったとも言えます。Qanonの「Q」と呼ばれる謎の人物/集団は、そういう意味では非常に有能なファシリテーターだったと言えます。
──オリンピックという運動を、アスリートたちの主権性を最大限に生かしたやり方で運営しようと思えば、IOCという組織は、一種のファシリテーター、もしくはコミュニティマネージャーのような存在として合意形成をつくっていく存在にならなくてはいけないということですね。
はい。これは、例えば「ステークホルダーキャピタリズム」と呼ばれるものが実際に指し示している組織運営のあり方で、要は、ワーカーからサプライチェーンに連なる企業を含むステークホルダーを、事業のパートナーとみなして協働しようというモデルなのですが、これは何も「ソーシャルグッド」というコンテクストからのみ語られるべきものではなく、むしろ不確実性がデフォルトの環境のなかで、いかにリスクを最小化するかという観点から必要となる考え方なのだと、わたしは理解しています。

──なるほど。ここまでの話、実はずっと今回の〈Field Guides〉のお題である「コロナの1年が仕事にもたらしたもの」(What a year of Covid has done to work)につながる話題ですよね。
長い前置きになってしまいましたが、その通りなんです。オリンピックの問題で起きていること、「欧州スーパーリーグ構想」などで起きていることは、実は、いま現在、会社というものにおいて起きていることと、それなりに相似形になっているように思うところがありまして、わたしたちは、いま起きていることを、よほど注意深く見ておく必要があるかと思います。
──どの辺を注意しておくべきでしょう。
まずは、先にお話した合理化のところですね。「分散化」はあたかもいいことのように語られることがもっぱらですが、これが「合理化」という目的にだけ向けて発動されますと、先ほどの国際会議の事例で見たように「中心」の権限がより高まるということが間違いなく起きます。これは先日ある方が教えてくださったのですが、リモート化によって、出社組とリモート組の情報格差が明確に生まれはじめているそうで、これが進行していくと、これまで以上に「本社」の決定がブラックボックス化していく懸念があります。
──ふむ。それは日本企業での話ですよね。
そうです。今回の〈Field Guides〉には、Qualtricsという雇用環境の分析を専門とするリサーチ会社が行ったサーベイの結果などがクイズ形式で掲載されていますが、ここで、そのクイズを出しておきましょうか。面白いので。
──はい。
全部で10個の質問がありますが、注目すべき6つを紹介しますね。
- 第1問「世界各地の4,000人の対する調査のうち〈住む場所を自由に決められることが大事〉と答えた人は何%?」「① 31% ② 51% ③ 79% ④ 90%」
- 第2問「第1問と同じ調査において、〈居住の自由と仕事の選択の自由の両方が大事〉と答えたアメリカ人は何%」「① 27% ② 55% ③ 82% ④ 95%」
- 第3問「マイクロソフト『Teams』で世界31カ国3万人のワーカーを対象に行った調査において大半の人が〈チームメンバーと対面で会う必要なない〉と答えた」「① 本当 ② 間違い」
- 第4問「リモートで効率的に働くために何が最も必要とされているか」「① 社外のクライアントや顧客と対面で会うこと②先の予定がもっと明確に決まること ③必要なときにオフィス空間を使えること ④必要なときに同僚と会えること ⑤ オフィスにある物理的な機器などを使えること」
- 第5問「リモートワークのメリットとして一番多くの答えが上がったのは〈時間をフレキシブルに使えること〉。2番目に多かった答えは?」「①仕事を中断されなくて済むこと ②集中できる環境で働けること ③ より多くの時間を家族と一緒に過ごせること」
- 第6問「オフィスで働くことのメリットの最も多い答えは〈私生活と仕事を切り離せる〉ことである」「① 本当 ② 間違い」
──えーと。わたしがここで答えてもしょうがないですから、正解を教えてもらってよいですか?
はい。これもざっと。
- 第1問「③ 79%」
- 第2問「③ 82%」
- 第3問「② 間違い」
- 第4問「③ 必要なときにオフィス空間を使えること」
- 第5問「② 集中できる環境で働けること」
- 第6問「② 間違い」
──なるほど。面白いですね。
はい。例えば、第3問で明かされているのは、人はできるだけ自由に住む場所を選びたいと思ってはいながらも同僚やチームのメンバーと会うことは重要だと考えているということで、こうした声は60%に上るとされています。また、第6問でのオフィスのメリットとして最も多い答えは「同僚とたやすく協働できること」だとされています。全体で見ると、自由という観点からリモートワークは望ましいことなのですが、とはいえ問題も少なからずあるという結論で、エグゼクティブ層も、若年層も同様に適応に苦労しているとしています。
──ふむ。
この調査結果は、リモートワークとは、自分なりに業務をマネージして集中して遂行するのにはいいのだけれども、そこには同僚やチームメンバーとのコミュニケーション不足という問題があることを明かしています。これは、「社内の各部門が社員のメンタルヘルスのためにできること」(How to support employee mental health from every level of the firm)という記事でもレポートされている通り、ワーカーのメンタルヘルスという問題にも直結していますが、同時に、先にお話したような「情報格差」に対する不安して理解することも可能だと思います。
──そうですか。
先ほどからお話している通り、リモートワークによる分散化は、いろんなレベルで効率化を促進させるものとして作用します。上記の調査の第5問が明かしているように、業務を集中して遂行するには、会社にいるよりも家のほうがいいという人は少なからずいるわけですね。ということは、きっちりとタスクが分業化された業務の遂行にあたってはリモートのほうが業務効率は高い可能性があるということですよね。つまりリモートワークは、業務の断片化を促進させる方向に作用する効果がありうるということにもなりますが、それは業務の官僚化・管理化をより進行させうるものともなります。

──そうなると当然、業務量に対する評価がワーカーの評価に直結していくでしょうから、業務時間は増えてもいきそうですね。
それはまさに「パンデミックから1年を経て仕事はいかに変わったか」(How work has changed a year into the pandemic)という記事でも問題にされている点でして、実際に、そうなんですね。『Bloomberg』の記事によれば、英国、アメリカ、オーストラリアといった国では、1日の業務時間が2.5時間増えているとされています。
──そうなってくると、その増加分が残業とみなされるのかといった問題も出てきますね。
はい。この辺は会社の経営側が、そうした変化をどう考えるかによって、大きく考え方や運用のルールは変わってくることになりますが、「分散」を、それ自体がいいことのようにぼんやり考えてしまうと、経営側から変な言い分が出てくることにもなりまして、それを問題にしたのが、「都市から移住したリモートワーカーの賃金を削るのはアリなのか」(The case against cutting remote workers’ big-city salaries)という記事なんですね。
──それまで都会に住んでいたワーカーたちが、リモート化を機に郊外のより家賃の安いエリアに引っ越した場合、家賃が安くなった分、賃金をカットするということですよね。
これは特にシリコンバレーで起きている現象だそうですが、記事によればFacebook、Twitter、MicrosoftやVMWareといった企業がそうした施策を行っており、Stripeは永続的にリモートワークを選択したワーカーに対して2万ドルの引越手当の支給と引き換えに10%の賃金カットを命じたそうです。
──むむむ。これはどう考えたものか、難しいところですね。
記事は上記の企業は、この判断を後悔することになるだろうと指摘していますが、たしかに、これはどう考えるべきなのか難しい問題ではあります。ワーカーが居住している場所の生活コストに応じて給料が設定されるということそれ自体は、多くの人がなんとなく当たり前のことと受け入れていることのように思いますし、実際記事内で紹介されている『Bloomberg』の記事によれば、Blindというソーシャルメディアが行った5,900人を対象にした調査では、こうした減俸に対して、反対の人は49%で、受け入れる人は44%だったそうです。
──だいたい半々、と。
ワシントン大学の社会学教授のジェイク・ローゼンフェルドさんは、記事内で、居住エリアと給与を連動させるアイデアは「20世紀中葉のモデル」であり、それが有効だったのは「終身雇用が制度として機能しているうちだけ」だと指摘し、現在のワーカーは、自らをいつでも取り替え可能なフリーエージェントでしかないことを多かれ少なかれ認識しているので、過去の給与体系を受け入れることはないだろうと語っています。「同一労働同一賃金」という原則が、こうした環境下でより強まっていますし、男女間や人種間などの賃金差も今後、より一層厳しく査定されるようになりますと、この傾向はますます強化されていくことになります。
──とすると、基本、そうした給与体系は是正されていくことになりますか。
こうした流れを受けてSpotifyやRedditといった企業は「どこで働いても給与水準はサンフランシスコやニューヨークに暮らすワーカーと同じ」という原則を打ち出していますし、記事は「Help Scout」というカスタマーサポートソフトをつくっている100人強の会社の事例を紹介しています。
──ほお。
この会社は10年前の創業以来100%リモートで経営されていまして、4割がアメリカ国外のワーカーなのですが、2018年までは、タイのエンジニアとサンフランシスコのエンジニアでは異なる水準に基づいて賃金を払っていたそうですが、創業CEOのニック・フランシスさんは、それがどうにも腹落ちしかなったらしいんですね。そこで2018年以降は、ニューヨーク、シアトル、ボストンといった「2級都市」(1級はサンフランシスコ)の水準に揃えるようにしたそうなんです。
──へえ。
フランシスさんは「ボーダーレス企業だと自分たちのことを謳っているのに、なんで給与水準に国境があるんだ?」という問いを投げかけつつ、一方で、水準の一律化は「世界中の都市の生活コストや為替レートに合わせて、各人の給与計算をする面倒から解放してくれた」とも語っています。

──これは、しかし、面白い問いですね。
そうなんですよね。これまでのグローバル企業は、地域ごとの生活コストの水準の差分を利益に変えてきたものでもあることを考えると、この考え方は、それなりにラジカルなものと言えるのかもしれませんよね。世界の大都市にオフィスを構えるような企業が、ホワイトカラーのワーカーの給与水準を揃えることはさほど難しいことでもないのかもしれませんが、これが例えば工場のワーカーなどにまで援用しようと考えたなら、製造業などはビジネスモデルが一気に崩壊しそうです。
──ほんとですね。「低開発国」の安い労働力を食いつぶしていくのが、これまでの製造業のありようでしたからね。
そうなんですよね。これはおそらくこれまでの資本主義のあり方を、面白いやり方で揺さぶることになるのかもしれません。それこそ「ステークホルダーキャピタリズム」のようなことを言い出してしまうと、ワーカー、サプライチェーンを同等のパートナーとして扱うことが要件となっていきますが、それを実行しようとすれば、程なく、こうした「平等性」の問題に突き当たることにもなりそうです。
──そんなこと言い出すと、すわ「社会主義か」といった批判も出てきそうですが。
そうですよね。これは決してワーカー全員が同じ給与になるということではもちろんなくて、きちんと平等にみなを取り扱おうということなのですが、これを理解する上では、「Equality」ということばと「Equity」ということばの違いを理解しておく必要があるかもしれません。いま、とあるプロジェクトに関連して読んでいる『B Corp Handbook』という本では、こう説明されています。
「Equialityはすべての人が同じように扱われること。Equityはすべての人が個々人の状況やニーズにしたがって扱われること」
──ふむ。
いま例として挙げた給与水準の一律化の話は、どこにいても暮らしていても、どんな働き方をしていても選別の対象とならないという意味で「equity」が考慮され、そのequityに則って誰にもみな等しく同水準が適応されるという意味で「equality」が考慮されているということになるのではないかと思います。この違いを説明した有名なイラストがありますので、これを併せてご覧いただけるとわかりやすいと思います。
──考え方として、そうしたことが重要だというのはわかるのですが、先ほど指摘された通り、これまでの経済が「格差」をドライバーとしてきたものであるのだとすれば、それを均していこうという動きは、企業にとっては死活問題ともなりますよね。
それはそうだろうと思います。それこそ新疆ウイグルの問題などで企業がやり玉に挙がっているのも、人権抑圧によって生じた格差を「低コストの旨味」と引き換えにほっかむりしてきたことに対する批判であるわけですが、その批判を率直に受け入れたとすると、コスト構造が壊れて、現状のビジネスモデルが成り立たなくなりそうですからね。だからこそ、なんとなくうやむやにしようという方向で現状全体が動いているように見えるわけですが、そう考えていくと、冒頭で話題にしたオリンピックや欧州スーパーリーグ構想といったものは、経済そのものが岐路に立たされているところを、強引に突破しようとしているようにしか見えないんですね。
──これまでであれば、なんとなく大義名分を持ち出してうまく懐柔できていたものができなくなって、なんだか開き直っているような感じですもんね。
「格差や人権なんか知ったことか」と隠し立てもせず、露骨に語られるようになっている状況をコロナが後押ししているところがあるのだと感じますね。経済が沈んでいけばいくほど、そうした声はどんどん露骨になっていくと思いますが、そのやり方ではおそらく突破できないのは冒頭にお話した通りで、その意味では、20世紀型の企業経済と21世紀型の市民運動とのせめぎ合いは、さらに熾烈化していくのではないかと思います。
──厳しいですね。
そうした泥沼のせめぎ合いを抜け出す可能性のヒントとして、個人的には、市民参加型の経済圏というものをもう少し詳細に検討する必要があるのではないかと思っていまして、そのひとつのヒントとして、K-POPとゲームのコミュニティの動きは注視すべきだと思いますし、そうした観点からも田中絵里菜さんの『K-POPはなぜ世界を熱くするのか』は必読書だと思いますので、最後に激しく推奨しておきます。
──冗談抜きで、ですよね。
あ、もちろんです。ちなみに、この本で描かれた経済モデルをC-POPが爆速で取り込んで巨大な経済圏を形成しているということを、つい昨日知人に教わったのですが、このあたりも気にかけておいたほうがよさそうで、これはいままでわたしたちが知っていたような、企業がメインプレイヤーである経済とはまったく違う様相を呈しています。ビジネススクールなどでも詳細に分析すべきと思いますよ。
若林恵(わかばやし・けい) 1971年生まれ。『WIRED』日本版編集長(2012〜17年)を務めたのち、2018年、黒鳥社設立。本連載をまとめた書籍「週刊だえん問答 コロナの迷宮」もぜひチェックを。
🌍 申込み締切、迫る! Quartz Japanメンバーシップ読者であれば無料で参加できるウェビナーシリーズ「Next Startup Guides」の第6回は、4月28日(水)、Global Brainの上前田直樹さんをゲストに迎え、英国を中心としたヨーロッパにフォーカスします。詳細・お申込みはこちらからどうぞ。
🎧 Podcastでは月2回、新エピソードを配信しています。Apple|Spotify
👀 Twitter、Facebookでも最新ニュースをお届け。
👇 のボタンから、このニュースレターをTwitter、Facebookでシェアできます。ニュースレターの転送もご自由に(転送された方へ! 登録はこちらからどうぞ)。
