A Guide to Guides
週刊だえん問答
世界がいま何に注目しどう論じているのか、米国版Quartzの特集〈Field Guides〉から1つをピックアップし解題する週末ニュースレター。Quartzの原文(英語)と、原稿執筆の際に流していたプレイリストとあわせてお楽しみください。
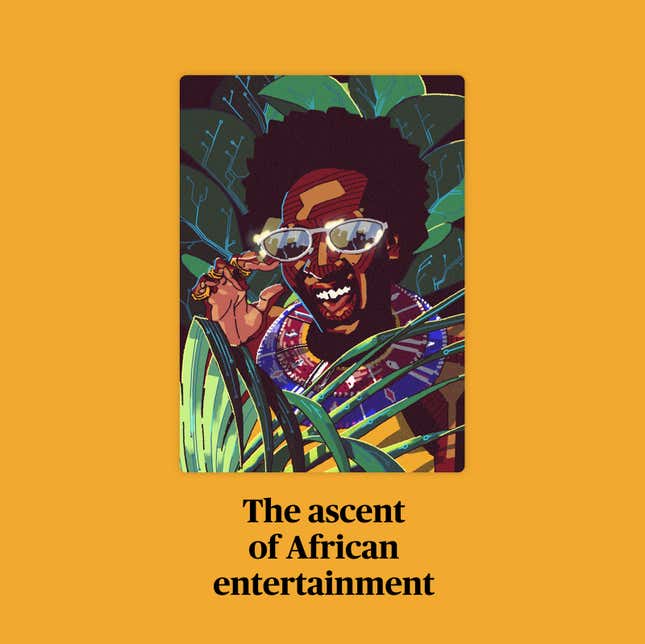
The ascent of African entertainment
アフロポップの優美
──どうもです。ご機嫌いかがですか?
まあ、普通です。
──今回が、『週刊だえん問答』の第2巻に収録される最後のエピソードになるとのことですので、まあ、いわばこの半年の総決算的な意味がありそうですが、なにかお伝えしておきたいことなどあれば、ぜひ。
そうですね。日本で起きていることは、ニュースを見ることすらうんざりするほどに、くだらないことしかないですから、もういいんじゃないですか。相手にするから図に乗るということなのでしょうし、違う話をするのがいいんじゃないでしょうか。
──真面目にやってる人には気の毒にもなりますけどね。
みんなが真面目にやってるのが、もはや問題なんだろうという気もしますから「よかれと思ってやること」はいい加減ほどほどにしないといけないのではないかと思います。「真面目にやってる人もいるんだ」という言説は、当たり前の前提条件を言っているだけですから、自戒もこめて、それを口実の人の善意を動員するのも、動員されるのもやめた方がいいと思います。
──いいニュース、ないですね。
昨日、河合某という議員が実刑判決を受けたのは久しぶりにいいニュースでした。
──そうですね。
毎日新聞の速報記事を読んでいて呆れはてたのは、河合某側が、「議員辞職したことや、逮捕後に支払われた歳費の一部700万円を児童福祉関連の財団法人に寄付したことなどを挙げ、執行猶予付きの判決を求めていた」という点で、「児童福祉に寄付したんだから、減刑できる」と考えるそのマインドは、まさに善意の悪用でしかなくて、まあ、そういう輩はこの世に事欠かないのだとは思いますけれど、それを受け取る側も、どうかしてますよね。自らの組織が体よく、ロンダリングに使われているわけですから事業側も怒ったほうがいいと思うのですが。
──お金が欲しいのは、現実としてはそうなんでしょうけれどね。
それはもちろんそうです。でも、なんらかの理念があったとして、それを経営や財務と天秤にかけて、簡単に理念をねじ曲げていいなら、経営なんてよほど簡単なことですよね。理念と財務の対立を二者択一の問題にして、どっちかを選べばいいという問題にしてしまうなら、話しは簡単ですよね。それが対立しない方策を考えるというのは難しいチャレンジですが、そのチャレンジをしないなら「頭のいい人」はなんのためにこの世にいるんですかね。

──理念を曲げずに、きれいな経営をするというのは、でも難しいですよね。
そりゃそうでして、だから、そういう企業なり組織は尊敬されるわけですよね。多くの人が「ミッション」や「ビジョン」が大事だと簡単に言いますが、それを実践することは、とてつもなく難しいわけで、その難しさをどう解消しうるのかを必死に考えるのが経営というものでしょうし、そのために行動するのが事業というもの本質じゃないですか。でも、それは難しいことで、そんなことができるのはほんの一握りで、とても希少なものなんで、だからこそ尊いわけですよね。
──そうであればこそ、それは希望にもなると。
逆に、言い訳まみれの事業をいったい誰が応援したり敬意をもったり信頼したり憧れたりするんでしょうか。
──昨日(18日)開催された「GDX」のイベントに北國銀行の杖村頭取という方が出演されていましたが、まさに、何かそういう本質的なものを見た感じがしますね。北國銀行では、これまで自社のDXや構造改革をレポートした3冊の本が出ているそうですが、北國銀行さんは、それを書店に卸さず、自分たちが経営するECサイトだけで地道に売っているとおっしゃっていましたが、あのスタンスはすごかったですね。
「世の中の本は中身がないじゃないですか」という言い方をされていたと思いますが、その指摘は本当に正しいものだと思います。自分も含めて反省すべきは、何かを出版して、それでお金を回収することがあまりにも産業化され、自動化されてしまったことで、いったい何のために、誰のためにそれをつくって届けようとしているのか、問うことを怠っていることです。
私の理解では、その自動化されたルートに何の考えも持たずに乗ることは、「何のために、誰のためにそれをつくって届けようとしているのか」を問わずにそれをやっている人たちと同じ土俵に乗ることを意味している、という認識があったのではないかと思います。だから、あえてそこに乗らないわけですね。
──「一緒にすんな」という身振りですね。
オルタナティブであるというのはそういうことだと思うんです。どなたのことばだったか忘れてしまいましたが、「人のキャリアは、何をしたか、ではなく、何をしなかったかで測られるものだ」といったことが書かれていて、いまだに強く記憶に刻まれています。人の行動において、何をやらなかったか、というところを、人はもっと見るべきなんです。
──面白いです。
これはミュージシャンの仕事を見るときなどでもとても重要な視点で、例えば、あるアルバムを出したときに、そのアルバムが完成にいたるまでには、実際にはいくつもの選択肢がありえたわけで、それを選び取っていく過程で、排除された道が無数にあるわけですね。
──こっちに進むべき道筋もありえたのに、それを選ばなかった、ということですね。
そうした判断には、明確に「ある可能性を捨て去る」必要があるわけですから、そこにこそ勇気というものが必要になるわけですね。ある道を通るためには、それ以外の道が捨てられているわけで、そここそに判断や選択というものの重みは宿るのだと自分は思うのですが。
──最近そういう事例ありました?
自分が感心したのは、ペク・イェリンという元K-POPアイドルだったミュージシャンの動きですね。
──昨年末に出たアルバムは、ほんとうに傑作でした。
はい。そこで自身の音楽的なキャパシティを十全に披露し、それを確固たるものにしたのですが、その後、自分でつくったイメージを自分で裏切るような格好で、インディロックバンド、The Volunteersの一員としてアルバムを出したんですね。
──ちょっと驚きましたよね。そこまでガラッとやっちゃうんだ、という感じで。
そこに、自分は彼女が、とかくパブリックイメージを固定させようとする世間というものに思い切り中指を立てた感じが見て取れて、爽快感があったんですよね。自分のレーベルをつくって、自分がやりたいことを自由にやる、というメッセージを自分は受け取って、「おお、ぜひ、そうしてくれ!」と、ますます好きになったのですが、彼女のキャリアを考えれば、おそらく、自分としては排除したい道を死ぬほど歩かされてきたことへの反発があるんだと思うんです。その道を取らずに済むよう、彼女は自身でレーベルをつくったのでしょうから、そこにはやはり強い決意と勇気が必要ですし、しかも、いまのところ彼女は、そこで得た自由を、ダイナミックに行使しているように感じますので、これは見ていて非常に胸がすくものです。
──いいですね。
彼女には一度話を聞いてみたいです。いま一番インタビューしたい人ですが、仮にインタビューしたとしても、おそらくまともには答えてくれないんだろうなと想像できそうなところも、いいなと思います。不機嫌な感じで応対されたりしたら、ますますファンになります(笑)。

──今回の〈Field Guides〉は実は、ほぼほぼ音楽の話なんですが、つながりそうな話しでしょうか。
どうでしょうね。つながるかどうか、やってみますか。
──アフリカ音楽が世界化しつつある状況についてです。昨今のアフロポップと呼ばれているムーブメント、お好きですよね。
大好きです。面白いんですよね。
──何が面白いですか。
自分がいわゆる最近のアフロポップの動きを気にし始めたのは、たぶん3年くらい前のことだと思うのですが、そこで何に惹かれたと言えば、その驚くほどの優美さだったんです。そのとき聴いていたのは、ナイジェリアのラゴスやガーナのアクラから出てきた音楽で、それこそのちにシーンを代表するグローバルスターとなったバーナ・ボーイがデビューしたあたりだったと思います。
──優美さ、ですか。
現在のアフロポップは、レゲトンやトラップといったグローバルで採用されている音楽様式が、ある意味先祖返りを果たし、アフリカ流に咀嚼されたものと言っていいと思いますが、自分が驚いたのは、そうやって世界のあらゆるトレンドがアフリカに還流したものがアフリカというフィルターで濾過されたときに、ひどくシンプルかつミニマムなものになっていたことなんです。つまり、もうほんとうに、世界の音楽のエッセンスを極限にまで煎じ詰めて取り出したような感じがあって、しかもそれが、ただ簡素になっているのではなく、様式のなかに眠っていたエレガンスだけを取り出したような感覚を受けたからなんです。
──すごいすね。
自分が、それらを聴いて真っ先に思い浮かべたのは80〜90年代に活躍したシャーデーというイギリスのグループのことでして、彼女らのつくる音楽というのは、ポップでありながらものすごく純度の高い抽象性をもっていて、それでいてめちゃくちゃセクシーだったんです。で、そうか、とはたと気づいたのですが、シャーデーのボーカルのシャーデー・アデュは、ナイジェリアにオリジンをもつ人だったんです。
──ああ、彼女自身が30年以上も前からアフロポップだったというわけですね。わかる気がします。
シャーデーの音楽は、あらゆる都市やリゾート地などでかかっていたりするもので、自分が覚えている限りでも、それこそカリブのリゾートでも、英国のブラックプールでも、ケニアのナイロビでも、エジプトのカイロの街中などでも聴いた記憶があるのですが、それがどこで聴いても、なんというか同じように景色になじんで、同じように気持ちいいんです。シャーデーの音楽のある種のユニバーサル性というのは、もうこれはすごいんです。普遍性の高さがすごいんですよ。
──想像するだにハマりそうですもんね。
しかも、それは、欧米ポップスがもつ帝国主義的画一化とは明確に異なる感覚のもので、そこで見出されたユニバーサル性というのは、欧米が考えてきた「普遍」の概念とは違う、オルタナティブな「ユニバーサル」を夢見させてくれるものなんですね。自分にとっては。

──いいですね。
もうひとつ自分にとって大きな発見だったのは、ナイジェリアなど西アフリカを中心としたアフロポップとは音楽的には異なるものですが、南アフリカのハウスミュージックでして、なかでもBlack Coffeeというアーティストなんです。
──へえ。
南アフリカは、どういう経緯なのかわからないのですが、ハウスミュージックがポップスとして広く一般に聴かれている不思議な土地でして、Resident Advisorが、Black Coffeeが故郷であるダーバンの小学校を訪ねるというドキュメンタリーを公開していますが、それを見ると、Black Coffeeが、ほんとうにもう大スターなんです。子どもたちが彼の登場に狂気乱舞するんです。
──すごい(笑)。
で、Black Coffeeの音楽というのは、聴いてみていただくとわかるのですが、めちゃくちゃストイックなハウスミュージックなんです。ポップス的な味付けなんて、ほとんどなくて、もう淡々とエレガントで、とにかくめちゃくちゃ気持ちいいものなんです。
──へえ。
このBlack Coffeeさんには一度インタビューさせていただいたことがありまして、そこでも彼は、「南アだとハウスはポップスなんだよ」と語っていたのですが、「んなわけないだろ」とこちらは思うわけです。日本からみたら、彼の音楽は「アフリカン・ディープハウス」なんて言われているものですから、それが国民的ポップスになっているなんて想像の埒外なんですね。ところが最近、Apple Musicで世界の都市ごとのチャートが見られるようになり、「へえ」と思ってダーバンのチャートを見たらほんとに彼が言っていた通りで、南アのハウスアーティストの曲がずらりと並んでいまして、それがまた、もう、腰を抜かすほどストイックな楽曲ばかりで、心底驚いたんです。
──ほんとだった、と(笑)。
この都市チャートというのを見るのはとても面白くて、結局世界のほとんどの大都市は、なんだかんだ言ってアリアナ・グランデやウィークエンドやBTSといった、グローバルスターがチャートの上位にきてしまうものでして、それはApple Musicのユーザーの質を考えれば当然そうなるのですが、そうした傾向がまるで通用していない都市、かつローカルの音楽が、グローバルスタンドードを超えて面白い都市が自分が見た感じ、いくつかありまして、その筆頭がダーバン、そしてラゴスやアクラ、あとアメリカでもアトランタは独特だな、という感じがあります。
──いいですね。
もちろん地域的な独自色が強いチャートは世界中にいくつもあるのですが、音楽的に見ますと、グローバルトレンドをローカライズしたものという印象のものが多く、かの音楽大国ブラジルでも、ローカルなチャートはそこまで面白くないんです。そうしたなかで、まったく違う音楽的価値観を示しているのが、自分のなかではアフリカでして、とくにダーバンは気持ちいいほどの異世界です。
──面白いですね。
ダーバンやラゴスの面白さは、その独自性にかかわらず、そこに先にお伝えしたような、なんともいえない世界性・普遍性があることで、そのチャートを見ていると、自分たちはなんてゴテゴテしたダサい音楽を聴いているんだろう、アフリカの耳は自分たちのそれよりどれだけ先に行っているのか、と思わされてしまいます。
──なるほどなるほど。Apple MusicやSpotifyといったプラットフォームが、これから開拓すべきフロンティアとしてアフリカ大陸を目指すようになり、その結果として、アフリカの新しい音楽がグローバルマーケットに逆流しはじめ、それを例えばドレイクやビヨンセといった人たちが大きくエンドースしたことで、もはやアフロポップは、ただの「ワールドミュージック」ではなく、グローバルポップのひとつの基軸として、立つようになってきているわけですね。
そうですね。これはもちろんビジネス的観点からも、グローバルプレイヤーにとって見過ごせない動きになっていまして、「アフリカン・エンタメが自立し始める」(African entertainment comes into its own)という記事には、こんな状況がレポートされています。
「アフリカと中東の録音音源の収益は、2019年から2020年で8.4%伸びている。ストリーミングの収益についていえば、前年比36.4%の伸長を記録しており、これが音楽産業のメインの収益源となっている。
ワーナー・ミュージック・グループのサイモン・ロブソンはあるレポートでこう語っている。
『K-POPはもちろん継続して好調だが、今年最もエキサイティングな伸びを見せたのは、アフリカ音楽で、アフリカのアーティストはいまや世界のファンに聴かれている』」
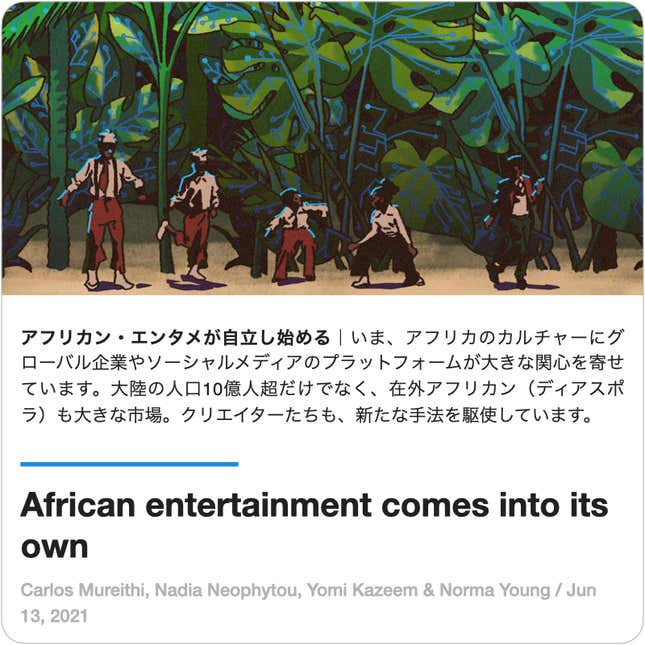
──K-POPと並ぶグローバル勢力になっている、と。
おそらくいま世界のポップスの勢力図でいいますと、目立って巨大勢力を形成しているのは、K-POP、アフロポップ、そしてラテンアメリカ発のレゲトンということになるのではないかと思います。
──おお、レゲトン。昨年、Spotifyで一番聴かれたのはたしかプエルトリコ出身のBad Bunnyでしたもんね。
そうなんです。レゲトンは、そもそもアメリカのラテンアメリカ人口が、非常に多いことから早くグローバル化したとものと言えますが、アフリカ、アジア、ラテンアメリカの3つの軸が、大きな影響力をもつにいたっているのは、単にそれぞれの地域が大きな人口を抱えているからだけでなく、それらの地域にオリジンをもつ人たちが、世界中にディアスポラとして拡散しているからでもありまして、例えばナイジェリアの若者の間でカルト的な人気を誇るナイラ・マーリーは、ロンドンのペッカム育ちだったりします。

──なるほど。
かつてであれば、そうやってグローバル経済のなかで流動する人たちは散り散りになったままであったかもしれませんが、インターネットとグローバルアプリが、そうした人たちが縦横無尽にコンタクトしあえる環境をもたらしていまして、アフリカ国内のアーティストのみならず、世界に点在するアーティストが手を取り合える状況を、「アフリカのエンタテインメント・ビジネスはDMで起きている」(Africa’s entertainment deals are going down in the DMs・日本語版はこちら)という記事は明かしています。
──個人同士が、どんどんやりとりしちゃうわけですね。
ちょうど今週、アフリカ音楽の重鎮でベニン・オリジンのアンジェリク・キジョーさまが新譜「Mother Nature」をリリースしましたが、このなかにSampa the Greatというアーティストをゲストとして迎えています。Sampa the Greatは、ザンビア生まれ、ボツワナ育ちで、サンフランシスコとLAで視覚メディアを学んだのち、シドニーの大学で音響工学を学び、現在はメルボルンを拠点に活動しています。彼女の音楽をキジョーさまは、NPRの「Tiny Desk Music」で見て、DMを送ったそうです。
──いいですね。
また、南アでは2010年ほどから、ローカルなハウスの派生系として「Amapiano」というジャンルがメインストリーム化していますが、このシーンでは、「WhatsApp」を使って音源をコアファンにシェアしてフィードバックをもらいながら制作を行うスタイルが一般化しているとも記事はいいます。
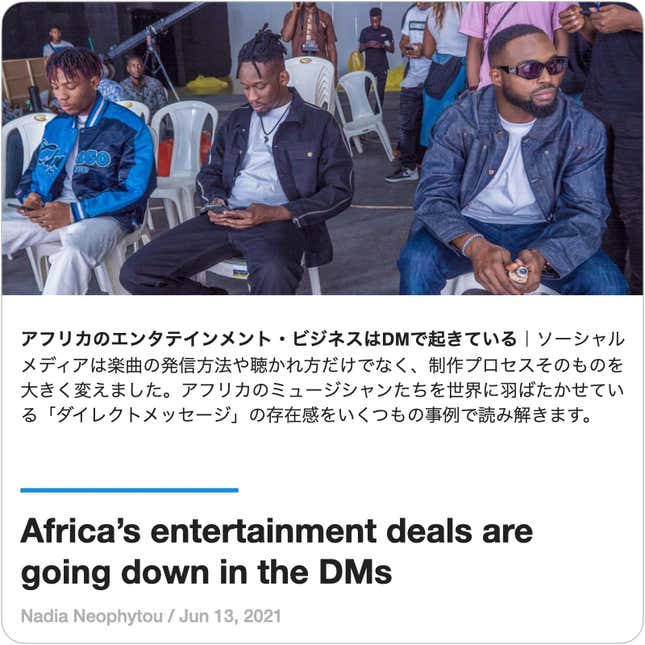
──面白いですねえ。ユーザー参加型のアジャイル開発じゃないですか(笑)。
ユニバーサル ミュージックのアフリカ担当デジタルディレクターは、「ミックスやマスタリングに高い費用を払うことなくアーティストとそのチームは十分にそれができる能力をもっていて、レコードが完成する前にテストすることもできる」と語っています。
──面白いですね。アーティストたちが、どんどん先に走っていっていく感じが、ほんとうにダイナミックです。そうなっていくと、レコード会社とか、実際なんの意味があるのか、という感じになってきますよね。
これは、44話の「ティックトックの訓戒」でお話したことですが、ひとつの大きな問題は、ミュージシャン側の制作面における自由やコンピテンシーが上がっているにもかかわらず、結局のところ、それを「換金」するところの仕組みにまだ大きな不自由があるということがあるということですよね。レーベルやレコード会社は、そこにおける戦略の策定や、実際のツールを、もっとフェアなかたちでアーティストにシェアしながら、自分たちのビジネスをも構築していくようなモデルに変わっていくんじゃないかと思います。これはデジタルプラットフォームの機能面においても、今後さらに考慮されていくはずです。
──これはまさに、53話「スモールビジネスの希望・下篇」でお話されていたことですね。
はい。このあたりの話は、アメリカなどでも議論されていまして、先日、あるブランディングやファンダムに関する戦略を行う会社のファウンダーが、「クリエイターの収入を再想像する」(Reimagining Creator Compensation)と題するブログで、中国のエンタテインメントビジネスについて書いているのを見つけました。2020年の記事ですが。
──ほお。
彼女はこう書いています。
「中国のエンタメ空間において実験されている収入源の多角化は、大きなインスピレーションとなるものだが、これまで何年もの間成功を収めてきたにもかかわらず、わたしたちは注意を払ってこなかった。
こうした実験のなかで生まれてきたのは、ただ単に新しい収益源を生み出すことではない。完全にプロダクト、サービス、エコシステムを再創造したものもある。それらはカスタマーの行動をよく見て、そこから学んだ結果として生まれたもので、新しいマネタイズ手法によってドライブされてきた」
──レベニューストリームを変えることで、プロダクトの考え方や、それを取り巻いていたエコシステムのあり方が一気に変わるということが起きるということですね。
とはいえ、ここで検証されているのは、そこまでドラスティックなアイデアでもないんです。エリカ・バドゥが自分でライブストリーミングの会社を設立した事例や、アーティストにチップを支払って応援できる機能、ブスクリプション機能、マイクロトランザクションの強化、対面コーチングビジネスの拡充といったことでして、こうしたサービスの先行事例として、ここではTwitchのようなゲーミングプラットフォームが紹介されていますが、今後、まだまだ新たなサービス、機能は生み出されていくものと思いますし、それが一般化していくにしたがって、以前にお話したように、アーティストとオーディエンスの関係性を含めた、産業の「エコシステム」そのものが変化していくことになるのだと思います。

──これから大きく変わってきそうですね。
はい。さらに、これはまったく別の観点からの議論ですが、『Havard Business Review』に、「ステークホルダーキャピタリズムのナイジェリアモデル」(A Nigerian Model for Stakeholder Capitalism)という記事が掲載されていまして、これはいま学ぶべきひとつの経済モデルとして、とても面白そうです。
──へえ。
ここで紹介されているのは、ナイジェリア東部のイグボの人たちのコミュニティで何百年と受け継がれてきたシステムだそうで、ある事業で成功した人は、必ず新しいビジネスをやる人を育て、資金も与えて独立させないといけないという一種の徒弟制度なのだそうです。「Igbo Aprrentice System」と呼ばれるこのシステムは、実は世界最大のビジネスインキュベーターとさえ言われているそうで、何千もの「ベンチャー」を生み出しているとされています。
──面白いですね。
こうした仕組みがどのように作動し、結果としていかに独占企業を生むことなく、コミュニティの経済を底上げし、かつ市場のダイナミズムを減退せずにいるかは、記事にあたっていただけたらと思うのですが、この話が重要かもしれないのは、実は、今回の〈Field Guides〉のなかでも引き合いに出されるナイジェリア/ガーナの音楽シーンの重要人物であるMr.Eaziが、まさにそのような動きをしているからでして、彼は「emPawa Africa」というイニシアティブを展開しているそうで、「Jerusalema」という曲で一躍スターとなったJoeboyは、エド・シーランのカバー動画がMr.Eaziの目に止まり、いきなりDMをもらうところからスターへの道を歩むこととなったそうですが、こうした動きを先の記事に重ね合わせてみますと、そこには、循環的で、あらゆるステークホルダーにとってフェアな新しい音楽経済のあり方が、持ち上がる可能性を見ることができるのかもしれません。
──ワクワクしますね。
とはいえ、その一方で、音楽の産業化は、どうしたって音楽そのものの画一化をもたらす方向性はもっていまして、市場が大きくなると、それこそ似たようなアーティストで溢れかえることにもなるのかと思いますが、それがどのように回避されながら、活気あるエコシステムを生み出せるのかは興味あるところです。また、そうした観点からいきますと、いわゆるポップマーケットを対象としていない、アンダーグラウンドミュージックの豊かさは、どんな文化産業においても重要ですから、ウガンダのカンパラを拠点とする「Nyege Nyege Tapes」のような活動は、ナイジェリアのアフロポップシーンとは直接関係がないとは思いますが、やはり同じように注目すべきだろうと思っています。
──日本人電子音楽家のDJ Scotch Eggさんが、 それこそNyege Nyege Tapesの姉妹レーベル「Hakuna Kuala」が主催するレジデンスプログラムを通じて制作されたScotch Rolex名義の『Tewari』は凄まじいアルバムでした。
最高でしたよね。いずれにせよ、音楽における話が大事なのは、それがいずれ社会が向かっていく方向を指しているからですし、わたしたちがいま音楽というものを大事にすべきなのは、いくら産業化しようとも、結局のところ、それは個人が生み出す「価値」に立脚していて、かつ、それぞれ違った個性をもった個人がいればいるほど豊かな市場を生み出すものだからです。そうした経済が現実として存在していて、それがさらに豊かになっていく可能性を、いま目の当たりにしているのだとすれば、それは楽しいことですよね。
──しかも世界最高峰の優美さをもって、それが体現されていたりするわけですもんね。
そこですね。ナイジェリアは、それこそ警察による暴力もひどく、現実はまったく優美なものではないのだとは思いますが、そこから生まれてくるものが、あれだけの優しさと柔らかさを湛えているのは、それ自体が驚くべきことだと思うんです。それは決して現実逃避じゃないと思うんです。その優美さをもって応えるのが、彼ら/彼女らの闘争のスタイルなんじゃないかと思うんです。
──なるほど。
シャーデー・アデュの高貴さは、そこにあるんですよ。彼女の美しさは、音楽の優美さをもって、醜さをきっぱり拒絶したところにあって、その一番困難な闘い方を貫いた彼女を自分は、ずっと崇めています。
若林恵(わかばやし・けい) 1971年生まれ。『WIRED』日本版編集長(2012〜17年)を務めたのち、2018年、黒鳥社設立。責任編集を務めたデジタルガバメントについてのハンドブック「GDX:行政府における理念と実践」の序文がこちらで公開されています。『働くことの人類学【活字版】』もAmazonで予約受付中です。
👇 のボタンから、このニュースレターをTwitter、Facebookでシェアできます。ニュースレターの転送もご自由に(転送された方へ! 登録はこちらからどうぞ)。
